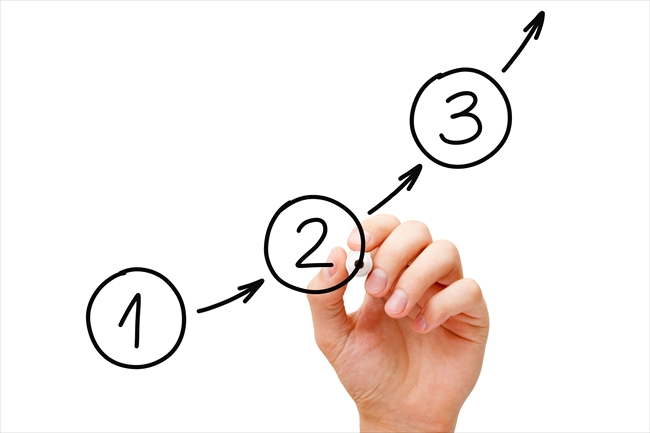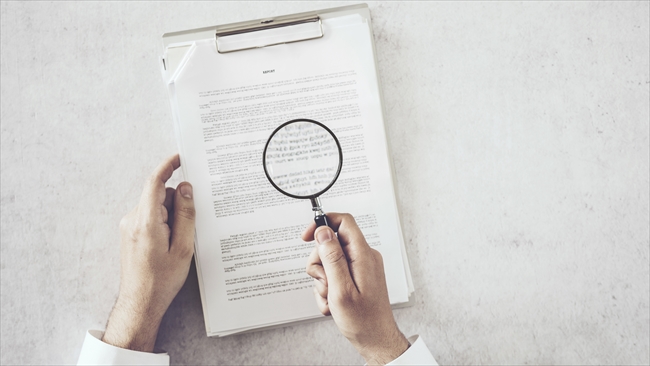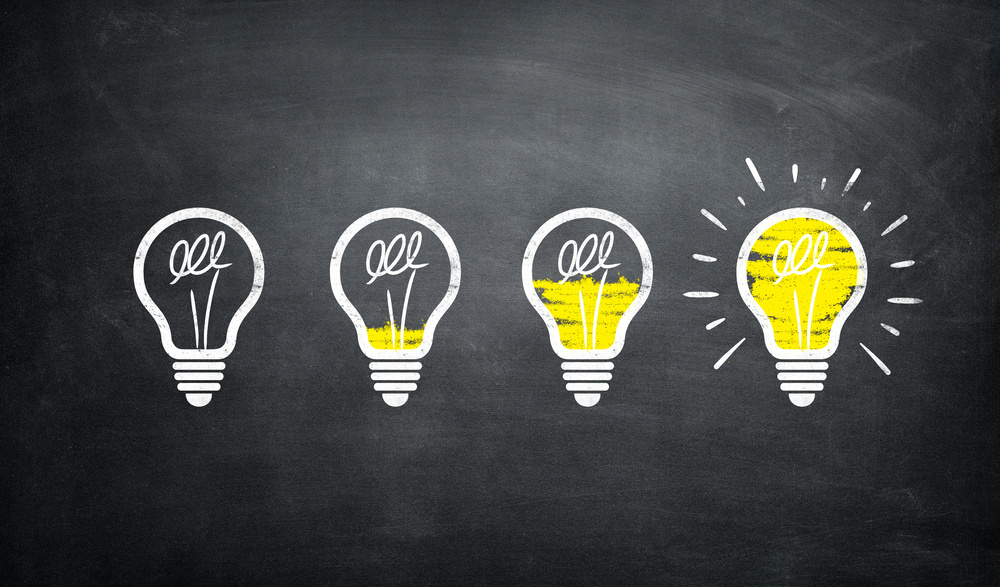※本記事はプロモーションを含みます。創業時に融資を受けるならば、日本政策金融公庫の創業融資を利用するか、あるいは地方自治体の制度融資を利用するのが良い方法です。
しかし、このどちらからも融資を受ける場合には、どちらを優先して融資を受けるか、あるいはどちらか片方から融資を受ける場合には、どちらを優先して融資を受けるかという問題があります。
そこで本稿では、両方に融資を希望する際に先に申し込むべきもの、または片方に融資を希望する際に申し込むべきものについて解説していきます。
まずは制度融資を利用する理由

日本政策金融公庫と制度融資を比較するためには、双方のメリットを見てみるのが一番です。
まず、地方自治体の制度融資には、次のメリットがあります。
創業融資に利用できる日本政策金融公庫も地方自治体の制度融資も、どちらも民間の金融機関に比べて、金利が低めに設定されています。
金利が低めであるということは、ローン返済時に支払う利息負担が小さくなるということですから、資金繰りにはプラスの効果をもたらします。
特に創業後間もない頃はキャッシュフローが出にくいので、金利負担が小さいことは見逃せないメリットです。
しかし、どちらかというと、制度融資は日本政策金融公庫に比べて、さらに低めの金利設定になっています。
さらに、地方自治体によっても違いますが、金利を補助してくれたり、保証協会に支払う保証料を補助してくれたりといった優遇措置も設けられています。

CFイエロー
この優遇措置を利用することで、金利が1%未満になることも多いよ!
日本政策金融公庫は、基本的に2%台の金利で貸し付けていますから、これはかなり魅力的なメリットだと言ってよいでしょう。
このことから、日本政策金融公庫の制度融資と地方自治体の制度融資を選ぶにあたり、次のように選ぶべきと言えます。
- 両方を利用する場合には地方自治体の制度融資を優先的に
- 片方を利用する場合にも地方自治体の制度融資を優先的に
制度融資のデメリット
金利が低く設定されており、なおかつ優遇措置まであることによって、制度融資は優先的に利用すべき融資制度だと言えます。

CF戦隊
しかし、制度融資にもデメリットがるよ!
自己資金の負担が大きい
制度融資の最大のデメリットは、自己資金の負担が大きいということです。
なぜならば、制度融資では、自己資金額までしか融資を受けられないことが多いからです。
例えば、1000万円の融資を希望しているならば、自己資金も1000万円必要ということです。自己資金が100万円しかないならば、融資限度額も100万円となります。
低い金利と優遇措置の裏には、このような大きなデメリットもあります。
自己資金をある程度用意できる人にとっては、それと同額の融資を低金利・優遇措置ありで受けられることが大きなメリットとなりますが、自己資金が少ない人にとってはデメリットとなります。
審査期間が長い

制度融資では、保証協会の保証をつける必要があります。
このため、制度融資で利用する金融機関の審査に加えて、保証協会の審査も受けなければならず、日本政策金融公庫よりも審査が長くなるというデメリットがあります。
審査時間は、その時々にもよるでしょうが、早くても1ヶ月、遅ければ2ヶ月以上かかる場合もあります。
日本政策金融公庫が1~3週間で審査を済ませることと比較すると、長い時間がかかります。
しかし、平常時の資金繰りではなく、創業にあたっての融資ですから、1ヶ月程度長引いたとしても、経営そのものに大きな影響を与えることは少ないでしょう。
また、計画的に起業していく上で、日本政策金融公庫と併用する場合には、日本政策金融公庫よりも1ヶ月ほど早く制度融資を申し込めば良いとも言えます。
日本政策金融公庫よりも審査が厳しい
大きなデメリットとして、日本政策金融公庫よりも審査が厳しいという点が挙げられます。
なぜならば、制度融資では、地方自治体から委託を受けた民間の金融機関が審査をするからです。
一般的に、日本政策金融公庫などの公的金融機関よりも、民間の金融機関は審査が厳しいものです。
公的金融機関は、基本的に創業を応援するというスタンスであるため、創業計画に基づいて積極的な融資を検討するのに対し、民間の金融機関にはこの姿勢が欠けているからです。
したがって、日本政策金融公庫に比べて、制度融資の方が審査に通りにくいというデメリットがあることも覚えておきましょう。
信用保証料の支払いがある
制度融資では、信用保証協会の保証を受けて融資してもらいます。そのため、信用保証協会に支払う信用保証料の負担もあります。
信用保証料は、融資実行時に保証協会に一括で支払います。
支払額は、以下の計算式で計算します。
信用保証料=融資金額×保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数
この計算式のうち、保証料率は明確に決まっているものではありません。信用保証協会のホームページでも、
信用保証料の料率は、中小企業者の方の財務状況などを考慮し、原則として9つの料率区分から適用されます。担保のご提供がある場合や、『中小企業の会計に関する指針』の適用状況を確認できる場合などには、割引も行っています。
と記載されており、明確にわからないようになっています。
また、分割係数とは、「分割返済により返済の進捗を考慮した掛け目のこと」とされており、簡単に言えば「分割での返済回数によって決められている割合」のことです。これは、
(出典:東京信用保証協会『信用保証料の計算例』)
と定められています。
したがって、500万円の融資を受けて5年返済(60回払い)をし、保証料率が1.50%であったとすれば、
保証料率=500万円×1.50%×60/12×0.55=20万6250円
となります。
20万円以上の保証料を一括で支払うのは資金繰り的に厳しいと考える人もいるでしょう。
しかし、制度融資では保証料の軽減措置として、保証料の全額または一部を補助する制度があります。

CFブルー
それをうまく活用していくのがポイントだ!
もっとも、自己資金の負担が大きい、審査期間が長い、日本政策金融公庫に比べて審査が厳しいなどのデメリットがあっても、このデメリットゆえに、制度融資よりも日本政策金融公庫の方が良いということにはなりません。
金利が低く優遇措置があるというメリットを考えると、
- 自己資金で借りられるだけでも優先的に借りる
- 審査期間が長くても申し込みのタイミングを計って優先的に申し込む
- 審査が厳しくても優先的に審査を受けてみる
などして、制度融資からの借入を図った方が良いでしょう。
信用保証料にしても、優遇措置を受けることで低く抑えることができますから、やはり制度融資を優先的に受けるべきです。
さらによい条件で利用するには?

メリット・デメリットを見ただけでも色々な違いがありますが、制度融資と公庫融資には大きな違いは他にもあります。
それは、次の通りです。
- 日本政策金融公庫は「国の政策に基づいて」中小企業を支援している
- 制度融資は「地方自治体の政策に基づいて」中小企業を支援している
この違いから、日本政策金融公庫は、日本全国に支店を持っており、どの支店の窓口に行っても同じパンフレットが置かれていて、融資制度も同じです。
もちろん、金利などの融資条件にも差がありません。
支店は全国にありますから、どこに住んでいる人でも同じ条件での利用となります。

CFレッド
これに対し、制度融資は地方自治体ごとに独自の制度を設けているよ!
したがって、融資を受ける地方自治体によって、融資の種類、金利、融資限度額などの融資条件が異なります。
このため、起業時に会社や事業所をどこに設けるかによって、制度融資の内容も変わってくるのです。
また、制度融資は制度融資でも、都道府県が提供しているものと市区町村が提供しているものとがあります。
例えば、東京都が提供している制度融資がある一方で、新宿区や渋谷区が独自に提供している融資制度もあるのです。
市区町村ごとに財政状況や中小企業への支援状況は異なるため、それぞれで融資条件や優遇措置が異なります。
とはいえ、都道府県と市区町村の制度融資を二重で受けられるわけではありません。
これは、保証するのが東京都信用保証協会だからです。
東京都で保証を受けても、新宿区で保証を受けても、渋谷区で保証を受けても、保証しているのは東京都信用保証協会であり、保証額の上限は決まっています。
このことから、都道府県と市区町村の双方の融資条件や優遇措置を比較して、よりよい条件で融資してくれる制度融資を利用するのがポイントと言えます。
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングについての記事はこちら

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
制度融資の条件と流れ
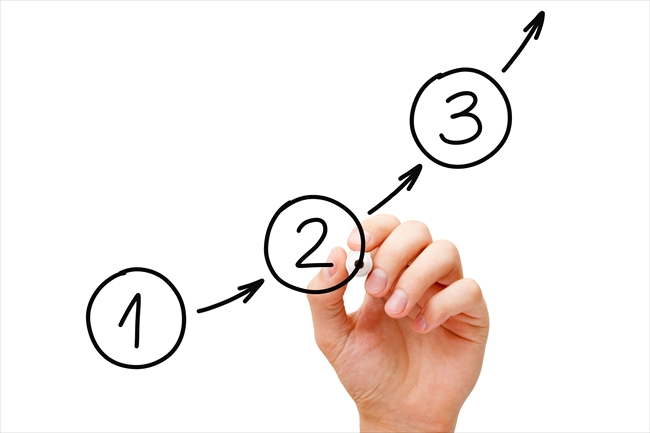
では、制度融資を優先的に受けるにあたり、その条件と流れをおさえていきましょう。
制度融資の条件
制度融資は、地方自治体と信用保証協会が連携して、中小企業や起業家を支援していくものです
支援を受けるためには、次の二つの条件を満たしている必要があります。
- 中小企業者であること
- 信用保証協会の対応業種であること
中小企業者であること
中小企業者であるための条件は、以下の通りになります。
(出典:中小企業庁『中小企業・小規模企業者の定義』)
なお、製造業その他には、次のものを含むとしています。
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- 建設業
- 不動産業
- 運送業
- 印刷業
- 出版業
- 損害保険代理業
このほか、ゴム製品製造業者は従業員数が900人以下である、旅館業の従業員数は200人以下であるなどの特殊な分類があるほか、サービス業と間違いやすい飲食業は小売業に含まれます。
上記の定義に当てはまっていれば、制度融資を受けるための第一の条件はクリアしたことになります。
信用保証協会の対象業種であること
また、制度融資では信用保証協会の保証が必要ですから、信用保証協会が保証対象としている業種であることも条件となります。
保証協会では、基本的に商工業のほとんどの業種を対応としていますが、次の業種は利用できないとされています。
- 農林漁業
- 遊興娯楽業のうち風俗関連営業
- 金融業
- 宗教法人
- 非営利団体(NPOを含む)
- LLP(有限責任事業組合)
詳しくは、信用保証協会の保証対象外業種を参考にするのが良いでしょう。
(URL:http://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_taishougai_list_H30.pdf)
制度融資の利用の流れ
制度融資の利用の流れも、簡単に見ておきましょう。流れは以下の通りです。
- 自治体の窓口に相談をする。
- 自治体の窓口に斡旋を申し込み、紹介状を発行してもらう。
- 紹介状を民間金融機関に持ち込み、融資を申し込む。
- 金融機関の審査を受ける。
- 信用保証協会へ保証を申し込む。
- 信用保証協会の審査を受ける。
- 信用保証書が発行される。
- 融資が実行される。
制度融資を申し込むためには、上記の通り、都道府県と市区町村の制度融資を比較して、よりよい条件の自治体を利用すべきです。

CFイエロー
利用する自治体を決めたら、その自治体の窓口に出向いてから制度融資を相談しよう!
この時、多くの自治体では、中小企業診断士などによって積極的なサポートが期待できます。東京都内ならば、全ての区の窓口に創業アシストプラザが設置されています。
相談する中で制度融資の利用を決めたら、まずは自治体に融資の斡旋を依頼し、紹介状を発行してもらいます。
その紹介状を金融機関に持ち込んで融資を依頼し、金融機関の審査を受けます。
次いで信用保証期間にも保証の申し込みと審査を依頼し、融資が問題なしと判断されれば、保証協会から金融機関に対して信用保証書が発行されます。
ここに至って、ようやく金融機関は融資を実行するという流れとなります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
日本政策金融公庫からも借りよう

制度融資を日本政策金融公庫では、上記の通り、制度融資を優先的に利用すべきです。
しかし、制度融資だけでは十分な借り入れができなかった場合や、制度融資で借りられなかった場合などには、日本政策金融公庫から借りることになります。
日本政策金融公庫よりも制度融資を優先すべきだからと言って、日本政策金融公庫が決して悪いというわけではありません。
日本政策金融公庫のメリット
日本政策金融公庫から借りるメリットには、以下のようなものがあります。
借りやすい
民間の金融機関は、リスクを嫌います。
そのため、基本的に起業を志す人に融資しようとはしませんし、そもそも融資のためのノウハウにも乏しいのが実情です。
したがって、起業しようとしている人が融資を受けるのは困難です。
しかし、日本政策金融公庫は国の政策によって、中小企業者を支援することが目的です。
国の政策では、新規創業による経済の活性化や雇用の創出を目指しているため、新規創業への融資にも積極的です。
だからこそ、創業時に借りやすいということが、日本政策金融公庫の最大のメリットと言えます。
無担保無保証で受けられる
普通、民間の金融機関から借り入れる際には、担保を差し入れたり、保証人をつけたり、信用保証協会をつけたりするのが普通であり、無担保無保証で融資を受けるのは困難です。
しかし、日本政策金融公庫の融資制度の中には、無担保・無保証で融資を受けられる制度もあります。
また、日本政策金融公庫では信用保証協会をつけることもないため、保証料がかからないこともメリットです。
金利が低い

制度融資には劣りますが、日本政策金融公庫の金利は、民間の金融機関の金利よりも低いです。
民間の金融機関では、融資額や会社の実績などに応じて金利が変化し、時に高い金利を支払われなければならない場合もあります。しかし、日本政策金融公庫は融資制度ごとに金利が決まっており、どれも金利は低めに設定されています。
創業時はまだ何の実績もないのですから、普通ならば高い金利が要求されそうなものですが、日本政策金融公庫ではそのようなこともありません。
また、民間の金融機関では、基本的に変動金利での返済になるのに対し、日本政策金融公庫の金利は固定金利です。そのため、安定した長期計画を立て、返済を進めていくことができます。
長期の借入が可能
民間の金融機関では、事業資金を借りる場合、短ければ1年以内、長くても7年以内などの返済になるのが普通です。
あまり長期間になると、その期間中に経営状態が悪化するリスクも高まることから、基本的には長期間での融資を嫌い、できるだけ短めの設定を好むのです。
しかし、日本政策金融公庫では返済期間が長めに設定されています。

CFブルー
場合によっては20年という長期間での借入も可能だよ!
融資制度が豊富
このほか、制度融資との大きな違いと言えば、日本政策金融公庫は融資制度がたくさんあるということです。
それぞれの融資制度には、対象となる要件や融資限度額、金利、返済期間などが異なるため、自分に最も合う融資制度を選べるということも大きなメリットと言えます。
詳しくは日本政策金融公庫の融資制度一覧のページを参考にしてください(URL→https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html)。
上記のメリットにより、日本政策金融公庫が起業時の融資に向いていることが分かります。
政府が100%出資して中小企業を支援する機関であることから、貸し倒れリスクが未知数の創業に対しても融資してくれるため、起業時や独立開業時には積極的に利用を検討すべきです。

CF戦隊
制度融資を利用できなかった場合や、制度融資だけでは開業資金が足りない場合には、ぜひ利用すべきだよ!
日本政策金融公庫の利用条件

地方自治体の制度融資と同じく、日本政策金融公庫でも利用条件が設けられています。
その利用条件とは、次の2点です。
- 中小企業者であること
- 公庫融資の対象業種であること
この二点とも、制度融資の場合とほぼ同じであるため、上記を参照してください。
日本政策金融公庫の利用の流れ
日本政策金融公庫の利用の流れも、簡単に紹介しておきます。
- 日本政策金融公庫の支店窓口に融資の相談をする。
- 日本政策金融公庫に必要書類を提出する。
- 日本政策金融公庫の担当者から面談を受ける。
- 日本政策金融公庫の審査を受ける。
- 問題がなければ融資が決定され、融資が実行される。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
公庫融資も制度融資も、据置期間を賢く利用

ちなみに、日本政策金融公庫も制度融資も、どちらも据置期間というものが設けられていることが多いです。
据置期間とは、元本の返済を据え置くことで、金利だけを支払う期間のことです。
元本返済の負担がないだけに、資金繰りにプラスの効果をもたらします。
会社の経営が厳しく、返済が難しくなった際に金融機関に要請するリスケジュールでも、元本据置の期間を設け、経営再建を図ります。
このことからも、資金繰りが不安定な会社にとって、元本を据え置くことの効果が大きいことが分かるでしょう。
資金繰りには色々な方法がありますが、基本的には会社のお金をうまく回していくための方策を「資金繰り」と言います。
資金繰りといえば、お金を借りるなどして資金を調達することをイメージしがちですが、元本を据え置いて資金繰りをラクにすることも、立派な資金繰りなのです。
創業後間もない頃は、利用できる資金繰りの方法は限られています。
そんな中で、日本政策金融公庫や制度融資において据置期間を利用できることは、非常にありがたい仕組みだと言えます。
据置期間の効果の例
このことは、実際の例を見てみると良くわかります。ある会社の資金繰りにおいて、据置期間を利用した場合と利用しなかった場合を比較してみます。
この会社を起業するAさんは、手元資金を500万円持っており、制度融資では手元資金と同額の500万円、日本政策金融公庫からも補助として500万円を借りました。
生活費のためには、役員報酬として毎年400万円を確保しています。
このとき、1年間の据置制度を利用した場合、1年目に金融機関に支払う利息は50万円となりました。つまり、このことを表にすると、
となり、余裕資金が130万円残ることが分かりました。
この余裕資金は、想定外の出費や売上が予想を下回った場合に役立つことになります。
しかし、据置制度を利用しなかった場合にはどうでしょうか。この場合、
となりました。借入金返済が膨れ上がったことで、60万円の資金が不足していることが分かります。
赤字の補填として定期預金などを確保して起業する人も多いですが、そのような予備の資金を初年度から切り崩していくのは好ましいとは言えません。

CFレッド
、またどこかから(多くは親族などから)の資金調達を図ることになるだろう。
資金が不足する状況は、できるだけ避けるべきです。
なぜならば、会社の失敗の多くは資金不足による焦りから、経営者が判断ミスを犯すことにあるからです。
だからこそ、起業を成功に導くためにも、手元資金はできるだけ余裕を持たせるべきです。
そのためには、据置制度を利用することで余裕を持たせることが大切です。
据置期間利用の注意点
ただし、据置期間を利用するにあたって、注意点があります。
それは、据置期間を利用すると、あらかじめ決められていた返済期間の一部が据置期間となるため、据置期間終了後は元本返済額が増えるということです。
このように、据置期間は、その期間中に事業を軌道に乗せるなどしなければ、据置期間終了後の資金繰りが厳しくなります。
据置期間は安易に利用するのではなく、あくまでも計画的に利用すべきものなのです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
本稿で開設した通り、地方自治体の制度融資は金利が引くことや優遇措置があることなどから、日本政策金融公庫よりも優先的に利用すべきです。
ただし、制度融資は自己資金の必要額が大きいことや審査が厳しいことなどから、希望額を調達できない場合もあります。
そのような場合には、日本政策金融公庫から補完的に融資を受けるのがおすすめです。
このように、地方自治体の制度融資と日本政策金融公庫はどちらも創業時に役立つ融資ですが、まずは地方自治体の制度融資を、次に日本政策金融公庫を利用すると考えましょう。
創業時の賢い融資の受け方!まずは制度融資から受ける理由