銀行から融資を受けた資金をどのように使うかということは、銀行の融資判断で非常に重要になるポイントです。
これを、資金使途と言います。
資金使途を正しく伝えることができれば、銀行は融資に積極的になるものです。
しかし、正しく伝えるためには、資金使途に応じた資料が必要になり、資金使途の内容と銀行からの観られ方を知っておく必要があります。
資金使途とは?

資金使途とは、読んで字のごとく、資金の使い道のことです。
融資を受ける際には、銀行に対して、融資を受けた資金をどのように使っていくのかを説明します。
銀行は資金使途を必ず聞いてくるからです。
融資を申し込んだ会社は「事業を営む上で資金需要が生じ、それを賄う資金がなかったり」「長期的に見ていずれ資金不足に陥る可能性があったり」した場合に、銀行に融資を申し込みます。
銀行は、次のようなことを聞くことで融資の判断をしていくことになります。
- なぜ資金が足りないのか
- どれくらい足りないのか
- 融資を受けた時にどのように使うのか
- それが経営にどのような影響を与えるのか
資金を必要としている理由がまともなものであり、融資を受けた時の資金の使い方にも問題がなければ、融資によって事業がスムーズに回っていきます。
利益を出すこともできるのです。
利益が出れば、銀行はそこから元金と利息を返済してもらうことができますから、融資をしても良いという判断になります。
しかし、中小企業の中には、資金使途が曖昧なまま融資を受けようとする会社もあります。
そのような会社では、運転資金として借りたはずの資金を、経営者個人が生活費や遊興費に充ててしまったり、個人的な借金の返済に流用してしまったりすることがあります。
これでは、経営改善のために融資した資金が正しく使われず、相変わらず資金不足の状態が続きます。
もちろん利益も思ったように出ていきません。

銀行にとっては避けるべき、不良債権が出てくることになるのです。
だからこそ、融資審査では色々な項目が審査される中で、資金使途も厳しく審査されることになります。
提出した決算書で、財務内容や業績が良かったとしても、資金使途が適当ではないと思われれば、銀行は融資をしないものなのです。
そこで、資金使途にはどのようなものがあるかを理解し、自社で生じている資金需要はそのうちのどれであるかをきちんと把握しましょう。
適切な資料を揃えて、銀行に正しく説明できるようにしておく必要があります。

ファクタリングについての記事はこちら

運転資金には色々なものがある
運転資金とは、会社を運転していく、事業を営んでいくにあたって必要な資金のことです。
会社の事業では「原材料を仕入れ、製品を製造して販売したり、商品を仕入れて在庫として販売したりする」ことで、初めて売掛金や受取手形が発生します。
それを支払期日に現金で回収し、利益が出ます。
しかし、売掛金や受取手形の回収日までは、自社が取引先の代金を立て替えていることになります。
この時、原材料や商品が現金に変わるまでの間、会社は現金がない状態で営業を続けていくことになります。
現金が乏しい状態で営業を続けることもあり、資金需要が発生します。
その際に、事業を回すために使う資金のことを運転資金と言うのです。

建設業などでは、工事に必要な材料費や外注費を先に支払い、工事代金を分割で受け取るのが普通です。
そのため、受取までの期間内には運転資金が必要になります。
このほか、アパレル製造業などがそうですが、季節によって資金繰りが大きく変化する業種でも、運転資金の重要性が高いです。
売れる季節に備えて在庫を備蓄しようと思えば、製造量や在庫量が増えて費用がかさみます。
売れる季節までは資金が回収できないため、運転資金が重要です。
運転資金の分類
会社が事業を進めていくために必要となる運転資金は、細かく分類すれば、以下のように色々な運転資金があります。

経常運転資金
上記の通り、原材料や商品を販売して売掛金が発生します。
それを回収するまでの期間に発生する資金需要を賄うための資金を運転資金と言いますが、正確には「経常運転資金」と言います。
経常運転資金がどのくらい必要であるかを知るためには、以下のような計算式によって計算します。
(売掛金+受取手形+棚卸資産)-(買掛金+支払手形)=経常運転資金
会社は、棚卸資産から売掛金が発生し、現金に変わるまでのあいだ、経常運転資金によって立て替えます。
それだけの十分な現金があるならば問題ありませんが、そうでないならば銀行から融資を受けることで、事業を回していきます。
この時の融資は「手形貸付・証書貸付・手形割引」などの方法があります。
手形貸付は、短期間(1年以内)での一括返済を前提としており、証書貸付は、長期(1年以上)の融資を前提としています。
手形割引とは、保有している受取手形を銀行に資金化してもらうものです。
手形貸付のことを、コロガシということもあります。
これは、手形貸付が短期の融資であり、一括返済が完了すると、また同じ条件で融資を受けることができるものだからです。
返済期日に一括で返済する融資であり、返済期日まで分割を行わないということは、銀行にとってはリスクが高い方法です。
分割返済ならば、銀行は少しずつ回収していけるため、リスクを下げることができます。

したがって手形貸付は、主に銀行から評価が高い会社が利用できる方法です。
多くの会社は証書貸付によって融資を受けることになります。
増加運転資金

経常運転資金として融資を受けたものの、何らかの理由によって、当初想定していた以上の資金需要が発生した時に、さらに融資を受ける必要があります。
これを、増加運転資金と言います。
なぜそのような事態になるのか言えば、いくつかの理由が考えられます。
- 売上の増加によって売掛金や受取手形も増加し、また需要増によって棚卸資産も増加した結果、経常運転資金がもっと必要になった。
- 売上は変わらなかったものの、取引先の売掛金の支払いが延び、しかし平常の事業のために棚卸資産を確保し、売掛金や受取手形は発生した結果、経常運転資金がもっと必要になった。
このような理由によって増加運転資金が必要になることは、普通に考えられることです。

しかし後者の場合、取引先の与信管理ができていなかったという可能性もあり、その場合には回収不能リスクも出てきます。
そのため、ネガティブに捉えられることもあります。
どちらの理由にせよ、どのような経緯でどれくらいの増加運転資金が必要となり、増加分の追加融資を受ければ経営にどのような好影響がもたらされるのかを、銀行に説明する必要があります。
つなぎ資金
つなぎ資金というキーワードは、よく聞くことがあると思いますが、経常運転資金とつなぎ資金を混同していることも多いです。
つなぎ資金は運転資金の一種であり、一時的に経常運転資金が足りなくなった場合に、それを補填する場合に融資を受けるものです。
ならば増加運転資金と同じではないかと思うかもしれません。
同じように考えてもそれほど問題ないと思いますが、あえて違いを説明するならば、
- 増加運転資金→売上や在庫の増加、取引環境の変化などによって、その増加分が継続的に生じる可能性がある資金需要を賄うもの
- つなぎ資金→売掛債権回収日よりも買掛債務支払日が多少先行した場合など、一時的に生じる資金需要を賄うもの
という違いがあります。

例えば、ある会社で一時的に仕入れを増やす必要がり、月末の売掛金回収によって支払えることが分かっているとします。
この時、つなぎ資金の融資を受けて仕入れを行い、月末の売掛金で返済することになります。
つなぎ資金は、融資を受けたのち、それほど日を置かずに返済するものですから、手形貸付で行われます。
支払いも一括払いか、分割しても2~3回の分割です。
支払期日は、売掛金が入るとわかっている日に定めます。
売掛金の支払いは、長くても数ヶ月先ですから、つなぎ資金は数週間や数ヶ月で返済することになります。
つなぎ資金の融資を申し込んだ時、銀行は短期間で確実に返済を受けられることを確認します。
したがって、会社側としては「売買の際の契約書や注文書、請求書の控え」などを根拠として、売掛金が「いつ、いくら入るか」を証拠と共に提示する必要があります。

現在の資金状況はこうなっている。そのためこれくらい資金が不足している。
つなぎ資金の融資を受ければ資金状況がこうなって経営が回り、 ○月には売掛金がこれくらい入り、銀行への返済をすれば資金状況はこうなる。
このように説明すれば、説得力があります。
季節資金

季節によって在庫量や仕入れ量が変化する業種では、支払いが多くなる時期が生じます。
もちろん、回収が多くなる時期も生じ、この差が激しくなればなるほど、季節性の資金需要が増えます。
支払いが多くなる時期には現金が不足し、回収が多くなる時期には現金が潤沢になるわけです。
ですが、それでは経営がうまく回っていかないこともあります。
そこで、現金が不足している時期に融資を受け、現金が潤沢な時期に返済を行います。
これを季節資金と言います。季節性のあるつなぎ資金と考えることもできます。
季節資金が必要になる業種にも色々ありますが、アパレル製造業はその代表的なものです。
例えば、秋から冬にかけての販売に備え、6~8月にたくさん製造して在庫を備蓄するとなると、これらの月では支出がかさんで資金が不足します。
季節資金の融資を受けるにあたって、銀行に説明する際には、資金繰り表によって説明するのが良いでしょう。
現時点での資金状況はこうなっている。 ○月から○月にかけて季節性の資金需要が発生するが、このままではその資金需要に応えられない。
そこでこの時期にこれくらいの融資を受けると、資金状況はこのようになり、経営が回っていく。
そして○月から○月にかけて売掛金を回収し、これくらいの現金が入り、返済も可能となる。
このように説明すれば、説得力があります。
また、そのような業種では、毎年決まったパターンで資金繰りしていることも多いものです。
ですから、過去の実績を提示しながら説明すれば、銀行は融資を出しやすくなります。
納税資金
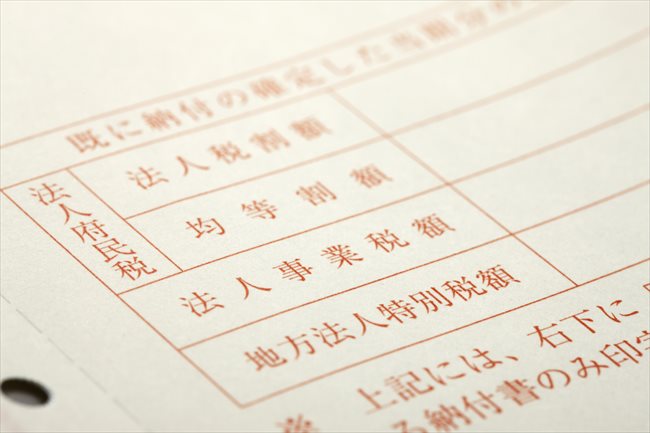
納税資金とは、納税のために必要となる資金を賄うもののことです。
これも、会社の資金需要の中ではよくみられるものです。
会社が支払う法人税は、決算日の2ヶ月後が納付期日に設定されています。
金額によっては、期の途中で中間納税が発生します。
法人税の納税額は、利益が大きいほど高くなっていきます。
法人税のために、普段から資金の積み立てをしておく会社もありますが、多くの会社ではその余裕がなく、法人税の納付期日が近づいてから、融資を受けるなどして支払うことを検討します。

なぜならば、他の資金使途よりも使い道が明確だからです。
納税額が大きい会社ならば融資額も大きくなりますが、それだけ利益を出しているという証拠にもなります。
銀行としてはプラスに捉えやすいです。
納税資金の融資を受ける際の注意点は、早めに融資相談を行なうことです。
納税期日は確定しており、それに遅れると滞納とみなされるので、必ずその日までに融資を受けて支払う必要があります。
だからこそ、税理士に相談し、今期の経営結果では法人税がどれくらいになるかを算出してもらいます。
それをもとに銀行に早めに融資を申し込んでおくことが大切です。
それによって銀行が審査を行い、融資を出せるとわかったならば、納税額が確定した後に納税通知書などを提示することで、融資を出してもらうことができます。
ちなみに、納税資金の返済期間は、6ヶ月に設定されることが多いです。
消費税の納付は融資できない


そもそも、消費税は預り金の性質があります。
消費税の納付に困っているということは、預り金として積み立てておくべき消費税を使い込んでしまっているということです。
それを融資によって銀行が立て替えるのは好ましくないと考えるからです。
賞与資金

賞与資金とは、従業員に賞与を支払うために融資を受けるものです。
賞与を支払うと、手元資金が薄くなってしまい、資金繰りに悪影響を与えることになります。
事前に融資を受けて賞与を出すことで、それを防ぎます。
賞与資金の返済期間は次の賞与までとなっていることが多く、その期間内で分割して返済していきます。
ハネ資金
資金使途のうち、銀行の建前上、表向きは認めていないものの、暗黙の了解として融資されるものがあります。
その一つがハネ資金と呼ばれるものです。
ハネ資金とは、銀行から長期的な借り入れを行い、それを計画的に返済していったところ、いずれ現金が尽きてしまうことがわかったとき、経営が回るように補填する資金のことです。
融資を受け、返済を続けるうちに資金不足に陥るということは、年間返済額が年間キャッシュフローを超えているということです。
これは、慢性的な資金不足に陥っている状況であり、銀行からすれば好ましくありません。
逆に、1年間のキャッシュフローが1年間の返済額を超えるならば、キャッシュフローの中から十分に返済していくことができますから、融資審査はかなり通りやすくなります。
しかし実際には、それができていない会社が多いのが実情です。

融資審査の際に銀行は、長期的なキャッシュフロー計算書も審査します。
キャッシュフロー計算書を見れば、融資をしても徐々に現金残高が減っている様子が分かることもあります。
本来、返済はキャッシュフローの中から行なうものですから、これは銀行にとって好ましくないことであり、融資を断る原因にもなります。
しかし、その会社が複数の銀行から融資を受けており、現金不足に陥った場合にも支援が受けられる可能性が高いならば、
「当行からの融資は、将来的に資金不足に陥った場合にも、他行からの融資によって賄われ、問題なく回収できる可能性が高い」
と判断することになります。
このような理由で、本来ならば将来的に資金不足になると思われる会社が、実際に資金不足に陥ったときに出される融資をハネ資金と言うのです。
もちろんこれは、不足するべくして不足した資金を融資によって賄うものです。
さらにハネ資金は他行への返済に充てられるため、好ましいものではありません。
会社がやっていることは自転車操業そのものであり、銀行が最も嫌うところのものです。

ハネ資金と言うのも俗語のようなもので、普通は「支払手形決済のための運転資金」といった名目で融資が行われます。
しかし、ハネ資金を必要とする財務体質は好ましいとは言えません。
また、銀行が必ずハネ資金を出してくれるとは限らず、もし出してくれなければ返済が滞ってしまいます。
ハネ資金を必要とした時には、融資を申し込むほかないでしょう。
しかしいずれはハネ資金なしでも十分に経営が回っていくように「利益率を改善したり、利益率は同じでも売上を伸ばしたり、経費削減に努めたりする」ことによって利益を増やし、キャッシュフローを向上させていく必要があります。
ハネ資金と言う、本来好ましくない融資を受けやすくするためには、経営計画書によって将来的なキャッシュフローの向上をアピールします。
他行が融資に積極であることをアピールしたりすることが効果的です。
後ろ向き資金

色々ある資金使途の中でも、もっとも融資が通りにくいのが後ろ向き資金と呼ばれるものです。
これはその名の通り、後ろ向きな、あまりよくない理由で生じた資金需要を賄うためのものです。
よくあるのが、次の事態に陥った時の穴埋めをする融資です、
- 会社が過剰な在庫を抱えてしまった
- 売掛先が倒産して入ってくるはずのお金が入ってこなくなった
- 赤字になってしまった
これは、返済財源が見えないため、融資を受けにくくなって当然です。
例えば、売掛先が倒産して、回収できるはずのものが回収不能となった。そのために資金繰り困難に陥ったとすればどうでしょうか。
融資を出しところで、回収できなかったお金は相変わらず回収できないため、返済財源が見えてきません。
企業は、事業の結果として得られた利益を返済に充てます。
しかし、過剰在庫を抱えて利益が出にくくなっている、売掛先が倒産して利益が失われた、利益が出ないからこそ赤字になったなどの事情を抱えた会社は、返済財源が見えません。
もちろん、時間をかけて経営を立て直していくことはできるでしょうが、返済期間中に経営状況がより悪化する可能性も高いです。

後ろ向き資金の融資を受けるためには、後ろ向き資金を必要とした経緯を説明しましょう。
それと同時に、経営計画書を提示して、経営を立て直して返済を進めていけることを納得してもらう必要があります。

何らかの担保を求めたり、担保がない場合には、信用保証協会保証付融資を利用したりすることによって、融資を受けることができます。
銀行としても、その融資を行わなければ、企業の経営が立ち行かなくなり、既に融資したものが貸し倒れになることはわかっています。
そうなっては元も子もありませんから、何らかの方法によって追加融資を出すのです。

しかし、追い貸しをしなければ銀行も困るからと言って、何度も繰り返して追い貸しされるようなことはありません。
基本的には、銀行は渋々融資しているのですから、いつ融資が出なくなってもおかしくない状況です。
いずれ銀行が、「いずれ倒産は避けられないだろう、これ以上追い貸しを続けても意味はないし、貸し倒れの際の損害が膨らむだけだ」と判断すれば、融資は出なくなります。
したがって、追い貸しを受けなければならなくなったときは、追い貸しを受けられるうちに、できるだけ早く経営を改善していかなければなりません。


設備資金

設備資金とは、設備のために必要となる資金のことです。
設備費用と言えば、工場の機械設備にかかる費用などをイメージする人も多いと思いますが、それ以外にもあるのです。
- 事務所や店舗内の設備費用
- 事務所や店舗や工場を建てるための費用
- それらを建てるための土地購入費用
これらも設備資金にあてはまります。
設備を購入するためには、かなりまとまった資金が必要となります。
会社が内部留保している資金だけで賄うことは難しいため、融資を受けるのが普通です。
中には、無借金経営を重視するあまり、自社の資金だけで設備投資を行なおうとする経営者もいます。
しかし、多額の支出を行えば、それによって資金繰りが悪化してしまうケースが非常に多いです。
潤沢な資金があるとしても、将来にわたって資金が潤沢であり続けるとは限りません。
たまたま、一時的に販売が上手くいき、たくさんの売掛金が入ってきただけと言う可能性もあります。
そのため、設備資金の融資を受けたほうが好ましいでしょう。
設備資金は長期返済


短期の返済は不可能な多額の融資を受けることになりますから、短期返済になることはまずありえません。
また、設備投資には多額の資金が必要となりますが、それによって企業は長期間にわたって効果を得ることができるものです。
返済の原資となる利益は、設備投資によって長期間にわたってもたらされるものですから、そのような意味でも長期返済になっています。
設備を導入した会社は、長期にわたって減価償却を行なっていきます。
減価償却は、実際に現金を支出するわけではないものの、費用として計上していくものですから、減価償却分を返済に充てることが可能となります。
したがって、長期返済であることは会社にとっても都合の良いことですから、できるだけ長期での返済プランを立てたいものです。
設備資金の注意
設備資金は多額の資金を融資しますから、銀行も注意深く融資します。
企業が設備の導入先に支払いを済ませると、受け取った領収書を銀行に提出する必要があります。

これによって銀行は、設備資金のために行なった多額の融資が、他の目的に流用されていないことを確認します。
もし流用が発覚すれば、銀行から一括返済を求められ、今後の融資も受けられなくなります。
経営者の中には、運転資金で受けた融資を設備資金に回そうとする人がいます。
設備資金として融資を受けると、領収書の提出や銀行員の調査などが行われるため、それを面倒がるからです。
確かに、設備資金では提出書類も多くなって面倒なことも多いです。
しかしその反面、長期での返済が可能になるというメリットもあります。
長期で返済したほうが、資金繰りに与える影響は少ないのですから、設備資金として融資を受けたほうが良いでしょう。


投資資金

投資資金とは事業拡大のために必要となる資金のことです。
新規の事業を展開する、海外に進出する、新分野に進出するなどの場合には資金を必要としますから、それを融資によって賄うことを考えます。
このような投資によって、会社は事業を拡大していき、利益を高めていくことができます。

投資資金は、事業展開や企業買収といったことに使われる資金ですから、かなり金額が大きくなります。
そして、うまく拡大していくことができれば、長期間にわたって利益を増やすことができますから、長期での返済となります。
しかし、投資はすべてうまくいくものではなく、失敗する可能性もあるものです。
大きな勝負でもあり、それに失敗したことで衰退していく会社もありますから、銀行は投資資金の審査をかなり慎重に行います。
審査では「その投資によってどのような効果があり、どのような計画によって進めていくか」を説明することで、銀行にプランを納得してもらう必要があります。

事業計画書では、その投資の効果がどれくらいの期間で出てくるのかを示します。
新規に始める事業や新規に進出する分野が「既存の事業の足を引っ張ることがないこと」むしろ相乗効果をもたらすことなどを説明するのが効果的です。
審査に通らないケースとしてよく見られるのが、既存の事業が安定していないことです。
既存の事業が赤字の場合など、一発逆転を狙って投資資金の融資を受けようとする経営者もいますが、銀行がそのような冒険に乗っかってくることはありません。
それよりも、既存事業を立て直すのが先であると考え、融資を断ってくることでしょう。
逆に、既存の事業が着実に利益を生んでおり、事業拡大しても問題ないと思われる場合には、銀行は融資に積極的になります。
融資を受けることに成功したら、その投資の効果がどのように出ているか、定期的に銀行に報告するのが好ましいです。
そうすることによって、銀行との信頼関係を構築することができれば、その後の融資にもプラスになります。

認められない資金使途の例

ここまで、色々な運転資金、設備資金、投資資金と見てきました。
融資を申し込んで銀行に資金使途を説明するときには、
- なぜ運転資金や設備資金必要可
- なぜ投資資金が必要か
きちんと区別をして、それぞれに適した形で相談することが大切です。
上記のような資金使途であれば、たとえ後ろ向き資金のようなネガティブなものでさえ、融資が通る場合があります。
では逆に、融資が絶対に通らない資金使途には、どのようなものがあるのかを簡単に見ておきましょう。
本業とは関係のない資金

例えば、当初のアベノミクスのように株式市場の状況がかなり良く、ほとんど何を買っても利益が得られるような相場であったとしましょう。
お金を借りて株式投資をし、大いに利益を出していきたいと考える経営者がいるかもしれません。
しかし、それは本業とは無関係であり、投資に失敗する可能性も十分にありますから、そのようなことに銀行が融資することはありません。
経営者の個人的な資金
経営者が、個人的に銀行に申し込んでマイカーローンを組んだり、住宅ローンを組んだりするのは問題ありません。
しかし、会社と経営者個人のお金が混同されているような会社では、経営者が個人的な用途で使う資金を、会社で借りようとすることがあります。
このような資金使途も、銀行は認めません。
転貸資金
関係会社が資金繰り困難に陥っており、財務内容や業績も悪いく融資を受けられない場合があります。
その別の会社が融資を受けて転貸しようとすることがあります。しかし、これも銀行が認めない資金使途です。
資金使途違反
もし、運転資金や設備資金などの名目で受けた融資を、別の目的に流用していたり、上記のような銀行が認めない目的に流用していたならば、銀行から資金使途違反を犯したとみなされます。
融資の際に話していた資金使途と異なる内容に使ったということは、銀行を騙したということです。
会社と企業の信頼関係によって融資が行われたにもかかわらず、会社側からその信頼関係を壊す行動をとったのですから、銀行はその会社へ二度と融資をしなくなります。

まとまった融資を長期返済の約束で借り入れ、他の目的に流用して手元にはない状態で一括返済を求められれば、資金繰りが困難になることは目に見えています。
あくまでも、銀行に説明した通りの資金使途で使っていくことが大切です。
まとめ
会社は、資料を揃え、資金使途について説明していきます。
この説明が上手くできれば、財務内容や業績が少々悪い会社でも、融資に積極的になることがあります。
もちろん、決算書の内容は非常に重要なものですが、資金使途はそれに次いで重要なのです。
融資を受けるためには、資金使途に納得してもらうよう、資料をきちんとそろえていく必要があります。
そのためには、自分の必要としている資金の内容を詳しく知っておいた方が良いですから、本稿の内容を参考にして欲しいと思います。



