
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
流動資産と流動負債の関係

―――この3つを、どのように見ていきましょうか。
具体的な例で考えていきましょう。
仮に、
- 流動資産:40%
- 固定資産:60%
- 流動負債:30%
- 固定負債:45%
- 資本金:25%
という会社があったとします。
―――流動資産と流動負債の比率は2:1ですね。
そうですね。
流動資産と流動負債の比率を見たとき、少なくとも流動資産のほうが大きくなっていることは、「借りられる決算書」の絶対条件だと言われています。
この比率を流動比率と言いますが、2:1は理想的といわれる配分ね。
―――流動比率が2:1の会社は、そうそうないと思います。
なかなかありませんね。
しかし、流動資産のほうが大きい状態に持ち込むことは充分に可能でしょうし、そうなっていなければ融資以前の問題です。
―――流動資産のほうが低いと、なぜ問題なのでしょうか。
それは、「流動資産のほうが大きい」という状態は、当面の決済能力に問題がない状態だからです。
流動資産の内訳を見てみると、売掛金や受取手形なども構成要素になっています。
一方、流動負債は、短期間で出ていく現金のことです。
つまり、流動資産が流動負債より小さい状態であれば、近々入ってくる現金よりも、近々出ていく現金のほうが大きい状態ですよね。
近い将来における支払い能力に問題あり、ということになります。
銀行が「当面の資金繰りに問題ない」とみなすためには、どうしても流動資産が流動負債よりも大きくなければいけません。
それが、「借りられる決算書」の条件と言えます。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
固定資産と資本金の関係

―――では、固定資産と資本金の関係はどうでしょうか。
理想的なことを言えば、銀行などから借りることなく、返済の必要がない資本金で設備投資が全て賄える状態です。
借金が少なくなるのですから、資金繰りの安定性は高いですよね。
ですから、固定資産が資本金よりも小さい状態が理想的と言えます。
―――例の会社では、固定資産60%、資本金25%になっていますね。
中小企業の財務を見たとき、固定資産が資本金より小さいというケースはほとんどないでしょう。
私がこれまで見てきた会社にも、そのようなケースは1社もありません。
ですから、固定資産と資本金の関係を考えるとき、資本金と固定負債の合計額で考えます。
固定負債は、返済期間が1年以上の借入金です。
資本金だけで設備資金をカバーするのは現実的ではなく、実際には足りない部分は固定負債でカバーしているのですから、資本金プラス固定負債で考えるわけです。
―――「固定資産と資本金の関係」から、「固定資産と資本金+固定負債の関係」になると、銀行の判断には大きく影響しないのでしょうか。
短期の負債ならば、短期間でまとまった償還が必要になりますから、短期間での資金繰りにそれなりの影響があります。
しかし固定負債は、長期にわたって返済していくものですから、資金繰りに与える影響は安定しています。
ですから、固定資産が「資本金と固定負債の合計」より小さければ、大きな問題はないと考えます。
―――固定資産が資本金と固定負債の合計より大きい状態は、どうして不安定と言えるのでしょうか。
それは、固定資産の一部を短期の流動負債で賄っている状態だからです。
この図を比べると分かりますよ。(貸借対照表を簡単に図示してもらう)
この図は、固定資産が資本金+固定負債より小さいです。
つまり、安定的な資金で設備資金をまかなっています。
しかしこの図は、固定資産が資本金+固定負債より大きいです。
超過した固定資産の資金はどうやって賄われているか・・・流動負債ですね。
固定資産とは、長期にわたってじわじわと経営にプラスになる資産だ。
長期にわたってじわじわ返済していくならまだしも、短期間で返済しなければならない資金で賄っていると、資金繰りには良くない影響を与えます。
―――その場合、どう対処すべきでしょうか。
この図によって単純に考えるならば、固定資産が資本金+固定負債の合計より小さくなればいいのですから、長期の借入れを増やすのがいいでしょう。
ただし、借入金が増えると支払利息も増えますから、その点もよく考えるべきでしょう。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
総資産と資本金の関係
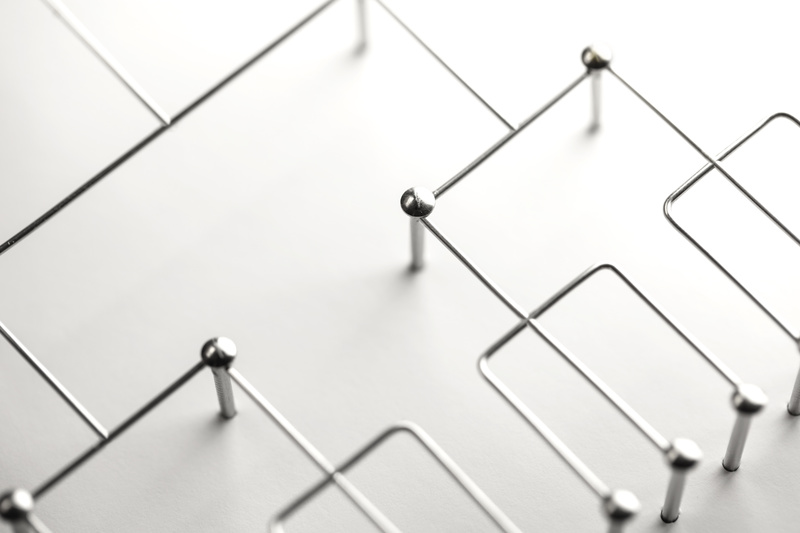
―――最後に、総資産と資本金の関係について教えてください。
では、まずはこの図から見てください。
右側の合計は総資産、そのうち右下は資本金です。
この図のように、総資産の合計が5、資本金が1の場合、総資産と資本金の関係は5:1で、資本金は20%となります。
総資産に占める資本金の割合を、自己資本比率と言いますね。
自己資本比率が20%の会社は、一般的にはあまり良くないです。
―――理想的な自己資本比率はどれくらいですか?
30%以上あれば合格というのが、銀行の見方だと思います。
ただ、中小企業では30%を切っているケースもよく見ますし、業種や業態によっても変わりますから、一概に悪いとは言い切れないでしょう。
一般的には30%以上が望ましい、しかし中小企業ではそれをクリアできない会社も多いので、30%を大きく下回らないように気を付けて、できるだけ上回るようにするという意識づけが重要でしょう。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
本稿で解説した通り、借りられる決算書を作りたいならば、
という2点を確実にクリアし、なおかつ
の条件もできる限りクリアすることがポイントです。

CF戦隊
この3点をクリアしていれば、借りられる決算書であると言えるだろう!
今後、融資をスムーズに引き出していくにあたっても、この3点を好ましい状態に近づけるように工夫していくことによって、融資を受けられる可能性は大きく高まるはずです。
借りられる決算書とは?銀行員にインタビューしてみました













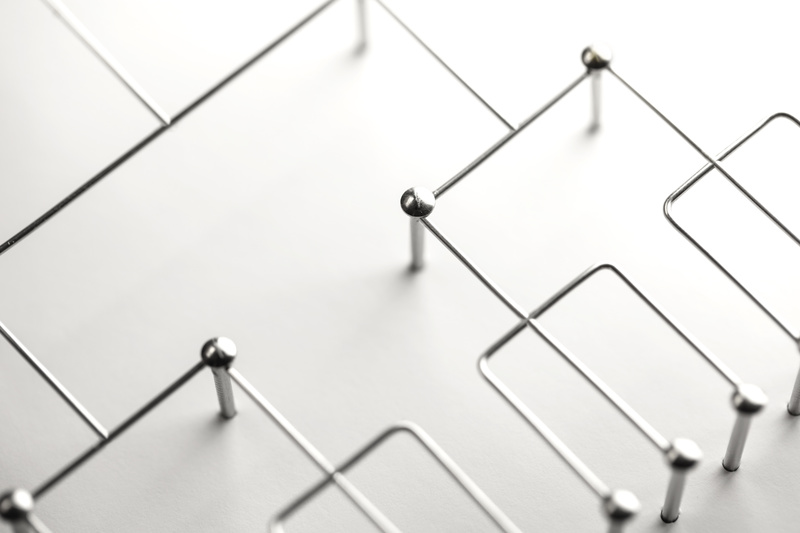




コメント