融資の際「決算書が重要である」ということは、既にご存知の方も多いと思います。
しかし「融資がなぜ重要であり、どのような影響を与えるものであるか」また「銀行はどのように審査に活用して、融資の判断に反映しているのか」を詳しくは知らないという人も多いと思います。
そこで本稿では、決算書が融資審査に与える影響がどの程度であるか、そしてどのように影響をもたらすかを解説していきます。
決算書の重要性

融資を受ける際には、銀行は様々な点を審査します。
その会社や代表者の背景はもとより、融資を受けた資金をどう使うのか、提出書類の内容はどうか、日々の取引の内容はどうか、経営計画どうかなどなど、多岐にわたって審査していきます。
それらの審査項目には、当然ながら重要度・影響度に差があります。
中でもかなり重要と言えるのが、決算書の内容です。
融資を簡単に受けられる会社も、融資が難しい会社も、決算書の内容によってその判断がなされているわけですから、大きな影響力を持つことがわかります。
決算書の内容が悪ければ、融資を受けることは困難になります。
決算書は、それが粉飾決算でないならば、一定期間の経営の結果が決算書に表れるものであり、一時的な努力では良い決算書はできません。
そのため、融資審査に有利になる決算書を提出するためには、日頃からの経営努力が求められます。
融資を受ける時のタイミングで、融資を引くためにどのような努力をするかが重要だと考える経営者も多いです。
しかし、融資審査を受けるタイミングで努力をするよりも、日頃から努力をしておくことの方がはるかに重要なのです。
とはいえ、良い決算内容を決算書にしっかりと反映すること、または良くない決算内容でも決算書の作り方を工夫することによって、融資を受けやすくすることは可能です。
その方法を知るためには、決算書の中心となる貸借対照表と損益計算書における、それぞれの科目を銀行がどう見るかということを理解しておく必要があります。
基本的に銀行員は、以下の流れで決算書を見ていきます。
- 貸借対照表の純資産、借入総額などを見る。
- 損益計算書の売上、営業利益、経常利益などを見る。
- 貸借対照表の各勘定科目を見る。
したがって本稿では、この流れに沿って解説を進めていきます。

ファクタリングについての記事はこちら

貸借対照表で重要な科目

まず銀行員は、決算書の審査をするにあたり「貸借対照表」を見ます。
貸借対照表の中で最も重要なのは、純資産です。
貸借対照表には純資産が記載されていますが、純資産とは総資産から総負債を差し引いたものです。
つまり、総資産から総負債を差し引いた時にマイナスになれば、それは債務超過状態だということが分かります。
貸借対照表における純資産がマイナスになっていれば、その企業が保有する資産を全て売っても、負債が残る状態ということです。
そのような企業に対しては、銀行は融資したくないと考えます。
しかし純資産の科目は、単にプラスかマイナスかという見方だけでは不十分です。
それに加えて、以下の観点を持ちましょう。
自己資本比率
純資産に関連して考えておきたいのが、自己資本比率です。
自己資本比率とは、純資産を総資産で割ることで得られるものであり、総資産に占める純資産の割合を示すものです。
自己資本比率が高ければ高いほど、財務体質が健全であると判断され、融資にも有利になります。
株式投資などでも、企業の財務体質が強いことは重要ですから、自己資本比率が60%以上は欲しいなどと考えられています。
もっとも中小企業の融資審査においては、20%以上あればまず安全圏と言えるでしょう。

借入金月商倍率
銀行員が最初に貸借対照表を見る時「純資産はプラスか、実質債務超過でないか、自己資本比率はいくらか」と見たのち、借入金総額を確認していきます。
これは、貸借対照表の負債の部によって確認していきます。
短期借入金と長期借入金の合計が、借入金総額となります。
もっとも、借入金総額は企業の規模によっても大きく変わりますから、「借入金総額がいくらか」ということよりも、「借入金総額は月商の何倍か」という見方になります。

例えば、月商が2000万円、借入金月商倍率が5000万円の企業があったとします。
この場合の借入金月商倍率は、2.5倍であることが分かります。
言い換えれば、月商2.5ヶ月分=借入金総額です。
借入金月商倍率には、適切な水準がありますから、それを大きく超える場合には融資審査に悪影響をもたらします。
一般的には、借入金月商倍率は次のように判断されます。
- 2倍未満ならば、ちょうどよい
- 2倍以上4倍未満ならば、やや多い
- 4倍以上ならば、多い
もっとも、不動産賃貸業など、業種によってはどうしても借入金総額が多くなり、借入金月商倍率が高くなる企業もあります。
その場合には、また別の水準で見ていくことになります。


損益計算書で重要な科目

貸借対照表を見たら、次に損益計算書を見ていきます。
損益計算書とは、その企業の一定期間の経営成績を表すものです。
これによって「どれくらいの利益あるいは損失が、どのように出たか」を知ることができます。
つまり、その企業の「稼ぐ力」を知ることがでるのです。
営業利益・経常利益
特に銀行が注目するのは、営業利益と経常利益です。
利益の科目の中には、「当期純利益」というものもありますが、これは有価証券の売却や不動産の売却その他の理由で、特別利益や特別損失が発生すれば、大きく左右される科目です。
ある特定の期だけ当期純利益が伸びることもありますから、銀行はそれほど重要視しません。
それよりも、営業利益と経常利益を見ることによって、稼ぐ力を見ようとします。
営業利益とは、営業活動によって得らえた利益のことであり、事業に企業の稼ぐ力を見るものです。
一方、経常利益は財務活動によって得られた利益のことであり、稼ぐ力をより広く見るものです。

なぜならば、銀行が融資した際の元金と利息は、企業が得た利益の中から支払っていかなければならないからです。
営業利益や経常利益がマイナスになり、稼ぐ力がないとわかれば「それは返済する力がない」ということでもありますから、銀行は貸し渋るのです。
もちろん、営業利益と経常利益は、単にプラスであるだけではなく、大きければ大きいほど融資に有利になります。
利益率

利益率とは、売上高に占める利益の割合です。
この割合が高ければ高いほど、企業は効率的に利益を出して稼いでいることが分かります。
営業利益を売上高で割ったものを売上高営業利益率といい、こちらは5%以上あるのが好ましいです。
経常利益を売上高で割ったものを売上高経常利益率といい、こちらは3%以上あるのが好ましいとされています。
損益計算書への質問
貸借対照表では、資産価値や負債の有無を調べていくのに対し、損益計算書は前期に比べて損益がどのように変化したかを見ていきます。
それと同時に、その変化を踏まえて、経営者は今後どのようなビジョンを抱いているのかも重要です。
そのため、それをもとに銀行員と会話する中で、銀行員からの質問に答えられないようでは、非常に印象が悪いです。
銀行員は、「この経営者は損益をきちんと把握しているのだろうか?損益を踏まえた経営ができていないのではないか?」などと怪しむため、審査に悪影響になります。
ちなみに、銀行員が質問してくるとすれば、おそらく以下のようなことです。




損益計算書の内容をきちんと把握していれば、これらの質問に答えられるはずです。


貸借対照表の各勘定科目

上記の通り、銀行が決算書を見る時には、まず「貸借対照表の純資産と借入金月商倍率」、次に「損益計算書の営業利益と経常利益」それぞれの売上高に対する倍率などを調査します。
この数値が良くなるように日頃から経営努力をしていれば、銀行もスムーズに審査を通しやすくなります。
これが、融資を受けるために最も重要なことと言っても、過言ではないかもしれません。
しかし、これらの情報だけで、銀行は融資を決定することはありません。

例えば、純資産がプラスであっても、実質的に債務超過状態になっていることがあります。
これを、実質債務超過と言います。
なぜ純資産がプラスなのに債務超過になるかと言えば、資産として計上しているものが「実際には計上されているだけの価値がなく、妥当な価値で再計算すると、マイナスになる」ことがあるからです。
例えば、売掛債権をたくさん保有している企業は、それを計上することで純資産をプラスにできることと思います。
しかし、もしそれらの売掛債権が全て回収困難なものだとすれば、資産価値は非常に低くなり、実質債務超過に陥る可能性が高まります。
この観点から、銀行員が貸借対照表を見る時にも、単に純資産がプラスかマイナスかということだけではなく、資産科目を精査して実質的な価値を計算していきます。
これによって、貸借対照表においては純資産がプラスになっていても、実質債務超過であることが判明し、融資に大いに不利になることがあります。
このようなことがありますから、銀行は貸借対照表の各勘定科目を詳細に見ていくことになります。
そもそも、貸借対照表とは、決算時点における会社の資産状況を表したものです。

資産科目
勘定科目のうち、まずは資産科目について見ていきましょう。
銀行が資産科目を見る時には、そこに計上されている資産が果たして計上されているだけの価値を備えているか、あるいはその資産が架空ではないかを見ていきます。
そして、実質的な価値が計上されているものより少ないとわかれば、マイナスの評価をし、架空の計上が露見した場合には、銀行は融資を断ることになります。
現金
まず、流動資産のうち、現金が記載されています。
現金は、いつでもすぐに利用できるものですから、それが潤沢である場合には、銀行は評価の対象とします。
しかし中小企業の場合には、現金が潤沢になっていても、マイナスに判断される場合があります。

しっかりしている中小企業や、放漫経営が許されない上場企業では、現金出納帳を作り、会社の現金の動きをきちんと把握しています。
しかし、それができていない会社が中小企業には多いものです。
そのような会社は、現金出納帳を作っていません。
そして、経営者は会社から役員報酬として給料を受け取るだけではなく、会社のキャッシュカードを経営者個人が所有し、いつでも会社の現金を引き出せる状態になっていることがあります。
例えば、経営者個人の給料は月40万円なのに、生活費や遊興費に20万円を必要として、会社のキャッシュカードで現金を引き出します。
この時、貸借対照表の仕分けでは、
(借方)現金200,000円、(貸方)預金200,000円
となり、現金勘定が膨らんでいくことになるのです。
このような場合には、現金勘定が増えていたとしても、銀行はその現金を差し引いて見ていくことになります。

また、本来ならば、経営者個人がプライベートに使うお金は、給与の中から賄うべきです。
それを、会社の現金をいつでも引き出して使える状態になっていたために、経営者が会社の現金を使いすぎてしまい、資金繰りに行き詰まることがあります。
預金
預金とは、決算日に銀行に預けていた預金残高のことです。
これは、銀行で残高証明書を発行して証明します。
銀行によっては、提出された勘定科目内訳書の各銀行の預金残高が、残高証明書と一致することを確認する場合もあります。
売掛金・手形
売掛金や手形は、取引先に掛け売りをし、数ヶ月先に回収を予定しているお金のことです。
銀行は、売掛金や手形の金額を見る時、平均の月商の何ヶ月分にあたるかを特に確認します。
例えば、ある会社は月商が2000万円であり、売掛金が5000万円であったとします。
この場合、売掛金は月商の2.5倍であることが分かります。
もし、この会社が銀行からのヒアリングの中で、ある月の売掛金の回収は2ヶ月後の月末であると答えていたとすれば、計算が合いません。
2ヶ月ごとにきちんと回収していれば、売掛金は月商の2倍になるはずです。
しかし、ここでは2.5倍と算出されるわけですから、0.5倍すなわち半月分多くなっています。
銀行はこれに対して、半月分相当の回収できない売掛金があるのではないか、または架空の売掛金があるのではないかなどと疑います。
具体的には、次のように疑います。
- 売掛先の会社が倒産しているのではないか
- 資金繰り困難に陥って回収不能になっているのではないか
- 前期の売掛金残高がそのまま持ち越されているのではないか

このため、売掛金残高と月商を照らし合わせたとき、聞いていた売掛金回収期間と計算が合わなければ、銀行はなぜそうなっているのかを聞いてくるものです。
もし、それが真っ当な理由によるものであれば、「決算月の売上高が多くなり、売掛金も多くなった」、「決算日が銀行休業日と重なり、翌月初めに回収した」などの説明が可能だと思います。
売掛金が多ければ流動資産も多くなり、融資にプラスになると考えがちですが、必ずしもそうとは言えないことを知っておきましょう。
棚卸資産

棚卸資産とは、将来的に販売するために保有している資産のことです。
「棚卸資産」ではなく、次のような名目で記載されていることもあります。
- 商品
- 製品
- 半製品
- 仕掛品
- 原材料
- 貯蔵品
棚卸資産が多いということは、稼ぐ手段あるいは現金化できる資産をたくさん持っているということであり、プラスに考えることもできます。
しかし、棚卸資産を過剰に保有しており、会社の販売力に見合わない場合には、たくさんの売れ残りを抱えて値引きを余儀なくされたり、在庫管理に資金を奪われたりすることがあります。
また、商品相場が下落すれば、多大な損失を被ることになります。
したがって銀行は、年間仕入高や年間製品製造原価を月平均で見て、棚卸資産がその何ヶ月分相当であるかを見ます。
このとき、業界平均よりも多すぎる場合には原因を探り、融資審査に活用していきます。

この時、棚卸資産勘定が1500万円であったとすれば、1.5ヶ月分にあたります。
この数値が業界平均に比べてどうであるかが重要です。
この会社の業界が、在庫を抱えてから売れるまでに1ヶ月程度を要する業界であったならば、1.5ヶ月分の棚卸資産を保有していることは、平均よりも多く保有していることが分かります。
銀行はこれに対して「その会社独自の戦略によるものなのか・在庫過多なのか¥架空の在庫なのか」などを調査していきます。
したがって経営者は、棚卸資産を考えるにあたっては、業界平均を気にして、適正値を保つようにしておきたいものです。
もちろん、業界平均より多い場合でも、それが会社の体質や戦略によるものであり、自社にとっては適していることを説明できれば問題ありません。
未収金
未収金とは、まだ回収できていないお金のことであり、売掛金に類似したものです。
しかし、売掛金はメインの営業活動で発生するものであるのに対し、未収金はそれ以外で発生するものです。
例えば、有価証券や固定資産を売却した代金をまだ回収していないもの、会社の余剰資金で購入した不動産収入のうち回収していないものなどがそれに当たります。

売掛金が大きければ、営業利益が高いことになりますが、未収金が大きければ不正会計を疑われる可能性が出てきます。
実際、勘定科目が大きい場合には、銀行はなぜ大きいのかを聞いてくるものです。
もし未収金が大きくなっているならば、銀行からの質問に答えられるようにしておきましょう。
未収入金、未収収益、前払費用などと記載されていた場合も、同じ考え方です。
貸付金・立替金・仮払金


問題とみなされるケースでよくあるのが「仮払金や貸付金という名目で、自社の経営者や従業員、あるいは関係会社などにお金が流れている」というものです。
その場合、銀行からの評価は低下して融資を受けることが難しくなるだけではなく、資金使途違反に見なされることもあります。
上記の通り、貸借対照表では純資産を重視されるわけですが、この純資産は、計上されている資産に価値があってこそ評価されるものです。
もし、計上されているよりも価値が低ければマイナスに見なされ、実質債務超過に陥ることもあります。
貸借対照表で貸付金や仮払金、立替金などが計上されているものの、それが実質的に返還されないものであったとすれば、銀行は資産価値をゼロとみなして再計算することになります。

もし、これが返ってくる見込みのないものであれば、貸借対照表における仮払金の価値はゼロとみなすことになります。
貸付金の場合も同様です。
ある会社において、関連会社に2000万円の貸付けをしていたとすれば、銀行はこの貸付金に2000万円の価値があるかどうかを判断する必要があります。
そこで銀行は、貸し付けている関連会社の決算書の提出を求めて調査し、全額返済の見込みがあれば2000万円の価値があると見なし、返済の見込みがなければ実質価値をゼロとみなします。
このように、貸付金や立替金、仮払金などは、本来価値があるものなのですが、返済に見込みがなければ、その分だけ資産は目減りすることになります。
ならば、なぜこのような実質的な価値を伴わない勘定科目が発生するのかと言えば、以下のような不正が考えられます。
- 取引先にバックマージンを支払ったものの、経理処理することができないため、経営者への貸付けとした。
- 会社のお金を経営者個人の生活費や遊興費に使い込み、帳尻を合わせるために経理処理の際に貸付金として計上した。


それだけに、銀行は貸付金・立替金・仮払金などの名目で計上されている資産には敏感になり、実質的にゼロとみなすことも多いです。
さらに、この会社がすでに借入金のある会社ならばどうでしょうか。
そのような場合に、銀行は、


などの疑いを抱くことになります。
そもそも、融資の際には資金使途、つまり融資を受けた資金をどのように活用していくかを明らかにしておくものです。
そのほとんどは運転資金や設備資金であり、又貸しや経営者個人の生活費を貸すことはありません。
それが流用されているとわかれば、銀行は騙されたと判断する可能性が高いです。
もし、関連会社がお金を必要としている、あるいは経営者個人がお金を必要としているなら、それは関連会社や経営者個人が銀行に相談して借りるべきです。
しかし、一旦融資を受けてしまえば、その資金は会社の自由に使ってよいと考え、銀行に説明した資金使途を無視して流用してしまう会社も多いのです。
しかし、決算書には資金の流れがはっきりと表れますから、流用をしたこともバレてしまいます。
これによって資金使途違反であることが分かれば、銀行からの信用を著しく損なうことは言うまでもありません。
新規融資を受けることは困難になるでしょう。
有形固定資産

有形固定資産とは、固定資産のうち形のあるものを指しており「土地・建物・機械・設備・車両・工具・事務所備品」などが含まれます。
融資審査の際に、銀行が特に目を付けるのは土地です。
銀行は、その土地の時価評価から、含み損がどれくらいであるかを判断します。
もし、土地の評価に含み益があるならば、路線価図などの資料によってそれを証明することで、融資にプラスの影響をもたらします。
しかし、価値ある有形固定資産をたくさん持っていれば、必ず融資に有利になるとは限りません。

流動比率とは、流動資産を流動比率で割ったものであり、この数値が高いほど財務体質が良いとされます。
土地や建物、その他の有形固定資産に投資し、現金や預金などの流動資産が減ってしまえば、流動比率も低下してしまうため、審査に悪影響をもたらします。
この場合、同様に当座資産(流動資産のうち短期間に換金できるもの。現金・預金のほか、売掛金、受取手形、有価証券など)も少なくなります。
当座資産を流動負債で割った当座比率も、銀行が審査の際に用いる指標ですが、有形固定資産が多く当座資産が少ない場合には当座比率も悪化し、審査に悪影響をもたらします。
以上のように、有形固定資産が潤沢であることは、必ずしもプラスになるとは限らず、むしろ銀行の信用格付けが悪くなることの方が多いです。

このことから、必ずしも必要のない有形固定資産を持っている場合には、売却するのも良い方法です。
例えば、担保に入っていない遊休地があるならば、それを売却してしまうことによって、有形固定資産は減らします。
預金を増やし、流動比率や当座比率を高めて融資によい影響を与えることができます。
また、必要な有形固定資産でも、外部に売却し、売却先からリースして使う方法によっても、財務内容を改善することができます。
無形固定資産
無形固定資産とは、固定資産のうち形のない資産のことです。
多くの会社では、それほどの無形固定資産を持っていませんが、電話加入権、営業権、特許権、ソフトウェアなどがこれに当ります。

投資その他資産
投資その他資産とは、固定資産のうち有形固定資産と無形固定資産以外のものを指す科目です。
他の企業への出資、資産運用のための投資などのほか、差入保証金や敷金、保険積立金などがあります。
このうち、銀行が重視するのは出資金です。
関連会社に出資している場合、それが本当に価値ある出資なのかどうかを見るのです。
例えば、関連会社の決算書を見たところ、関連会社が債務超過に陥っていることなどが分かれば、その出資金の価値はゼロとみなされます。
また、出資金以外にも、差入保証金・敷金・保険積立金なども、架空の計上がなされている場合もあるため、怪しい場合には実態を調査することがあります。

負債科目
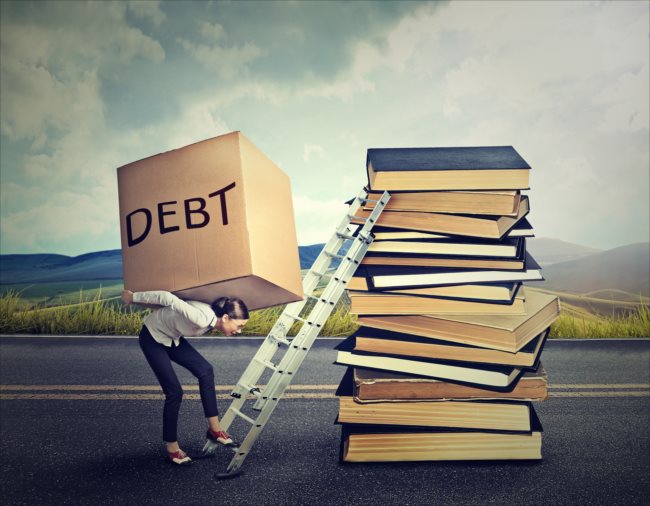
次に、負債科目について見ていきます。
負債科目の見方は、資産科目の見方とは異なります。
資産科目は、それが本当に価値ある資産であるか、架空の資産ではないかなどを見ていくのですが、負債の場合は、簿外債務があるかどうかを見抜く必要があります。
簿外債務とは、決算書に記載していない負債のことです。
例えば、本当は負債総額が5000万円あるにもかかわらず、決算書には3000万円と記載していた場合には、純資産が実際よりも2000万円多くなり、銀行の審査に有利になります。
しかし、それはあくまでも偽装なのですから、銀行はそれを見抜く必要があります。
では、銀行はどのような観点で審査し、不正を見抜こうとするのでしょうか。
各科目を見ていきましょう。
買掛金
買掛金は、年間仕入高を月平均に換算し、買掛金が月平均の何ヶ月分にあたるかを見ます。
例えば、年間仕入高が1億2000万円の会社では、月平均の仕入高が1000万円です。
この時、買掛金が2000万円あったならば、買掛金は2ヶ月分となります。
銀行では売掛金の場合と同様に、経営者に買掛金の締め日と支払日をヒアリングしているものです。
この会社が、月末締め翌月末日払いとしていたならば、常に買掛金は月平均仕入高の1ヶ月分で推移していくべきなのですが、貸借対照表では2ヶ月分となっています。
このとき銀行は、「資金繰りが厳しく、買掛先にお願いして支払いを待ってもらっているのでは?」と疑います。
もしそうならば、資金繰りをうまく管理できずに買掛先に迷惑をかけている会社なのですから、銀行は大きくマイナスに評価します。
もちろん、
- 決算月にたくさんの仕入れを行ったために買掛金が大きくなっている
- 決算日が銀行休業日と重なり、翌月初めに支払いをしたために買掛金が大きくなっている
など、銀行が納得できる理由があるならば問題ありません。

銀行はつじつまが合わない会計を嫌いますから、これも「決算月の仕入れが少なかった」など、理由を話しておきたいものです。
未払金・未払費用・未払法人税等・未払消費税等・預り金
買掛金は、営業活動の中で発生した金銭債務であるのに対し、未払金は営業活動以外で発生した金銭債務のことです。
未払費用とは、未払金と似ていますが「確定債務は未払金・未確定債務は未払費用」として区別します。
これらのうち、銀行が特によく見るのは、社会保険料や税金の未払いです。
年金や健康保険料は、毎月一定額を支払います。
もし、ここで未払いが発生していれば、未払費用や預かり金として計上されます。
法人税や消費税は、決算期の2ヶ月後が納付期限となっています。
支払額が決まっている場合には、未払法人税等や未払消費税等として計上されますが、すでに支払期日を過ぎたものが未納のままになっていると、この未払いが多くなります。
基本的に、銀行は「年金・健康保険料・税金」などの滞納を非常に嫌い、滞納があると融資を受けられないことも多くなります。
したがって、これらの勘定科目を計上するときには、銀行が嫌う要素であると知り、気を付けながら計上する必要があります。
前受金・仮受金

前受金とは、売上を計上する前に、取引先から入金されたお金のことです。
仮受金とは、入金されたもののうち、勘定科目が確定していないお金を、一時的に計上しておく科目です。
これらは、特に銀行に注目される科目ではありませんが、内訳を正確に把握しておくことが大切です。
短期借入金・長期借入金
負債科目のうち、銀行や個人からの借入金がある場合には、短期借入金または長期借入金として計上します。
- 短期借入金とは、1年以内に返済しなければならない借入金であり、流動負債に計上します。
- 長期借入金は、1年以上をかけて返済していく借入金のことであり、固定負債に計上します。
有形固定資産の時にも説明しましたが、銀行が審査するときには流動比率と当座比率を確認します。
流動比率は「流動資産÷流動負債」ですから、この数値を大きくするためには流動負債が少ない方が好ましいです。
また、当座比率は「当座資産÷流動負債」ですから、これも流動負債が小さい方が良いことが分かります。

ちなみに、借入金を計上する際に、ノンバンクからの借り入れがあるならば、銀行や政府系金融機関、信用保証協会はそれを嫌います。
「ノンバンクから借り入れている」ということは、裏を返せば「ノンバンク以外から借りられなかった」ということであり、大きなマイナスに見られるのです。
もしノンバンクから借り入れているならば、決算日だけ一時的に返済しておくように資金繰りできないかを考えたり、借りる際には会社で借りるのではなく経営者個人で借りられないかを考えたりしてみましょう。
ノンバンクは個人向けの中には、消費者金融、ノンバンクのカードローン、ノンバンク保証付きの銀行カードローンなどがあります。
経営者個人でこれらの融資を受け、会社に貸し付けておくことによって、決算書では経営者個人からの貸付けた形で計上することができます。
このほか、他の会社や個人からの借り入れを計上しており、その会社や個人が反社会勢力である、または社会的な問題を起こしているなどの場合には、銀行は融資を断る可能性がかなり高くなります。
融資審査を有利に進めるために

では、融資審査を有利に進めるためには、どのような方法が考えられるのでしょうか。
そのためには、純資産が重要です。
純資産がマイナスということは債務超過ということであり、銀行からの融資はほぼ不可能になります。
そして、プラスであるだけではなく、その金額が大きければ大きいほど審査には有利になります。
したがって、融資審査を有利に進めるためには、純資産額を厚くすることがポイントだと言えます。
そのためには、営業努力によって利益を増やしたり、財務体質を改善したりしつつ、さらにそれをできるだけ賞与や配当によって流出させないようにする必要があります。
そうすることで、内部留保が増えていき、純資産が厚くなっていきます。
しかし、営業努力によって利益を増やしたり、財務体質を改善したりするには時間がかかります。
もし、そのような努力を払う余裕がない場合には、資本金を増やすという方法が考えられます。

増資には、二通りの方法があります。
- 新たな資金を会社に入れることで増資を行なう
- 借入金を振り替えることで増資を行なう
1の方法では、例えば経営者個人の資産を会社に入れることで資本金を増やすなどして、増資することが可能です。
出資や増資と言えば、一般的に個人投資家やベンチャーキャピタルなどから資金を入れてもらうことを考えるものですが、経営者が個人投資家やベンチャーキャピタルのように資金を入れることで、増資することができるのです。
この方法は、単に純資産を厚くする以外にもメリットがあります。
個人投資家やベンチャーキャピタルなどの外部から資金を入れると、経営者をはじめ、それ以前の株主の持ち株比率が下がってしまい、新規に参入した株主が経営に口出しをしてくることになります。

2の方法では、会社に経営者からの借入金がある場合に、その借入金を資本金に振り替えるという方法です。
例えば、ある会社では経営者から会社に500万円の借入金があり、会社の純資産は100万円の債務超過で、うち資本金は200万円でした。
この時、経営者からの借入金500万円を資本金に振り替えれば、資本金は200万円から700万円に増え、さらに純資産は400万円になり、債務超過を脱することができました。
| 増資前 | 増資後 | ||
| 経営者からの借入金 | 500万円 | 経営者からの借入金 | 0円 |
| 純資産 | △100万円 | 純資産 | 400万円 |
| 資本金 | 200万円 | 資本金 | 700万円 |
この方法を使えば、会社の負債額は減り、純資産は増えるという一挙両得のメリットがあります。
債務超過状態になっており、経営者からの借入金がある場合には、ぜひ活用したい方法です。
営業利益と経常利益の改善

純資産と同様に重要なのが営業利益と経常利益で、こちらもマイナスであれば融資が非常に困難になり、プラスの場合には金額が大きければ大きいほど融資にプラスとなります。
そこで、融資を受けやすくする第二の方法として、営業利益と経常利益を増やすという方法が考えられます。
そのためには、特別損失を有効活用するのです。
特別損失とは、突発的な要因で発生した、一時的な損失のことです。
不動産や有価証券の売却によって損失がでたり、自然災害によって損失がでたり、訴訟によって損失がでたりする場合が挙げられます。
売上原価・売費・営業外費用・一般管理費などに計上しているものを再度仕分けしてみると、特別損失に計上できるものがあるかもしれません。
それらをまとめて特別損失に計上してしまえば、営業利益と経常利益は改善します。
同時に、特別利益に計上するはずだった利益を再度仕分けして、それを売上や営業外収益に計上できないか検討してみましょう。
もしそれが可能になれば、これもまた営業利益と経常利益の改善につながります。
「特別損失・特別利益」の振り分けを同時に工夫すれば、営業利益と経常利益が改善します。
損益計算書の内容が良くなり、融資にプラスに働く可能性があります。
まとめ
銀行が融資の際に決算書をどう見るかを解説してきました。
決算書は、融資に大きな影響を与えるものです。また、銀行の独自の見方でそれらを審査します。
もし、決算書の影響力を知らずに、何の努力もしていない決算書で融資審査を受けたり、銀行の見方を知らず、何の工夫もない決算書で融資審査を受けたりすれば、融資受けることは難しくなります。
しかし、決算書の重要性を知り、日頃から努力をしましょう。
さらに工夫を施した決算書で融資審査を受ければ、融資を受けられる可能性は大いに高まります。
ぜひ本稿を参考にして、決算書づくりを考えてみてください。




