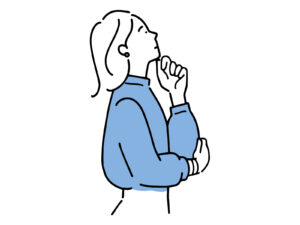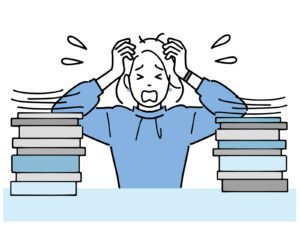ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
融資を受けるのが難しい状態とは?
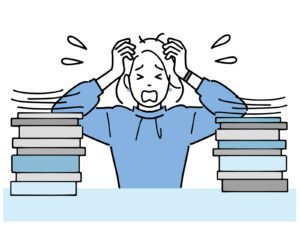
融資を受けるのが難しい状態について解説していきます。
これは、「融資をまったく受けられない」、「希望額の融資を受けるのが難しい」という状況を指しています。
現在は融資が難しくても、適切な対策によって融資が受けられる可能性が出てくるため諦めずに環境改善をしていきましょう。
問題1:経営者が経営を把握していない
銀行は、経営者の能力も見ています。
経営者が経営を把握していないと判断すれば、融資を渋るようになります。
融資の際には、銀行の担当者と経営者が面談を行います。
決算書の数字について質問された時、その数字の意味が分からずに答えられなかったとすれば、経営者の能力は疑われます。
決算書自体についても疑いを持たれることとなるでしょう。
自分で答えられないときに、「税理士に任せているので……」などと答えるのもいけません。
これも、経営者が決算書の内容を把握していないとみなされます。
対策
- 決算書の内容を理解したうえで融資を申し込む
- 決算書で疑問を持たれそうな内容の想定問答集を作っておく
問題2:減価償却が適正でない
固定資産の減価償却は、税法上は任意に行う項目です。
しかし、任意であるものの銀行はこの点を厳しくチェックしています。
これは、わざと償却を減らすなどして、見た目上の利益を増やすなどの操作ができてしまうためです。
減価償却を通じて、利益を大きく見せていないかのを確認しています。
このような償却漏れが見つかると、銀行の評価が下がり、融資に悪影響をもたらす危険性が高いです。
対策
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
問題3:価値のないものが資産に計上されている
貸借対照表の資産の部で計上されている資産についても厳しく確認されます。
というのも、資産の中には、実際には計上されているほど価値がなかったり、まったく価値のないものが紛れている可能性があるからです。
よくあるのが、在庫による資産の水増しです。
在庫となっている商品の中には、すでに流行遅れのものや、傷んで売れない商品もあるかもしれません。
それらに対し、価値の減少を見込まずに資産計上するケースがあります。
【注意】
ほかにも明らかに回収困難な売掛金をそのまま資産として計上しているケースも問題です。
実態に即した会計処理をするように心がけてください。
対策
- 資産の計上が実態に即するようにするる
- 字や債務超過に陥る場合には利益の多い期に処理する
問題4:返済原資が足りない
基本的に、銀行は「利益」を返済原資と考えています。
そのため、返済原資が足りていない会社には、融資が困難になります。
ここでいう「返済原資が足りていない」とは、「利益は出ているものの、既存の返済などを考えると返済原資が足りなくなる状況」のことです。
たとえば、返済原資となる税引後利益と減価償却額を足すと、年間1,000万円の返済利益が出ている会社があったとしましょう。
この会社は、1年返済で1,000万円の借入をしたり、5年返済で5,000万円の借入をしたりすることが可能です。
しかし、この会社が既に10年返済で5,000万円の融資を受けていたとすれば、年間の返済利益のうち500万円は返済に充てられることとなります。
この状況では、年間の返済利益は500万円に減っています。
借入希望額に対して返済原資が足りない場合、銀行が満額を融資することはほぼありません。
対策
- 借入余力を考慮し、計画的な資金繰りを行う
- 役員報酬を減らして利益を増やす
- 営業費用のうち、特別損失として計上できる項目があれば特別損失として計上し営業利益の黒字を確保する
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
融資を受けるのがより困難な状態とは?

次に、融資を受けるのがより困難な状態を見ていきましょう。
これは、新規融資やプロパー融資が困難であり、日本政策金融公庫や信用保証協会を利用しなければならない状況です。
完全に融資が不可能とは限りませんが、平常時における資金繰りでは対応できない状況だと考えてください。
問題1:債務者区分が低い
銀行は、金融庁のマニュアルに従い、各融資先を債務者区分によって格付けしています。
債務者区分には「正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先」の6種類があり、融資を受けられるのは正常先と要注意先だけです。
債務者区分は画一的なものであるため、ある銀行で要管理先となっている会社は基本的にほかの銀行でも融資が受けられません。
「基本的に」というのは、債務者区分の影響度は銀行によって異なるからです。
債務者区分が上がるように積極的に対策を行うような銀行では、保証協会付き融資などの条件付きで融資を受けられるケースもあります。
対策
- 自社の債務者区分を把握し、必要に応じて対策を図る
- 債務者区分を引き上げるのに効果的な項目を積極的に改善する
問題2:返済実績が乏しい
銀行に新規融資を依頼すると、あっさりと断られてしまった経験がある人は多いでしょう。
これは、返済実績による原因が大きいです。
新規融資を申し込むとき、どんな人でも「必ず返済します」と言いますが、銀行にとって大切なのは実測に裏付けられた信用です。
返済実績が乏しい会社は断られるか、信用保証協会を利用することが条件となるでしょう。
【ポイント】
銀行融資を受けるには、返済実績の積み上げが非常に重要です。
まずは、少額でもいいので保証協会付き融資を受け、返済実績を作っていきましょう。
対策
- 新規に融資では保証協会付き融資を利用する
- 追加融資は6ヶ月以上の返済実績を積んでからにする
- 返済開始から6ヶ月未満で追加融資が必要になる場合、初回の融資でまとめて借りるようにする
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
問題3:直近の決算が赤字になっている
これは単純な話で、赤字の会社は利益が出ていないからです。
すでに書いた通り、銀行は利益が返済原資になると考えます。
利益が出ていない赤字状態では、返済原資がないとみなされて融資は非常に難しくなります。
また、直近の決算が赤字の会社は、銀行の債務者区分で「正常先」と認識されることはなく、少なくとも「要注意先」以下に区分されるのが普通です。
直近の決済が赤字の状況で融資が必要な場合には、日本政策金融公庫の利用が考えられます。
日本政策金融公庫は、民間の金融機関が対応できない融資を補完することが目的であり、赤字の会社への融資も検討してくれます。
【ポイント】
なお、銀行に十分な返済実績があり、赤字の原因があくまでも一過性のものであることを経営者から説明できるなどの場合には、融資を受けられる可能性があります。
対策
- 日本政策金融公庫や信用保証協会を利用する
- 赤字の原因が一過性の場合にはそれをアピールする
問題4:二期以上の連続赤字になっている
上記の通り、直近一期の決算が赤字になっているだけでも融資は厳しくなります。
それが二期以上続いたとなると、融資はより困難になります。
まず、一期目の赤字の際に、債務者区分は「正常先」から「要注意先」に引き下げられるのが一般的です。
その後、二期目も赤字になると、債務者区分は要注意先の中でもさらに注意が必要な「要管理先」以下に落ちることとなります。
一般的に、銀行が融資できるのは要注意先までとされており、要管理先以下に落ちた会社は融資を受けられなくなります。
二期以上の連続赤字に陥っている会社が融資を受けるためには、日本政策金融公庫や信用保証協会を頼ることになります。
ほかにも、セーフティネット融資などの特別な公的融資制度を利用することも重要です。
対策
- 日本政策金融公庫や保証協会を利用する
- セーフティネット融資を検討する
- 経営改善計画書を銀行に提出する
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
問題5:税金が未払いである
税金の支払い状況と融資には、密接な関係があります。
法人として支払わなければならない税金を事業で使ってしまい「未払い状態」になっていると、融資を受けることが困難となります。
特に税金の未納に厳しいのは「公的機関」です。
ここまで、経営状況が良くない会社は日本政策金融公庫や信用保証協会を利用すべきと書きましたが、税金の未払いは公的機関の判断に大きな影響を与えます。
税金が未納の状態では、融資を受けることは不可能と言ってよいでしょう。
また、融資申込前に納付すれば融資を受けられるというものでもなく、過去の未納を理由に融資を拒否されることもあります。
対策
- 税金の未納がないことを確認して融資を受ける
- 未納がある場合、融資を申し込む6ヶ月以上前に支払いを済ませる
問題6:資金使途に問題がある
会社が銀行に依頼する融資は、事業のための融資です。
融資を受けて資金を充填することによって、事業が継続され、利益がきちんと出て、銀行が元金と利息を回収できることが重要です。
このため、銀行からみて意味のない資金(=生活費に使われそうな兆候がある場合など)では、銀行は融資を行いません。
これは民間の金融機関でも公的な金融機関でも同じことです。
対策
- 事業用の資金として申し込み、資金使途を疑われそうな場合には事業計画によって説明する
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
融資を受けるのがほぼ不可能な状態とは?

最後に、融資を受けるのがほぼ不可能な状態を見ていきましょう。
この状態では、民間の金融機関、公的金融機関、救済措置などのさまざまな方法を検討しても、融資を受けられる可能性はほとんどありません。
場合によっては、回収に乗り出す銀行も出てくる可能性もあります。
問題1:融資できない事業である
金融機関は、融資対象外業種というものを設けており、風俗店やパチンコ店、政治団体、金融業、一部を除く農林水産業などには融資を行っていません。
上記にあてはまる業種では、基本的にすべての金融機関で融資を受けられません。
会社が取り組んでいる事業のうち、一つでも融資対象外業種が含まれていれば、融資を受けることはできなくなります。
このほか、国内で登記されていない会社や、国内で営業していない会社なども融資対象外となっています。
対策
問題2:債務超過状態である
決算書の貸借対照表において、資産よりも負債の方が多い状態を債務超過といいます。
債務超過に陥っている会社に対しては、銀行が融資を行なうことはありません。
公的金融機関でも融資することはほとんどありませんし、融資の回収に乗り出してくる可能性もあります。
ごく軽微な債務超過状態であり、早期解消の見込みが高いなどの場合には、いきなり回収に遭うようなことはないでしょう。
しかし、融資を受けられる可能性はまずないと言っていいです。
債務超過状態が深刻である、改善の目途が立っていない場合には、銀行も強硬姿勢に出てくる可能性が高いと考えてください。
【注意】
債務超過は赤字よりも深刻度が大きいです。
軽微な債務超過であっても発生させないようにしてください。
対策
- 利益を伸ばすように努力し、マイナスを解消していく
- 代表者から会社に貸し付けていた貸付金を資本に振り替える
- 代表者に対する未払の給与を資本金に充当する
問題3:リスケジュールをしている
リスケジュール(以下リスケ)とは、従来の返済が難しくなった会社が、銀行に返済額の減額や元金返済の一時的な猶予をお願いしている状態です。
銀行と交渉し、合意の結果としてリスケに至ることから、延滞などをしてしまうよりもずっと良い対処となります。
しかし、経営状況が悪化したからこそリスケに至っているというのは事実です。
銀行も、その事実を鑑みて債務者区分を引き下げます(一般的には要管理先に引き下げられます)。
この影響で、リスケ期間中はもちろんのこと、リスケ終了後の一定期間は銀行からの融資は受けられなくなります。
リスケによって経営が立ち直り、6ヶ月以上の返済実績を作ることができれば、新規に融資を受けられる可能性も出てくるでしょう。
リスケを行うと、日本政策金融公庫からの借入も基本的にはできません。
対策
- 複数の融資を一括で借り換え、長期分割返済に組みなおすことで、リスケを避ける
- リスケを利用するならば、経営再建にしっかりと取り組み、返済を再開し、返済実績を作っていく
問題4:信用保証協会の否決事由に該当する
銀行から融資を受けられないならば、信用保証協会を利用するという方法が考えられます。
銀行側から、信用保証協会の利用を条件としてくることもあるでしょう。
しかし、必ずしも信用保証協会を利用できるとは限りません。
▼信用保証協会の否決事由(代表例)
- 信用保証協会の代位弁済を受けており、信用保証協会に対して債務が残っている
- 銀行からのプロパー融資や、信用保証協会を利用した保証付き融資を延滞している
- 確定申告をしていない
これらに該当する会社が、信用保証協会の保証を受けられる可能性はゼロであり、銀行からの保証協会付き融資も見込めません。
対策
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ:銀行融資と会社の状態について
銀行が融資を判断するときには、いろいろな角度から判断していきます。
多くは決算書から判断しますが、決算書を表面的に見るのではなく、実態との乖離を見抜いて判断することもあります。
決算書やその他によって、銀行が危険だと捉えてしまう状態に陥ってしまうと、融資を受けることが困難になります。
銀行側の視点に立って、問題視されない状態を作っていくことが、スムーズに融資を受けるためのポイントとなるでしょう。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼