赤字決算の会社は、銀行から融資を受けることが難しくなります。二期以上の連続赤字ともなれば、融資交渉は困難を極めます。
しかし、二期以上の連続赤字だからといって、100%融資を受けられないということではありません。
連続赤字から脱却できる見通しを具体的に説明し、銀行を納得させることができれば、支援を受けられる可能性はあります。
本稿では、二期以上連続赤字の会社が、融資を受けるための交渉について解説していきます。
二期以上連続赤字の危険性
中小企業の経営基盤は弱く、また外部からの影響を受けやすいことから、業績が赤字に転落してしまうことがあります。
しっかりと経営している会社でも、大手取引先の経営環境が悪化して受注が減ったり、業界全体が不景気になって売上が下がったりすることによって、赤字になることがあるのです。
黒字を維持することが難しい環境にあるからこそ、業績を安定させて黒字を維持し続けている会社は、融資交渉もかなり有利に進めていくことができます。
スムーズに融資を受けて資金繰りを安定させるのはもちろんのこと、融資条件も良くなることが多いです。
逆に、赤字になってしまうと、銀行は融資に消極的になります。
銀行の融資は、事業からの利益によって返済されるのが原則であるため、それが期待できない(利益が出ていない)赤字の会社には融資しにくいのです。
とはいえ、その赤字が創業以来はじめての赤字であるとか、一時的な赤字で原因も明らかであるとかの場合には、融資交渉は十分に可能です。

融資交渉の大きな障害になるのは、赤字が続いた場合です。
一期だけ赤字に転落しただけでも、銀行は融資に慎重になります。
ましてや、二期、三期と赤字が連続してしまうと、銀行は融資にかなり消極的になります。
赤字補填のために、財務面でも相当の影響が出ているでしょうから、
「業績も赤字続いているし、資金繰りが続かない可能性が高い」
とみなして、融資を拒否する可能性が高いのです。

ファクタリングについての記事はこちら

二期以上の赤字でも融資は受けられるか?
このような理由から、二期以上連続赤字の会社では、融資を受けることが困難となります。
二期以上連続赤字であることに加えて、他の悪材料も抱えているならば、状況はさらに悪化します。
例えば、
- これまでに延滞をしたことがある
- 債務超過である
- 繰越損失がある
など、色々な悪材料が考えられます。
そして、二期以上連続赤字に加えてこれらの悪材料が加われば、銀行は「破綻懸念先」とみなします。
したがって、おそらく融資は不可能です。
そのような会社では、リスケジュールを進めて立て直しを図ることになるでしょう。
あるいは、リスケジュールによっても立て直しが不可能な状態ならば、早い段階で破産を進めていき、債権者に与える損失や、破産後の自分や周りの人達への影響を最小限に止めることを考えるべきです。
したがって、本稿で対象とするのは、二期以上の連続赤字であるものの、それ以外には目立った悪材料(銀行への延滞、債務超過など)がない会社に限ります。
銀行の立場を考える
まず、銀行側の立場を考えてみると、融資に消極的になる理由がよく分かります。
既に述べた通り、利益からの返済が見込めないのですから、赤字の会社を危険視するのは当然のことです。
さらに、二期以上の赤字になっているということは、赤字という危機的状況から抜け出せていないのですから、徐々に弱体化していることは間違いありませんし、将来性も危ぶまれます。
将来性が危ないとなれば、追加の融資を出すどころか、早期回収に乗り出す可能性もあります。
そのまま放置しておくと、やがて会社の資金繰りが回らなくなり、倒産から債務整理に至り、債権をほとんど回収できなくなるからです。
唯一の突破口は?
さて、本稿のタイトルにもある通り、このような会社が融資を引き出して資金繰りを続けていくための突破口は一つしかありません。
上記の銀行の立場を考えてみると、すでにピンときた人もいるでしょう。
二期以上連続の会社が融資を引き出していくためには、業績回復の見通しを具体的に説明し、納得を得るほかありません。
業績回復の見通しとは、短期のうちに黒字に転換する見通し、あるいは赤字を確実に縮小させていき、近い将来には黒字に転換する見通しです。
当然ながら、黒字に転換する計画があっても、それ以前に資金繰りが破綻すれば意味がありませんから、それまでは資金繰りが回っていくことも具体的に説明する必要があります。
これができなければ、融資を受けることはほぼ不可能となり、倒産待ったなしの状態に陥ります。
具体性が命
この唯一の突破口によって融資を引き出すには、具体性が何より重要です。
おそらく、二期以上連続赤字の会社は、最初の赤字や二期目の赤字の際、銀行に何らかの説明をしていると思います。
業績回復の見通しを説明して、銀行から支援を受けているかもしれません。
このため、銀行員の会社に対するイメージは、
「業績は回復すると説明していたから支援したのに、話が違う。今後はそのような説明をされても信用できない」
というものです。
融資担当者に、口だけで説明したり、具体性に乏しい計画によって業績回復の見通しを説明しても、それが融資交渉に役立つことはないでしょう。
だからこそ、具体性がかなり重要です。
まず、今後の経営計画を提出することになるでしょうが、その中で具体的な数字をもって、業績が回復することを示さなければなりません。
具体的な数字とは、根拠のある数字のことです。
業績を回復させるためには、しっかりと利益が得られることが前提となりますから、どのような根拠で利益を予測し、経営計画に反映しているかを示す必要があります。
一番分かりやすいのは、証拠を添えて受注状況を見せることです。
受注契約書を提示し、確保される売上を見せることによって、計画の信ぴょう性はかなり高まります。
また、業績の見通しはもちろんのこと、業績回復まで資金繰りが続くことも、具体的な計画によって説明しなければなりません。
例えば、
- 資金繰り予定表を提示
- その資金繰りが成り立つだけの手元資金を確保している
- 他行からも融資を期待できるだけの担保を保有している
などの説明をするのです。
以上のように、二期以上連続赤字の会社にとって、唯一の突破口は業績回復しかありません。
それを具体的に説明し、業績回復までの資金繰りのアテもあると分かれば、銀行が支援してくれる可能性が出てきます。
どこに依頼するか?
業績回復の見通しに納得してもらうことは絶対条件であり、それに付随して資金繰りを維持できることも条件です。
資金繰りを維持するためには、銀行からの融資を引き出すことが重要です。
真っ先に検討するべき相手は、基本的に支援すべき立場にあるメインバンクです。
メインバンクは、その会社に対して最も融資シェアが大きいのが普通ですし、融資以外の取引も多数獲得しているものです。
このため、その会社が破産することになれば、貸し倒れによっても、融資その他から得られていた収益の面でも、大きな損失を被ることになります。
これにより、メインバンクはできるだけ支援したいと考えるのが普通です。
とはいえ、メインバンクでも、二期以上連続赤字の会社には厳しい見方をするのが普通です。
今後も赤字が改善されなければ、会社はいずれ倒産します。
そのような会社の支援をいつまでも続けていれば、やがて倒産した時の被害が大きくなるだけだからです。
そうなるよりも、早めに見切りをつけ、できるだけ回収を進めていき、倒産の際の被害を最小限に止めようと考えます。

メインバンクが支援の方針を維持できるように、今後の見通しを上記のように具体的に説明することで、何とか支援してもらうことが重要です。


融資交渉は迅速に
メインバンクからの支援を引き出すことができれば、資金繰りの安定性はいくらか高まります。
また、他行でも「メインバンクがまだ支援している」ということが安心材料となり、融資を検討する可能性も出てきます。
したがって、メインバンクから支援を引き出したならば、それだけで満足せず、支援を期待できる銀行から順に融資を申し入れていくべきです。
融資を受けられない可能性も高いですが、二期以上連続赤字という危機的状況では、なりふり構っていられません。
依頼した銀行のうち、いくらかでも融資に応じてもらうことができれば、業績回復まで資金繰りが維持しやすくなるため、それが好材料とみなされ、その後も融資が出る可能性が高まります。
なお、複数行への交渉では、交渉先の結論を待ってから次の銀行に交渉するよりも、できるだけ同時進行で、早急に交渉していった方が良いでしょう。
基本的に融資が出にくいのですから、交渉した銀行の結論を待って動いていたのでは、融資を拒否されてから別の銀行へという流れになる可能性が高いからです。
ある銀行から融資を拒否された後に別の銀行に依頼した場合、「他行で断られたからこっちに来たな」という見方をします。
その先入観によって危険視されると、融資を受けられない可能性が高まります。
そうならないうちに同時並行で融資交渉を進めていき、他行の動きがまだ明らかでないタイミングで交渉することが大切です。
また、複数の銀行に交渉することで、必要額の一部だけ融資を受けられることもあります。
例えば、
「希望融資額は5000万円となっていますが、現在担保にいただいている不動産の担保価値が5000万円、融資残高が3000万円ですから、うちで出せるのは2000万円が精いっぱいです」
といった形での融資です。

同時並行で交渉しながら、どのような形にせよ支援が受けられることになれば、それを交渉カードにしていきましょう。
したがって、
- 支援を仰ぎやすいメインバンクから融資を依頼し、支援を引き出す
- メインバンクからの支援を交渉カードに、積極対応が期待できる銀行にも融資を依頼する(交渉は早急に)
- メインバンク以外にも支援が得られれば、それを交渉カードとしていく
という流れになります。
もちろん、複数行との交渉を早急に進める必要がありますが、性急に進めるのは禁物です。
しっかりとした交渉を短期間で進めなければならないので、今後の計画などを入念に準備してから、一気に交渉していくことが大切です。


実際の銀行交渉
ここまで書いたポイントを、実際の交渉ではどのように活かしていくべきか、具体的な例を見ていきましょう。
三期連続赤字の会社の経営者と、メインバンクの融資担当者の交渉の様子です。
例とするA社の概況は、以下のように設定します。
- 土木業者
- 受注先は主に官公庁
- 入札競争の激化により、3期前から赤字が続いており、前期までに改善の兆しは見えていない
- 赤字続きの中で、自己資本も減少している
- メインバンクに、運転資金4000万円の融資を申し入れる
このような状況であると仮定します。
融資担当者が最も気を付けるのは、言うまでもなく三期連続赤字の事実であり、メインバンクといえども融資には積極的にならざるを得ません。
しかし、受注先が主に官公庁であり、数年前までは安定した業績になっていたことから、以前の状態へと戻していくことができるならば、銀行にとっては良い取引先となるでしょう。
ここで見放すべきか、もう少し支援するかを見極める必要に迫られています。
では、交渉の様子を見ていきましょう。
担当者「前期まで、業績回復の兆しは見えていません。三期連続赤字となると、主力行である当行としても、今後の見込みについて確認する必要があります。今後の業績については、どのような見通しでしょうか。」
経営者「これまで、良くない状況でも支援していただいたことを感謝しています。今後は、徐々に良い結果になっていく見通しが立っています。」
担当者「受注状況が改善しているということでしょうか。」
経営者「そうです。まず、足元の受注状況ですが、このような案件を受注しています。こちらが、その契約書になります。(契約書を見せる)」
担当者「契約書もお持ちいただいて、ありがとうございます。」
経営者「そして、今後の見込みはこの資料の通りです。(受注見込みの資料を見せる)」
担当者「なるほど。どの程度まで受注が見込めるものですか?」
経営者「この資料に、交渉の経緯なども記載しています。順を追って説明しますと、・・・(省略)・・・という交渉をしてきました。この経緯から、ほぼ受注できると考えて間違いないと思います。」
担当者「それはよろしいですね。足元の受注と、見込みの案件を合わせると、今期の決算はどのようになりますか?」
経営者「売上は前期並み、良くても微増と思われます。しかし、採算性は大幅に改善します。こちらの資料をご覧ください。受注見込みも織り込んだ計画ですが、このように500万円の黒字となる予想です。」
担当者「なるほど、ついに黒字転換ですね。」
経営者「はい、なんとか。」
担当者「回復の見通しが立つならば、当行としては前向きに検討したいと思っています。すでに受注したものの契約書の写しを頂けますか。」
経営者「もちろんです。」
担当者「あと、今後も受注が確定したものは、その都度写しを頂ければと思います。」
経営者「わかりました。」
担当者「保全についてですが、当行にお預け頂いている定期預金2500万円を、担保としていただきたいのですが。」
経営者「そうですね。不動産担保などはありませんし、それでお願いします。」
担当者「ありがとうございます。1500万円については、無担保で検討させていただきます。」
実際には、もっと込み入った話が行われるものと思いますが、まとめるとこのような交渉になると思います。
融資担当者は、メインバンクとしても慎重にならざるを得ないという立場から交渉に入っていますが、経営者の見通しを聞いて、徐々に融資に前向きになっています。
受注した案件の契約書の写し、今後の受注見込みの詳細、それらを織り込んだ黒字転換の計画を提示したことが効果的だったようです。
上司はどう見る?
しっかりと説明したことで、融資交渉の第一段階である融資担当者はクリアできました。
しかし、融資は支店内で複数人の判断によって行われるものであり、稟議の方向性を上司と協議する必要があります。
上司との協議においても、業績改善の具体的な根拠を示したことが効果を発揮します。
担当者「A社から、運転資金の依頼がありました。」
上司「A社か。業績が悪かったよね。」
担当者「はい、三期連続赤字です。」
上司「三期連続か・・・。正直、そろそろウチも限界に近いんじゃないか。」
担当者「たしかに、三期連続は大きな問題だと思います。しかし、今期の業績は黒字転換となる見込みです。」
上司「本当か。根拠は?」
担当者「社長から、足元の受注状況と、今後の受注見込みについて説明がありました。現時点での受注案件は、すでに契約書の写しももらってきています。見込み案件は、まだ確定しているわけではありません。しかし、交渉の経緯や記録について資料をみると、受注の可能性は高いと思います。」
上司「なるほど。A社はこれまでも官公庁相手に安定した経営を続けてきたからね。業界内でも信頼はあるのだろう。苦しい状況も、ようやく終わるかな。」
担当者「そのように感じました。」
上司「契約書の写しだけど、見込み案件についてももらえるのかな?」
担当者「契約次第、速やかにもらうことで了解を得ています。」
上司「わかった。管理はしっかりとね。」
担当者「はい。」
上司「それと、保全はどうする?」
担当者「当行に、2500万円の定期預金があります。それを担保とすることで了解を得ています。1500万円は無担保扱いとなります。」
上司「分かった。主力行として、支援の方向で行こう。じゃ、稟議をあげてくれ。今期の黒字転換について、しっかりとな。」
担当者「分かりました。」
融資担当者は、黒字転換の見込みについて積極的に説明しており、上司も黒字転換の根拠や具体性についてしっかりと確認しています。
その上で、問題なさそうだと判断し、融資実行の方向で協議を終えています。
もちろん、上司がリスクに厳しい人であれば、黒字転換の見込みを慎重に見極めたいと考えることもあります。
その場合には、担当者任せにせず、上司自ら経営者と面談し、今後の見通しについて詳しく説明を受けた上で判断することもあります。
三期連続赤字ともなれば、そのような対応になる可能性も十分にあります。
しかし、「担当者の話では融資しても良いと思うが、自ら確認して万全を期したい」と考えて、上司自らの対応になっているのですから、マイナスに捉える必要はありません。
上司と面談することになったら、融資担当者よりも権限を持っている人に説明できる機会だと捉え、しっかりと説明しましょう。
そこで納得が得られれば、融資の実行に大きく近づくこととなります。
稟議書はどうなる?
上司との協議の後、融資担当者はいよいよ稟議書の作成に取り掛かります。
稟議書は、稟議を進めるうえでの最重要書類となりますから、稟議書の良し悪しによって融資判断は大きく左右されることとなります。
この例では、上司は担当者に対し、稟議書には今期の黒字転換についてしっかり記載するようにと指示しています。
では、連続赤字の会社の稟議書とは、どのようなものなのでしょうか。
一例を見てみましょう。
概況
- 官公庁を主な受注先とする土木業者。
- 創業以来、安定した業績を維持してきたものの、数年前から入札競争の激化により業績が悪化。
- 三期連続赤字で現在に至る。
- ただし今期は採算性が大幅に改善し、5百万円の黒字に転換する見込み。
資金使途
- 経常運転資金。
- 手元資金水準を高め、資金繰り安定を図るもの。
融資条件
- 証貸
- 金額40百万円
- 期間3年の分割返済
- 利率1.9%。
保全
- 定期預金担保25百万円を取り受け。
- 本件後15百万円の保全不足となるが、取引振りは当行に集約されており、ここ半年の当行預金平残は50百万円あることから、広義の保全は確保されているものと思料。
資金調達余力
- 会社および代表者に見るべき資産なく、担保余力はなし。
- マル保は限度額一杯まで利用しており、現状では保証余力は認められないもの。
狙い
- 長年の当行主力先であり、取引振りも当行に集約。
- 前期まで三期連続の赤字となっており、厳しい決算が続いていたが、今期は受注回復と採算改善により黒字転換の見込み。
- 官公庁主体に安定した販路を持つ先柄でもあり、本件主力行として支援いたしたい。
連続赤字決算の会社に対する融資はリスクが高いため、稟議も慎重に進められます。
融資実行のためには、黒字回復の見込みを検証する必要があり、稟議書にはそれを裏付ける情報が添えられます。
検証に有利となる、具体的材料がどれだけ揃っているかがカギとなります。
したがって、融資担当者を説得するだけではなく、稟議全体を見据えて説得する必要があります。
融資担当者に与えた材料は、そのまま稟議書に反映されるのですから、その時に融資担当役席から支店長まで、多くの人を納得させることを見据えて説明することが大切です。
面談では融資担当者を納得させ、その後に担当者が上司を納得させ、やがて稟議書が支店長まで納得させていくという流れを意識して交渉することができれば、連続赤字の会社でも、融資の可能性はかなり高めることができるでしょう。

まとめ
二期以上連続赤字は、銀行にとって大きな懸念材料です。
融資を実行するならば、貸し倒れリスクが高いことも覚悟しなければなりません。
並大抵の交渉では、銀行にそこまで腹をくくってもらうことはできません。
融資しても問題ないと思わせるだけの、具体的な材料を提供する必要があるのです。
もし、そのような交渉ができるならば、連続赤字の会社でも融資を受けられる可能性はあります。
連続赤字だからといって、融資交渉が不可能だとは考えず、その状況でも融資を受けられるような交渉をしていくことを考えましょう。






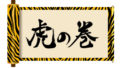
コメント