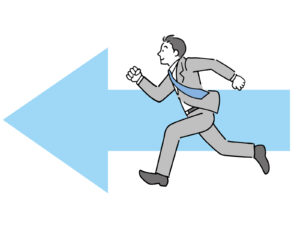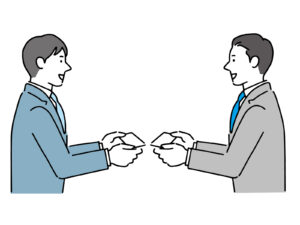ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
銀行融資で仲良くなるべきキーパーソンは?

では、銀行融資を通しやすくするテクニックとして、親密にすべきキーパーソンは誰でしょうか。
銀行で融資に関わっているのは、おもに「渉外担当者」、「融資担当者」、「融資担当役席」、「支店長」の4人です。
▼役職と役割
- 渉外担当者:その会社の担当者
- 融資担当者:融資案件の担当者、小規模な銀行では渉外担当と兼ねることが多い
- 融資担当役席:融資担当者が作った稟議書の確認
- 支店長:決済者
基本的に融資を行う際は、融資担当者が「資料」や「稟議書」を作成します。
作成された稟議書は、融資担当役席に回されます。
融資担当役席は、稟議書を総合的に判断し、支店長に判断を伝えます。
そして、支店長が最終的な判断を行う流れです。
しかしながら、支店長は多忙であるため、融資担当者や融資担当役席ほど細かい分析はできません。
支店長は融資担当役席の判断をもとに決済しており、融資担当役席の判断が覆ることはほとんどありません※。
※判断が覆るケースとしては、融資を依頼している会社と支店長が特殊な関係にある場合など非常に珍しいケースです。
親密に付き合うべき銀行員は融資担当役席
上記の通り、融資の決済で大きな影響力をもっているのが「融資担当役席」です。
自社の状況がよくなく稟議書の内容が悪くなった場合などでも、融資担当役席とパイプを持っておくと融資が通りやすくなる可能性があります。
また、融資担当者の能力が低いために稟議書のできが悪くなったケースでも、融資担当役席とのパイプは有効です。
融資担当役席と頻繁に会い、情報交換をしておくことで、融資担当者が稟議に書ききれなかった自社のプラス面を補ってくれる可能性が高まります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
融資担当役席とのつながりの作り方

融資担当役席を紹介してもらうには、すでに面識のある渉外担当者にお願いすればOKです。
「そういえば、○○さん(渉外担当者)の上司にまだ挨拶をしていませでした。一度ご挨拶に伺いたいので、アポイントを取っていただけませんか。」
このようにお願いしてみましょう。
このように伝えて、「ダメです」と言われることはそうありません。
渉外担当者が、融資担当役席と話をつけ、訪問日を設定してくれます。
初回の面談では何を話す?

最初の面談では、本当に挨拶だけで十分です。
名刺交換など行い、挨拶をします。
あとは、初回面談をムダにしないために、下記2つのことを聞いてください。
- 今後もたびたび融資担当役席を訪ねていいか
- 頻繁に自社の情報提供をしたい
今後のつながりを作る流れにもっていきましょう。
「これを機に、自社の状況報告や情報提供をしていきたいと思っています。今後も○○さん(融資担当役席)宛にお伺いしてもよろしいでしょうか?」
このように伝えるといいでしょう。
あわせて、初回面談の際は、アポイントメントを取ってくれた渉外担当者との関係性にも注意を払っておきましょう。
「いつも○○さん(渉外担当者)には良くして頂いています」など一言伝えておけば、渉外担当者とも円滑な人間関係を築いていけるはずです。
2回目の面談
初回の面談の時に2回目のアポイントを取り、資料を持って訪問しましょう。
2回目以降の面談では、自社の状況を伝えていきます。
この時に必要となる資料は、「事業計画書」と「予想損益計算書」です。
これによって、会社の方向性と収益目標を説明することができます。
2回目の訪問の際には、「今後は、月に1回は報告に伺います」と伝えましょう。
3回目以降の面談
3回目以降の面談では、「試算表」と「月次事業報告書」を持って訪問しましょう。
試算表には前月の内容が記載されており、月次事業報告書には計画と実績の差が現れています。
これを提出することで、銀行に会社の実態を詳しく伝えられます。
これを毎月継続し、1年が経過した時に計画と実績に大きな差がなければ、2回目の面談で説明した事業計画通りに進捗したことが証明されます。
事業計画通りの進みであれば、大きな信頼を勝ち取ることができるでしょう。
仮に、計画と実績に差が生じたとしても、銀行は毎月の報告である程度予測していますから特に驚きません。
計画通りに運んでいなくとも、毎月訪問・報告してくる社長の誠意も伝わります。
また、毎月会ったことで融資担当役席と関係を作れたのですから、結果的に大きなメリットがあったと言えます。
【ポイント】
人間は、よほど相性が悪い相手でなければ、会えば会うほど親しみが増すものです。
情報共有も兼ねて頻繁にアポイントを取ることは非常に重要です。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
月1回の訪問を習慣づける
融資担当役席宛ての訪問は「月1回のペース」で行っていきましょう。
融資担当役席に定期的に会い、自社の状況を知らせておくと、融資担当役席はいつ頃に融資の依頼が来そうかということを予想するようになります。
通常、いきなり融資を希望ても、すぐに融資を進めるのは非常に難しいです。
しかし、日頃から関係性を作っておき、融資担当役席も融資希望を予想している状況ならば、「さあ、きたぞ」という雰囲気になり話を聞いてもらいやすくなります。
毎月訪問の意外な効果
また、毎月訪問することは、自社の状況を報告し、融資担当役席と関係性を構築する以外の効果もあります。
たとえば、毎月訪問していると、融資担当役席が何となく冷たかった、愛想が良かったなどの印象を持つことがあります。
これは、自社が金融機関の中で、立ち位置が良くなった、悪くなったという判断の材料になるでしょう。
また、人事異動があり、支店長が代わったなどの情報も素早く仕入れることができます。
毎月訪問は、金融機関とのお付き合い全般において、素早い対応を可能にしてくれます。
【ポイント】
なお、訪問の際に毎回菓子折りなどを持っていく必要はありません。
旅行の際にちょっとした話題作りとして渡す程度でOKです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

月次事業報告書と決算書を説明しよう
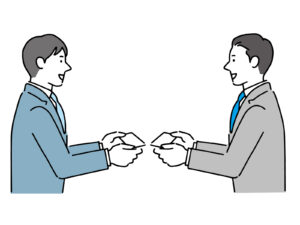
融資担当役席を訪問する際には、いくつかの資料を携えて訪問します。
中でも重要となるのが、月次事業報告書と決算書です。
月次事業報告書
月次事業報告書とは、売上高、売上原価、売上総利益、販管費、営業利益、経常利益、在庫、顧客数、支払利息などの計画と実績を対比・分析した資料です。
これを毎月作っておくことで、月ごとの状況を分析し、今月以降の事業に役立てられます。
また、月次事業報告書が事業計画通りになっていれば、計画書の精度が高いことの証明にもなります。
計画が正確ということは、計画に盛り込まれている投資計画の見通しも正確である可能性が高いということになります。
たとえば、設備投資を事業計画に盛り込んでいたならば、その設備投資の効果も計画通りになる可能性が高いと期待できます。
銀行側としても、こういった正確性の高い企業からの融資依頼はスムーズに勧めやすいです。
しかし、月次事業報告書が事業計画通りに進んでいなかったとしても、へこむ必要はありません。
早期改善に努めている姿勢が見えれば、融資担当役席も安心して付き合ってくれるきっかけとなります。
【ポイント】
事業計画通りであるかどうかにかかわらず、重要な数字を毎月しっかりと報告している会社は銀行も「支援しやすい取引先」として考えるでしょう。
決算書
決算書は、融資担当役席への訪問の有無にかかわらず、融資を受けている会社なら、年に1回提出しなければならない資料です。
ただ、毎月、融資担当役席を訪問していれば、自然と決算書の説明機会を得られるでしょう。
決算書は、1年間の実績を記載した資料で、融資の際に大きな影響力を持つ資料です。
決算内容が悪いときほど、定期的な訪問で決算内容が悪化した理由等を丁寧に説明すべきです。
定期的な訪問時にきちんと事情を説明できていれば、決算内容が悪くても支援を受けられる可能性が出てきます。
決算が悪いときの説明は、社長としても気が重いでしょうが、想定質問を考えるなどの事前準備をしっかりして臨みましょう。
訪問を避けるべき日時とは?

最後に、訪問を避けるべき日時を押さえておきましょう。
訪問を避けるべき日とは、金融機関の繁忙日です。
30日、31日といった月末、5と10が付く五十日(ごとうび)を避けるのはもちろんのことですが、週末と月曜日も避けたほうが無難です。
スケジュール的にあわなければ、週末や月曜日に訪問しても構いません。
最悪の場合、25日を除く五十日に訪問しても大丈夫です(五十日の中でも25日が最も忙しいため)。
また、連休明けの五十日も忙しくなるため避けるべきです。
避けるべき時間帯

避けるべき時間帯もあります。
金融機関が最も忙しい時間帯は、朝の9~10時です。
この時間は、前日の処理を済ませなければならないため非常に忙しいです。
さらに、14~16時の時間帯も、その日の勘定を占める作業のために忙しく働きます。
これらの時間には訪問を避けるようにしてください。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ:融資担当役席には積極的な情報共有を
融資は会社の生命線です。
融資が引きやすくなるように、細かく会社の現状を銀行側に伝えるにしましょう。
訪問時に会社の現状を説明できるよう、社長自らが財務や業績の数値は常に把握しておくべきです。
融資担当役席とのつながりをもち、定期的に会社の現状を伝えていれば、銀行との付き合いにおいて大きなメリットになります。
実践していない社長は、ぜひ今日から実践してみてくださ。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼ ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
 ▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼