
多くの会社では、毎年夏と冬の二回、あるいはどちらかの一回、従業員に賞与を支給しています。
賞与を支給するためには、まとまった資金が必要となるため、銀行から賞与資金を借り入れる会社が多くあります。
賞与資金はほかの資金と比べると、使途がわかりやすく融資交渉もしやすいですが、注意点が2つあります。
この注意点でミスをすると、融資交渉が難しくなるため交渉前に本記事でご確認ください。
銀行からの融資が間に合わない場合は、売掛金を使った「ファクタリング」で資金調達ができる可能性があります。

賞与資金の性質

一般的に賞与(=ボーナス)の支給は、従業員の士気を高めるのに役立つと言われています。
経営が苦しい会社では少額しか支給できないこともあるでしょうが、支給があるだけで従業員は嬉しいものです。
逆に言うと、賞与が出せない状態ということは、業績や財務に問題があるため賞与以外の給与等でも金銭的に従業員に報いるのが難しいと言えます。
このような状況では、従業員の士気が低下するだけでなく、優秀な人材が集まらない、離職率が高くなるなどの弊害も予想されます。
状況次第ではありますが、このような弊害を考えると少額であっても賞与はなるべく支給すべきでしょう。
財務的に余裕がない場合は、銀行から「賞与資金の融資」を受けて賞与を支給する方法も検討してみてください。

賞与資金の融資交渉は比較的容易

融資を申し入れる際には、必ず「資金使途」を聞かれます。
資金使途には、運転資金、納税資金、設備資金、減産資金などのさまざまな項目がありますが、この中でも賞与資金は融資を引き出しやすいとされています。
資金使途によって審査の難易度が変わるわけではありませんが、資金使途が与える融資の印象は大きく異なります。
たとえば、赤字補填資金ですと後ろ向きな融資と捉えられる反面、競争力強化を目的とした設備資金などは前向きな融資として捉えられます。
賞与資金の場合、賞与の支給によって経営にプラスの効果があるため、前向きな融資として感じる銀行担当者が多いと思われます。
賞与資金は金額的にも借りやすい
賞与資金は、ほかの資金使途と比較すると融資額が少額で、返済力を見込みやすいです。
融資が比較的少額で済む点も、賞与資金は融資を引き出しやすいと言われている理由です。
よって、少なくとも経営に大きな問題がなく、運転資金などもそれなりに借りられている会社であれば、融資が受けられる可能性は非常に高いと言えます。
賞与資金の融資交渉を行う時の注意点

比較的容易とされる賞与資金の融資でも、銀行との融資交渉は必要です。
交渉の内容によっては、融資を受けるのに苦労したり、受けられなかったりする可能性も出てきます。
本記事を参考に、賞与資金をうまく引き出すための注意点を確認しておきましょう。
注意点は2点のみで、しかも簡単に実践できるものですので安心してくださいね。
1.毎回同じ銀行に依頼する

賞与資金の融資を申し入れる銀行は、毎回同じ銀行にすることが大切です。
賞与資金は、会社が賞与の支給を打ち切らない限り毎年発生する資金です。
毎年ある支出ですので、賞与資金の調達先を同じ銀行に決めておくと、銀行側も会社の資金需要を把握しやすいです。
賞与の時期が近付くと、担当銀行員も「今年もそろそろ、A社から賞与資金の申し込みがあるだろう」と予測できます。
担当銀行員の予想通り、賞与資金融資の申し入れがあれば、銀行も「例年通りの方針」として融資しやすくなります。
以上の理由から、賞与資金の借入は毎回同じ銀行に依頼するとスムーズでしょう。
2.例年並みの金額を申し入れる
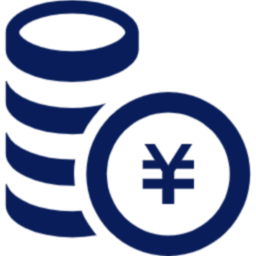
前述の通り、毎回同じ銀行に申し入れる理由は、銀行から「例年通りの方針」という答えを引き出し、交渉を容易にするためです。
例年通りの方針としてもらうには、賞与資金の金額も「例年並み」とする必要があります。
多少の金額差は問題ありませんが、銀行が「例年通りの判断で問題ない」と考えられる内容にしておくと交渉を進めやすいです。

賞与資金の融資交渉が難航する理由

注意点といっても、「①毎回同じ銀行に融資を申し入れる」、「②例年並みの融資額を希望する」の2点だけですから難しいものではありません。
しかし、簡単な注意点だからこそ、このポイントを外してしまうと逆に融資交渉が難航する可能性があります。
依頼先の銀行を毎回変えていると……
賞与資金の融資を毎回違う銀行に依頼していると、銀行側は資金需要を把握できません。
銀行側からすると、「突然融資を申し込まれた」と見えます。
当然ゼロの状態から賞与資金融資の稟議を始めるため、融資実行までに時間がかかってしまいます。
希望の融資額が例年と大きく異なると……
希望の融資額が例年の金額から大きく異なるケースでも、融資交渉は難航します。
「業績が好調で賞与を増やした」、「従業員が増えた」このような正当な理由があれば希望額の増加の説明がつきます。
しかし、これといった理由もなく賞与資金が大幅に増えている場合、銀行は「例年通りの方針」とは判断できなくなります。
銀行がもっとも嫌うのは「使途不明の融資」です。
例年並みの金額から大きく額が外れる場合は、事前にきちんと正当な理由を担当銀行員に伝えておきましょう。
使途不明金は貸し倒れリスクにつながる

銀行が使途不明金を嫌うのは、貸し倒れリスクにつながるからです。
銀行は、融資したお金の使途をわかってこそ、貸し倒れリスクを量ることができます。
希望融資額が増加しているのに銀行が納得できる説明がない場合、銀行は増加分を使途不明金とみなしす可能性が高いです。
- 銀行が把握していないところで経営が悪化しているのではないか
- 賞与資金に赤字補填資金などの後ろ向きな資金を紛れ込ませているのではないか
このような疑いをもたれる可能性すらあります。
融資は資金使途によって区別する

中には、「ちょうど運転資金も必要だから、賞与資金とまとめて申し込もう」などと考える経営者もいます。
しかし、銀行はまとめて判断することはなく、賞与資金は賞与資金として、運転資金は運転資金として審査を行います。
仮に、賞与資金と同時期に別の資金需要が発生したとしても、それらは別物としてきちんと区別して銀行に相談することが重要です。
場合によっては、使途不明金を疑われ、賞与資金の交渉が難航した会社もあります。

【コラム】ファクタリングという手段も!
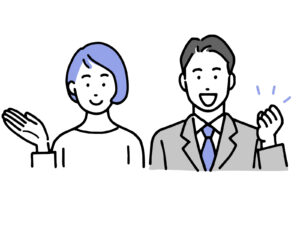
銀行との融資交渉が難しい場合は、売掛金や注文書を活用した「ファクタリング」で運転資金を確保できるかもしれません!
ファクタリングとは、売掛金を専門業者に売却することで運転資金等を調達する方法です。
本来、売掛金を現金としてもらうには支払日まで待たなくてはいけません。
これを専門会社に売却し、先に現金として受け取る方法がファクタリングです。
専門業者は売掛金額から報酬(=手数料)を引いて会社に入金するため、本来の売掛金額よりも受け取る金額は少なくなりますが、早めの資金調達が可能です。

まとめ
本記事で解説した通り、、賞与資金の融資交渉はほかの融資交渉と比べ容易なものです。
しかし、融資であることには変わりませんので、注意点を確認のうえ交渉に挑んでください。
とくに注意したいのは、銀行が想定していた金額と大きく異なり、説明もつかず、使途不明金を疑われることす。
そうなってしまえば、融資交渉は簡単にはいかなくなり、関係悪化の可能性も出てきます。
賞与資金は、あくまでも例年通りの内容を意識し、例年と異なる場合にはきちんと説明できるように資料をそろえるなど、準備を整えてから交渉するように意識しましょう。






コメント