
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
バンクミーティングとは?

バンクミーティングとは、経営状態が厳しい会社の今後について、取引金融機関が集まり話し合うことを指します。
通常、リスケ交渉は各銀行に対して個別に行いますが、借入先が多い会社ではメインバンクが中心となってバンクミーティングを開くことがあります。
実はこのバンクミーティング、これからリスケを依頼する会社側にとって非常に厄介な行事です。
事前にバンクミーティングの内容を知り、準備をしたうえでミーティングに臨みましょう。
メインバンクはなぜバンクミーティングを開きたがるの?
メインバンクは「リスケ前に全体像を把握するため」のためにバンクミーティングを開催します。
会社が複数の銀行に対し個別にリスケ交渉を進めると、メインバンクは各銀行と会社の動きを把握できません。
方針の差によっては、特定の銀行に有利不利が生まれてしまう可能性があります。
こういった差をなくすために、メインバンクは会社に対してバンクミーティングの開催を希望します。
バンクミーティング開催までの流れ
バンクミーティングは、基本的にメインバンクから「バンクミーティングを開くので各銀行の担当者を集めてください」とお願いされるところから始まります。
借入額の大きいメインバンクからのお願いですので、経営者のほとんどはバンクミーティングに応じます。
自分で各銀行担当者に声をかけても良いですし、保証協会付き融資であれば保証協会の「経営サポート会議機能」を利用してもいいでしょう。
バンクミーティング当日の流れ
バンクミーティングは一般的に下記のような流れで進みます。
▼バンクミーティングの流れ
- 経緯と状況説明
- 経営改善計画案の説明
- リスケについての話し合い
- 質問、各銀行からの要望の確認
当日はメインバンクが主動となり、「なぜバンクミーティング開催に至ったのか」、「今後どのように経営を再建していくか」についての説明を行います。
多くのケースでは、経営再建のために取引先銀行に対しリスケを求めていくことになります。
メインバンクが、「リスケは借入総額に応じて、全ての銀行で平等になるように図りますので同意をお願い致します」などと言いまとめていきます。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

バンクミーティングが厄介だと言われる理由

リスケに限らず、すべての銀行交渉は基本的に銀行が情報を共有していない状態で、個別に行う方が会社にとって有利に進められます。
たとえば、複数の銀行に融資を依頼している状態を想定しましょう。
A銀行の金利提示に対し、経営者は「A銀行は金利2.0%なんですね、B銀行は1.5%を提示してくれましたよ」と持ち掛けることができます。
銀行同士が情報を共有しておらず、あくまでも個別に交渉するからこそ、このような会社にとって有利な交渉が可能となります。
これはリスケであっても同じです。
A銀行でリスケが認められたのに、B銀行で否認された場合は「A銀行は応じてくれましたがどこが問題でしょうか?」と交渉できます。
基本的に、銀行は他行に追従する業界ですので「A銀行が認めたならば、うちも積極的に検討しよう」などと考えることが多くあります。
バンクミーティングではこういった駆け引きができない

バンクミーティングでは、取引銀行が一堂に会するため個別交渉はできません。
また、全体の方針自体もメインバンクの意向にあわせるのが基本です。
会合を通して、各銀行の担当者が情報を共有してしまうのも会社側にとっては不利です。
全担当が同じ情報を共有するため、今後の各銀行との個別交渉はほぼ不可能になるでしょう。
銀行が債権より資金回収を考え出すとより厄介に
銀行が会社再建よりも「資金回収」を重視し始めると会社にとってはより厄介な状況になります。
こうなると、各行が「どのようにすればすべての銀行にとって有益な回収ができるか」と銀行視点で団結することもあります。
バンクミーティングによって、銀行がリスケによる再建ではなく資金回収に目がいってしまうと会社としてはミーティング失敗です。
せっかくうまくいくはずのリスケも、バンクミーティングのせいで失敗する可能性があります。
【ポイント】
会社ごとに状況は異なりますが、バンクミーティングの前に個別にリスケ交渉ができないか考えてみてもいいでしょう。
【コラム】ファクタリングという手段も!
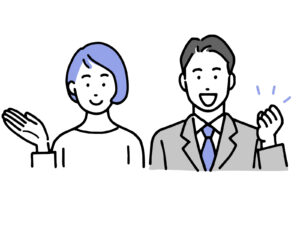
リスケ交渉まで行かなくても、売掛金や注文書を活用した「ファクタリング」で運転資金を確保できるかもしれません!
ファクタリングとは、売掛金を専門業者に売却することで運転資金等を調達する方法です。
本来、売掛金を現金としてもらうには支払日まで待たなくてはいけません。
これを専門会社に売却し、先に現金として受け取る方法がファクタリングです。
専門業者は売掛金額から報酬(=手数料)を引いて会社に入金するため、本来の売掛金額よりも受け取る金額は少なくなりますが、早めの資金調達が可能です。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
リスケを受け入れてもらわなければ経営が破綻してしまうような状況では、バンクミーティングに応じる経営者が非常に多いでしょう。
しかし、バンクミーティングを開くと、各銀行のリスケ方針が固定されてしまい、各銀行への交渉の余地がなくなります。
銀行同士が情報を共有することによって、完全に動きを読まれてしまい手も足も出なくなる可能性があります。
バンクミーティングに応じる前にこういったリスク等をぜひ認識しておいてください。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
バンクミーティングとは?リスケで失敗しないために注意したいポイント、流れを紹介











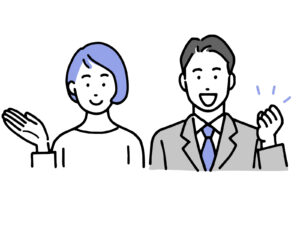




コメント