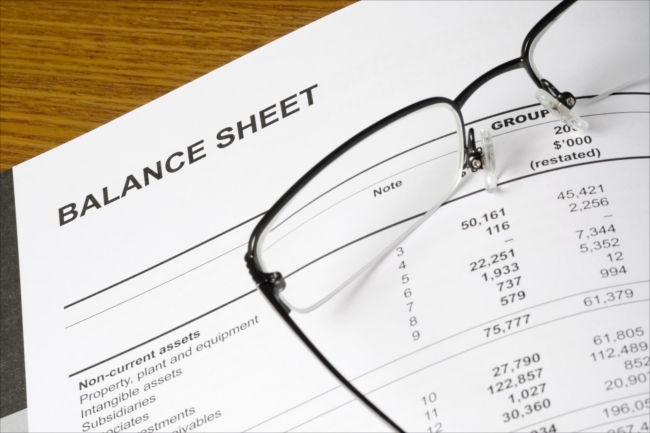皆さんも、銀行が会社に対して格付けを行なっているということは知っていることでしょう。
しかし、「では、どのように格付けされているか知っていますか?」と聞かれたとき、正確に答えられる人は少ないものです。
格付けは、会社の資金繰りを左右する重要なものです。
それだけに、格付けが高まるように努力を払い、高い格付けを維持する努力も重要となります。
そのためには、銀行が格付けを行なう際の考え方を知り、その考え方に即した企業努力を払うのが近道となります。
銀行の格付けとは?

会社情報を分析したり、株式投資をやりながら四季報を読んだりした人には身近にわかることと思いますが、企業に対して「格付け」というランク付けをすることがあります。
「BBB」とか「A-」といった形で格付けがなされています。
投資判断における格付けは、日本格付研究所(JRC)やムーディーズといった信用格付業者が行なっています。
目的は違いますが、最近の銀行でも、全ての取引先企業に対して独自に格付けをするのが普通です。
投資における格付けでは、「投資適格」「投機的要素あり」といったことを意味するのに対し、銀行の融資における格付けでは「正常先」「要注意先」といった格付けを行います。

格付けが低い会社は融資を受けられなかったり、融資を受けられても融資条件が悪くなるのが普通です。
逆に、格付けが高い会社はスムーズに融資を受けやすく、融資条件も良くなる傾向があります。
銀行によっては、格付けを聞けば教えてくれるところもあります。
会社は銀行の格付けを把握し、融資が円滑になるように、格付けを維持したり、改善したりする努力が求められます。

ファクタリングについての記事はこちら

格付けは2種類
銀行の格付けには2種類あります。
ひとつは財務格付けであり、これは主に融資条件を左右するものです。
もうひとつは債権者区分と呼ばれるもので、これは融資対象者の健全性を評価するためのものです。
銀行の格付けと債権者区分、格付けの意味、金利・担保などの条件を図示すると、以下のようになります。
| 財務格付け | 債務者区分 | 格付けの意味 | 金利条件 | 担保条件 | 融資方針 |
| 1 | 正常先 | 格付けの数値が小さいほど業績がよい 数値が大きくなれば、 今後の経営実績に注目すべきである。 |
格付けの数値が小さいほど低金利での融資が可能 数値が大きくなるほど高金利になる |
格付けの数値が小さいほど無担保で融資されやすい 数値が大きくなるほど担保が必要となる |
格付けの数値が小さいほど融資に積極的になる 数値が大きくなるほど回収に積極的になる |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 要注意先 | 業績が悪化しており、注意を要する。 | |||
| 8 | 要管理先 | 会社の再建支援のために 融資条件を緩和している |
融資しない | ||
| 9 | 破綻懸念先 | 業績悪化によって返済が滞っている 元本回収に時間がかかる。 |
|||
| 10 | 実質破綻先 | 返済が長期間滞っており 再建の見込みも薄い |
|||
| 11 | 破綻先 | すでに倒産している あるいは民事再生法や 会社更生法を適用したり、 破産を申し立てた会社 |
|||
この表を踏まえて、財務格付けと債権者区分を見ていきましょう。
財務格付け
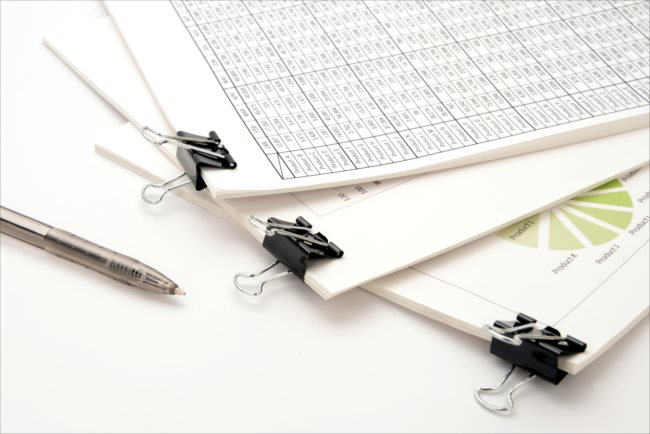
財務格付けとは、会社の直近3年程度の経営実績をもとに格付けを行い、融資条件を決めるための参考にするものです。
財務格付けにあたっては、「借対照表・損益計算書」から時価を計算して評価します。
上の表から、評価の高い会社ほど、有利な条件で融資が行われることが分かります。
逆に評価が低い会社は、融資条件が悪くなったり、そもそも融資されないことも多くなります。

財務格付けが高い会社ならば融資条件は良くなり、会社側の要求も通りやすくなります。
逆に財務格付けが低ければ、会社側の要求は通らなくなり、融資条件も悪くなります。
銀行が提示する通りの金利条件で、担保も差し入れた上で融資を受けるような状況です。
上の表の格付1の会社ならば、低金利に無担保の条件で融資を受けることができるでしょう。
返済期間や返済スケジュールなども、会社の希望が通りやすいです。
金利条件については、金利スワップなどのデリバティブ商品も活用しながら、より低リスクでの資金調達が可能になります。
しかし、格付7や格付8の会社ならばどうでしょうか。

返済期間などでも、会社の希望は通りにくく、資金繰りへの圧迫も大きくなりがちです。
特に、融資に伴って提供できる商品は、格付が低い会社にはかなりの制限がかけられます。
財務格付けが低下したということは、その会社の倒産リスクが高まったということにほかならないからです。
また、格付が低い会社は銀行よりも立場が弱くなるため、この立場の強弱を利用して、銀行の商品を無理に契約させる可能性が出てきます。
これを「優越的地位の濫用」といいますが、このような行為は法律で禁止しているため、格付けの低い会社は金融商品の提供を受けにくくなるのです。
このことからも、有利な条件で融資を引き出し、資金繰りを円滑に進めるためにも、財務格付けを良くしていくことが非常に重要です。
銀行によって評価方法には若干の違いがあるでしょうが、はじき出された評価は、おおむねこの表の通りの方針で融資されることとなります。
債権者区分

銀行の貸借対照表では、融資した資金は資産の部に分類されます。
しかし、決算の際には資産の回収見込みを把握しなければならないため、融資先の会社を査定していきます。
この査定を自己査定と言います。
自己査定によって、融資先は「正常先・要注意先・要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先」の6種類に分類されることになります。
この区分が債権者区分です。
財務格付けが融資条件を左右するのに対し、債権者区分は銀行が債権者の会社にどのような態度で臨むかを左右します。
当然ながら、この区分が悪くなると融資はせず、むしろ回収に積極的になっていきます。

要注意先でも融資を受けられないわけではないのですが、メインバンクがなんとか支援してくれるといったレベルであり、メインバンクでさえ消極的です。
要管理先は以下の区分では、新規融資は基本的に不可能であり、既に受けた融資に対しても厳しい対応を受けることが多くなります。
債権者区分によって、銀行が「この会社には、融資よりも回収を優先する」と判断したならば、その会社は資金調達が困難になるのです。
格付けはとても重要
財務格付けや債権者区分によって、銀行が行なう格付の重要性が良くわかると思います。
会社が必要な時に必要な額の融資を受け、資金繰りに役立てていくためには、債権者区分は少なくとも正常先に維持しなければなりません。
財務格付けを少しでも良くするように努力しなければならないのです。
これができず、必要な時に必要な額の融資を受けることができなければ、経営戦略の実践もままならず、経営が上手くいかなくなります。


格付けの仕組み

格付けは改善したほうが良いものですが、とはいっても格付けはどのような仕組みになっているのかを知らなければ、改善のしようがありません。
そこで、格付けの仕組みを学んでいきましょう。
格付けのうち、最初に行なわれるのは財務格付けであり、これは財務分析による定量評価によって行われます。
この次に行われるのが債務者区分の決定であり、これは「経営環境・経営状態・融資状況」などの定性評価によって決められていきます。
定量評価
定量評価では、「財務の安全性・その会社の収益力・借入金の返済能力」などから判定されていきます。
財務分析では、財務諸表に現れている数値をそのまま評価に用いるのではなく、実質的な価値と共に判断していきます。
したがって、財務諸表では資産として計上されているものでも、例えば回収不能な売掛債権や処分が難しい棚卸資産などは、実質的な価値を低く見積もって定量評価を行います。
定量評価では、以下のように様々な指標を用います。
【定量評価の指標】
| 項目 | 意味 | 計算式 |
| 安全性 | ||
| 当座比率(%) | 純資産のうち、すぐに現金化できる資産の比率 支払い能力を量る |
(現金+預金+売掛金+受取手形+有価証券) ÷流動負債 |
| 流動比率(%) | 1年以内に現金化できる資産と、 1年以内に支払う負債の比率 特に短期的な支払い能力を量る |
流動資産÷流動負債 |
| 固定比率(%) | 純資産のうち、固定資産の比率 固定資産が自己資本の範囲内で 賄われているかどうかを見る。 |
固定資産÷純資産(自己資本) |
| 固定長期適合率(%) | 固定資産が自己資本の範囲内で 賄われているかに加え、 長期借入金や社債などの 固定負債を考慮する。 |
固定資産÷(純資産+固定負債) |
| 自己資本比率(%) | 総資本に対する自己資本の比率 変事対応力があるかどうかを量る |
純資産÷総資本(純資産+負債) |
| 債務超過解消期間(年) | 債務超過の解消にかかる年数 債務超過に陥っている会社が 適正な年数で債務超過を回収できるかどうかを量る |
債務超過額÷当期利益 |
| 借入依存度(%) | 総資本のうち、借入金によって賄っている割合 有利子負債が適正な水準に収まっているかどうかを量る。 |
有利子負債 (割引手形+短期借入金+長期借入金+社債)÷総資本 |
| 収益性 | ||
| 総資本経常利益率(%) | 総資本と経常利益の比率 投下資本がどれだけの効率で 利益を上げたかを見る。 |
経常利益÷総資本(期首・期末平均) |
| 売上高営業利益率(%) | 売上高と営業利益の比率 利益あるいは損失の発生要因を分析する |
営業利益÷売上高 |
| 売上高経常利益率(%) | 売上高と経常利益の比率 利益或いは損失の発生要因を分析する |
経常利益÷売上高 |
| 総資本回転率(回) | 1年間に、売上によって総資本が何回入れ替わったかを示す 資本の運用効率を見る。 |
売上高÷総資本(期首・期末平均) |
| インタレストガバレッジレシオ(倍) | 金融費用に対する事業利益の比率 利払い能力を判定し、安全性を見る |
(営業利益+受取利息+配当金)÷支払利息+割引料 |
| 償還能力 | ||
| 借入金返済可能期間(年) | 借入金の返済にかかる年数 償還能力の判定に用いる |
(借入金-運転資金)÷キャッシュフロー |
定性評価

しかし、定量評価では決算書が用いられるため、決算日から融資申込時点までのタイムラグが生じます。
この期間で財務状況が悪化していることもあり得るため、定量評価だけで判断するわけにはいきません。
そこで、定性評価を加味することになります。
銀行員が経営者の話を聞いたり、現場を視察したり、興信所を使ったりすることによって、企業の実態を調査していきます。
これによって得た情報と事業計画を照らし合わせることによって、事業計画が現実的なものであるかどうかを評価することもできます。
定性評価では、点数をつけて格付けに反映させることのほかに、債務者区分を再検討するときの判断材料にもなります。

しかし、どの銀行でも共通するのは、「融資側である銀行の主観によって評価が行われている」ということです。
つまり、その会社の実態がどうであれ、銀行がその会社の業績に不安を覚えたならば、定性評価によって格付けが落ちてしまうということです。
それだけに、格付けのキモは定量評価でありながらも、定性評価の重要性もきちんと認識しておきたいものです。
格付けの具体例

では、銀行が行なう格付けの手順を、具体的な事例と共に見ていきましょう。
A社では、3期分の決算によって格付6と評価されました。
ただし、決算後に事業環境が変化し、今期は受注が大きく減少することが分かっています。
これは、銀行が債務者区分を引き下げるだけの理由になり得る要素です。
このような状況に加えて、メインバンクが支援を躊躇しているという情報も入り、これも債権者区分引き下げに相当する内容です。
これらの定性的な要素から、銀行は債務者区分を要注意先に引き下げました。
さらに、債務者区分を要管理先に変更し、返済条件を緩和することを決定しました。
この格付けのポイントは、
- A社の財務分析は、定量分析における格付けは6であり、正常先に分類される
- しかし、決算後の変化、メインバンクの融資方針の変更という定性的な要素を踏まえ、債権者区分を一つ引き下げて、要注意先とした。
これによって、財務格付けは7に落ちたことになる - さらに、返済条件を緩和したということは、債務者区分が要管理先に引き下げられたということであり、財務格付けも8に落ちたことになる
ということです。
銀行の格付けはこのように行われます。
格付けの指標で特に重要なもの

上記において、財務格付けに用いられる指標を記載しました。
色々な指標が用いられることが分かったと思います。
しかし、この中でも銀行が特に重視する指標は、「借入金返済可能期間と債務超過解消期間」です。
借入金返済可能期間
借入金返済可能期間とは、現在抱えている借入金を、その会社の資金繰りから考えて、何年で返済可能であるかを示す指標です。
上記の表の通り、(借入金-運転資金)÷キャッシュフローの数式によって算出します。
この数式では、借入金から運転資金を差し引いています。
数式だけを見ると、借入金のうち運転資金に相当する部分は返済しなくていいようにも見えますが、そうではありません。
企業が事業を継続している以上は、運転資金は必ず発生するものであり、これは借入によって賄うものです。
つまり借り入れとして常に残るものであるために、借入金から差し引いて計算しています。

債務超過解消期間
債務超過解消期間とは、債務超過の解消にかかる年数のことです。
現在、債務超過に陥っている会社が、適正な年数で債務超過を回収できるかどうかを量るための指標です。
現在の収益力が継続されると仮定した場合、理論上では債務超過解消までの期間が分かります。
これは、債務超過額÷当期利益という数式によって算出します。
貸借対照表では純資産がプラスになっていても、それぞれの資産の実質的な価値を考慮した場合に、債務超過に陥ってしまう場合は往々にしてあるものです。
そのような場合、債務超過解消期間は3年以内を目安とし、3年以内に債務超過を解消できない会社は要注意先以下の評価を受けることになります。
借入金返済可能期間と債務超過解消期間の2つをチェックすれば、自社の格付けをチェックできることでしょう。
- 借入金返済可能期間が10年以内である
- 債務超過ではない
- あるいは債務超過でも解消期間が3年以内
このような場合には、債権者区分を正常先に維持することができます。
つまり、要注意先以下に区分されている会社よりも、ずっと資金調達がスムーズになるのです。


格付けはこうやって引き上げる!

格付けの良し悪しによって、資金調達の状況は大きく変わってきます。
だからこそ、格付けが良い場合にはそれを維持し、悪い場合には引き上げていくことを考えることがとても大切です。
では、ここからいよいよ、格付けを引き上げる方法を考えていきましょう。
財務内容を改善する
格付けを引き上げるためには、上記でも重要な指標として解析した「借入金返済可能期間と、債務超過解消期間」を改善するのが効果的です。
借入金返済可能期間を短縮するためには、この計算式である「(借入金-運転資金)÷キャッシュフロー」から考えるに、借入金を減らすか、キャッシュフローを増やすかしなければなりません。
債務超過解消期間を短縮するためには、この計算式である「債務超過額÷当期利益」から考えるに、債務超過額を減らすか、利益を増やすかしなければなりません。

借入金を減らし、債務超過額を減らすための取り組みは、貸借対照表の改善が必要です。
一方、利益を増やすためには、損益計算書の改善が必要です。
貸借対照表の改善
まず、貸借対照表の改善から見ていきましょう。
貸借対照表を改善することのメリットは、即効性があるということです。
借入額や債務超過額を減らすためには、資産売却によって資金を調達して借入金あるいは債務超過額を減らすなどの方法が考えられます。
もちろん、借入金と債務超過額を減らせるならば、その他の資金調達方法でも構いません。
資産を売却する方法
貸借対照表の改善のためには、資産を売却して資金を調達するという方法が良く用いられます。
事業に関係のない資産を売却したり、不動産や売掛債権といった流動性の低い資産を売却したりすることによって資金を調達するのです。
売掛債権を売却する方法はファクタリングと呼ばれ、近年注目されつつある方法です。
また、資産を売却や流動化すれば、総資産は減少することになります。
そのため、自己資本比率を高めることにもつながります。
このように、資産をうまく使うことによって、借入金返済可能期間を減らします。
さらに自己資本比率も改善することができるため、これによって格付けを引き上げられる可能性が高まります。
資金調達によって純資産を増やす

債務超過解消期間を短縮するためには、債務超過額を減らすことが重要であり、そのためには純資産を増やしてプラスの状態に持ち込むのが効果的です。
純資産を増やすためには、増資が用いられます。
返済義務があるお金を借り入れては、負債まで増えるため債務超過額の改善にはつながりません。
しかし、増資によって返済義務のない資金を調達すれば、純資産をプラスに持ち込むことが可能です。
これによって債務超過状態を解消したり、債務超過解消期間を短縮できれば、格付けの改善につながります。
増資のためには、ベンチャーキャピタルや投資ファンドから出資を受けるという方法が考えられます。
しかし、このような機関から出資を受けられる会社は一握りです。
また、出資を受けた場合には、経営に口出しをされることにもつながるため、デメリットも大きいです。
損益計算書の改善

損益計算書を改善するということは、会社の稼ぐ力を向上させるということでもあります。
なぜならば、損益計算書の改善とはすなわち、「売上を増やし、原価を抑え、経費を削減する」ことによって、利益を増やしていく取り組みに他ならないからです。
貸借対照表を改善する方法は、格付け改善のための即効性の方法です。

しかし、これは根本的な改善にはつながらず、この方法に頼ってばかりでは、いずれ行き詰る時が来てしまいます。
しかし、損益計算書を改善するということは、「即効性はないものの、根本的な改善を目指し、事業を成長軌道に乗せる」ということです。
いわば漢方薬のように、困難な状況や辛い症状を起きない健康な体質を作っていくものです。
漢方薬による体質改善のためには、長期にわたって漢方薬を飲み続ける必要があります。
これと同じく、損益計算書の改善も、効果が出るまで地道な努力を求められます。
即効性がないだけに、出口の見えない努力を続けることになることもあります。
それでも格付けを上昇させ、維持していくためには、損益計算書の改善は欠かすことはできません。
事業計画による銀行への説明
以上は、定量評価における格付けを改善するための取り組みです。
これと同時に、定性評価を改善するための取り組みも重要です。
定性評価で積極的な評価をしてもらうことも、格付けを引き上げるためには効果的な方法です。

銀行に対して事業計画を説明し、その事業計画に現実味があることを納得してもらうことができれば、要注意先以下の会社でも「この会社は近い将来、確実に正常先に復活できる」と認めてもらえるかもしれません。
実際、金融庁の金融検査マニュアルを見てみても、経営改善計画は画一的に判断するのではなく、債権者側の実態をよく踏まえた上で評価するように指導がなされています。
つまり、銀行でもマニュアル通りに、杓子定規に判断していくのではなく、会社の事業計画を詳しく見て判断することが多いです。
今は業績があまり良くなく、要注意先や要管理先とみなされている会社でも、具体的な取り組みを踏まえた、現実的な事業計画を提示することができれば、銀行はそれを評価してくれます。
これによって、格付けが下がらずに維持されたり、格付けの向上に役立ったりすることがあります。
決算書は良いものを
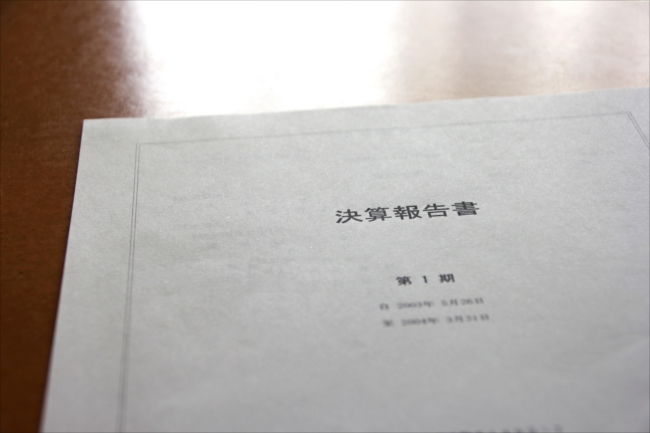
最後に、決算書はできるだけ良いものを作る努力が大切です。
会社と経営者個人が混同されることなく「きちんと事業が営まれ、そのことが決算書に現れ」財務内容がより健全なものになるように努力していれば、格付けの維持に役立ちます。
これができていない、つまり会社の利益を経営者がプライベートなことに使い込んでしまったり、それを隠すために粉飾決算をしたりしているようでは、決算はゆがんだものとなります。
決してよい決算書になることはなく、格付けの維持や向上に役立たないのです。

銀行格付けと損益計算書

銀行は、金融庁の監督を受けて運営されています。
金融庁から銀行へなされている指導には、会社に大きな影響を与えるものが少なくありませんが、その一つに金融検査マニュアルというものがあります。
金融検査マニュアルとは、各融資先の業績や財務、その他の情報に基づいて債務者を区分するよう、銀行に求めるものです。
このマニュアルによって、銀行は取引する会社を「正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先」に区分し、融資判断に役立てています。
この区分のうち、融資を受けられるのは基本的に要注意先までだとされており、安定して融資を受けるためには、債務者区分を要注意先以上に維持する必要があります。
なお、債務者区分は明確なものであり、次の要素によって決められています。
- 業績は赤字か黒字か
- 債務超過ではないか
- 延滞はないか

しかし、各銀行は規模や使命などが異なります。
都市銀行よりも地方銀行の方が地域密着であり、信用金庫はその要素がより強いといった違いです。
このため、各銀行は債務者区分を基準として、さらに銀行内で独自に格付けを行うことで、銀行ごとの差異を反映しています。
銀行格付けは、融資の判断に大きな影響を与えます。
債務者区分は同じ正常先でも、銀行格付けによって「優良な正常先」「一般的な正常先」「要注意先に近い正常先」といった分け方がなされるからです。
債務者区分と銀行格付けの関係を簡単に表すと、以下のようなイメージとなります。
| 銀行格付け | 債務者区分 | 概要 |
| 1~6 | 正常先 | 業績や財務状況に問題がない会社 |
| 7 | 要注意先 | 業績が下がっている、 軽微な延滞が起こっているなど、 今後の返済に注意を要する会社 |
| 8 | 要管理先 | 要注意先のうち、3ヶ月以上延滞している、 リスケジュールを依頼しているなど、 管理の必要がある会社 |
| 9 | 破綻懸念先 | すぐに経営が破たんするわけではないが、 経営難に陥っており、 今後の破綻が懸念される会社 |
| 10 | 実質破綻先 | 法的な破綻に陥っているわけではないが、 実質的に破綻していると見なせる会社 |
| 10 | 破綻先 | 法的な破綻に陥っている会社 |
銀行は、融資先をこの表のように格付けし、管理しています。
できるだけ有利な条件で、安定的に融資を受けるためには、債務者区分を改善するのはもちろんのこと、銀行格付けも改善する必要があります。
黒字であり、債務超過状態ではなく、延滞もない会社は正常先に区分されます。

大まかな部分で良い債務者区分を勝ち取り、なおかつ決算書の細かな情報から良い銀行格付けを勝ち取っていくのです。
銀行員が、決算書をどのようにチェックしているかを知っていれば、銀行格付けにプラスやマイナスの影響を与える点も把握することができます。
その点を改善すれば、銀行格付けアップに役立つことでしょう。
本稿では、業績から銀行格付けアップを図るために、損益計算書のポイントを解説していきます。

ファクタリングについての記事はこちら

損益計算書のポイント

損益計算書とは、1年間の利益または損失の状況を表す資料です。
これを見ることによって、売上や経費、利益、損失などが分かります。
良い銀行格付けを勝ち取るためには、損益が黒字になっていることが最低限の条件です。
ここで赤字になってしまうと、銀行は債務者区分を引き下げ、銀行格付けもダウンすることになります。
ただし、赤字が一過性のものであり、実質的な返済能力にあまり問題が見られない場合などには、債務者区分は正常先に据え置き、銀行格付けがいくらかダウンするだけという場合もあります。
銀行格付けアップのためには、損益計算書の内容を、銀行にとって好ましいものに近づけていくことが大切です。
そのためには、損益計算書の各項目について、以下のポイントをチェックし、必要に応じて改善していくことが重要です。
売上の推移
銀行員は、過去3年分の損益計算書を比較し、売上高がどのように推移しているかを見ます。
この時、売上が順調に伸びているかどうか、売上が低下しているならばなぜか、その理由は深刻なものかどうかといったことをチェックします。
また、その会社の売上の推移だけではなく、その会社が属する業界での一般的な推移とも比較されます。
たとえ売上が伸びていたとしても、同業他社の平均と比較して伸び率が低い場合には、伸び悩みの原因はどこにあるのかを見られます。
期首商品棚卸高・期末商品棚卸高
期首商品棚卸高は、前期の貸借対照表の「商品残高」と一致している必要があります。
また、期末商品棚卸高は、今期の貸借対照表の「商品残高」と一致していなければなりません。
ここで誤差が見られる場合、粉飾を疑われることになるため、チェックしておく必要があります。
売上総利益
売上総利益とは、売上から原価を差し引いたものであり、「粗利」とも呼ばれるものです。
この中からあらゆる支払いをして、残ったものが純利益となります。
また、売上総利益率という指標もあります。
これは、売上総利益を売上高で割ったものであり、この推移を比較することによって、会社の収益力を判断するのに役立ちます。
一般管理費・販売費
一般管理費・販売費には、「役員報酬や従業員の給与、福利厚生、宣伝広告費、接待交際費、水道光熱費」など、様々な項目が含まれます。
銀行員は、過去の決算書を用いて各項目の推移をチェックします。
その会社が同じ事業を行っているならば、一般管理費・販売費はほとんど変化なく推移しているものです。
そのため、ある項目が急激に変化しているような場合には、その原因を特定して判断に役立てます。
一般管理費・販売費の中でも、特に詳しくチェックされるのが役員報酬・従業員給与・接待交際費・減価償却です。


役員報酬
銀行は中小企業に対して、会社と代表者を一体と考えるのが普通です。
したがって、役員報酬も返済力の一部とみなします。
会社が返済困難に陥り、リスケジュールを依頼する際には、リストラ策のひとつとして役員報酬の削減を申し出ることが一般的ですが、これも役員報酬を以て返済力とみなすことの現れと言えます。
しかし、いくら会社と代表者が一体であり、代表者個人の収入を返済力の一部とみなすとしても、役員報酬が過大な場合には問題とされます。
役員報酬が大きいことによって会社の利益が圧迫されているような場合には問題なのです。
したがって、会社の規模や業界水準から考えて、役員報酬が適正であるかもチェックされます。
従業員給与
従業員の給与についても、会社の規模や業界水準から考えて適正であるかどうかをチェックします。
また、新規雇用に伴う増加、退職に伴う減少が反映されているかどうかもチェックされます。
接待交際費
接待交際費は、代表者の個人的な付き合いなどに流用されることも多いため、その会社の規模や業界水準と比較して適正であるかどうかをチェックされます。

そのため、利益への影響度という観点からもチェックされることになります。
減価償却費
減価償却費は、主に法定限度額まで正しく計上されているかどうかを見られます。
これは、減価償却費を敢えて少なくすることで、利益を大きく見せかけるなどの操作が可能だからです。
もし、減価償却費が過少に計上されている場合には、限度額まで計上したものとみなして査定されるため、利益が目減りすることとなります。


営業利益
営業利益とは、売上総利益から一般管理費・販売費を差し引いたものであり、これが赤字になっている場合には、その事業で利益が出ていないということになります、
そのため、銀行格付けに大きくマイナスの影響を与えます。
また、営業利益を売上高で割った「売上高営業利益率」という指標は、会社の収益力や管理効率を把握するために指標であり、こちらもチェックの対象となります。
支払利息
営業外費用の中でも、支払利息はよくチェックされる項目です。
というのも、借入額に対して利息が大きい場合には、ノンバンクなどで高金利の借り入れをしている可能性があるからです。
会社がいきなりノンバンクから借りることはあり得ず、普通の銀行では借りられなかったからこそ、ノンバンクで借りているのです。
業績や財務などに何らかの問題があり、銀行から融資を受けられなかったのですから、ノンバンクからの借り入れが発覚すると、銀行格付けに大きなマイナスとなります。
経常利益
経常利益は、営業外収益と営業外費用を考慮したうえでの利益です。
営業利益は本業での稼ぐ力を表すのに対し、経常利益は会社全体での稼ぐ力を表します。
経常利益が赤字の会社は融資を受けるのが困難とも言われるように、経常利益は銀行格付けに大きな影響を与える項目です。
特別利益・特別損失
特別利益・特別損失とは、臨時に発生する利益や損失のことです。
よくあるのは、不動産や有価証券の売却によるものです。
不動産や有価証券を売却し、利益が得られたならば特別利益に計上し、損失が発生したならば特別損失に計上します。
特別利益や特別損失は、あくまでも一時的なものであり、(内容にもよりますが)銀行格付けにもそれほど大きな影響を与えません。
しかし、特別利益や特別損失の内訳を精査し、他の項目に振り替えることで、銀行格付けアップに役立つ可能性があります。
例えば、特別利益のうち、営業外収益に振り替えられるものがあれば、経常利益を増やすことにつながります。

当期純利益
当期純利益とは、経常利益に特別利益・特別損失を加味し、そこから税金を支払った結果、最終的に会社に残るお金のことです。
銀行は、会社の得た利益の中から返済を求めますが、これは当期純利益を返済力とみなすということです。
このため、当期純利益がマイナスになっている場合には、返済力がないと判断されます。
そのような状態では、新規融資が不可能であることは言うまでもありませんし、既存の融資にも危機感を持たれることとなり、銀行格付けには大きなマイナス評価となります。

まとめ
銀行の格付けの考え方や方法を知ることによって、会社側が格付けを上げるための取り組み方も見えてきます。
特に、損益計算書を改善して利益を増やすことは、格付けを向上させるための根本的な取り組みとなります。
格付けの向上を目指しながら会社の稼ぐ力も伸ばしていくことができるため、全ての企業が積極的に取り組むべきことと言えるでしょう。
単に格付けを上げるためではなく、真の目的はよりよい会社に育てることであると認識し、様々に取り組んでいくことをお勧めします。