※本記事はプロモーションを含みます。
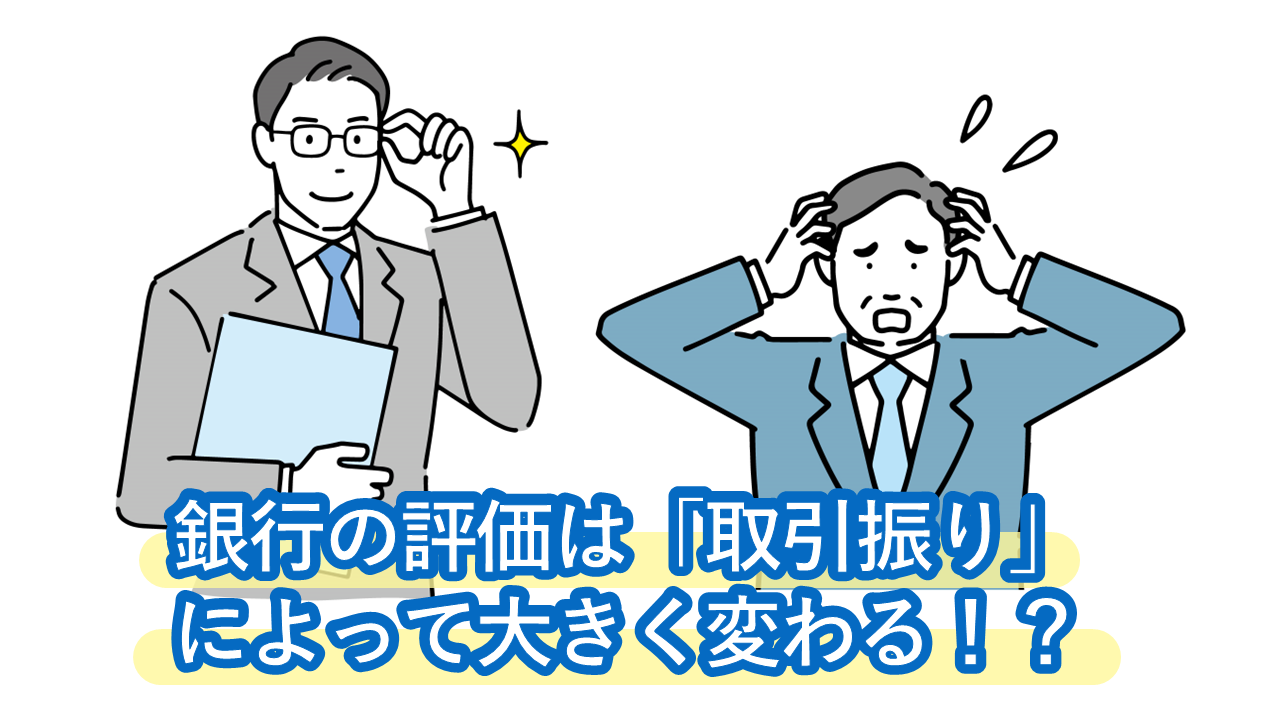
銀行が取引先の会社を評価する基準は多種多様です。
多くの経営者は、業績や財務状況が評価の基準になっていると思うかもしれません。
確かに、業績や財務が良好であるに越したことはないのですが、銀行の評価はそれだけでは決まりません。
取引先の会社が、「銀行にとってどれだけの収益をもたらしてくれるか」も重要なポイントとなります。
そこで知っておきたいのが、「取引振り」を融資交渉に活用する観点です。
本記事では、困難な融資交渉を成功させた実例とともに、取引振りの重要性を解説していきます。
【ポイント】
追加の銀行融資が期待できない場合でも、売掛金を使った「ファクタリング」で資金調達ができる可能性があります。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

取引振りとは?

取引振りの意味には幅があり、広義と狭義では少し意味が異なります。
▼取引振りとは?
- 広い意味:取引先の会社とどのような取引関係にあるか
- 狭い意味:取引先の会社と融資以外にどのような取引関係にあるか
銀行員が稟議書などで用いる場合には、おもに後者の意味で用いられます。
取引振りの重要性

銀行と会社の関係において、取引振りは非常に大きな意味を持っています。
なぜなら、銀行にとっての収益源は、融資で得られる利息収入だけではなく融資先との関係の中で生まれる包括的な収益で見るからです。
銀行から融資を受けている会社から見ると、「会社は融資が受けられる」、「銀行で儲けられる」ため両者に利益があると考えられます。
しかし、銀行経営は利息収入だけで成り立たず、取引会社との全体的な「取引振りの充実度」が非常に重要になります。
これは、具体例で考えるとよくわかります。
取引振りの具体例
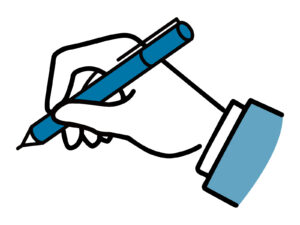
ある銀行が、A社とB社の両方に1億円の融資をしていたとしましょう。
貸し倒れリスクや融資条件などはどちらも同じで、金利は2.0%と仮定します。
この時、A社とB社がきちんと返済すれば、銀行は年間200万円の利息収入を得ることができます。
しかし、A社とB社では取引振りが異なっていました。
▼A社とB社の取引振り
- A社:預金取引、支払い取引、外為取引など
- B社:融資以外の取引なし
B社は融資以外の取引がない一方、A社は多くの項目で取引があり、取引振りが充実しています。
この差は銀行の収益にも大きくかかわっており、銀行はA社から利息以外にも各種手数料が得られます。
当然ですが、B社からは利息の200万円いがいの収入は入ってきません。
銀行が、A社とB社のどちらを優良顧客であるとみなすかと言えば、もちろん「収益性の高いA社」です。
【ポイント】
銀行はA社を積極的に支援し、囲い込みのために良い条件で融資する可能性が高いです。
取引振りとリスクヘッジ
取引振りは収益性の観点だけでなく、リスクヘッジの観点からも銀行にとって重要です。
A社とB社のケースで再び考えてみましょう。
この両社に1億円ずつ融資したとき、年間200万円の利息収入が期待できますが、1年で貸し倒れになれば9,800万円の損失になります。
この貸し倒れリスクに備えて銀行は担保などを求めますが、中には担保や保証協会からの融資枠もない会社があります。
このような無担保プロパー融資は銀行にとってハイリスクな融資になるため、よほど業績に強みがなければ銀行は融資を避けたいでしょう。
A社とB社に置き換えると、両社ともに無担保だった場合、B社の場合は融資以外に何の利益もないのに9,800万円の貸し倒れリスクを背負うことになります。
A社に関しても無担保であることは同じですが、取引振りが充実しているため200万円の利息収入以外にさまざまな収入が期待できます。
A社なら同じハイリスクな融資だとしても、それに見合うだけのリターンが期待できると考えて融資する銀行もあるでしょう。
【ポイント】
取引振りは、高い収益性が期待できるだけではなく、その収益性が銀行にとってのリスクヘッジになることもあります。
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングについての記事はこちら

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
取引振りを意識して融資交渉をしよう!

先ほどの例かわわかるように、銀行にとって各社との「取引振り」は非常に重要です。
取引振りは、銀行が積極的に融資を検討するに足る、強力な交渉カードとなります。
会社側これを理解し、融資交渉の際に取引振りを意識して交渉してみましょう。
取引振りを交渉カードにする具体例

取引振りを交渉カードにしたことで、困難な状況でも融資を引き出せた実例を紹介します。
【実例紹介:電子部品の製造会社C社のケース】
電子部品の製造会社であるC社は業歴40年と長く、国内での営業基盤が確立されている中小企業です。
しかし、当時のC社は電子部品製造の拠点が中国に移ったことで、直近の業績が悪化していました。
C社も数年前から生産拠点を中国に移していましたが、それに伴う出費が大きく資金繰りに苦労している状態でした。
銀行目線で見ると、財務的に苦しく、業績も安定しないなど懸念点の多い会社だと言えます。
運転資金増加の申し入れと保全不足
そんな時にC社は、国内大手企業から大型の受注を獲得したため、運転資金増加のカバー目的で準主力行のB銀行に4000万円の増加運転資金を申し入れました。
この大手からの受注は継続される見通しも立っており、業績に大きな好影響を与える前向きな融資に間違いありません。
しかし、B銀行はメインバンクでもなく、不動産などの担保がメインバンクに独占されている関係ですでに相当の無担保融資をしていました。
これ以上の追加融資には保全が必要な状況です。
【C社への追加融資が難しい理由】
- 担保がない(メインバンクに取られている)
- 信用保証協会の保証枠がない(使いきっている)
- すでに相当の無担保融資がされている
- 業績が不安定かつ財務状況も厳しい
こういった理由から、B銀行はリスクの高い融資に当初は消極的でした。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

取引振りが突破口に
こんなとき、準主力行は融資を断るのが普通です。
その際の常套句は、「メインバンクから融資を受けてはどうですか?」というものです。
こういうときは「メインバンクが支援すべきだろう」という銀行にとって一般的な考え方です。
しかし、C社はすでにメインバンクに融資を断られており、B銀行にも断られると非常に苦しい状況にありました。
そこでC社が持ち出した交渉が「今後の取引振りについて」です。
今後の取引振りを引き合いに出した交渉
【C社の主張】
経営計画書からもわかる通り、今回の取引でわが社の業績は大きく改善される見通しです。
この販路が拓かれることでで、年間○千万円の輸出為替が発生します。
新たに発生する輸出為替をB銀行さんにお願いすれば、大幅に預金も増えると思います。
運転資金を融資していただくことで、当社の輸出為替とそれに伴う預金を提供することができます。
融資額以上の預金増加は確実ですし、保全につながると考えますので融資を検討してほしいです。
このように将来の取引振りをカードに交渉を持ち掛けたのです。
本来は、保全を確保した後に融資を実行するのが普通であり、保全を確保するために融資を実行するのは順番が逆です。
しかし、結果的に保全確保につながることや今までになかった融資以外の取引ができるメリットにより、本件の交渉は一気に前向きになりました。
検討の結果、将来的な保全の充足、取引振りの充実という交渉材料は合理的な理由になり、融資実行にこぎつけることができました。
【コラム】ファクタリングという手段も!
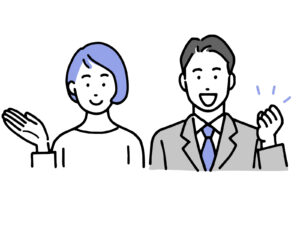
「銀行との交渉に使う取引振りなんてない!」
「銀行融資は難しそう……」
そんなときは、売掛金や注文書を活用した「ファクタリング」で運転資金を確保する方法もあります!
ファクタリングとは、売掛金を専門業者に売却することで運転資金等を調達する方法です。
本来、売掛金を現金としてもらうには支払日まで待たなくてはいけません。
これを専門会社に売却し、先に現金として受け取る方法がファクタリングです。
専門業者は売掛金額から報酬(=手数料)を引いて会社に入金するため、本来の売掛金額よりも受け取る金額は少なくなりますが、早めの資金調達が可能です。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
C社の例のように、取引振りを交渉カードにすることで、銀行の懸念する保全不足をカバーできる場合があります。
銀行に、どれだけの旨味を与えられるかによって、交渉の成否は変わってくるでしょう。
このような交渉を知っておくと、銀行にとって付き合いたい相手と思わせることができ、付き合いがスムーズになります。
ぜひ、交渉の手段として知っておくと良いでしょう。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
銀行の評価が変わる「取引振り」の意味とは?資金調達・融資を引き出す交渉カードにしよう
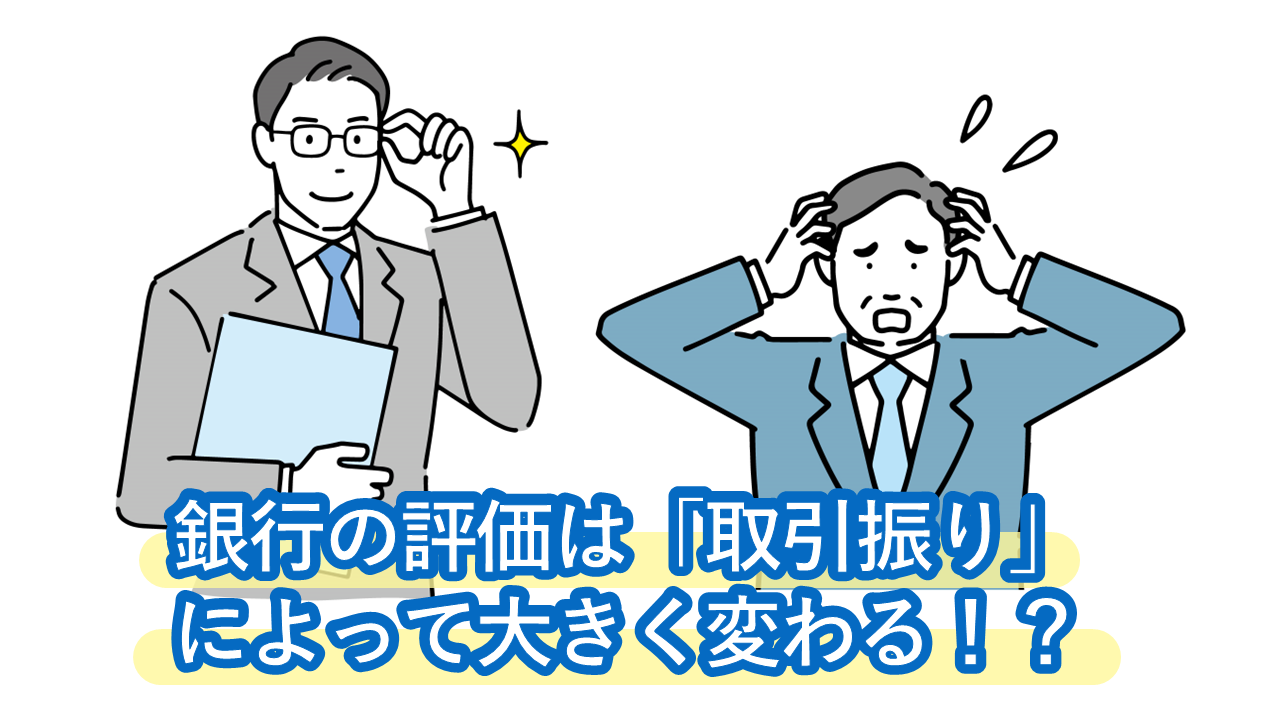



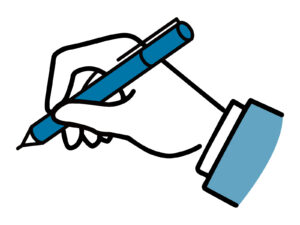





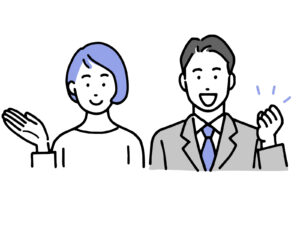




コメント