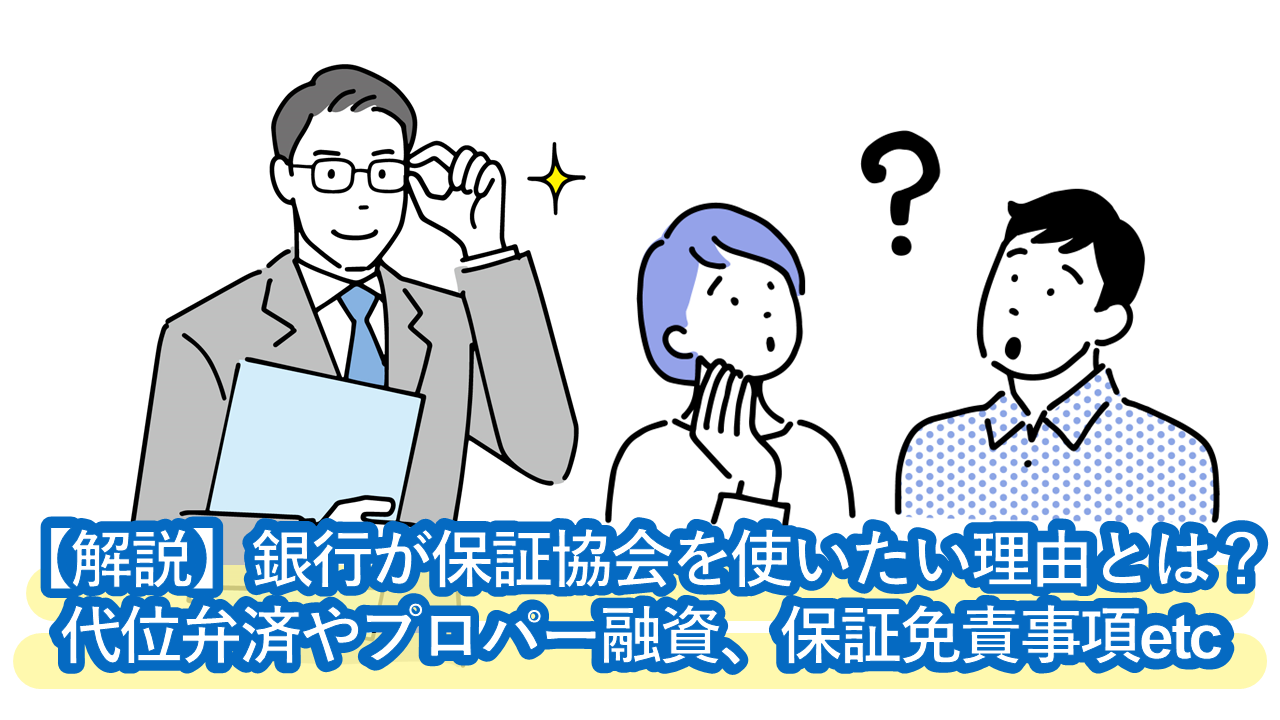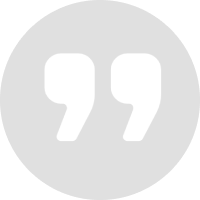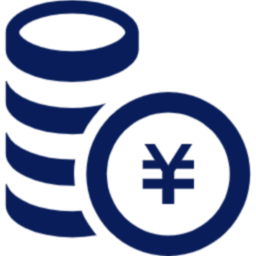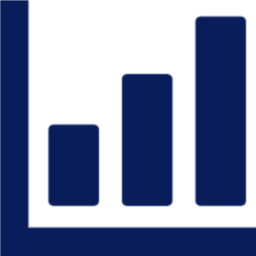ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
1.銀行の保険として役立つから

銀行が保証協会付き融資を好む最大の理由は、「融資を保証協会が保証してくれるから」です。
万が一、融資が貸し倒れてしまった際も、保証協会が代位弁済してくれるため銀行が受ける損失は最小限となります。
たとえば、銀行がある会社に1,000万円を融資したとしましょう。
これが貸し倒れてしまった場合、基本的に銀行は民間のサービサー※に数十万円で債権を売却します。
※金融機関から委託を受けて債権回収を行う専門業者。
このケースでは銀行が担保をとっていなければ、900万円以上の貸し倒れになる可能性が高いです。
しかし、保証協会付き融資ならば、保証協会が代位弁済(=第三者による借金の返済)をしてくれます。
銀行は、この保険効果を狙って、中小企業に保証協会付き融資を勧めている側面があります。
【ポイント】
銀行と保証協会が貸し倒れを共有する「責任共有制度」の利用でも、銀行が受け持つ貸し倒れは融資残高の20%で済みます。
【注意】お金を借りた企業の借金は消えない!
【注意】銀行への返済は保証協会が行ってくれていますが、お金を借りた企業の借金が消えるわけではありません!
保証協会が代位弁済した金額は、保証協会から会社に請求されます。
経営者の中には、保証協会付き融資を受け、保証料を支払えば、返済不能時の借金を肩代わりしてもらえると勘違いしている人がいますが、これは誤りです。
代位弁済が行われても、企業の借金は減りません。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

2.銀行の利益保全に役立つから
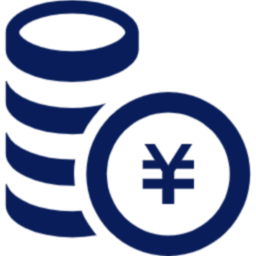
銀行にとってのメリットは、先ほど紹介した「保険効果」だけではありません。
ほかにも「利益保全効果」があります。
まずは貸倒引当金の仕組みを解説
利益保全効果を知るために、まずは銀行の「貸倒引当金」について解説します。
【貸倒引当金とは】
貸し倒れに備えて、プロパー融資の融資額の数割を事前に計上しておくこと。
融資先の信用ランク等※で積立額が変わります。
※信用ランクとは自己査定を意味し、融資先の状況に応じて、通常先、要注意先、要管理先、破たん懸念先などに分けられます。
通常先や要注意先ならば無担保融資額の数%を積み立てるだけでいいのですが、要管理先になると20%以上の貸倒引当金を積むことになります。
貸倒引当金として積み立てたお金は、他の用途に流用することはできず、ただただプールされているだけのお金です。
銀行としては、お金をそのように遊ばせておくのではなく、有望な融資先を見つけ貸し出し、利息収入を得たほうが良いと考えます。
貸倒引当金をたくさん積むのはこんなにも非効率
たとえば、金利3%で1000万円の融資を出したとしましょう。
融資当初は正常先に認定しており、貸倒引当金も数%で済んでいました。
しかし、融資後まもなく要管理先まで自己査定が落ちて得しまい、20%の貸倒引当金をプールしなければならなくなりました。
つまり、3%の利益(1000万円×3%=30万円)のために、20%の現金(1000万円×20%=200万円)をプールする必要が生じました。
このように融資先の信用度が下がると、貸倒引当金が多くなり、銀行の利益を食いつぶすことになってしまいます。
保証協会付き融資なら銀行の利益を守れる!
しかし、証協会付き融資なら、この心配はありません。
万が一の際にも保証協会の保証がありますから、自己査定が下がりにくくなり、貸倒引当金のプールも少なくて済みます。
これにより、銀行は利益をより活用できるようになり、大きなメリットが得られることになります。
このように、保証協会付き融資には、銀行の利益を保全する効果があるのです。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

3.銀行員の個人成績に反映されるから
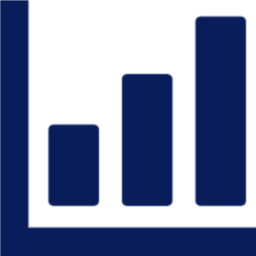
保証協会付き融資には、銀行の経営だけでなく「銀行員個人」にとってもメリットがあります。
銀行にとってリスクの少ない保証協会付き融資は非常に好ましい商品です。
よって、銀行は行員に対し、「保証協会付き融資を出すと本人の得になる制度」を用意しています。
たとえば、ある銀行では融資に対してポイントが付与されるのですが、そのポイントがプロパー融資より保証協会付き融資の方が高くなっています。
ボーナスを多く貰いたい、早く昇進したいと考えるなら、行員はプロパー融資を出すよりも保証協会付き融資を出した方が有利なのです。
こういった銀行の仕組み、行員個人の事情にも、保証協会付き融資を強く勧める理由があります。
4.融資を断る口実として便利だから

最後に、保証協会付き融資なら「融資を断る口実として役立つ」というメリットもあります。
融資を断る際はトラブルが発生しやすいです。
融資を率直に断ってしまうと、ゴネたり逆切れしたりする経営者が多く、銀行員はそれを恐れています。
そこで、融資を断る際のトラブルを減らすために保証協会を理由に使うことがあるようです。
こんなときにも保証協会が理由になる!?
通常、企業が融資を打診した際、下記のような流れで融資が行われます。
【保証協会付き融資の流れ】
- 銀行が会社に対し保証協会付き融資を提案
- 会社が受け入れると稟議が行われる
- 保証協会に提出する「信用保証委託申込書」を作成
- 3の書類に会社、銀行が記入し保証協会に提出
- 保証協会で審査
- 問題がなければ、保証協会から銀行に「信用保証書」が送付
- 銀行は信用保証書を得たことを踏まえ、再度稟議を行う
- 稟議で問題がなければ、融資が実行される
このように、保証協会付き融資では、たくさんの書類のやり取りが行われます。
これだけ書類のやり取りが多いと、時に書類を送り忘れていたり、書類を紛失してしまうことがあります。
このような場合、まさか「送り忘れていたのでもう少し待ってください」などと素直に言うことは非常に難しいです。
そこで、「信用保証協会の審査に時間がかかっており……」などと保証協会を口実に言い訳するケースもあるようです。
【ポイント】
銀行からすると、経営面でも個人のメリット面でも保証協会付き融資は便利でお得な商品として勧めやすいです。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

銀行が嫌う保証免責事項とは?

以上の4つからわかるように、基本的に銀行は保証協会を利用することで、さまざまなメリットを得ています。
しかし、銀行と保証協会とのかかわりの中で、銀行が一つだけ非常に嫌うものがあります。
それは、保証協会が保証にあたって設ける「保証免責事項」です。
会社が信用保証協会に保証をお願いするとき、銀行を通じて「信用保証委託申込書」を提出し、問題がなければ保証協会が保証をしてくれます。
ただし、保証協会が認識している申込内容と実際の融資の様子が異なっている場合は、保証免責事項が発動します。
具体例としては、保証額を満額融資していなかった、返済期間が違っていた、資金使途が違っていたなどです。
銀行はなぜ保証免責を嫌うの?
保証免責が発動すると、保証協会は保証を解除できます。
すると、貸し倒れが発生した際に、銀行は保証が受けられず大変困ります。
当然、銀行は保証免責を嫌うため、ミスがないように手続きをしますが「資金使途違反」は銀行の手続きに関係なく起こる可能性があります。
たとえば、設備資金として融資したはずのお金が運転資金になっていたなどのケースが良く見られます。
この場合にも、保証協会は保証免責事項を理由に保証を解除します。
銀行が資金使途違反を勧めてくる場合がある!?
銀行が資金使途違反を勧めてくるケースがあり、この方法を「旧債務振替」と言います。
【旧債振替(きゅうさいふりかえ)】
新しい貸付債権に信用保証協会の保証をつけて、当該金融機関の既存債権を消滅させることをいいます。
金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、 金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となります。
ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、 例外的に認められることがあります。
引用:愛媛県信用保証協会-用語解説集
具体的には下記のような流れで行われます。
- 元々プロパー融資で3,000万円融資していた
- 銀行は5,000万円の保証協会付き融資を持ち掛ける
- 会社はこれを受け入れ、保証協会付き融資に切り替える(運転資金として5,000万円を借りる)
- 融資を受けた5000万円のうち、3000万円はプロパー融資の返済に充て、2000万円を運転資金とする。
このような方法によって、銀行はプロパー融資を保険と利益保全の効果のある保証協会付き融資にすり替えることができます。
当然、この旧債振替は一部の例外を除き禁止されています。
このような話を銀行員が持ち掛けてきた場合には、断るようにしましょう。
【注意】
プロパー融資を受けられているということは、会社の財務内容や業績がそれなりに評価されていると考えられます。
それを、銀行にメリットが大きいという理由だけで保証協会付き融資に乗り換え、高い保証料を支払って資金調達する必要ないでしょう。
まとめ
保証協会を利用すれば、会社にとって融資を受けやすくなるメリットがありますが、それ以上に銀行側のメリットが大きいのも事実です。
銀行や担当の銀行員によっては、こういった内部の事情から保証協会付き融資を過度に勧めてくることもあるでしょう。
保証協会付き融資の利用には、保証料が必要です。
本当に保証協会付き融資を利用した方がいいか、申込前にさまざまな角度から検討してみてください。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼