
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
銀行との面談で損しないための注意事項

定性面でマイナスの印象を与えないよう、当然ではありますがビジネスマナーはきちんと把握しておきましょう。
ビジネスマナーと一言で書けば簡単に思えますが、銀行面談においては「銀行が考えるマナー・常識」を表現する必要があります。
中には融資を受けたいという気持ちから不適切なふるまいをしてしまう経営者もいます。
定性評価でマイナスとならないよう基本ポイントをしっかりとおさえておきましょう。
1.資料の説明は完璧にできるように
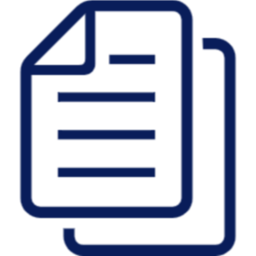
面談に臨む経営者は、第一に資料をきちんと説明できなければ話になりません。
資料の内容を深く理解し、資料の数値の根拠やそれぞれの相関性なども含めて説明できるよう事前に準備しておきましょう。
経営者が事業内容を深く理解しており、担当者の質問にも難なく回答できれば、融資にプラスの印象を与えられることもあります。
2.時間厳守が鉄則

融資を申し入れて面談が決まると、面談日と面談時間が決められます。
面談では時間厳守が鉄則であり、10分前には到着しておくべきです。
これは当たり前のことで、時間厳守は当然だと考えている経営者がほとんどだと思います。
しかし、取引先との商談ではきちんと時間を守る経営者でも、銀行との面談では時間にルーズになる人がたまにいます。
銀行との面談で時間を守らない経営者は、以下のように考えていることが多いです。
①自社は銀行の客である
あくまでも自社は客であるという考え方があげられます。
「銀行からお金を借り、銀行に利子を払うわが社はあくまで銀行のお客である。だから少し遅刻しても問題ないだろう」
このような考え方です。
このような考え方をする会社は、比較的経営状況が良好でスムーズにお金を借りられそうな会社に多いです。
たとえ、銀行から「融資を受けませんか?」と提案された側であっても、銀行も取引先の1つと考え時間厳守は徹底しましょう。
②自社の立場を分かってくれているだろう
次に、自社の立場を分かってくれているだろうという考えがあります。
「今は非常に厳しい時期で、仕事も忙しい。面談時間には遅れてしまうけれども、銀行もこの状況はわかってくれるだろう」
経営が非常に苦しい会社では、経営者はさまざまな対処に追われていることでしょう。
たとえば、取引先に売掛金の支払いを少し待ってもらうようにお願する交渉が長引き、銀行との面談に遅れてしまったとします。
確かに、銀行も会社の状況は理解していますが、やはり遅れそうな場合は事前に連絡すべきです。
「苦しい状況をわかってくれているはずだから大丈夫」とは考えないようにしましょう。
これは会社が好調な場合も同様です。
会社が忙しく商談等で遅れそうな場合であっても、一言遅れそうだと伝えるだけで印象は大きく異なります。
③時間を守れない人には貸せない
基本的に、銀行相手であっても面談を設定した以上、「時間厳守は鉄則」です。
ビジネスでは「時間を守れない≒約束を守れない」と考える人が多くいます。
融資を返済することは、経営状況や外部要因なども関わり、時間を守るよりも何倍も難しいことです。
銀行担当者によっては、「面談の時間も守れない会社が事業計画を守れるのか?」と考えてしまっても無理はありません。
業績が好調な会社で、銀行から融資を提案している状況であっても、フォローもなく時間を破られた場合、銀行からの印象はかなり悪くなるはずです。
【ポイント】
事情があり面談時間に遅れそうなときは必ず銀行に連絡するようにしましょう。
大幅に遅刻しそうなときは日程変更も検討してください。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
3.面談日時の変更は避ける

時間だけでなく、緊急の事情がある場合を除いて、面談日時の変更も避けた方がいいでしょう。
銀行員は1人で複数の企業を担当しているため、日程変更をお願いしても「すぐには再日程を組めない」、「希望の日程が空いていない」ということがあります。
絶対に受けたい融資などの場合は、日付変更をしなくてもいいように面談を中心にスケジュールを組んでおくのが無難です。
経営が苦しいからこそ面談日は変更しない
経営が苦しい場合、「この融資がなければ経営が立ちいかなくなる」という危機迫る状況のときがあります。
取引先との交渉などさまざまなタスクが降りかかっていますが、資金調達は非常に重要なミッションです。
経営が苦しいときこそ、銀行面談の日程は変更しないようにしましょう。
経営が順調なときであっても、日程変更は避けた方がいいです。
4.面談用の服装はいりません

銀行面談時の服装は特にこだわる必要はありません。
基本的に、銀行面談は提出資料の確認や経営者の人柄確認を目的に行われるため、服装が審査に大きく関係するとは考えにくいです。
「金銭に関する面談を行うのに適した服装」であれば問題ありません。
普段スーツを着ている方であれば、普段通りのスーツで大丈夫です。
普段が作業着の方であれば、汚れのない清潔な作業着で臨めばそれで問題ありません。
わざわざ高いスーツを用意する必要はないです。
基本的に、「経営者としてどうなの?」と品格を疑われるような服装でなければ問題ありません。
【銀行面談での服装ポイント】
- 普段の仕事着で問題ない(作業着でもOK)
- 衣類は清潔にしておくこと
- 華美な服装になり過ぎないようにすること
一般的に銀行員は保守的な考え方の人が多いため、迷った際は派手過ぎないスーツを選ぶのが無難でしょう。
清潔なスーツであれば、見た目で大幅なマイナスを受けることはほぼないはずです。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

5.手土産はいりません
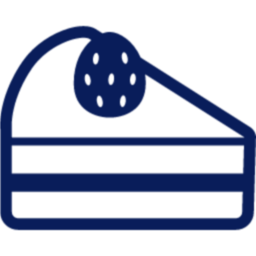
銀行面談とはいっても過度に気を遣う必要はありません。
融資がかかっている会社にとっては少しでも担当者からの印象を良くしたい、良い関係を築きたいと考えている方もいます。
そんな気持ちから手土産を持参する経営者もいます。
ですが、銀行への手土産・お菓子(菓子折り)の持参は不要です!
銀行は顧客とお金に関する取引をするため、顧客から簡単な手土産であっても癒着と見られるのを警戒し受け取りにくいことがあります。
角が立つため受け取りを拒否することはそうありませんが、代わりに同額のお礼を渡すケースが多いです。
手土産を渡すとこのような物品のやり取りが発生してしまうため、手土産・お菓子は不要です。
手土産の有無で融資への判断が変わることはないので安心してください。
銀行からの手土産は受け取っていいの?
担当者との付き合いが長い場合、休暇明けの担当者からお土産を渡されることがあります。
このような銀行からの手土産は遠慮なく受け取って問題ありません。
銀行からの手土産となると何か意味がありそうですが、そこに意味はなく本当に「単なるお土産」です。
お菓子程度のものでしたら、変に断ることはなく受け取っておきましょう。
少なくとも好印象を持っていないお客さんにはお土産など買わないのですから、プラスに考えて受け取るようにしましょう。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

【コラム】ファクタリングという手段も!
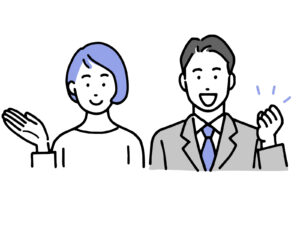
「銀行との融資交渉が上手くいかなさそう……」
「銀行融資では時間的に間に合わない!」
そんなときは、売掛金や注文書を活用した「ファクタリング」で運転資金を確保する方法もあります!
ファクタリングとは、売掛金を専門業者に売却することで運転資金等を調達する方法です。
本来、売掛金を現金としてもらうには支払日まで待たなくてはいけません。
これを専門会社に売却し、先に現金として受け取る方法がファクタリングです。
専門業者は売掛金額から報酬(=手数料)を引いて会社に入金するため、本来の売掛金額よりも受け取る金額は少なくなりますが、早めの資金調達が可能です。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
銀行との面談では、経営者のビジネスマナーやふるまいなども見られています。
解説を読んでみると、どれも当たり前のことばかりだと思うかもしれませんが、ここで失敗してしまう経営者は残念ながら実際にいます。
また、知らず知らずのうちに間違いを犯していることもあります。
定性面でマイナス評価がつかないように、面談前に基本をおさえておくと安心です。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
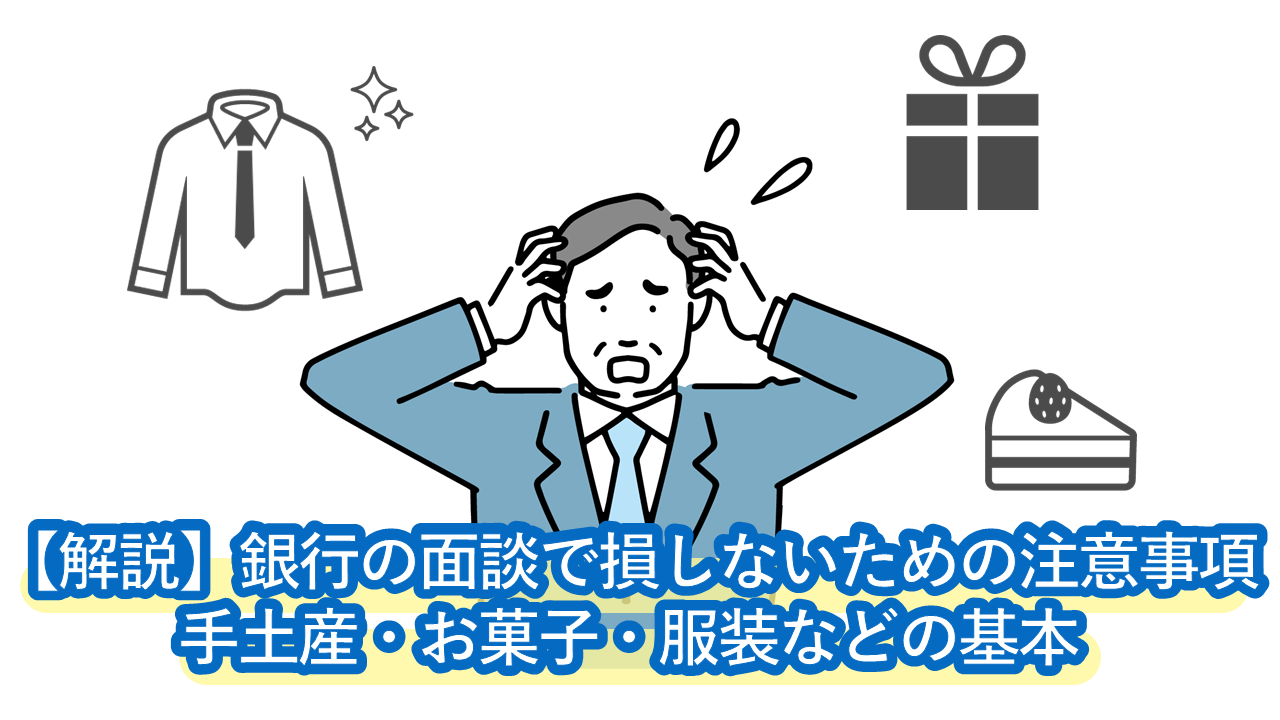








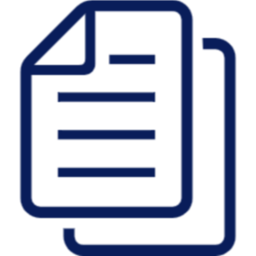




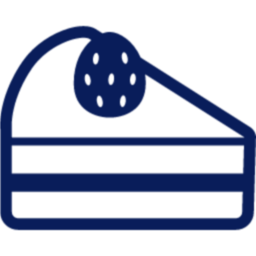
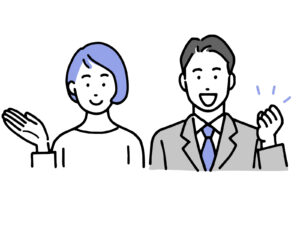



コメント