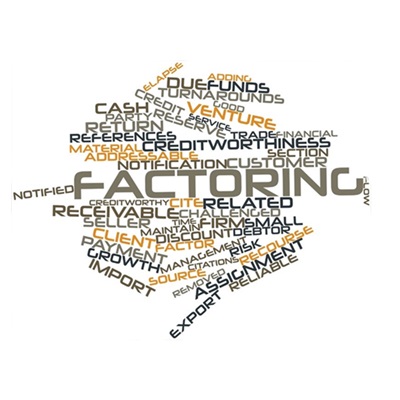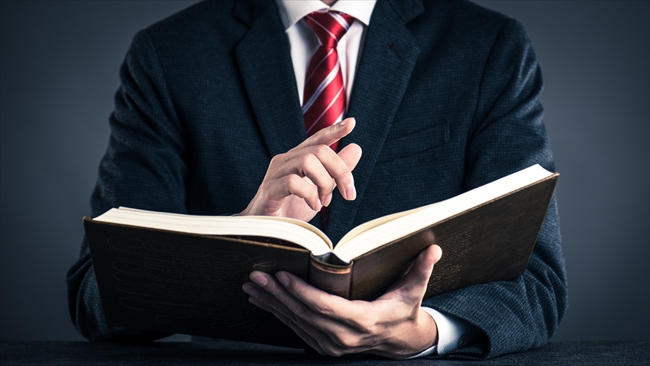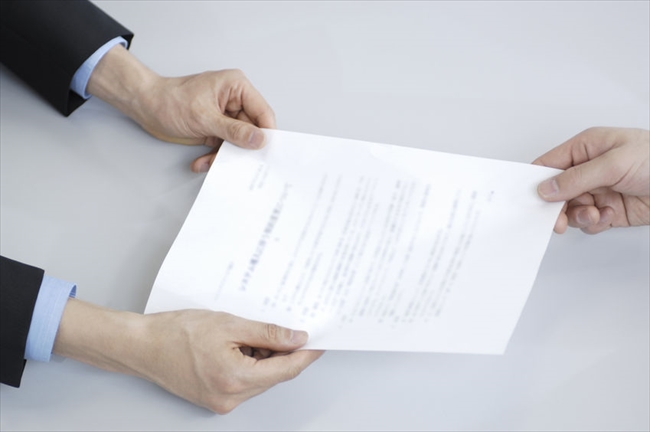資金繰りに困った企業が銀行などから借入をしようとしたとき、通常は担保を用意して資金調達をすることになるものですが、そうしなくてよくなるメリットは大きいと言ってよいでしょう。
最近までは優良企業と目されていた大企業でさえ、一回の不祥事で経営危機に陥ってしまうケースがあるのです。どの程度の不祥事であるかにもよりますが、東芝のケースなどが良い例でしょう。
日本の株式市場の回復などをみるにつけ好景気と言われますが、あの動きは投機的な市場の熱狂という側面も確実にあり、実際にはアベノミクスの恩恵を受けた実感できない中小企業も多いのではないでしょうか。
売掛債権をどの程度持っているかということは、その企業が属する業種によっても異なりますが、売掛債権をたくさん持っている企業がその売掛債権を売却して資金を調達することができたならば、資金繰りが良くなると同時に経営を単純化することもできます。
この企業はソフトウェア関連のベンチャー企業なのですが、ファクタリングを取り入れたことで信用力や販売力の強化に成功し、経営規模を短期間で拡大することに成功しました。
ベンチャー企業は、成長力を秘めているものの資金繰りに窮して潰れてしまうことが多いものですが、ファクタリングによって売掛債権をスピーディに資金化することができれば、成長の助けとすることができます。
ベンチャー企業は成長によって売上を伸ばし、それに比例して売掛債権の保有も急速に増えていくことがあるため、その売掛債権を短期間で資金化して利益を回収することができれば、成長力のままに経営規模を拡大していくことが可能なのです。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
ファクタリングの概要
世界のファクタリングと日本のファクタリング

ファクタリングは、歴史や伝統においては銀行業務に匹敵するほどのものですが、それほどの歴史と伝統を持っているシステムとしては高い効率を保っており、電子商取引にも対応した現代的な方法でもあります。

CFイエロー
そもそも、ファクタリングが生まれたのは14世紀後半のイギリスなのよ!
その後、アメリカで発展を遂げた金融手法であり、欧米では(特に中小企業向け金融の分野で)ごくごく一般的に利用されています。
ファクタリングは国内取引と国際取引のどちらにも対応しています。とはいっても、現在ではまだ国内取引が大部分を占めています。

CFブルー
ファクタリングは世界的に普及しているものであり、その国の経済環境や顧客ニーズによってもそれぞれ特徴が異なるんだ!

CFイエロー
そして、国内取引と国際取引のウェイトも国によって異なるよ!
例えば、ヨーロッパはEUという経済圏がありますし、多くの国が隣接していることから、国際取引の比率が高くなる傾向があります。
これに対し、アメリカなどは国内市場が巨大であり、輸出入比率が比較的小さくなりますから、ファクタリング業務においても国内取引が大きくなります。

CFイエロー
では日本はどうだろう。
海外との貿易が活発である日本は、ファクタリング業務において国際取引のウェイトが大きくなりそうと思われますが、実際には1~2%という非常に小さなウェイトに過ぎません。
このことの理由を細かい部分も含めていえば色々な理由があるのですが、大きな理由を挙げるならば欧米諸国と比較して日本はまだファクタリングの普及が十分ではないこと、総合商社がファクタリング機能を代行してきたことなどが挙げられます。
国際ファクタリングの過半数はイギリス、アメリカ、イタリアが占めており、この3国を基軸として国際ファクタリングが発展しています。
今後、社会経済情勢の変化と共に、日本でもファクタリングはどんどん普及していくものと思われます。

CFイエロー
実際、日本でもファクタリングの将来性に注目が高まってきているのよ!
1970年代から銀行系を中心としてファクタリング会社が次々と設立されましたが、欧米との商習慣や金融システムの違いから普及が遅れていました。また、欧米とは異なる日本独自の業務展開もなされて行きました。
ファクタリングの取扱量では、日本の取扱量は3兆円規模になっていますが、これは世界シェアで見れば1割未満です。

CFブルー
しかし、最近ではファクタリングが見直されている!
手形が中心であった商習慣が変化していること、信用リスクの高まり、銀行の選別融資の強化、企業間信頼の収縮などが背景となっているほか、従来の銀行型金融に対する中小企業の不満が募ったことによって、ファクタリング普及の機が熟しているのです。
先述の通り、ベンチャーなどは資金調達の必要に迫られたときに銀行の融資を受けられないことも多いものです。
これらの新規事業を育成するためには、ファクタリングが有効であると注目されるようになっています。このように、ファクタリングが中小企業や振興事業に非常に有効な金策となっているのです。

CF戦隊
これまでの課題に行政が気づいたことによっても、ファクタリングの普及は進められている!
世界的に見れば行政の動きは遅いと言えますが、それでも債権流動化を進めるにあたっては従来の構造では無理であり、行政の後押しによって自立したファクタリング会社が生まれてきたのは非常に好ましいことです。
ファクタリングと売掛債権担保融資保証制度を比較する

日本における売掛債権を活用して資金を調達する手段としては、ファクタリングのほかに売掛債権担保融資というものがあることは先述の通りです。
当サイトでは主にファクタリングを推奨し、解説していますが、売掛債権の資金化をより活用していくためには、そのための手段はいくつかあることを知っておくべきです。
その方法の一つが売掛債権担保融資であり、ファクタリングと売掛債権担保融資を両輪としていくことが望ましいと言えます。
とはいえ、なぜ当サイトが数ある方法の中からファクタリングを推奨しているのかと言えば、それは単純にファクタリングの方が売掛債権担保融資よりも優れたシステムだからです。

CF戦隊
ファクタリングは、長い歴史の中で鍛えられてきたシステムですから、当然のごとく優れている!
多くの方法を知っていることの有意性から売掛債権担保融資も知っておくに越したことはないのですが、仮に売掛債権の資金化に関する仕組みがファクタリングだけだったとしても、それほど困らなかっただろうとも思えます。
売掛債権資金化に銀行が関わるにあたって、従来の銀行業務の歴史や伝統に沿う方法として、売掛債権担保融資が生まれてきただけのことであり、もし銀行がファクタリングを取り扱っていたならば、そもそも売掛債権担保融資というシステムは生まれてこなかったことでしょう。
しかしながら、ファクタリングが日本に入ってきたころはまだまだ手形流通が盛んであったことや、債権を譲渡することへの抵抗も強かったため、独立したファクタリング会社がファクタリングを行うよりも、銀行が業務の一環として行い、その手段として売掛債権担保融資が生まれたことは仕方のなかったことでもあるのです。
銀行が参入したことで売掛債権の資金化が抵抗なく受け入れられることとなれば、銀行の好影響も大きいと言えます。

CFレッド
]ファクタリングと売掛債権担保融資を簡単に比較すると、以下のような違いが見られる!

CFイエロー
この比較を見ても分かる通り、売掛債権担保融資とファクタリングでは、ファクタリングの方が優れていることが分かるわね!
借入ではなく譲渡であること、取引限度額に上限がないこと、様々なサービスが付属した総合金融サービスであることなどだ!
しかしながら、公的機関からの保証が受けられるという点においては、売掛債権担保融資が優れていると考えることもできます。
ファクタリングの機能と総合商社

ここまで書いたことを見ると、ファクタリングが非常に優れた方法であることが分かると思います。
しかし、ファクタリングは全ての産業に適しているとは言えません。
また、同じ業界内においても、ファクタリングが有効である企業と有効ではない企業とがあります。
これは、日本が戦後に輸出を振興していくにあたって、総合商社が大きな金融機能を果たしたことが関係しています。

CFイエロー
これを知ることは、ファクタリングの仕組みの一面を知るために有益だよ!
総合商社には色々な機能がありますが、基本的機能としては取引媒介機能、金融機能、危機回避・情報提供機能が挙げられます。
特に取引媒介では、様々な商品を総合的に取り扱うことによって、取引にあたっての複雑さを軽減し、流通過程を効率化することができます。
商社金融は、商品取引を円滑化することを目的として、取引先企業から信用を得るための手段として利用されることが多いものです。
情報機能では、国内外の様々な情報を収集・分析して取引やリスク軽減に役立てています。

CFブルー
日本では、このような業務を担う総合商社が巨大企業として君臨している!
三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事などが有名です。この存在が、ファクタリングの浸透を阻害してきたと言われています。
確かに、日本の高度経済成長期における商社金融の役割は大きかったでしょう。高度経済成長期といえども、中小企業は資金調達が容易ではありませんでした。
中小企業は担保にできるものが少なかったため銀行からも融資を受けることが難しく、受けられたとしても金利は高く、効率の良い資金調達手段とは言えませんでした。
そのような状態の中で、総合商社が商品の販売権を引き換えにして低金利で融資を行いました。
これを利用すると、中小企業は販売と金融の両面を商社に任せ、自分は商品の製造に専念することができました。
商社は銀行から低金利で融資を受けることができるため、そこから資金を調達し、中小企業に貸し付けて結びつきを強化し、大きな利益を獲得できます。総合商社と企業の関係はまさにWin-Winだったのです。

CFレッド
総合商社は危険回避機能にも優れている!
ファクタリング会社はカスタマー(顧客・債務者)とクライアント(売主・債権者)に対して危険を回避する機能を持っていますが、それはあくまでも債権回収に関わる部分のみです。
しかし、商社は商取引の段階から色々なリスクを背負うため、盛んに情報を収集して信用調査を行う必要があります。
このことから、商社金融とファクタリング会社を比較した場合には、商社の方が高い情報収集能力を有しています。

CFブルー
もちろん、ファクタリング会社でも信用調査は欠かすことができないのだ!
カスタマーとクライアントに関する情報を収集して審査を行う能力が、ファクタリング会社の営業成績を左右すると言ってもいいほどです。
ファクタリング会社の信用調査部門では、クライアントとカスタマーに関する膨大な情報が蓄積されており、定期的に見直し作業なども行われています。
とはいっても、国内取引に関する情報は収集しやすいものの、国際取引に関する情報は収集しにくいものです。

CFブルー
そこで、ファクタリング会社でも大きな会社になると、国際ファクタリング組織を構築して海外情報の収集に努めていることもあるのだ!
最近では金融事情が変化してきたため、従来の商社金融の意義は薄れつつあります。しかし、商社の総合力は未だに巨大であることも事実です。
特に、商社は取引媒介機能を通じて取引先企業の情報をより詳細に把握できること、それらの情報の活用においても一日の長があるのです。

CFイエロー
しかしながら、ファクタリング会社も記帳代行や電子商取引といった付属サービスを行うことで、独自性を持っているのよ!
ファクタリング会社と商社は取引媒介機能を除けば類似点が多く、互いに競合する存在です。総合商社の存在が巨大であることから、今後もファクタリングの普及が阻害されることもあるでしょう。
しかし世間の風潮はどうであれ、資金調達を考える皆さんが商社金融とファクタリング会社のどちらを利用すべきか、当サイトを見ながらよく考えていただければと思います。
ファクタリング会社の機能

ここまで、ファクタリングの機能について触れてきました。ファクタリング会社といえば、主に売掛債権の買取りばかりを行っていると思われがちですが、そんなことはありません。

CFブルー
ここからさらに詳しく機能的な面を見ていこう!
ファクタリング会社は、売主が商品の販売、サービスの提供、工事の施工などによって得た売掛債権の譲渡を受けると、それに対して様々な機能を提供します。
前払いで金融を行なったり、貸倒リスクを引き受けたり、会計処理や記帳事務を代行したりするのです。ファクタリング会社はファクタリング業務の提供によって、複雑な流通機構を単純化し、合理化します。
上記の総合商社との比較の観点から考えるならば、ファクタリングは商権を持たない総合金融機関といった位置づけをすることができます。

CFレッド
つまり、売掛債権の回収にあたっての複雑な手続きを依頼業者に代わって円滑に進めるための様々な機能を提供しているのであり、金融はその中のサービス機能の一つだ!
ファクタリング会社が持つ機能の基本は、譲渡を受けた売掛債権の回収が不能になった場合には、その回収リスクはファクタリング会社が負担するというものです。

CFイエロー
これを償還請求権なしファクタリングと言うよ!
ファクタリング会社では信用調査機能と情報提供機能が重要となります。
ファクタリング会社が企業の与信管理部門に代わって与信管理も行うことによって、「この顧客に販売してよいか」という判断をすることもできますが、これによってクライアントとなる企業は営業活動から与信管理を省き、より機能的に活動していくことができます。

CFレッド
信用調査や与信管理をファクタリング会社にゆだねることによって、経営資源を本業に集中することができるということだよ!
もっとも、企業の与信管理政策は企業自身が決定するものですから、ファクタリング企業は企業によって決定された与信管理政策の中でファクタリングを行っていくことになります。
しかし、ファクタリング会社が信用リスクを負担してくれることはファクタリングの大きな特徴であり、この機能をいかに発揮してくれるかということが、ファクタリング会社の優劣の決め手にもなります。
ファクタリング会社の機能


CF戦隊
ここで、ファクタリング会社の機能を整理しておこう!
1、金融サービス
企業の売掛債権の買い取り、売掛金の回収サービス、信用リスクの引き受け
2、信用調査サービス
情報データベースの構築による情報提供、売掛債権の保全
3、事務処理(会計処理)サービス
売掛帳簿の作成、記帳事務、売掛債権の期日管理などの事務処理・会計処理の代行
4、コンサルティング・サービス
電子商取引を含む経営上の様々な問題についての相談、経営管理資料の提供
しかしながら、これらはファクタリング会社とはどのようなものであるかということを考えたときの機能であり、現状ではこれらのすべての機能を完璧に備えているファクタリング会社は存在しないとされています。

CF戦隊
例えば、金融サービスと信用調査サービスをメインとして行い、それに付帯する業務として会計処理サービスや事務処理サービス、コンサルティング・サービスが行われるという形!
基本的には、ファクタリング会社は売掛債権を買い取って回収しており、その際に負うリスクの軽減のために信用調査を行っており、その傍らファクタリング会社の能力に応じて事務処理サービスやコンサルティング・サービスも行っているという事です。
しかし、近年の情報技術の急速な普及によって、ファクタリング会社とクライアントのデータベースの共有などが可能になってきており、それに伴って記帳などの業務代行サービスや経営管理資料の提供が重要な機能となります。

CFイエロー
また、日本におけるファクタリング会社には統一された定款がないことも、ファクタリング会社によって業務内容が異なる原因となっているの。
例えば、ある大手ファクタリング会社の定款を見てみると、目的の項には以下のように記載されています。
- 売掛債権の買取りおよび管理
- 売掛債権の買取りと管理に伴う融資および保証
- 輸出入の取次ならびに輸入信用状開設、輸入担保荷物貸渡、輸入荷物引取保証および輸入ユーザンスに関連する邦銀への保証
- 円建銀行引受手形の売買
- 円建銀行引受手形の売買の仲介、取次または代理
- 信用調査
- 売掛債権の記帳代行
- 経営コンサルティング
- 上記の項目に関連する一切の業務

CFブルー
これを見ると、大手ファクタリング会社の業務内容は多岐にわたっており、決して売掛債権の買取りだけではないことが分かる!
しかし、定款において多くの業務を請け負うとされていたとしても、実力がないファクタリング会社には幅広い業務の委託は期待できないでしょうし、必ずしも広くカバーしていることがよいとも言えません。
実力ある会社が広くカバーしてくれるならばそれに越したことはないでしょうが、もし単純に売掛債権の資金化だけを目的としているならば、会社の規模に関わらず多くのファクタリング会社を利用することができるでしょう。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングを深く知る
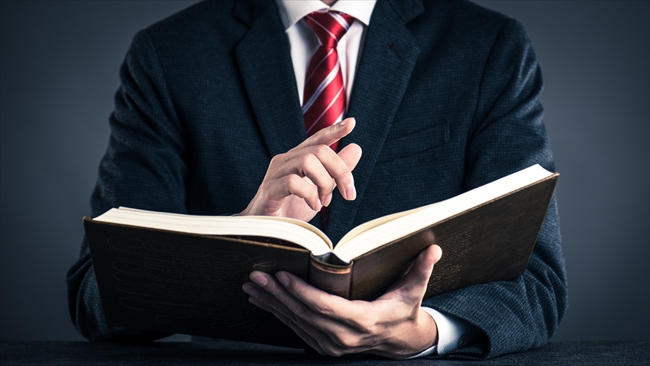
ファクタリングの分類・種別
次に、ファクタリングの仕組みを知るためには、そのディテールを把握することも大切です。
ファクタリングの分類
上記のファクタリング会社の機能でも書いた通り、ファクタリングは金融サービスと信用リスク負担サービスが主要な機能であり、その組み合わせに応じて三種類に分類されます。
償還請求権留保・前払方式ファクタリング(金融サービスのみ)
このタイプでは、売掛債権や手形の支払期日に一部や全部の支払いが滞った場合、または支払期日前でも滞ることが懸念された場合に、ファクタリング会社の請求によって一度譲渡した売掛債権を受け戻す義務があります。
クライアントが前払を受けている時は、クライアントは売掛債権・手形の返還を受けたときにその資金をファクタリング会社に弁済します。
償還請求権放棄・前払方式ファクタリング(金融サービス+信用リスク負担サービス)
ファクタリング会社は売掛債権や手形の譲渡を受けるとき、信用リスクを負担します。
しかし、特約として商取引の原因関係や手形用件に欠陥が合ったり、偽造や変造、詐欺、天災、公権力による債務の免除などを理由としてカスタマーが支払いを拒否した場合には、ファクタリング会社はクライアント会社に対して信用リスクを負いません。
信用保証ファクタリング(信用リスク負担サービスのみ)
このタイプは、企業に対してリスクヘッジの機能を提供するものです。

CFイエロー
つまり、一種の保険の提供だよ!
契約によって、全取引の包括支払保証をする場合と、取引ごとに個別支払保証をする場合があります。
このタイプは前払方式ではないため、売掛債権の譲渡に当たっての支払いは、回収が行われた後に行われます。
また支払保証は、売掛債権が回収不能に陥った場合に、あらかじめ決めた額までの損失を補填するサービスとなっており、債務者ごとの信用力を審査したうえで保証限度額が設定されます。

CFレッド
したがって、利用する企業にとっては、取引先の与信調査をアウトソーシングするというメリットもある!
前払いの有無による区分

通常、ファクタリングは金融サービスとして前払方式ファクタリングを行うのが一般的ですが、例えば資金繰りにそれほど困っていない場合などに満期方式ファクタリングを選択することもできます。
満期方式ファクタリングでは、売掛債権の満期に支払われることとなります。前払方式か満期方式かは原則的に選択可能となっています。

CFレッド
クライアントがファクタリング会社に求めるものは売掛債権をスピ―ティに資金化することであるため、ほとんどのクライアントは前払方式を選んでいる!
しかし、ファクタリング会社の資金源は銀行からの借入がメインですから、ファクタリング会社がクライアントに課す表面金利(手数料や貸付金利率)は銀行の金利よりも高いことも多く、それを嫌ったクライアントが満期方式を選ぶこともあります。
しかし実際には、ファクタリング会社は銀行とは異なり、拘束預金を必要とはしないため、金利だけでは判断できないと言えます。

CFイエロー
また、前払方式ファクタリングのほか、融資という形を取ることもあるよ!
買取りはファクタリング会社がクライアントから譲渡を受けた売掛債権・手形の代金を、売掛債権・手形の支払期日前にクライアントに支払う事です。
一方、貸付はファクタリング会社がクライアントから譲渡された売掛債権・手形の代金を、クライアントに貸し付けることです。

CFブルー
もちろん、貸付上限額は回収できる金額の範囲内だよ!
クライアントがファクタリング会社から貸付を受けることによって売掛債権・手形を資金化した場合、ファクタリング会社が譲渡された売掛債権・手形はすべて、借入金の担保として譲渡されたものとされ、ファクタリング会社は売掛債権・手形に関する一切の権利を行使できるようになります。
もちろん、クライアントが売掛債権・手形をファクタリング会社に譲渡する場合には、それが買取りであろうと貸付であろうと、カスタマーから債権譲渡の承諾をもらう必要があります。
債権譲渡通知の有無による区分
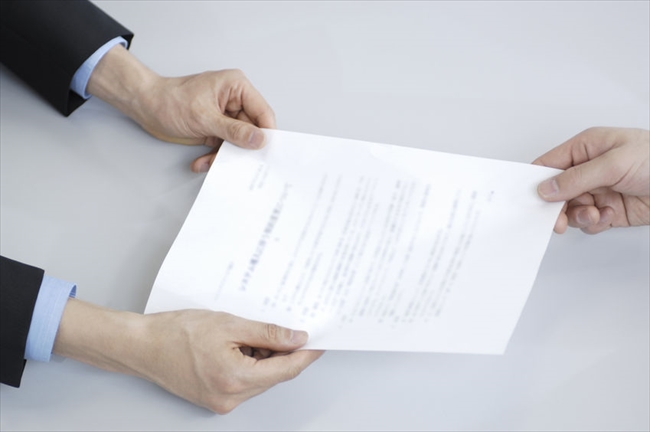
債権譲渡通知とは、クライアントからファクタリング会社へ売掛債権が譲渡されたことを、カスタマーに通知するものです。
譲渡通知を行う場合のファクタリングでは、ファクタリング会社はクライアントから譲渡を受けた売掛債権・手形の代金をファクタリング会社名義で管理・回収することになります。
一方、譲渡秘匿方式ファクタリング、つまり譲渡通知を行わない場合のファクタリングでは、クラインアントがファクタリング会社に代わって管理と回収を行い、クライアントがファクタリング会社へ回収金を引き渡します。

CFレッド
日本においては、ファクタリング会社のもとにクライアント名義で口座を開設し、そこにカスタマーから代金を振り込ませることが多いのだ!
カスタマーの業種による区分

日本のほとんどのファクタリング会社では、業種による区分は特に行われていません。
しかし、業種ごとにクライアントが集中した場合には、信用情報や営業効率の観点から区分して管理されることがあります。
実際に、アメリカでは卸売業と小売業でファクタリングが区分されており、ファクタリング会社は審査部門を卸売部と小売部に分けて管理しています。

CFレッド
例えば、生地生産者から中間加工業者への販売、木材業者から家具製造業者への販売などで生じた売掛債権は卸売ファクタリングとなり、完成品のメーカーによる百貨店やスーパーマーケットなどの小売店への販売で生じた売掛債権は小売ファクタリングとなる!
卸売ファクタリングは、カスタマーの数が少なく、取引単位は大きくなります。
そして継続取引が中心であるため、経営内容の把握は比較的容易であり、信用調査も簡単に行うことができます。
しかし、小売ファクタリングではカスタマーの数が多く、取引単位も信用状態も変化しやすいため、信用調査は困難となることが多いです。

CFブルー
日本のファクタリング会社ではこのような区分はほとんど行われていませんが、今後の変化によっては、このような区分が広まることもあるかもしれないよ!
ファクタリング契約と法律

ファクタリング契約とは
ファクタリング会社とクライアントは、一定期間継続してファクタリング関係を結ぶにあたり、ファクタリング取引契約を結ぶことになります。
契約書には、その契約における「ファクタリング」とは何を指すかの定義や、債権の範囲を明確に定めています。

CFブルー
上記の通り、ファクタリング会社には共通した定款がないことから、ファクタリング会社がファクタリングをどう定義しているかをチェックすることが大切なんだ!
もっとも、ほとんどの場合には、
「本契約において『ファクタリング』とは、取引先信用調査、債権管理回収、信用リスクの負担、債券の期日前資金化、ならびにこれらに付随する事務の総合引受をいう」
などと記載されることと思います。
債権の範囲の取決めも盛り込まれますが、これは非常に重要な部分です。
ファクタリングにおける債権のやり取りがどのように履行されていくのかを記した部分であり、一番重要な箇所と言ってもいいでしょう。
この箇所に関しては、概ね、
乙(ファクタリング会社)は本契約の定めるところにより、甲(クライアント)のためにファクタリングの全部又は一部を行う
などと書かれているはずです。
この契約では、売掛債権の全部または一部のファクタリングということになっていますが、原則的には全部の売掛債権が対象となります。
なぜならば、不良債権ばかりを請け負っていてはファクタリング会社としても業務効率が非常に悪くなってしまうだけではなく、多くのリスクを背負うことになるからです。

CFレッド
100%の債券を譲渡してもらい、全てに対して管理と回収を行い、中には不良債権もあるもののリスクは分散しておくことで、前払い金を確実に回収していくことができるのだ!
ファクタリング契約の仕組み
一般的なファクタリングの仕組みを、契約を交えながら簡単に説明すると、以下の通りになります。
- クライアント(依頼人・譲渡人)とカスタマー(支払人・債務者)が商品売買契約を結ぶ。
- クライアントがカスタマーに商品を納入する。
- 商品の納入に当たって、売掛債権が発生する。
- クライアントが売掛債権を資金化したいと思った場合、ファクタリング会社とファクタリング契約を結ぶ。売掛債権の譲渡に当たっては、カスタマーに承諾を受けて譲渡通知を行い承諾を受ける。
- クライアントとカスタマーがファクタリング取引基本契約書を交わす。
- ファクタリング会社はクライアントに対して買取代金を前払いで支払う。
- 売掛債権の支払期日までに、カスタマーはファクタリング会社に支払いを行う。
実際のファクタリングは、「ファクタリング取引条件に関する覚書」に沿って進められます。
この覚書は、対象となる売掛債権、手形、買取料、貸付金利、貸付限度額、振込口座、信用リスク負担、融資特約などについて詳細に取り決めたものです。
譲渡に関する取り決め

次に、取引契約書の中では売掛債権・手形の譲渡に関してもきちんと取決めが行われています。例えば、以下のような文言で記載されます。
「クライアントが、ファクター(ファクタリング会社)に売掛債権の譲渡をするときには、カスタマーから債権譲渡の承諾を取り付け、確定日付のある『債権譲渡承諾書』と添付してファクターに売掛債権の譲渡をする」
このように、債権譲渡承諾書を交わすことが条件となっています。

CFイエロー
売掛債権を譲渡する際には、必要に応じて以下の様式を利用することになるよ。
- 債権譲渡承諾依頼書
- 債権譲渡承諾依頼書・承諾書
- 債権譲渡通知書
- 取立委任解除通知書
- 債権譲渡および債権譲渡登記がされたことの通知書
- 登記事項証明書ご送付の件
- 債権譲渡禁止特約解除依頼書

CFレッド
この中でも、「債権譲渡承諾依頼書・承諾書」は承諾依頼書と依頼書を兼ねているため、譲渡手続きをスムーズに進めるのに便利だよ!
債権譲渡承諾書の添付については、クライアントとファクタリング会社の協議で猶予や別の方法への代替が可能であり、またファクタリング会社の都合で猶予の取り消しも可能となっています。
支払いの流れ

次に支払いに関して補足ですが、ファクタリング会社は売掛債権が譲渡されると、クライアントに前払金融を行います。
もちろん、取引契約書にはこのことに関してもきちんと記載がなされています。
多くの場合、ファクタリングの依頼者は早急な資金化が望まれるため、売掛債権・手形の支払期日前に、クライアントがファクタリング会社に資金化を申し出ることがあります。

CFイエロー
これをファクタリング会社が承諾した場合には、クライアントはファクタリング会社から融資を受けることになるよ!

CFブルー
これが、前述の前払方式ファクタリングと言われるものだ!
融資は買取りや貸付けの方法によって行います。
買取りとは売掛債権・手形の代金を支払期日前にクライアントに支払うことを指し、貸付けとはファクタリング会社がクライアントから譲渡を受けた売掛債権・手形の合計額の範囲内で資金を貸し付けることを指します。
ファクタリングの際には手数料の支払いが行われますが、ファクタリング取引の報酬として支払われる手数料も、契約の際にきちんと決められます。

CFイエロー
手数料は、譲渡時に支払うとされているよ!
ファクタリング会社は、売掛債権の譲渡を受けると、期日にカスタマーから代金の回収を行います。回収は、ファクタリング会社が管理するクライアントの口座に、カスタマーが振り込む形で行われます。
以上が、ファクタリング取引の契約と仕組みです。
ファクタリングと法律
ファクタリングにおける債権譲渡の性質

ファクタリング契約に続き、ファクタリングと法律の関連についても触れておく必要があるでしょう。
これまでも見てきたとおり、ファクタリングを行う際には、クライアントが持つ売掛債権・手形をファクタリング会社に譲渡することからスタートしますが、ファクタリングにおける「譲渡」は、民法や商法で一般的に規定されている「譲渡」とは異なる性質を持っています。

CFイエロー
一つ目の相違点は、民法での債権譲渡は個々の取引における個別の譲渡であるのに対し、ファクタリングではクライアントがカスタマーに対して持っている複数の債権を一括して譲渡するという点。
なぜ個別ではなく一括であるのかといえば、上記でも触れた通りリスクを分散するためです。
もっとも、契約の際に特約を設けることによって、個別の譲渡にすることも可能です。

CFブルー
二つ目の相違点は、ファクタリングでは将来に発生する債権も対象となっていること!
つまり、今後発生する債権も事前に譲渡するということであり、債券が発生すると随時クライアントからファクタリング会社へと移転されて行きます。
このことが可能となるということは、企業側からすれば現在保有している売掛債権だけではなく、将来的に発生する売掛債権も資金化することができるということであり、資金調達の可能性がより一層広がることとなります。

CFイエロー
将来債権の譲渡契約は、平成11年の最高裁の判決から有効性が認められているよ!
これは、保険診療をする医師が社会保険診療報酬支払基金に対する債権譲渡が問題視された際に、最高裁が「債権の発生可能性の隆でこの種の契約の有効性が左右されるものではない」と明言し、複数年の長期にわたる将来債権の譲渡契約を有効とみなしたものです。
債権の二重譲渡

債権譲渡に関する問題として、二重譲渡の問題があります。
債権の譲渡の際には、公示性を高めるために債権の譲渡人と譲受人、つまりクライアントとファクタリング会社が共同で登記を行うことになります。
しかし、登記官は提出書類に対して形式的な審査しか行わないため、譲渡人が二重譲渡を行う懸念(クライアントが複数の機関に対して売掛債権の資金化を持ちかける懸念)があります。

CFイエロー
これを防ぐためには、ファクタリング会社は先に譲渡が行われていないことを確認することで、二重譲渡を防ぐ必要があるの!
登記手続きには債務者であるカスタマーが関与していないため、二重譲渡が行われたことで二重に回収を受けた債務者は、後に譲渡を受けた譲受者のみに弁済することで免責をされることがあり、そうなると先に譲渡を受けた譲受者が損害を被ることになるのです。

CFブルー
そのため、先に譲渡がないことのほか、後に譲渡が行われないための対策も必要となるのだ!

CFイエロー
このような問題を解決するためにも、将来債権譲渡方式による債権譲渡が活きてくるのよ!

CFレッド
今後一定期間に発生する売掛債権の譲渡が行われることを書面によって債務者に承諾してもらうことによって、優先権を持つ譲受人を確定することができるということだ!
この書面を取り交わしていれば、後に二重の譲渡が行われたとしても、その契約は無効となります。
また、大企業の下請けとなっている中小企業は、一括決済方式で取引をしていることがあるものですが、一括ファクタリングの場合には、債権が発生するごとにファクタリング会社に売掛債権が譲渡されます。
そのため、もし中小企業が資金調達のために、銀行に売掛債権担保融資を依頼してその大企業への債権を担保にした場合には、これも二重譲渡となります。
クライアントが複数のファクタリング会社に対してファクタリングを持ちかけるということは、理論上では二重譲渡の問題として取り上げられますが、悪意がなければほとんど起こりえないことです。
しかし、クライアントの知識不足から、悪意無くして(売掛債権担保融資の利用などによって)二重譲渡が行われることもあります。

CFレッド
そのようにして二重譲渡が発生したときのために、ファクタリング会社は優先権を確保する必要があるのだ!
この必要性から、債務者から確定日付のある承諾書を取り付け、今後の一定期間に発生する債権の譲渡をあらかじめ承諾するという方法によって、優先権を確保するという方法が行われます。
もっとも、このように法律問題を取り上げると、譲渡というものが非常に複雑怪奇なものに思えるかもしれませんが、ファクタリングを利用する企業は基本的にその売掛債権の資金化は一つの対象のみ(ファクタリング会社にしろ銀行にしろ、一つの対処に絞って)に依頼するということを考えておけば、法律的な問題が起こることはないでしょう。
債権譲渡禁止特約

民法466条では、差譲渡禁止特約の効力を明確に定めています。
すなわち、
「債権は之を譲渡することを得。但其性質が之を許さざるときは此限に在らず。前項の規定は当事者が反対の意思を表示したる場合には之を適用せず。但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず。」
というものです。

CFイエロー
平たく言えば、「債券は譲渡してもよいものであるが、そうでない場合もある。当事者が嫌だと思えば無効にもなる」というもの!
債権譲渡禁止特約の効力はファクタリングにはどの程度影響してくるものなのかという事ですが、通説としては特約違反の効果を主張できるとされています。
つまり、譲渡禁止特約に違反する譲渡行為は無効となり、譲渡の効力が生じないという事だ。
では、譲渡禁止特約違反によって譲渡が一旦は無効になったものの、後に債務者が承諾した場合にはどうなるのでしょうか。

CFイエロー
その場合には、譲渡時にさかのぼって譲渡が有効になるとされているよ!
そもそも譲渡禁止特約は債務者の便宜のためのものですから、その債務者が承諾すれば有効になると考えてよいでしょう。
しかし、この特約があることによって、債務者が嫌だといえばファクタリングが不可能となってしまうため、ファクタリングの普及の障害になっています。
この問題に関しては、すでに改正のための動きがあります。
改正が行われれば、ファクタリングや売掛債権担保融資による資金調達がより円滑に進められるようになることでしょう。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
ファクタリングが企業にもたらすもの

キャッシュフロー経営を目指す
企業が経営体質を強化するためには、社債の発行、増資、ファクタリングなどによって資金を調達することが必要であり、それができれば積極的な経営を行うことも可能となります。
もちろん、企業の拡大のためには競争力が優れていることや市場性があること、組織のマネジメント力が高いことなどという条件もありますが、それらの要素が優れていても資金が不足したために倒産を免れないこともあります。

CFレッド
まずは資金力不足を避けることが、企業運営の鉄則と言ってよい!
元来経営体質が脆弱である中小企業や、資金力が乏しいベンチャーなどにおいては、特にそのことが言えるでしょう。
資金調達の方法の中でも、ファクタリングは最も強力な方法の一つです。すでに持っている売掛債権が資金調達の道を拓いてくれるからです。

CFブルー
これからの企業経営では(経営巧者のなかではこれまでも)、儲かる仕組みの一つとしてビジネスモデルの中にファクタリングを組み込んでいくのが良い!
キャッシュフロー経営、つまり現金を重視した経営スタイルを目指し、営業活動の中からいかに現金を生み出していくかを目指すのです。
企業の財務においては、流動資産が流動負債と比較して2倍以上あるのが好ましいとされており、この点だけを考えれば売掛債権でもよいと考える人もいるでしょう。
流動資産には現金だけではなく、売掛債権、有価証券、棚卸資産なども含まれるからです。

CFイエロー
しかし、なんらかのトラブルが起きたときに頼りになるのは売掛債権よりも現金であり、いくら売掛債権があっても現金が極端に少ないという状態は避けるべき。
営業活動でのキャッシュフローが黒字であり確実に増えていけば、銀行からの借入をする必要はなくなりますし、現時点で借入があるならば、それを返済することも可能になります。

CFブルー
営業活動で現金を得る能力が高いということは、企業価値そのものが高いことにもなるのだ!
これまでも書いてきたとおり、ファクタリングはこの目標を達成するための強力な手段となります。しかし、安定的な経営のためには、継続的に確実に利益を出していける経営が必要となります。
かつては、利益さえ出ていれば銀行から比較的容易に借入が可能な時期もありましたが、先行きが不安な昨今、金融機関に依存しない経営を目指さなければならないでしょう。

CFブルー
事業活動を通じてきっちりと現金を手元に残し、経営者の意思で資金を活用できる企業を目指していく必要があるのだ!
ファクタリングで財務体質を強化する

ファクタリングによって資金調達が円滑になれば、財務体質を確実に強化していくことができます。
財務体質の強化とは抽象的な概念ではなく、企業のバランスシートに好ましい変化をもたらし、財務構造そのものに変化をもたらすことによって、財務体質が強化されるのです。

CFイエロー
実際に、ある企業がファクタリングを導入した結果、バランスシートにどれくらいの変化がもたらされたかを見てみよう!
ある例を紹介すると、A社は、ファクタリング導入前は資産に対する売掛金の比率が35%を占めており、現金は少ないものでした。
当時は2000万円の売掛債権を保有していたのですが、ファクタリングを導入してこの売掛債権を全て売却しました。ファクタリング会社は手数料やその他の経費を指し引き、1800万円でこれを買い取りました。
A社は手に入れた1800万円を利用し、買掛金を800万円支払い、短期借入金を1000万円返済し、負債を全体で1800万円減らすことに成功しました。
この結果、A社のバランスシートには大きな変化がもたらされました。

CFブルー
まず、短期借入金を返済したことによって他人資本が減少した結果、自己資本比率が大幅に向上!
さらに、総資本が圧縮されたことで収益性は良くなり、効率的な経営が可能となったのです。
ファクタリングを利用すれば、財務体質が強化されるだけではなく、借入金の減少によって支払利息を削減する、買掛ではなく現金決済にすることによって仕入れコストを下げるなど、収益性を改善することさえ可能となるのです。
販売管理や資金管理がラクになる

中小企業は大企業を異なり、経営資源が乏しいのが普通です。そこで、限られた経営資源を重点分野に集中することで、経営効率を上げることができます。
そのためには企業内で不得意とする分野の業務を外部委託することが効果的であり、これをアウトソーシングと言います。
つまり、企業の経営資源に当たるヒト・カネ・モノ・情報のうち、不足しているものを外部の存在で補うことです。

CFイエロー
アウトソーシングは外注と混同されやすいですが、実際には違うのよ。
外注は業務の執行のみを委託するのに対し、アウトソーシングは業務の企画や計画、マネジメントに至るまでを外部委託するのです。
近年では経理業務の委託業務も広がってきました。

CFレッド
ファクタリング取引の場合にも、様々なことをアウトソーシングすることとなるのだ!
クライアントがファクタリング会社にファクタリングを依頼すると、ファクタリング会社は代金回収と共に記帳代行も行ってくれます。
また、仕入先に対する買掛債務の支払いも委託することができるほか、在庫の現物管理や経費の小口現金出納業務も委託可能です。

CFブルー
つまり、会計処理や資金管理業務をアウトソーシングすることができる!
企業の経営資源をどのように振り分けていくのか、そのためにアウトソーシングを利用するにあたって、どの程度までコストをかけられるのかなどを検討し、業務が最も効率化するように設計することが大切です。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

ファクタリングとリスクマネジメント

リスクマネジメントとは
企業を経営する人にとって、リスクマネジメントは必ず考えるべき問題です。
最近の経済界を見ていると、最近まで優良企業とされていた企業が不祥事で経営危機に陥ったり、明るみに出なかっただけで実は経営不振であった有名企業が外国企業から買収されたりといったケースが頻発しています。
日本においてはリスクマネジメントの手法にはまだ決まったものがなく、そのために企業が不祥事を起こすと「リスクマネジメントがうまくいかなかったのだ」と言われるのを耳にします。
また、会社に影響を与える何らかの要因(例えば円安円高など)が起きると、それに一喜一憂して「リスクマネジメントは大丈夫だろうか」などと言われます。
予想できる自体への対応はもちろんのこと、不測の事態への対応のためにも、リスクマネジメントは大切であるにもかかわらず、きちんと認識されていないことが多いようです。
リスクマネジメントとは、企業が健全に運営されていくために、企業にふりかかる様々なリスクを予見し、そのリスクから与えられる被害を予防するための対策を練り、予見できなかった事態が起きたときにもできる限り最小の被害にとどめるための経営手段のことを言います。

CF戦隊
企業がリスクマネジメントを検討する場合には、その目的や対象となるリスクの種類によって、検討すべき事柄は異なる!
企業として取り組むべきリスクマネジメントはなんであるのか、優先順位をつけ、範囲を明確にし、具体的な対策を練っていくことが大切なのです。
企業を取り巻くリスクには、様々なものがあります。
取引先の倒産、自然災害、賠償責任、労災事故、作業員の安全問題、セキュリティ、為替の変動、金利の変動などといった様々なものが含まれます。
たった一回の事故や過失によって企業の信頼が大きく失われ、倒産に追い込まれることもあるのです。

CFイエロー
リスクには純粋リスクと投機的リスクの二種類があるよ!
純粋リスクとは、自然災害をはじめとした偶発的なことをきっかけとしてリスクが顕在化するものであり、常に損害のみが発生するリスクです。
投機的リスクとは、リスクが顕在化した時に損害が発生することもある一方で、利益になることも期待できるリスクです。

CFレッド
純粋リスクに対しては、企業危機管理を行うことで、被害を最小限にとどめる!
投機的リスクに対しては、そのリスクが発生した時にどのようなシナリオで対応するかをあらかじめ想定しておき、リスクコントロールを行います。
これがリスクマネジメントの概要ですが、リスクマネジメントをシンプルに「企業を倒産から守り、合理的な運営を図るためにリスクに対応する」と考えるならば、ファクタリングはかなり有効なリスクヘッジになります。
不況の時代には、売掛債権の貸倒リスクが高まり、それによって深刻な経営不振に陥ることもあります。
それを避けるためにも、ファクタリング会社の保証を得て回収リスクを少しでも回避しようとする企業が増えています。
その他、償還請求権なしで売掛債権を買い取ってもらうファクタリングにいたっては、リスクマネジメントそのものともいえます。
ファクタリングとリスクコントロール

リスクコントロールのためには、以下の手法が挙げられます。
リスクの回避
これは、リスクの発生そのものを回避するというものです。リスクの回避策をあらかじめ策定しておき、損害をゼロにすることを目指します。
ファクタリングでは売掛債権を売却することによって、将来に起こり得る不良債権のリスクを未然に防ぐものであるため、リスクの回避に該当します。
損害の予防
これは、リスクの発生頻度を減らすことを目指して損害を予防するものです。マニュアルを徹底してリスクを人為的に減らすのが代表的な例です。
あらかじめ取引先の信用力を調査して与信限度を設けた取引を行い、損害が発生した場合には保険によって損害をカバーするのも損害の予防になりますが、これもファクタリングを通して可能となることです。
リスクの分散
リスクを分散させることもリスクコントロールになります。
リスクを分散させる例は、特定の取引先に頼ることなく、複数の取引先から平均的に売り上げるというものです。
リスクを分散するにあたって新規顧客の開拓が必要となることがありますが、その際にもファクタリング契約を結んで信用調査を行なったり、売掛債権支払保証を受けたりすることで堅実な顧客開拓が可能となり、リスクの分担がはかどります。
リスクの移転
これは、本来は自社で負うべきリスクを他者に移転するというものです。
ファクタリングによって売掛債権支払保証を利用すれば、本来は自社で負うべき回収不能のリスクをファクタリング会社に移転することができます。
情報管理とリスクマネジメント

リスク管理を行うためには、その前提としてまずリスクを認識することが必要となります。
そのためには、リスクに関する情報を収集しておくことが大切であり、この情報なくしてリスクに対応することは不可能です。
例えば、新規の取引先を取引を開始するにあたって、与信限度をどのくらいにするかというのは非常に重要な決定になります。

CFレッド
そこで活きてくるのが、ファクタリングを活用することによって与信審査や情報提供をしてもらう事!
例えば、ファクタリング会社の調査の結果、「ある取引先企業が経営危機だ」ということが分かれば、それによって生じる損害を避けられるかどうか、もし損害が生じるならどれくらいの損害か、避けられないにしてもどのくらいまで損害を小さくできるかなどといった危機判断があって、はじめて対策を練ることができるのです。

CFイエロー
リスクが発生する要因には、情報の欠如、管理の欠如、時間の欠如があるとされているよ!
もし管理が完璧であり、情報も充分に手に入れており、対応のための十分な時間があったならば、リスクは予防することができるのです。
したがって、これらの要素を整備するにあたって情報の収集は不可欠であり、ファクタリング会社との取引はここでも活きてくるのです。
まとめ

本稿は長くなったため、最後に要点をまとめておきましょう。
- ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することによって、早期に資金化を可能にするものである。
- 欧米に比べて日本はまだファクタリングがそれほど浸透していない。しかし、今後浸透していくものと思われる。
- ファクタリングと類似したシステムとして、銀行が提供する売掛債権融資保証制度というものもある。これは、売掛債権を担保に借入を行うものである。
- かつて総合商社が担ってきた働きが、ファクタリングに移りつつある。
- ファクタリング会社は売掛債権の買取以外にも様々な機能を持っている。信用調査、事務処理、コンサルティングなどである。
- 一口にファクタリングといっても、様々な分類がある。
- 償還請求は留保か放棄か、支払い方法の違い、信用保証の有無などによってサービス内容が変わる。
- ファクタリングの際には、クライアントとファクタリング会社の間でファクタリング契約を結び、細かな取り決めを行う。そして、法律に沿って契約が履行される。
- ファクタリングは利用することによって、企業の経営体質を劇的に改善することができる。キャッシュフロー経営を目指せるほか、ファクタリング会社に業務をアウトソーシングすることによって経営資源の活用も可能になるからである。
- ファクタリング会社の様々な機能を活用することによって、リスクマネジメントが容易になる。