
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
【要チェック】税理士報酬はこんなときに変化する!

税理士と顧問契約を結ぶと、税理士報酬を支払う必要があります。
税理士報酬は、税理士への依頼内容によって変わります。
税理士報酬は、主に以下のような場合に変化します。
帳簿の入力
税理士に帳簿のチェックと入力を依頼すると、税理士報酬が発生します。
税理士報酬を削減するために、会社側で帳簿の入力をした場合には税理士報酬は安くなります。
しかし、帳簿の入力に問題があれば、試算表や決算書の作成にあたって、税理士が帳簿を全てチェックしなければならないこともあります。
その場合には税理士の手間が増えた分だけ税理士報酬が高くなるのが一般的です。
訪問頻度
訪問頻度によっても、税理士報酬が変わります。
税理士の訪問は、毎月(年12回)、隔月(年6回)、四半期(年4回)、決算時(年1回)などのパターンがあり、会社の必要に応じて訪問頻度は変わります。
訪問頻度が高ければ、それに伴って税理士が費やす時間も増えますから、税理士報酬は高くなります。
会社規模
会社の規模によっても、税理士報酬は変わります。
会社の資本金、売上規模が大きいほど税理士報酬は高くなる傾向にあります。
その他
このほか、税理士に依頼する作業が多くなるほど、税理士報酬は高くなります。
源泉徴収票の作成、資金繰り表の作成などの作業を追加で依頼する場合には、その内容に応じて税理士報酬が高くなります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
税理士報酬をケチると却って損をする

以上のように、依頼内容に応じて税理士報酬は高くなります。
そのため、経費削減のために税理報酬をできるだけ安くしたいと考える会社も少なくありません。
しかし、税理士報酬を削減する場合には、それが果たして妥当な削減であるかどうかを、慎重に考える必要があります。
税理士報酬をケチるとどうなる?
そもそも税理士は、税理士報酬によって利益を得ているのですから、受け取った報酬の範囲内で作業をする必要があります。
税理士報酬をケチる会社では、ケチった範囲内だけでの働きしか期待できなくなり、満足な対応が受けられなくなる可能性もあります。
せっかく知識もあり、コミュニケーションも取りやすい税理士を選んだとしても、税理士報酬をケチってしまえば、受けられるサポートの範囲は狭くなります。
書類の作成にあたって、アドバイスの余地があっても機械的な作業に止まったり、質問や相談があってもそれほど丁寧に対応してくれなかったりするのです。
たとえば、税理士報酬をケチることで、訪問頻度を決算期の年1回に減らしたとすれば、期中に取り組むべき節税策があったとしても、情報提供が受けられない可能性が高いです。
税理士報酬をケチって10万円の削減に成功したとしても、20万円の価値がある情報やアドバイスを逃してしまえば、結果的に10万円の損になってしまいます。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
税理士は全面的に信用してはならない

さて、知識があり、コミュニケーションも取りやすく、さらに税理士報酬もきちんと支払っているならば、税理士は全面的に信用できるのでしょうか。
実は、そうでもありません。
なぜならば、知識がある税理士といっても、それは税務に関する知識が豊富なだけで、必ずしも経営にプラスになる知識であるとは限らないからです。
たとえば、税務に明るい税理士と顧問契約を結び、十分な節税をしたうえで決算書を作ったとしよう。
当然、銀行が融資の判断をする際には、この決算書をよりどころとします。
銀行は、融資をすることで利益を得ているのであり、銀行員も間違いのない融資を通すことで評価を得ています。
つまり、貸せる相手ならばいつでも貸したいと考えています。
ここでいう「貸せる相手」とは、きちんと返済してくれる会社のことです。
しかし、税務だけに明るい税理士が作った決算書には、銀行が好ましくないと考える決算書が少なくありません。
税金から逃れるためにわざと赤字決算になっていたり、債務超過になったりしている場合が多いのです。
税理士を信頼しすぎて失敗した例

たとえば、こんな例があります。
ある会社では、税理士を全面的に信頼して、会計処理を任せていました。
その結果、出来上がった決算書は債務超過に陥っていました。
税理士としては、言われた通りに機械的な会計処理をし、決算書を作っただけであり、債務超過は危険であることや、債務超過を解消するためのアドバイスもありませんでした。
債務超過に陥っている会社は、銀行から融資を受けることが困難になります。
困った社長が経営コンサルタントに相談して決算書を見せると、社長から会社に貸した貸付金が債務超過額以上にあることがわかりました。
もし、この税理士に経営についてもいくらかの知識があれば、社長にアドバイスして貸付金を放棄させ、債務超過を解消したうえで決算書を作成していたことでしょう。
しかし、この税理士は税務に関する当たり前の知識によって、当たり前に会計処理を行っただけでした。
税理士を信頼しすぎると赤字決算となる
また、赤字決算に陥っている中小企業が多いことも、税理士を信頼しすぎたことが原因です。
確かに、赤字決算に陥った場合には、会社は税金を支払う必要がなくなります。
支払う税金を少なくすることを目的に税理士を雇っているのですから、ある意味で税理士は目標を達成したとも言えます。
また、あまり知識のない経営者ならば、税理士から
「赤字にすれば税金は支払う必要がなくなります。来年以降、利益が出ても相殺できますから、支払う税金を減らすことができます。」
などと言われれば、ラッキーとばかりに赤字決算に満足します。
このような理由から、中小企業には赤字決算の会社が非常に多いのです。
赤字決算の問題点
しかし、そのような決算書を作ったことによって、銀行からの評価は低くなり、融資を受けられなくなってしまうならば本末転倒です。
そのような事例が非常に多いことを知り、税理士を全面的に信頼することは避けるべきです。
銀行にとって、赤字と黒字では印象が大きく異なります。
少しでも黒字を出している会社と、少しでも赤字を出している会社があるならば、銀行は黒字の会社を圧倒的に高く評価します。
利益は大きいほど好ましいのですが、そもそも中小企業は利益を出し続けることが困難ということが前提にあります。
利益が少ない年があっても、継続して黒字を出し続ける会社は高く評価されるのです。
このように、銀行は赤字の決算書を非常に嫌います。
既に取引のある銀行では、信用さえあれば追加融資を出したいと考えているのですが、赤字の決算書を出されてしまうと、追加融資も困難になります。
せっかく融資の可能性があるのに、安易に税理士を信頼したことで、その可能性を潰してしまうのです。
もし、経営に関して少しでも理解のある税理士ならば、銀行からの評価も考慮して決算書を作るでしょう。
節税対策には注意する
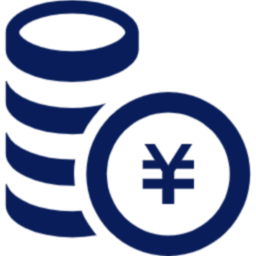
税理士の多くは、税務の知識のみで会計処理を行います。
節税には積極的に取り組み、利益を圧縮して納税額を減らそうとしますが、それが会社の首を絞めることもあるのです。
会社にとって、現金は最も重要な経営資源のひとつですが、節税の名のもとに現金の流出を招いていることが非常に多いです。
無駄な節税を辞めれば、まともに税金を払っても手元に資金が残ります。
それによって資金繰りがラクになるにもかかわらず、とにかく納税額を減らすことだけを考えてしまうのです。
また、赤字決算に持ち込めば、納税額を減らすという意味では最も良い結果を得たことになりますが、融資が厳しくなりここでも会社の首を絞めることになります。
- 節税のため現金の流出を招いて資金繰りが困難になる
- 資金繰り困難な時にこそ必要となる融資が受けられなくなる
- 資金繰りが行き詰ってしまう
したがって、本当に良い税理士とは、次のような税理士です。
- 効果のある節税だけを取り入れる
- 無駄な節税はせずに手元資金の流出を防ぐ
税理士はパートナー
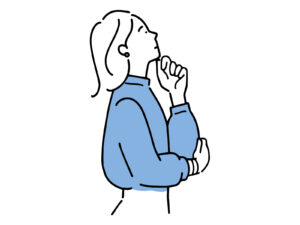
有能な税理士を選ぶためには、
- 知識とコミュニケーションに問題がない税理士を選び
- 税理士報酬は適切に支払い
- さらに経営にプラスになるという視点から会計処理ができる税理士を選ぶ
ことが重要です。
そのように選んでこそ、会社が安定感のある経営をし、順調に発展していくために、税理士が心強いパートナーとなってくれるのです。
もし、顧問契約をしている税理士に経営の知識がなく、銀行対策に役立たないことばかりしているようならば、すぐに税理士を変える必要があるでしょう。
また、新たに顧問契約をした税理士に対しても、全面的に信頼するのではなく、経営に役立つ会計処理を積極的に求めていきましょう。
税理士の知識と経営者の経験をうまく合わせて戦っていける関係を築いていくべきです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
税理士は、会社経営に必要不可欠な存在です。
しかし、税理士の能力には大きく差があり、選び方を間違えると経営にプラスにならないことがあります。
むしろ、税理士の働きによって、銀行からの評価が大きく下がって融資を受けられなくなり、経営にマイナスになることもあるのです。
経営にプラスになる仕事を税理士に求めるためには、営者自身が豊富な知識を持ち、税理士のアドバイスを取捨したり、具体的な要求をしたりすることも必要です。
そのためにも、当サイトの記事が役立てば幸いです。

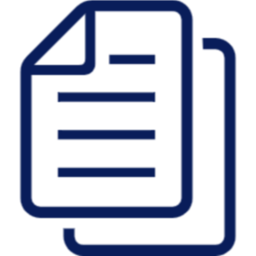











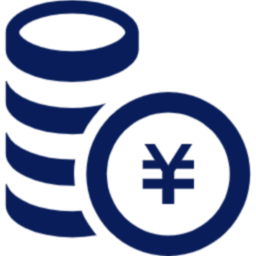
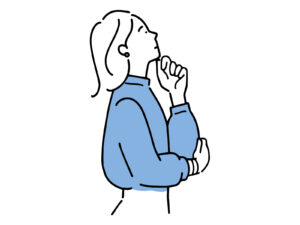



コメント