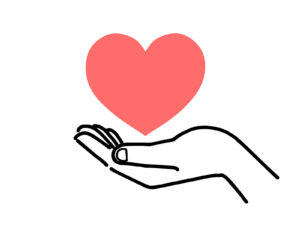ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
法人で契約している保険の見直し方

保険の見直し・解約を検討する際には正しい判断が求められます。
その判断基準として、次の点を考えていきましょう。
- 加入当初の目的は何であったか
- 資金繰りの緊急性はどの程度か
- 返戻金の金額と必要な金額を比較してどうか
中途解約の判断にあたっては、下記の流れとなります。
- 保険の加入目的を振り返る
- 加入時期と現状の変化により、現在は不要になっている、あるいは不要ではないものの資金繰りの方が緊急と言える保険を明らかにする
- 明らかになった保険を中途解約した場合の返戻金と、資金繰りに必要な金額を比較し、返戻金を受け取ることで資金繰りに役立つならば解約する
上記の流れで最も大切なのが、加入目的を振り返るところです。
そもそも、会社が法人契約で保険を加入した時、何らかの理由があったはずです。
しかし、当時と現在では会社の置かれている環境は変化しているでしょう。
当初の目的では保険が必要であったとしても、現在では必ずしも必要とは言えなくなっているかもしれません。
法人で契約している保険の具体的な見直し基準
具体的な見直しの基準は、以下のマトリックスによって考えるのが良いでしょう。
保険の種類によっては、節税効果も無視できませんから、その点も踏まえて整理すると、以下のようなことが言えます。
●・・・効果なし、〇・・・効果あり、☆・・・非常に効果あり
加入当初の目的と現状を比較した時、現状でも〇あるいは☆と言えることを目的として保険に加入し続けているならば、その保険の解約には慎重になる必要があります。
ただし、加入当初は〇あるいは☆であったものの、今では●になってしまったというならば、積極的に見直すべき保険であるといえます。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
保険商品ごとの返戻金の仕組み

返戻金の仕組みは、保険ごとに異なります。
終身保険
終身保険として支払った保険料は保険積立金として計上し、全額を資産とみなします。
このため、終身保険の加入によって節税効果は得られません。
加入期間が長くなると返戻率が高まり、ある時期では保険積立金より解約返戻金が上回ります。
平準定期保険
平準定期保険として支払った保険料は、全額経費として処理するため、保険積立金はありません。
したがって返戻金はなく、あったとしても少額です。
資金繰り目的で解約しても意味はありません。
逓増定期保険
逓増定期保険では、保険期間に応じて返戻率が異なります。
ある時期までは返戻率が高まり、それ以降は返戻率が下がります。
資金繰り目的で解約するならば、解約返戻金が保険積立金を上回る時期に解約するのが得策です。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
長期定期保険
長期定期保険として支払った保険料は、支払った保険料の2分の1が保険積立金となります。
これも時機に応じて返戻率が異なり、ある時期から解約返戻金が保険積立金を上回るので、その時期に解約するのが得策です。
しかし、その時期を過ぎると解約返戻金が保険積立金を下回り、最後はゼロになります。
養老保険
契約形態により、養老保険として支払った保険料の2分の1が保険積立金となります。
満期を迎えると満期保険金を受け取ります。
加入時期が長いほど返戻率は高まりますが、ほとんどの期間において、解約返戻金が保険積立金を上回っています。
がん保険
保険積立金はないものの、解約返戻金は常に増加していきます。
保険料は全額経費として処理するため、解約返戻金は雑収入として計上します。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
契約者貸付制度を検討する

保険を解約することが資金繰りに役立つとはいえ、加入当初も現在も必要な保険だから解約したくないこともあるでしょう。
- 解約返戻金を受け取ることによって納税が発生するため解約したくない
- 従業員に万が一の場合の保険なので解約したくない
このように、さまざまな理由から解約に抵抗がある場合も多いと思います。
この場合にも、保険を活用した資金繰りは可能です。
解約しなくとも、契約者貸付制度を利用することによって、資金繰りに役立てることができるのです。
契約者貸付制度とは、保険を解約することなく、解約した場合に受け取れる返戻金の80~90%を自由に使える制度のことです。
たとえば、2000万円の解約返戻金がもらえるとするならば、その80~90%にあたる1600~1800万円の資金を調達できます。
この制度を利用すれば、4~5日のうちに資金を調達できますから、緊急の資金需要にも対応可能です。
契約者貸付制度の流れ
- 必要書類を揃える:
契約者貸付申込書に記入し、発行後3か月以内の印鑑証明、保険証券を揃える。
- 提出:
保険会社の担当者に渡して本社に送ってもらう。
- 入金:
3~4日のうちに手続きが完了し、4~5日のうちに現金が振り込まれる。
このように、非常にスピーディに資金を調達することができます。
契約者貸付制度のメリット

契約者貸付制度のメリットは、上記の通り保険を解約せずにスピーディな資金調達ができるだけではありません。
以下のようなメリットを持っています。
返済条件がない
契約者貸付制度には、定まった返済条件がなく、返済条件は非常に緩く設定されています。
たとえば、満期日に一括して清算してもいいですし、満期日以前に資金的に余裕ができた場合には繰上げ返済も可能です。
満期日に一括清算する場合には、満期日に受け取るべき保険金から借入金を差し引いて支払うことになります。
金融機関よりも金利が低い
金融機関で融資を受ける場合、長期プライムレートや短期プライムレートを適用して金利を計算します。
金融機関の独自のレートを利用するため、金利を低く抑えることは難しいです。
しかし契約者貸付制度の場合には、保険会社の保険の運用利率によって金利を計算します。
保険の運用利率が高ければ金利も高くなる仕組みです。
しかし、運用利率と金利の差が0.5%程度になるように設計されており、昨今では運用利率は低くなっています。
そのため、金融機関よりも低金利での資金調達が可能となります。
固定金利である
契約者貸付制度は固定金利です。
このため、借入後に運用利率が高まったとしても、金利が上昇することはなく、契約時点での金利が維持されます。
運用利率が低いタイミングで利用していれば、低金利が適用され続けることとなります。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ
本記事で解説した通り、保険を利用すれば柔軟な資金調達が可能となります。
保険を見直し、今や必要ないと思える保険に加入しているならば、それを解約することによって解約返戻金を受け取るのが良いでしょう。
また、何らかの理由によって解約できない場合にも、契約者貸付制度を利用することによって、解約返戻金を根拠としたスピーディな借り入れが可能です。
ほかにも資金調達が必要な際には、対応速度の早いファクタリングの利用も検討してみてください。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼ ▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

法人契約の保険を見直し・解約して資金調達しよう!急ぎの資金需要にはファクタリングがおすすめ