
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
1回の手形不渡りで会社はどうなる?

法律上は1回の不渡りを出したからと言って、会社がすぐに倒産してしまうことはありません。
銀行口座が凍結されたり、会社や経営者の資産が差押えに遭ったりすることもありません。
会社はそれまでと変わらず事業を継続することができます。
しかし、これはあくまでも法律上の話です。
1回でも不渡りを起こすと、外部環境や経営環境というについては、不渡り以前とまったく同じ環境で事業を続けるのは難しいです。
では、1回目の不渡りを起こした会社には、具体的にどのような影響が出てくるのでしょうか。
信頼を失い多くの取引先から警戒される

不渡りを起こした際には、外部環境は確実に悪化します。
まず変化が起きるのは、手形の受取人である取引先の会社でしょう。
取引先からすれば、手形が不渡りになったということは、入ってくるはずのお金が入ってこなかったということです。
中小企業では、資金繰りに余裕がある会社はそれほど多くありません。
手形の不渡りを起こしたことで、取引先の資金繰りが圧迫される可能性も十分にあります。
取引先は、手形の不渡りによって資金繰りが悪化し、資金調達に奔走しなければならなくなるかもしれません。
【注意】
このように、手形の不渡りを起こすと、手形の受取人に多大な迷惑をかけることになります。
受取人である取引先との関係が悪化することは避けられないでしょう。
迷惑をかけた会社との取引を継続するには?
手形の不渡りで迷惑をかけた会社との取引では、今後「不利な条件」での取引となる可能性が高いです。
- 現金取引でなければ取引してもらえなくなる
- 掛け取引にしても決済までの期間が短く設定される
- 小型の取引でなければ応じてくれなくなる など
また、手形の不渡りを起こした事実は、何らかの形で広まることとなり、多くの会社から警戒される可能性も高いです。
どんな会社でも、貸し倒れの危険性は避けたいと考えます。
手形の不渡りを起こすことによって、さまざまな取引先からの信用を失い、取引環境が悪化することとなります。
全国の銀行に知られてしまい警戒されてしまう

不渡りを出した事実は、もちろん支払銀行に知られることになります。
この時銀行は、手形交換所に不渡届を出し、手形交換所は不渡報告を掲載し、全国銀行協会に通知します。
全国銀行協会とは、銀行業の健全な発展のためにルールを制定したり、さまざまな情報を共有したりする機関です。
全国銀行協会に不渡りが報告されると、全国の金融機関が不渡りの事実を把握することとなります。
不渡りの情報は、ほかにも全国の手形交換所、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターなどの、関連する多くの機関で共有されます。
全国銀行協会に不渡りが報告されるとどんな影響がある?
このため、1度でも不渡りを起こした会社は、全国の金融機関から警戒されることとなります。
前述の通り、1回の不渡りを起こしたことで口座が凍結されることはありませんし、入出金や当座取引も可能です。
とはいえ、不渡りの事実が銀行に知れ渡ってしまうことで、信用の低下は免れません。
すでに融資を受けている銀行からは、返済が滞る危険性があると警戒されるうえに、追加融資を受けることも困難になるでしょう。
融資を受けていない銀行からも、返済能力が低いと見なされ、新規融資を受けることが困難になります。
【注意】
手形の不渡りを1度でも起こしてしまった会社は、それ以降、銀行から融資を受けることが困難(ほぼ不可能)となります。
これが、手形の不渡りは絶対に起こしてはならないとされ、「不渡り=倒産」というイメージを抱かれやすい理由でもあります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
6ヶ月以内で2回の不渡りを起こすと「事実上の倒産」

1回の不渡りだけでも、経営には大きな打撃となることがわかりました。
では、2回の不渡りを起こした場合にはどうなるのでしょうか。
2回の不渡りを起こすケースには、「短期間のうちに2回目の不渡りを起こすケース」と「一定期間を経て2回目の不渡りを起こすケース」が考えられます。
より問題なのは前者で、6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こすケースです。
通常、6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こすと、「事実上の倒産」になるとされています。
「事実上の」と書かれている理由は、法律上は6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こしても、法律的な倒産に至るわけではないからです。
しかし、6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こすと、「手形交換所から当座取引停止処分を受ける※」こととなり、正常な業務運営ができなくなります(手形や小切手による取引ができなくなる)。
※当座取引を停止する処分のことであり、その後2年間にわたり、当座預金による取引ができなくなります。
この結果、倒産するしかない状態となり、「事実上の倒産」となるわけです。
当座取引停止処分の影響
当座取引停止処分を受けると、取引停止報告が全国の銀行に共有されます。
これによって、1回目の不渡り以上に警戒されることとなります。
もちろん、当座取引停止処分を受けても、停止されるのは当座勘定取引だけです。
普通口座での入出金は可能であり、現金決済や掛け取引は可能です。
しかし、1回目の不渡り以上に、取引先や銀行の対応が悪化するのは言うまでもなく、事実上の倒産は免れないと言えるでしょう。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
6ヶ月以内に2回の不渡りを起こさなかったとしても……

当座取引停止処分を受けるのは、6ヶ月以内に2回の不渡りを起こした場合に限られます。
1回目の不渡りを起こしてから、何事もなく6ヶ月が経過すれば、1回目の不渡りで出された不渡報告は効力を失います。
そのため、1回目の不渡りを起こしてから7ヶ月目以降に2回目の不渡りを起こした場合は、当座取引停止処分は受けず、「不渡報告」が出されるだけです。
ルール上はこのような取り扱いとなりますが、これは手形交換所の対応がどうかということであって、銀行や取引先からの扱いは予想できません。
2回目の不渡りを起こしたのが1回目の不渡りから1年後でも、取引先や銀行からすれば、「過去に2回の不渡りを起こした会社」という認識になります。
【注意】
不渡報告が効力を失っても、信用情報機関には不渡り情報が記録として残るため、銀行からの借り入れは困難となります。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
不渡りへの対策

上記のように、不渡りを起こした会社では経営環境の悪化は避けられません。
不渡りを起こさないための有効な対策として、下記の3点が考えられます。
▼不渡りを起こさないための対策
- 決済期日をバラバラにしない
- 融資を受けていない銀行口座をキープする
- 手形取引を控える
1.決済期日をバラバラにしない

手形の決済期日をバラバラにすることは避けてください。
具体的には、ある月の15日と20日と25日に3回の手形決済があるような状況です。
このような場合、支払期日が短期間で複数日に分散しており、手形の管理が煩雑になります。
手形決済日を把握できていなかったために決済がなされず、不渡りに陥ってしまう可能性があります。
また、このタイプでは、ごく短期間のうちに複数回の支払いをしなければなりません。
15日の支払いで資金がショートし、20日、25日の支払いができない可能性があります。
こうなると、ごく短期間のうちに2回連続で不渡りを出してしまうことになります。
【ポイント】
同じ日の手形Aと手形Bが不渡りになったとしても、不渡りは1回としてカウントされます。
決済期日を1日にまとめておけば、1回の不渡りに食い止めることができます。
2.融資を受けていない銀行口座をもっておく
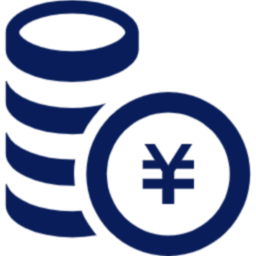
銀行は返済困難と思われる延滞を繰り返すと、融資引き上げのためにほぼ確実に預金口座を凍結します。
もし借入先の銀行で手形の決済口座を設けていたとすれば、手形決済用の口座も同時に凍結されることとなります。
通常、借入先の銀行との付き合いの中で、借入先の銀行で手形決済用の口座を設けることがありますが、これは実は危険なことです。
手形の決済用口座は、融資を受けていない銀行の口座を指定しておきましょう。
そうすれば、借入の返済が困難になって口座が凍結されても、別の銀行では手形の決済が可能になります。
借入先の銀行を手形決済用の口座にすべきでない理由
A銀行から融資を受けていたB社は、返済困難に陥り、A銀行から口座をロックされることとなりました。
しかし、B社は取引先のC社に手形の支払いをしなければなりません。
そこで、手形の決済口座もA銀行に指定していたため、決済代金の100万円をA銀行の決済口座に振り込みました。
しかしA銀行は、100万円の入金があったと知ると、それを返済資金としてすぐにおさえる可能性が高いです。
その結果、C社への手形の決済も不可能となり、不渡りを起こしてしまうことになります。
このように、借入先の銀行に手形決済用の口座を設けていると、返済困難時に困ることになってしまいます。
3.手形取引を控える

手形を振り出さなければ、手形決済をすることもなく、手形が不渡りになることもありません。
不渡りが100%起きないようにするためには、この方法しかありません。
資金繰りが厳しい時には、支払いを先送りするために、手形を使いたいと思うかもしれません。
しかし、そのような場合にも、掛け取引によって手形を避ける方法があります。
掛け取引をすれば、支払期日に買掛金を支払うわけですから、「後日の支払期日に代金を支払う」という意味では手形と何ら変わりません。
掛け取引なら、買掛金の支払いがどうしてもできない場合には、取引先と交渉することで支払いを延ばしてもらえる可能性もあります。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ:手形の不渡りは絶対に起こさないようにしよう
手形の不渡りを起こしてしまうと、たったの1回でも大きく信用を失うこととなり、その後の資金繰りが困難となります。
6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こしてしまえば、事実上の倒産を免れません。
そのようなことにならないためには、手形の決済期日を工夫したり、手形の決済用口座を借入のない銀行に指定したりなど対策を進めましょう。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼





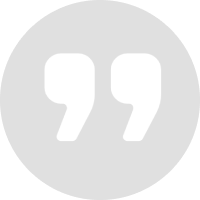
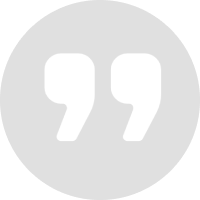


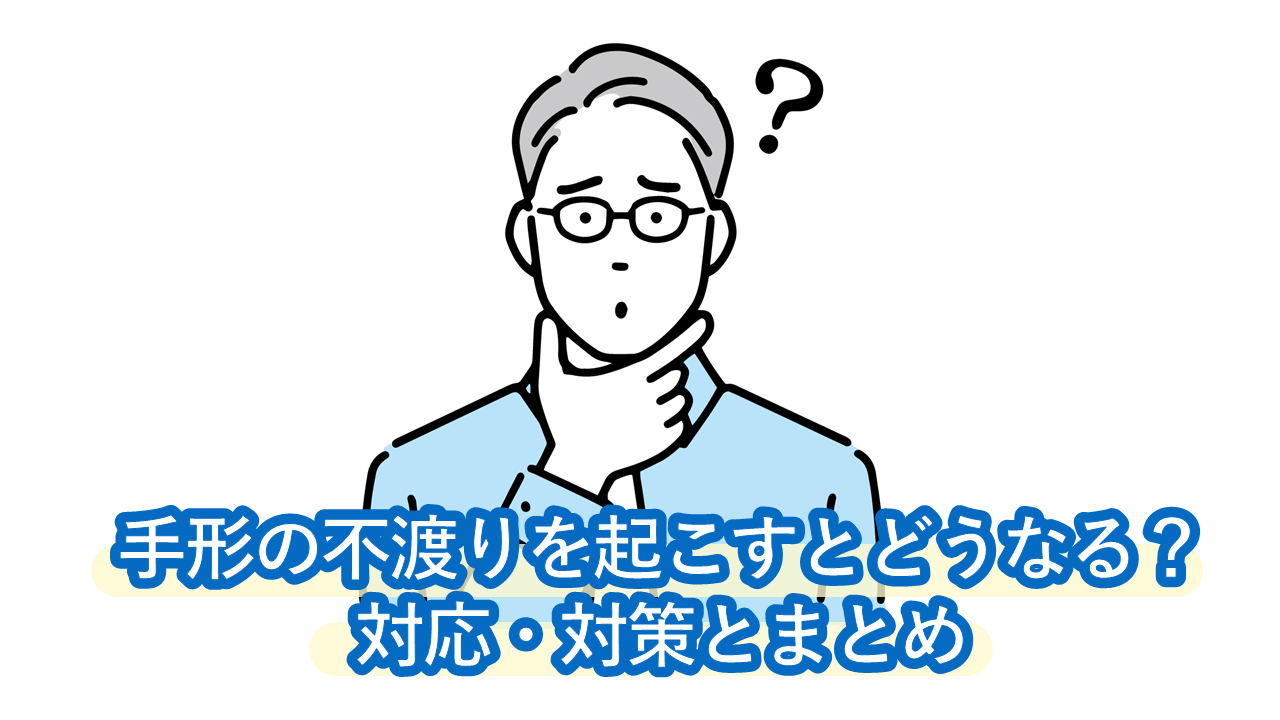











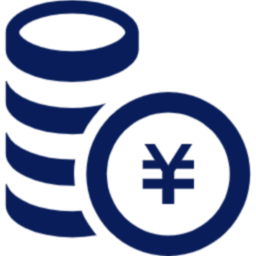






コメント