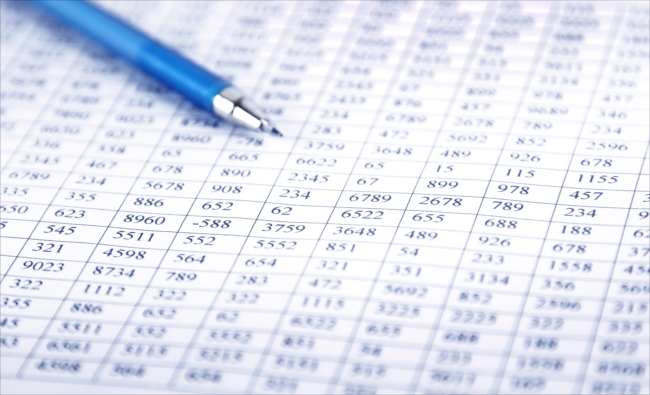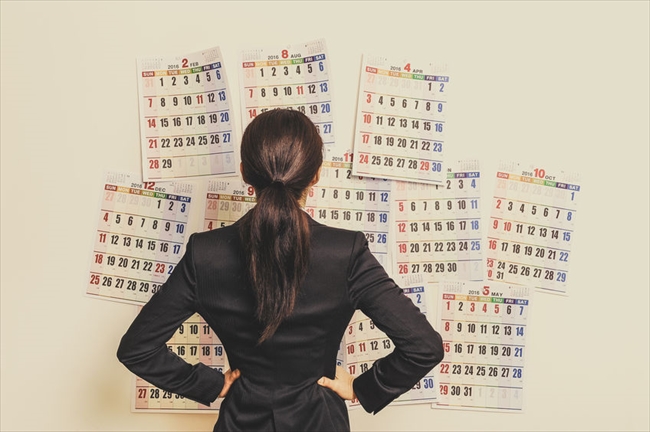皆さんの中には、子供の頃にお小遣い帳をつけたり、一人暮らしをしながら家計簿をつけたりしたことがある人も多いと思いますが、資金繰り表も、それらと基本的に変わらないものです。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
資金繰り表のメリット

以上のことからも分かる通り、資金繰り表には会社の過去・現在・未来を把握できるというメリットがあります。
会社が作成する書類にも色々ですが、資金繰りに最も役立つのは資金繰り表です。
決算書は過去だけを表し、試算表は現在だけを表し、経営計画書は未来だけを表すのに対し、資金繰り表は過去から未来までを網羅しているのです。
売上が落ちた会社が、決算書だけから対策を考える場合、
今期は売り上げが落ちた。
販路開拓に一層努力し、銀行から融資を受けて仕入れを増やして売上を上げなければならない。
などと考えるでしょう。
対策としては漠然としています。
しかし、売上低下の対策を資金繰り表から考えるならば、かなり正確な対策が立てられます。
売上が落ちた。
このままだと○月には資金が不足してしまう。
資金不足をカバーするためには、銀行からこの時期までにこれくらい借りなければならない。
これくらい借りたら、その返済のためにはこれくらいの売上と利益が必要だ。
ならば、利益率の高い商品Aを積極的に売っていく努力をしたい。
販路開拓のための資金はどう捻出しようか・・・
というように、具体的な情報をもとに、将来の資金繰りを見据えながら考えられるようになるのです。
つまり、決算書でわかる情報は、
[su_note note_color=”#eee” radius=”20″]今期と前期を比較して、どの項目の数字がどう変化したか[/su_note]
という結果だけであるのに対し、資金繰り表では、
- 過去から現在まで、各数字がどのように、どれくらい、どのように変化してきたか
- 各数字が、将来的にどのように変化していくのか
を知ることができるのです。
資金繰りに困っている会社は、資金繰り表を作ることによって、どうして資金繰りが苦しい状況になったのかを知ることができます。
将来的にどう苦しくなっていくのか、それを食い止めるにはどうすればよいのかが分かります。
もちろん、資金繰りに困っていない会社も、困っていない状況に安穏とするのではなく、資金繰り表を作ることで、その状況が長く続くようにしていくべきです。
銀行融資にもメリットが
また、資金繰り表には、銀行融資へのメリットもあります。
これは、資金繰り表は資金の流れがわかる表であるため、
- 銀行からの借入金がどう使われるのかが見える
- 銀行からの借入金をどうやっていくのかが見える
- 複数の銀行から借り入れている場合、他の銀行からの借入額や返済状況が見える
- 今期の業績がどのようになりそうかが見える
などの、銀行にとって把握しておきたい情報がたくさん含まれているからです。
銀行の担当者は、融資の申請を受けた際に稟議書を作成します。
稟議書に含まれる内容は多岐にわたりますが、稟議書の中でも資金使途や返済原資、他の銀行の動向や業績に関する情報は必ず盛り込まれます。
資金繰り表をしっかりと作っておき、銀行の担当者が知りたがっている情報を盛り込んでおけば、担当者の稟議書作成が簡単になります。
銀行員は忙しいものです。定時での退社を求められることも多く、効率的に業務をこなしています。
資金繰り表に大切な情報を盛り込んでおけば、銀行員は手間のかからない案件とみなし、すぐに稟議書を作ってくれる可能性が高まります。
銀行が融資を決定するまでには時間がかかるものであり、資金を必要としている会社にとってはデメリットとなっています。
資金繰り表を作っておくことで審査がスピーディに行われるならば、これは大きなメリットと言えるでしょう。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
なぜ資金繰り表を作らない?

上記のことを読めば、資金繰り表が非常に役立つものであることが分かるでしょう。
会社の資金繰りを計画的に回していくために役立ち、経営改善にも役立ち、銀行融資にも役立つのです。
こんなに便利なものならば、ほとんどの会社が資金繰り表を作っていてもよさそうなものなのですが、実際にはほとんどの中小企業が資金繰り表を作っていません。
上記でも少し触れましたが、なぜ資金繰り表を作らないのかと言えば、頭の中だけで資金繰りを回していれば十分と考えているからです。
しかし、それは単なる言い訳であって、本当のところは、
といった苦手意識を持っているのです。
(会計の知識はないし、計算は苦手だし)頭の中で資金繰りを回していれば十分だ
というように考えていることが非常に多いです。
また、節約のために作っていない会社もあるでしょう。
税理士に依頼すれば、資金繰り表も作成してもらうことができます。
しかし多くの会社では、資金繰りが苦しいために、記帳代行などの安いサービスだけを利用し、資金繰り表の作成まで依頼していないのです。
税理士も仕事ですから、依頼されたサービス以上のことは期待できません。

CFブルー
しかし、資金繰り表は誰でも作れるのだ!
会計の知識がなくとも、計算が苦手でも、税理士の力を借りなくても可能です。
ネットで検索すれば、資金繰り表のテンプレートを無料でダウンロードすることができます。
自社の資金繰りに合うように、多少の手を加える必要があるかもしれませんが、一度形式を作ってしまえば、エクセルなどで入力をして機械的に計算していくことができます。
多くの中小企業が資金繰り表を作成していないことを考えると、資金繰り表を作成して経営していくことができれば、それだけで他社より一歩先んじることができるとも言えます。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
資金繰り表作成の流れ

ここからはいよいよ、資金繰り表作成の流れを解説していきます。
家計簿感覚で始めてみよう
既に述べましたが、資金繰り表の基本的な構造は家計簿と同じです。
ですから、まずは家計簿感覚でいいので、資金繰り表の作成を始めてみるのが良いでしょう。
家計簿をつける際には、残高を記入し、入金があればそれに足し合わせ、支出があればそこから差し引きます。
それを繰り返すだけのシンプルなものです。
資金繰り表では、入金や出金の項目が細かくなるということと、将来の予定を書き込むということが加わります。
しかし、家計簿をつけるのも、何らかの目的があってやっているのですから、やはり資金繰り表とかなり似ていると言えます。
最初は単にお金の流れを把握したいと考えて家計簿をつけ始める人もいるでしょう。
しかし、その中で不要な出費を削ったり、お金が貯まっていくのを見たりするうちに、何らかの目的が見えてきます。

CFイエロー
例えば、車を買うという目的が見つかったとしよう。
このような目的が見つかったとすれば、家計簿に将来の予定も含めた観点が生まれてきます。
その観点が、目標設定、目標達成のための計画です。
すなわち、次のような観点です。
- 買いたい車の価格を調べ、目標金額を決める
- 年間の出費を確認する
- 1年後に車を買うために、稼ぐべき金額を計算する
という観点です。

CFイエロー
これを会社に置き換えるならば、次のようになるよ!
- 利益の目標額を設定する
- 年間の経費を確認する
- 目標利益に達するための、目標売上を設定する
このようなビジョンがあれば、利益や売上の目標を妥当なものにしたり、経費削減を心掛けて利益率を高め、目標利益を達成したりすることができます。
【1】収入と支出を調べ上げる
まずやるべきことは、実際のお金の流れを把握すべく、1ヶ月分の収入と支出を全て調べ上げることです。
これは、単に1ヶ月あたりの収入がいくら、支出がいくらというレベルではなく、
- いつ、どこから、どのようにして、いくら収入があったか
(〇月〇日、取引先のA社から、商品aの売掛金として、〇万円の入金があった)
- いつ、どこへ、どのように、いくらの支出があったか
(〇月〇日、仕入先のB社に対し、商品bの仕入れ代金として、〇万円を支払った)
というように細かく調べます。
これらを調べるためには、以下の資料を用います。
取引口座の通帳
通常の取引は、現金をそのままやり取りするわけではなく、金融機関への振り込みによってやり取りします。
したがって、取引口座の通帳の明細を見れば、「いつ」「どこから」「いくら」という情報を全て把握できます。
現金出納帳
通帳に記載されない、現金でのやり取りがあった場合には、現金出納帳にそのつど記帳しておきます。
これによって、通帳に記載されないお金の動きを掴むことができます。
手形帳
取引先ごとの手形の情報も記録しておきましょう。
これによって、手形の受取日、手形が期日通りに入金されているかを把握できます。
また、裏書譲渡や手形割引をした場合にも、その情報を把握できます。
クレジットカードの明細
法人カードを作り、クレジットカードによる支払いをしている場合には、クレジットカードの明細によって流れを把握します。
ただし、クレジットカードは月あたりの利用額を一括で支払うものですし、支払先のみ記載されて用途が記載されないこともあります。

CFブルー
したがって、意識的に把握していく必要があるよ!
リース
コピー機や車両、機械などをリースしている会社もあるでしょう。
特定のリース会社に複数のリースをしている場合には一括請求となり、内訳が分からなくなることがあります。
これは、リース会社に問い合わせて内訳を教えてもらうことで、把握することができます。
生命保険
会社では、万が一の場合に備え、代表者・役員・社員の福利厚生のために保険をかけているものです。
その他の保険に加入している場合もあるでしょう。
これも、複数の保険が一括請求されることがあるので、保険会社に問い合わせたり、保険証券と照らし合わせたりすることで内訳を把握しておきます。
その他
その他の支払いも全て把握しておきます。
例えば税金、社会保険、役員報酬、事務所家賃などであり、これらも支出としてしっかり把握し、資金繰り表に反映していかなければなりません。
- 上記の情報を把握していけば、入ってくるべきものが入ってきていない(未入金の発覚)
- 支払うべきものが支払えていない(未払金の発覚)
ことに気づく場合も多々あります。

CFレッド
特に、資金繰りに困っている会社には、その傾向が顕著だ。
直視したくない現実ですが、敢えて直視することによって、単に資金繰り表を作るのではなく、課題を抱えているという自覚のもと、資金繰り改善という目的意識を持って資金繰り表を作ることができます。
【2】変動費と固定費を明らかにする

支出が明らかになったら、次に支出を変動費と固定費に振り分けていきます。
資金繰り表においては、変動費として出て行くお金は原価支払い、固定費として出て行くお金は販売・管理費と分類します。
変動費とは、月や季節によって変動するもののことです。
仕入れなどがそれに当たり、売上に影響される費用です。
固定費は、月や季節によってほとんど変動せず、固定されているもののことです。
事務所家賃や人件費などは、売上に関わらず一定額が出て行きますが、このような性質のものを固定費とします。
どちらも支出であることに変わりはありませんから、変動費と固定費をまとめて計算している会社が非常に多いです。
しかし、本当に役立つ資金繰り表を作るためには、原価率の把握のためにも、変動費と固定費をきちんと分けることが大切です。
この「きちんと分ける」ということは、案外難しいことですから、注意深く分けていく必要があります。
広告費の例
広告費は広告費として、まとめて計上する会社が多いのですが、求人のための広告費と、販売のための広告費は性質が異なります。
求人広告費は売上に関係ないため固定費ですが、宣伝広告費は売上に関係するため変動費となります。
リース料の例
コピー機や電話などをリースしている場合、売上に関係なく一定額が必要となるため固定費に計上します。
一方、工場の機械をリースしている場合、売上に関係する費用ですから変動費に計上します。
水道光熱費の例
水道光熱費は、本社で使っているものは売上に直接関係がないので固定費です。
しかし、工場における水道光熱費は、受注状況によって大きく変化し、売上にも直接関係がある支払いですから、変動費に分類します。
人件費の例
本社勤務の社員は、売上と関係なく一定の出勤になることが多いため、固定費となります。
しかし、工場に勤務している社員は、売上が増えれば休日出勤や残業などをこなしていくため、変動費となります。
時間外労働によって上乗せされた給料は、しっかりとコストとして計上する必要があるのです。
このように細かく分けることができず、変動費にすべきものを固定費、あるいは固定費にすべきものを変動費として計上してしまうと、原価率が分からなくなります。
原価率が分からなければ、せっかく資金繰り表を作っても、あまり役に立たないものとなってしまいます。
したがって、売上に連動するものは変動費、売上に連動しないものは固定費という明確な基準のもと、支出を分類しましょう。
これが資金繰り表を作成する際に面倒な作業となりますが、手抜きは禁物です。
一旦分類してしまうと、その分類はずっと使えます。
固定費に関しては、基本的に増減することがありませんから、1年分くらいはまとめて記入することもできます。
【3】売上区分を作成する

CFブルー
次に、売上区分を作成するよ!
これは、売上計画を立てる際に役立ちます。
会社の売上というものは、一般的には一つの部門や一つの商品から上げられるものではなく、複数の部門で売り上げて行くものです。
部門ごとに売上額はもちろんのこと、商品も違えば利益率も違いますし、取引先や売掛金の回収状況も異なります。
いろいろな点で違いがあるのです。
売上を細かく分類しようと思えば、商品ごとに分析したり、取引先ごとに分析したり、製造している工場ごとに分析したりと、様々な分析手段が考えられます。
しかし、あまりにも細かい分析をすると、却って煩雑になり過ぎますし、情報の更新作業だけでもかなり大変になります。

CFレッド
そこで、中小企業が売上区分を作る際には、3~4つ程度の区分に止めるのがおすすめだよ!
その会社の事業に応じて、何を基準に分けていくのかが変わるため、自社の事業に適した区分にするのがポイントです。
例えば、全部で四つの工場で製造しており、工場ごとに分けていくと決めたならば、A工場、B工場、C工場、D工場のそれぞれにおいて、売上の実績と売上予測を記入していきます。
また、売上区分を作成するにあたっては、社長だけではなく他の役員、実際に売上を把握している営業担当者など、色々な人を巻き込みながら作っていくことが大切です。
【4】機械的に記入していく
【1】~【3】の作業によって、支出を固定費と変動費にわけ、売上をいくつかの売上区分に分け、売上の現状とある程度の予測ができました。
ここまでくると、資金繰り表の8割は完成しています。
残りの2割は、売上原価と売上回収、原価支払を記入していくことで完成となります。
まず売上原価ですが、【2】の変動費における原価支払を、【3】で分けた売上区分ごとに分類し、平均原価率を算出します。
また、売上高予想値からも売上原価を計算することが可能です。
例えば、A~Dまでの工場ごとに売上区分を作成し、それぞれの原価率がA工場70%、B工場60%、C工場60%、D工場70%とわかっているとしましょう。
この場合、まず当月の売り上げ実績と売上原価は、次のとおりです。
また、来月の予想売上高も、過去4期分の実績から予想が可能です。
その予想売上高に原価率をかけると、来月の予想原価支払も把握できます。
すなわち、以下の通りになります。
このように考えると、当月の売上原価を正確に把握し、また来月以降の売上原価の数字を埋めることもできますから、より正確な資金繰り表に近づいていきます。
次に、売上回収と原価支払についての記入です。
会社が抱える売掛債権と買掛債務を全て明らかにし、売掛金が会社に入る日と、買掛金を支払う日がいつであるかを全て把握します。
資金繰り表の該当箇所に記入していきます。
取引先が複数ある場合には、売掛金・買掛金の管理表では細かく管理していきますが、資金繰り表においては煩雑になりすぎることを避けるため、各取引先の平均値で記入していくのが良いでしょう。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

資金繰り表を作ったらここを見よ

ここまでの流れで、資金繰り表は完成です。
始めて作った場合には、改善点や不足な点もあると思われますが、資金繰り表をつけながら経営する習慣がつけば、より自社に合う形に、徐々に変化させていけることと思います。
さて、ここからは、資金繰り表を作ったら確認したい部分を見ていきます。
経常収支を見よう
資金繰り表では、現金収入の合計と現金支払いの合計をもとに、毎月の経常収支を見ることができます。

CFイエロー
この経常収支がプラスならば、問題なく資金繰りを回していると言えるわ。
しかし、資金繰り表を作ってみて、経常収支がマイナスになっていることが発覚したならば、資金繰りを早急に改善しなければなりません。
きちんと売上があって、問題なく経営しているように思っていたとしても、経常収支がマイナスであるならば、売掛金を順調に回収できていないなど、何らかの問題があることが分かります。
場合によっては、黒字倒産もあり得ます。

CFイエロー
具体的には、以下のような場合に経常収支がマイナスになるよ!
支払いサイトと回収サイトのバランスが悪い
支払いサイトが短く、回収サイトが長い場合には、お金が入ってくるスピードよりも出て行くスピードの方が速いことになります。
そのため、資金繰りが非常に厳しくなり、経常収支がマイナスになることが多いです。
この場合には、支払いサイトを延長し、回収サイトを短縮するように取引先と交渉します。
新規の取引先には長めの支払いサイト、短めの回収サイトで契約することによって、経常収支のマイナスを圧縮していきます。
回収サイトが長すぎる
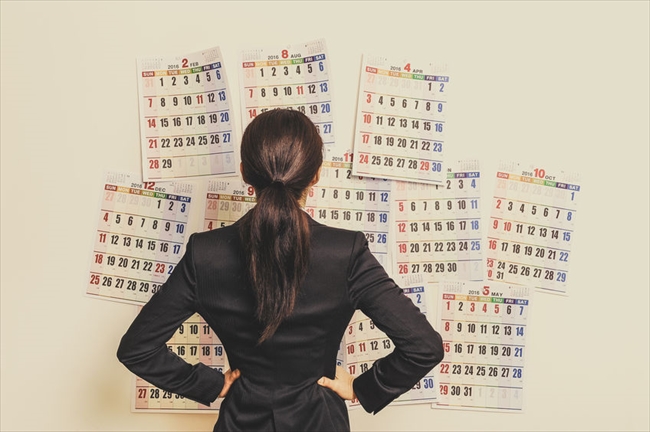
意外に多いのが、回収サイトが長すぎることです。
回収サイトが長期になっていると、現金がなかなか入ってこないのですから、資金繰りはかなり厳しくなります。
これも、支払いサイトとのバランスが悪いケースの一つと思うでしょうが、「バランスが悪い」というレベルではなく、回収サイトが長すぎる場合を指します。
この場合には、取引先と交渉して前受金を受けるようにしたり、手形で回収して手形割引をしたりといった対処が考えられます。

CFブルー
このようなケースは、建設業などでよくみられるよ!
建設業では、建物を解体したり、建設したり、道路工事をしたりしますが、工事の規模が大きくなるほど、完了までに時間がかかります。
もし、完了してから売上を受け取る契約になってしまうと、回収サイトはかなり長期化してしまいます。
だからこそ、完成基準ではなく進捗基準で売上を回収するのが普通で、一定の進捗の都度、回収できるようになっています。
普通の業種でも、回収サイトが長すぎると、完成基準の建設業のように、資金ショートに陥る可能性が高まります。
だからこそ、回収サイトを短くしたり、長いサイトを要求された場合には前受金などの折衷案を提案したり、手形で回収して手形割引をしたりといった対応が求められます。
在庫が多すぎる
在庫管理が良くできていない会社は、余分な仕入をしてしまいます。
仕入れが売上に追い付かない状況になっていると、経常収支がマイナスになる可能性が高まります。
この場合には、在庫と仕入れのバランスを取るようすることで、余分な資金の流出を防ぎ、経常収支をプラスに近づけることができます。
損益が赤字である
ただし、回収サイト、支払サイト、在庫量などに問題がなかったとしても、損益が赤字になっていれば経常収支も赤字になります。
この場合には、支出を減らすためにコストカットに取り組む必要があります。
家賃の安い事務所に移転したり、余分な人材を見直したりすることが重要です。
また、原価率が高すぎるために赤字になっている可能性もあります。
その場合には、原価率を抑えて利益を増やし、赤字を縮小することに努めましょう。
借入返済額を見る

CFレッド
多くの会社では、銀行から融資を受けて資金繰りをしているのだ。
これによって資金をある程度確保しておけば、経常収支がマイナスになる月があっても、月初現預金でカバーすることができるため、資金繰りに行き詰ることはありません。
そこで、資金繰り表で次に確認したいのが、借入返済額です。
銀行から借り入れたならば、当然返済をしなければなりません。
この時、返済額が資金繰りを圧迫していることがあります。
返済額の理想的な形は、経常収支の7割以下です。
残る3割は納税や未払金の支払いに充てるために確保しておきたいものです。
したがって、経常収支に占める返済額の割合を見た時、70%を上回っているようならば、改善を図る必要があります。
まずは経常収支を増やすことを考え、どうしても無理ならば銀行にリスケジュールを交渉し、返済額を圧縮するように努めます。
資金繰り表と試算表を比較する

次に、資金繰り表と試算表の整合性をチェックしていきましょう。
というのも、これらの資料を見比べた時、同じ項目で数字が異なることがしばしばあるのです。
なぜそうなってしまうのかといえば、試算表は会計ルールをもとに作られ、資金繰り表は実際のお金の動きをもとに作られるからです。
自社では、実際のお金の動きである資金繰り表によって経営していけばいいのですが、銀行などの融資を依頼するにあたり、資金繰り表と試算表をセットで提出した際に、このような数字の齟齬が見られるのは好ましくありません。
銀行としては、正しい審査のために正しい数字を求めており、数字が食い違っていることによって、どちらが正しいのかわからないことを嫌うのです。
そこで、銀行にこのような資料を提出する場合には、なぜ数字が食い違っているのかを説明できるようにしておきましょう。
銀行の担当者にきちんと説明し、納得してもらうことができれば問題ありません。
その前提として、資金繰り表と試算表とが、数字は違う箇所があってもきちんと連動しており、それを経営者自身が正確に理解しておくことが重要だと言えます。
資金繰り表をつくったら、この点もしっかりと確認しておくべきです。
まとめ

CF戦隊
本稿では、資金繰り表の基本的な作り方を解説してきたよ。
本稿を読んだだけではぼんやりとしかわからないかもしれませんが、実際に無料の雛形などをダウンロードして、記入していけば具体的にわかることと思います。
実際に資金繰り表を作ってみると、これまで曖昧に把握していたことを、正確に把握できるようになります。
資金繰り表のない状況で経営するよりも、ずっと堅実な経営が可能となるでしょう。