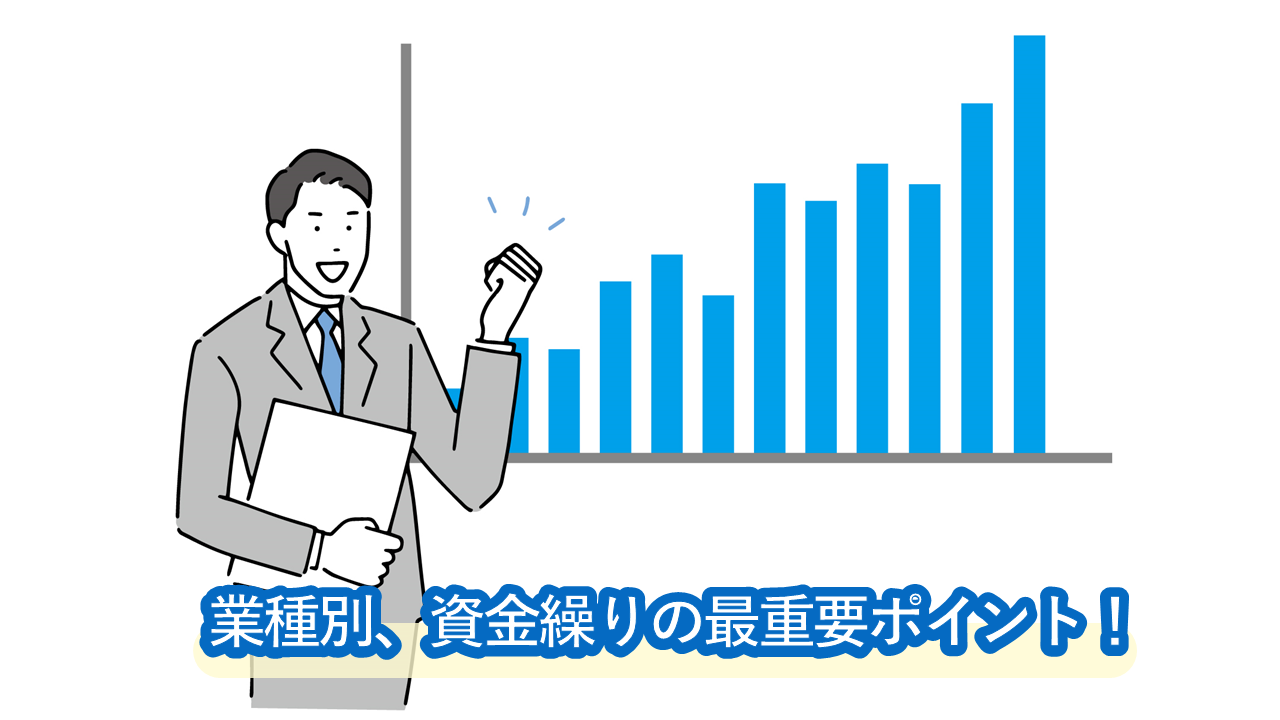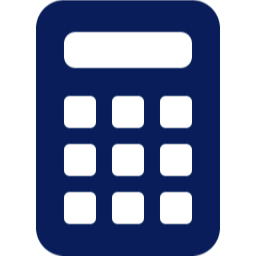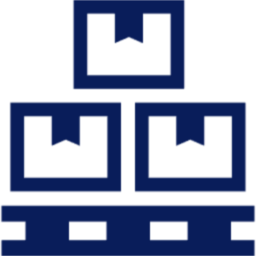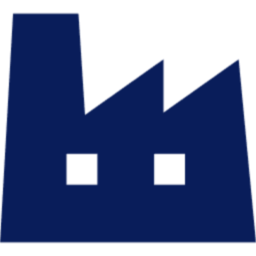ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
小売業の場合

小売業は、他の業種と比べて顕著な違いがあります。
それは、売上の回収方法です。
小売業者は、製造業者や卸売業者から仕入れを行い、最終消費者に販売します。
販売の対象が個人の消費者であるため、売上の回収が現金で即座に行われるのです※。
※クレジットカード払いでは即座に回収とはなりません。
売上を現金で回収できる点は、多くの業種で資金繰りを圧迫している「回収サイト」が存在しないということであり、非常に大きなメリットです。
したがって、小売業の会社が銀行から融資を受けるのは、新規出店などのために必要となる設備資金が一般的です。
小売業の短所
消費者に販売するということは、回収サイトが存在しないというメリットをもたらします。
しかし、買ってくれる消費者の人数や客単価は、いつも一定しているわけではありませんから、売上の予測が非常に難しいです。
1.流行の影響
多くの小売業は、その時の流行に大きく影響されます。
流行の商品を大量に仕入れたところ、翌月には流行が過ぎ去って大量の売れ残りを出した、などということがよくあります。
2.気候の影響
流行以外にも、その年の気候にも影響されます。
例年より暑い年と涼しい年とでは、売れる商品や売れる量が大きく変化します。
雨の日や雪の日には外出する人が減りますから、売上も落ち込みます。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
小売業の資金繰りのポイント
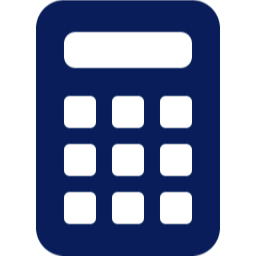
小売業の資金繰りのポイントは以下の通りです。
1.売上予測はシビアに
過去データから売上を予測するときには、下限データを参考にし、最悪の事態を想定しておくことが重要です。
過去の平均値を売上予測にするならば、それはやや見通しが甘いと言えます。
楽観的な予測を立ててしまうと、しばしば下方修正が起きてしまい、資金繰りに頭を悩ませることになります。
2.在庫コントロールをしっかりと
シビアな売上予測を立てると同時に、在庫コントロールも非常に重要です。
食品を取り扱う小売業では、毎日のように棚卸をしている会社も多いと思います。
これは、売れ残り発生のリスクが常にあるということです。
世間の流行や短いスパンでの売上推移を把握しながら、棚卸によって在庫を確認し、コントロールしていくことが非常に重要です。
3.出店の際の注意
小売業では回収サイトが存在しないため、銀行からの融資は新規出店のために受けるケースが大半です。
設備投資のための融資ですから、当然借入額も大きくなります。
そのため、減価償却期間と返済年数が一致しており、できるだけ長期の返済にすることができなければ、資金繰りが非常に厳しくなります。
シビアに資金繰りしていけない経営者は、銀行の返済条件が厳しい場合でも、見切り発車で融資を受けてしまうことがあります。
小売業のポイントまとめ
- 現金で回収するため、運転資金の必要がなく、資金繰りが回りやすい
- 流行や天候などの影響を受けやすいため、売上予測はシビアに立てる
- 店舗ごとに資金繰りを把握する
- 在庫の管理をこまめに行い、在庫をコントロールする
- 設備資金を借り入れる際には、返済期間をできるだけ長期にする
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
卸売業の場合
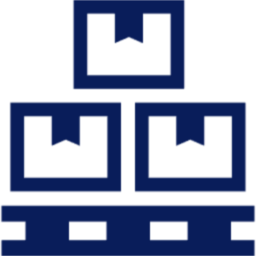
卸売業の特徴は、必ず仕入れを伴うことです。
仕入れた商品を売って売上がはじめて発生するため、売上の回収よりも仕入れの支払いの方が先になります。
このため、運転資金が必ず必要になります。
卸売業の短所
卸売業の短所は、上記の通り、売上回収よりも支払いが先行することです。
このほかにも、在庫を確保しておかなければならないのも短所です。
注文が入ってから仕入れをしていたのでは間に合いませんから、常に一定の在庫を確保しておき、注文の都度出荷していくことが重要です。
卸売業では、在庫のコントロールは、資金繰りにダイレクトに影響してきます。
【注意】
また、卸売業の多くは利益率が低いです。
したがって、過剰な在庫を抱えてしまうと、処分のための値引きや在庫管理費が、少ない利益をさらに圧迫することになります。
卸売業の資金繰りのポイント
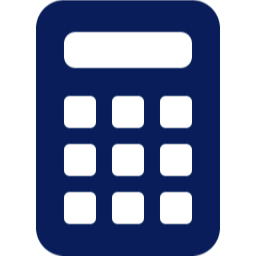
卸売業の資金繰りのポイントは以下の通りです。
1.仕入れと在庫のコントロールを適切に
仕入れと在庫のコントロールを適切に行うためには、仕入れ責任者を一人に絞ることが重要です。
一番悪いのは、複数が仕入れを担当し、経営者が仕入れと在庫の状況を把握できていないケースです。
仕入れ責任者を一人に絞り、なおかつ能力の高い社員を仕入れ担当に据えることが大切です。
必要な仕入れを見極め、余剰在庫を出さないようにできる人物が仕入れを担当するのが好ましいです。
2.最低ロット数を調整する
過剰在庫を作らないためもう一つ重要なのは、最低ロット数を調整しましょう。
たとえば、自社で取り扱う商品のうち、顧客からの注文は1個単位で行われるものの、仕入れは100個単位の商品があったとします。
このとき、「1年かけて売りきろう」などと考え、100個購入する会社は多いです。
このような方針で仕入れを行ない、うまく100個売りきることができればいいのですが、いずれ売れ残りが発生します。
最低ロット数を調整するために、取引先と交渉することが大切です。
「割高になってもいいので10個単位で仕入れる」、「10個単位で売ってくれなければ仕入れない」などの交渉が考えられます。
3.倉庫を縮小する
過剰な在庫を産まないために、倉庫を縮小することも重要です。
倉庫が大きければ、まだまだ仕入れる余裕があるように錯覚しがちです。
倉庫を少し小さめにしておくと、本当に必要な仕入れを検討し、無駄のない仕入れをしていくことができます。
4.回収・支払サイトの調整
販売より仕入れが先行するため、売上の回収よりも支払いのほうが早くなりがちです。
これは仕方ないとしても、売上の回収と支払いの間隔をできるだけ縮めることによって、資金繰りが回りやすくなります。
このため、支払いを少しでも遅らせる、回収を少しでも早くする、販売の一部を現金で回収するなどの工夫をしていきましょう。
卸売業のポイントまとめ
- 仕入れと在庫のコントロールを徹底する
- 有能な社員一人に仕入れを担当させる
- 仕入ロットを調整する
- 倉庫を縮小する
- 回収サイトと支払いサイトを調整し、運転資金を圧縮する
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
製造業の場合
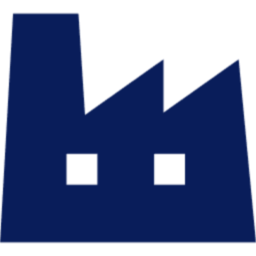
製造業の特徴は、商品を製造して売るため、他の業種よりも原価率が重要になるということです。
他の業種でも原価率は考慮しますが、取り扱う商品を製造するところを担う製造業では、原価率の重要性が他の業種より大きくなります。
製造業の資金繰りのポイントは、原価率を正しく把握することです。
そのためには、以下の点に従ってチェックしてみてください。
1.製品ごとに売上を分けているか?
資金繰り表の売上区分は、全ての製品や複数の製品をひとまとめにしていないでしょうか。
もしそのような状態になっていれば、仕入原価の予測が困難になり、資金繰りを回していく上で障害になります。
資金繰り表の売上区分は、製品ごとにわけるようにしてください。
2.変動費と固定費を正しく分けているか?
製造原価も、変動費と固定費で分けるべきです。
たとえば、変動費に組み込むべき工場の機械のリース代や、工場での水道光熱費を固定費に組み込んでしまうと、正しい原価率がわからなくなります。
同様に人件費にも注意が必要です。
工場に勤務しているスタッフの人件費が毎月一定になっているとすれば、それは何らかの間違いがあるはずです。
3.修繕費を考慮しているか
製造業は、機械を稼働させなければ事業が成り立たないため、定期的なメンテナンスが必要となります。
修繕費も考慮したうえで原価率を考えなければなりません。
4.返済は計画的に
製造業が銀行から工場の設備投資で融資を受ける場合、かなり巨額の融資を受けることになります。
このような設備投資の際には、返済期間も長期になるのが一般的です。
しかし、返済期間が長くなるということは、返済期間中に経営状況が悪化する可能性もあるということです。
借り入れた当初は問題なく返済できていたとしても、いつしか返済が困難になることがあります。
当初の計画での返済が、資金繰りを大きく圧迫しているような場合には、銀行に資金繰り表を提示しつつ、リスケジュールを相談しなければなりません。
5.保険は重要
製造業では、工場作業員の事故やケガのリスクが高いため、保険の重要性が他の業種よりも大きくなります。
自社のリスクをきちんと把握し、適切な損害保険や生命保険に加入しておきましょう。
製造業のポイントまとめ
- 変動費と固定費を正しく分けることで、原価率を把握する
- 製造工程における無駄を省く
- 設備資金の融資は、資金繰りを圧迫しすぎないように返済していく
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ:業種ごとに特徴が違うと知っておこう
本記事では、主要な三つの業種について、資金繰りのポイントを解説してきました。
これ以外の業種でも、考え方を応用することによって、資金繰りのポイントが見えてくることと思います。
一般的な資金繰りの方法を鵜呑みにするのではなく、自分の業種の特徴や長所・短所を踏まえて資金繰りをしていきましょう。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。