
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
旅費を損金にする

次に紹介したい節税策は、旅費を損金にする方法です。
もちろん、プライベートでの旅行の旅費は損金にすることはできませんが、会社に関連する旅費ならば損金にすることができます。
会社に関連する旅費には、次のものが挙げられます。
- 社長や社員の出張・視察などの際の旅費
- 社内旅行や研修旅行の旅費
交通費や宿泊費を経費として計上することができるのです。
社員旅行は、社員の慰労や士気を高めるためなど、事業と無関係ではありませんから、基本的に経費計上が可能です。
しかし、それが事業と関係しているか、それとも単なる遊興目的であるかとなると、曖昧な部分も多いものです。
そこで、社員旅行の旅費を経費とするためには、次のような条件があります。
- 国内旅行の場合には4泊5日以内、海外旅行の場合には現地での滞在期間が4泊5日以内であること
- 参加者が全社員の50%以上であること
- 不参加者に手当を支給しないこと
この条件を満たさない社員旅行は、単に社員に対する給与とみなされます。
給与とみなされるということは、会社の社会保険料と、社員個人の税金・社会保険料が増えるということです。
また、上記の条件を満たしていたとしても、あまりにも会社の負担が大きくなる場合にも問題とされます。
一般的には、社員1人あたりの会社の負担額を10万円までにすることが多いです。
出張手当を損金に
また、出張旅費規程に日当の定めを設けておくことにより、旅費だけではなく、出張した社員に支給する日当も経費にすることができます。
出張手当として支払われる日当は、損金に計上して会社に節税効果があります。
また、受け取る社員側も非課税所得として受け取ることができるため、両方にメリットがあります。
なお、ここで支払われる日当の意味は、交通費や宿泊費といった旅費に含まれるもの以外に、出張に伴って生じる食事代その他の費用を賄うものです。
このため、支払われる日当が大きすぎる場合には認められないことに注意し、自社の規模や業種から考え、適正な額を定める必要があります。
出張旅費規程を定めよう
日当を経費にするためには、出張旅費規程を策定する必要があります。
出張旅費規程に盛り込む内容は以下の通りです。
目的
出張旅費規程の目的です。
(例:「役員または社員が事業に伴い出張する場合の手続きと旅費に関して定める」)
定義
これは、出張の定義です。
一般的には、移動距離が片道100㎞を超えるものを出張とすることが多いです。
短い距離のものを近出張、長い距離のものを遠出張などとし、距離によって定義を分けることも可能です。
適用範囲
規程の適用範囲は、全社員を目的とするものでなければなりません。
この旨の記載も設けておくことで、出張旅費規程としての体裁を整えていきます。
金額
会社から支給される交通費や宿泊費や日当について、それぞれの金額を定めます。
交通費と宿泊費は、定額支給と実費精算のどちらも可能ですが、一般的には実費精算となります。
しかし、定額支給にすることで領収書の確認が必要なくなり、事務処理が効率化するため、定額支給を採用する会社もあります。
日当は、出張の日数や移動距離などに応じて変えたり、役職に応じて支給額を変えたりすることができます。
清算方法
旅費や日当の清算手続きを定めます。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
役員報酬を節税に活かす

役員報酬は、節税策の中でも比較的よく知られた方法です。
役員報酬は、一定の条件を満たすことによって損金にすることができるため、節税に役立てられるのです。
ただし、役員報酬を確実に損金として計上するためには、一定の条件を正確に満たしていく必要があります。
その条件とは、「定期同額給与」という条件です。
定期同額給与とは、定期すなわち毎月一定の時期に、そして同額の給与が支払われるという条件のことで、これを満たした場合のみに役員報酬が損金となります。
この条件を満たすためにも、例えば役員報酬の金額を変更したい場合などには、必ず事業開始年度から3ヶ月以内に改訂するなどの注意が必要です。
したがって、しばしば間違った節税方法として見られるように、期の途中で役員報酬を増やすことで節税を図る方法は間違っています。
例えば、決算時期が近付いた時に思わぬ利益が出た場合などに、役員報酬を増額することによって節税を図る場合があるのですが、増額分(定期同額給与における一定額からはみ出した部分)は損金にはなりません。
逆に、役員報酬を一定額に設定しておいたところ、期の途中に資金繰りが厳しくなって役員報酬を減額した場合にも、定期同額給与の条件を満たさなくなるため、減額分が損金として認められなくなります。
なお、役員報酬を節税に取り入れるにあたっては、会社への課税と、報酬を受け取った個人への課税の両面から検討して、メリットが得られるように設定すべきです。
これは、法人の実効税率は30%程度であるのに対し、個人への所得税と住民税の税率は最大で55%になるからです。
このため、多額の役員報酬を出した結果、会社としての納税額は少なくなったものの、個人での税率が高くなり過ぎたならば、トータルで税額が高くなってしまうため意味がありません。

CFレッド
役員報酬を支払うことによって、会社と個人のトータルで節税効果が得られるように設定していこう!
そのためには、役員報酬を支払うにあたって、社長一人に支払うよりも、役員をしている家族に分散して支給するなどの対策が効果的です。
税額控除は取りこぼさず

法人が認められている税額控除については、利用できるものは取りこぼすことなく使っていくことが重要です。
主な税額控除には、機械類を取得した場合に適用できるものや、研究開発を行った場合に適用できるものなどがあります。
機械の取得に伴う控除
まず、機械などの固定資産を取得した場合に受けられる税額控除があり、これは多くの会社が利用可能です。
中小企業の設備投資を促すために設けられている制度ですから、利用のハードルも低いと言えます。
ただし、機械類ならば何を導入しても控除の対象となるのではなく、一定以上の価格や規模のものに限られます。
代表的な例を挙げると、次のものなどがあります。
- 70万円以上のソフトウェア
- 1台160万円以上の機械や装置
- 1台120万円以上の、事務処理の効率化や、品質管理の向上などのために導入した機械や工具
- 3.5トン以上の車両
また、資本金が3000万円以上の法人や、特定の業種(不動産業や電気業など)は対象外となるため、自社が対象に含まれるかどうかをよく確認することが大切です。

CFイエロー
この仕組みを利用することで、取得価格の7%相当額を法人税から控除することができるわ。
ただし、法人税額の20%が上限とされているため、法人税額があまりに小さい場合や、導入した設備があまりにも高額である場合には、控除できる額が小さくなります。
といっても、控除しきれなかった部分は翌事業年度の控除に回すことができるので、これもうれしいところです。
研究開発に伴う控除
次に利用したいのが、研究開発に伴って発生した経費を控除するものです。
これも、機械の導入と同じように、中小企業の競争力を高めるべく、研究開発を促進するために設けられている制度です。
一般に、研究開発には多額の費用を要するものであり、会社の資金繰りを圧迫したり、相応のリスクを負う覚悟の上で取り組まれるものです。
そこで、この制度を利用することによって税金を減らし、現金の流出を防ぐことで、研究開発に伴うリスクの低減につなげられると言えます。
控除の対象となる研究開発には、製品の開発や改良、技術の開発や改良、ビッグデータを活用したサービスの開発や改良などが挙げられます。
複雑な制度であるため、詳しくは税理士などの専門家にも相談しながら進めるのが良いだろう。
しかし、この制度をうまく利用することによって、法人税額を大幅に(最大で法人税額の40%程度)控除できる場合もあるため、積極的に検討したいものです。
なお、このような税額控除は、その時々での社会や経済の状況を踏まえ、期間限定で設定されるものも多いです。
そのため、普段から情報収集しておくことで、利用できる控除を見つけていくことが大切です。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
社宅を使った節税法

社員の福利厚生を節税につなげる方法として、社宅を使った節税法が挙げられます。
一般的な社宅は、会社が不動産を借りた上で社員に提供するものであり、これを借り上げ社宅と言います。
この場合、会社は前提となる不動産の賃貸をするにあたって、不動産のオーナーと賃貸借契約を交わし、オーナーに対して家賃を支払っていくことになります。
まず、この家賃が会社の損金となり、節税につながります。
同時に、会社は社宅を提供した社員から家賃を受け取ります(もし、無料で住まわせた場合には給与として課税される)。
社宅は福利厚生を目的としており、安い家賃で貸し出すのが普通ですから、会社が不動産オーナーに支払っている家賃と、社宅に住む社員から受け取る家賃にはおのずと差が生じます。
例えば、不動産オーナーに対して毎月8万円の家賃支払い、社宅に住む社員からは3万円の家賃を受け取り、差額にあたる5万円だけ社員の給料を下げることとします。
この時、法人は元の家賃である8万円を損金として計上し、社宅に住む社員から受け取る3万円を益金として計上するため、差額の5万円が経費となります。
しかし、社員の給料を5万円下げることで、この経費分は相殺され、節税効果はなくなります。
一方、社員は給料が5万円下がり、本来の家賃よりも5万円安く済むことができ、なおかつ給料が下がったことで所得税と住民税、そして社会保険料もさがります。

CFイエロー
最終的な手取り額は増えることになるよ!
一見すると、社員だけにメリットがあって会社にはメリットがないようにも見えるかもしれません。
しかし、見方によっては、会社の負担を全く増やすことなく、社員の手取り額を増やしているとも言えます。
単に給与を増やすことによって社員の手取り額を増やそうとすれば、給与の増額によって社会保険料が上がり、会社の負担も増えることになるのです。
このように、社宅を利用することによって、会社と社員の両方にメリットがあります。
節税策として考えると、効果はそれほど大きいとは言えませんが、機会があれば検討してみる価値があるでしょう。
ちなみに、福利厚生の一種である住宅手当は、給与と見なされます。
したがって、会社の社会保険料が増えると同時に、個人の課税額と社会保険料も増えるため、社宅とは異なることが分かるでしょう。
食費を経費にする方法

食事代を経費にする方法は、多くの会社で取り入れていると思います。
生きていく上で必要不可欠な「食事」という行為を、できるだけ多く損金にしたいと考える人も多いでしょうから、その基準を知っておくのが良いでしょう。
まず、プライベートな食費は損金にすることができませんが、これは多くの人がすでに知っていると思います。
損金にできるのは、あくまでも事業に関係のある飲食費であり、主に会議費、接待交際費、福利厚生費が挙げられます。
会議費
例えば会議を開いた際にお茶やお菓子を購入したり、長時間に及ぶ会議の最中に弁当を出したり、あるいは喫茶店で会議をした場合などに発生した飲食費は、会議費に計上することができます。
接待交際費
取引先の担当者を食事に招いたり、取引先との親睦を深めるために懇親会を開いたりすると、飲食費が発生します。
このような支出は、接待交際費として計上することが可能です。
損金に計上できる金額には上限があり、資本金1億円以下の会社では、年間800万円までが損金として認められることになっています。
なお、1人あたり5000円以下となる場合には、この800万円の枠に含まず、少額交際費や会議費などとして計上することができます。
福利厚生費
社員の慰労のために発生した飲食費、例えば新年会や忘年会、その他の時期に応じて発生する福利厚生のための飲食費は、福利厚生費として損金にすることができます。
あくまでも、社員の慰労のために行うものですから、全社員を対象とする必要があります。
このため、役員だけ、特定の部署だけ、希望者だけといった形での飲み会などは損金の対象とはなりません。

CFレッド
もちろん、一部社員だけが参加する二次会や三次会などについても同様だ!
以上のように、一定の範囲内で飲食費を経費にすることが可能です。
何でもかんでも、食事を全て経費にすることはできませんが、できるだけ取りこぼさずに計上していくことが大切です。
もし、事業と関係ない部分の飲食費も損金に計上しているならば、すぐに改めるべきです。
税務調査に入られたとき、事業との関連性を証明できない飲食費がたくさん見つかれば、ペナルティを課せられることとなります。
このため、客観的に見て事業と関連のある飲食費とわかるように、領収書を取っておくと同時に、会議や接待に参加した人の名前、日時、目的などのメモを残しておくことが大切です。
残業時に食事代を提供する
食費を損金にすると言えば、社員に提供する食事代を経費にする方法もあります。
例えば、社員の残業に対する慰労のために、会社から食事代を提供する場合などには、福利厚生費として損金計上が可能です。
ただし、福利厚生の基本的な考え方に基づき、全社員を対象としていること、実費精算であること、常識的な範囲内であることなどが条件となります。

CFブルー
条件を満たさない場合には、給与とみなされるため注意が必要だよ!
この条件を満たすためにも、規程を設けて社員に知らせておくのが良いでしょう。
規程には時間、上限額、申請方法などを明確にしておきます。
例えば、夜〇時以降の残業の場合、1000円を上限として補助するものとし、制度を利用する際には部長の承認を受けるようにする、などの規程を設けておくのです。
このように決めておけば、いざ税務調査に入られた時にも説明がしやすくなります。
社員の技能習得も経費になる

社員に技能を習得させたり、資格を取得させたりするにあたり、その費用を会社が負担し、損金とすることも可能です。
ただし、資格や技能ならば何でもよいというものではなく、あくまでも会社に貢献するために必要なものであること、そして費用が適正であることが条件です。
例えば、以下のような費用を法人の損金とすることができます。
- 経理担当者が簿記を取得するための費用
- 海外派遣を予定している社員が、外国語を学ぶための費用
- 倉庫作業員がリフトカーの運転免許を取得するための費用
- 保険代理店の社員が、フィナンシャルプランナーを取得するための費用
- レストランのスタッフが、ワインソムリエの資格を取得するための費用

CFイエロー
このほかにも、応用できるものは色々あるよ!
社員が会社に貢献できる資格や技術を身に着けることによって、会社には長期的なメリットが得られるようになります。
そのための費用を損金計上するのですから、節税と同時に社員育成にもつながると言えます。
車両に関する損金

次に、個人の所有する車両を用いた節税方法です。
普通、個人が所有している車両を事業で用いた場合、ガソリン代や高速料金といったものは実費で清算することで、経費とすることができます。
多くの会社では、個人の車両で図る節税として、この方法を取り入れています。
しかし、個人名義の車両であるがゆえに、その車両を維持するための修理費用や車検費用、保険料などは個人が負担しなければなりません。
そこで、車両の名義を法人名義にすることで、車両の維持費用も法人負担とし、経費として計上することが可能となります。
このためには、名義を個人から法人へと変更するために、個人と法人の間で譲渡契約を結ぶ必要があります。
法人が個人から買い取り、譲渡するのです。
もちろん、この時に過大な価格で買い取っていれば、市場価格をオーバーしている部分を給与としてみなされてしまうため、あくまでも市場価格での買取となります。

CFレッド
このとき、売却によって個人が得たお金は非課税だ!
譲渡が完了すれば、車両は法人名義のものとなり、修理代や車検代、保険料など、維持のために必要となる様々な費用を法人の損金にすることができます。
ただし、このように譲渡したとしても、それまでと変わらずプライベートでも利用するケースが多いと思います。
この場合には、全てを損金とすることはできないことに注意しておきましょう。
というのも、プライベートで使用した部分は事業とは無関係であることから、その部分では損金とすることができないからです。
したがって、法人と個人の利用において、利用する日数や移動距離などに応じて、合理的な損金を計上する必要があります。
賃貸借契約はどうか
もう一つの方法として、法人に売却することによって譲渡するのではなく、個人から法人に車両を貸すことも可能です。
この時、個人と法人は賃貸借契約を結び、レンタル料が発生します。
この場合にも、法人が支払ったレンタル料は損金になるため、節税の効果を見込むことができます。
しかしながら、個人が受け取ったレンタル料は所得とみなされ、課税対象となります。
このことから、車両による節税は、賃貸借契約よりも譲渡契約のほうが優れていると言えるでしょう。
自宅の一部が職場の場合

小規模な会社では、自宅の一部を事務所として営業したり、自宅の1階部分を店舗として小売店を営業したりすることがあると思います。
このような場合には、自宅を法人登記しているならば、法人の利用しているスペースに応じて損金計上することができます。
この方法では、自宅が賃貸物件であるか、持ち家であるかによっても異なります。
賃貸物件の場合
まず、自宅が賃貸物件である場合には、毎月の家賃が発生しているはずです。
このため、自宅の床面積に対し、事業で利用している面積が占める割合に応じて、賃料や管理費、共益費などの一部を法人の損金とすることができます。
例えば、毎月の賃料が10万円であり、床面積が100㎡であり、そのうちの20㎡を事業に利用しているとします。
この場合、床面積全体の20%を法人が利用していると考えられるため、法人は毎月2万円を損金とすることができます。
持ち家の場合
次に、自宅が持ち家である場合には、法人が個人の持ち家の一部を間借りする形で賃貸借契約を結びます。
この場合にも、法人が個人に支払う賃料を損金として計上することができます。
ただし、個人側は法人に対して自己所有物件の一部を貸し出して利益を得ている、すなわち不動産所得を得ていると見なされるため、課税対象となります。
したがって、確定申告も必要となるわけですが、自宅にかかる固定資産税などに関しても、法人に貸し出している面積などから按分し、賃料から差し引いたうえで不動産所得として申告します。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
本稿で紹介した通り、節税策には色々な方法があります。
大きな効果が得られるものもありますが、効果がそれほど大きくないように見える方法でも、こまめに損金としていくことによって、積もり積もって大きな節税効果をもたらすこともあります。
長期的に大きな節税につながることもあります。
したがって、色々な節税策がある中で、自社が取り入られるものを探し、こまめに取り入れていくことが大切だと言えます。


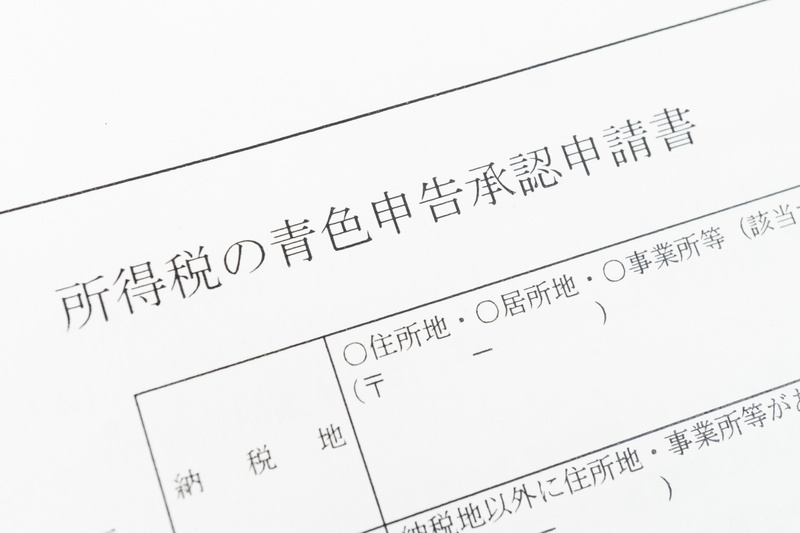

























コメント