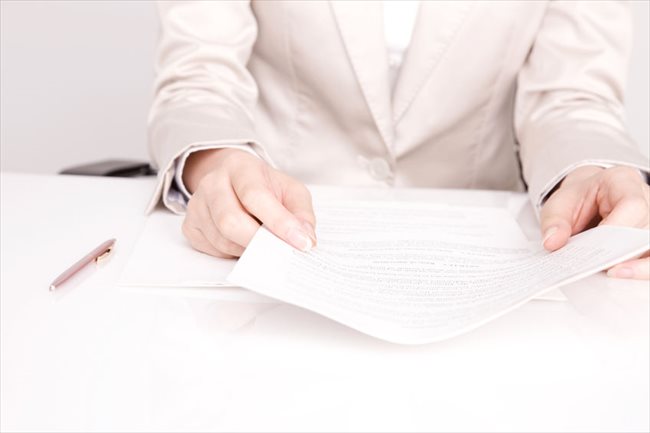ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
助成金・補助金の全体像

では、助成金・補助金とは具体的にどのようなものであるのか、その全体像を見ていきましょう。
助成金の全体像
助成金とは、厚生労働省が交付している資金であり、上記の通り返済不要です。
この助成金は非常にポピュラーで、助成金や補助金と言えばどれも、厚生労働省の助成金だというイメージもあります。
厚生労働省が担当している政策分野は、医療、子育て、福祉、雇用、年金といった分野です。
このことからもわかる通り、厚生労働省の助成金は雇用関係を目的としています。
例えば、これらがそれに当たります。
- 障碍者雇用や高齢者雇用を含む新規雇用
- 従業員の教育
- 残業の削減
- 有給休暇の充実
- 出産・育児に伴う休暇の普及
よく、「会社が障碍者を雇用するのは、慈善目的でやっているのではなく、実は助成金目的だ」などということを耳にすると思いますが、この助成金も厚生労働省から出ている助成金です。

CFイエロー
雇用の安定や労働環境の向上を目的としていることが分かるね!
助成金の額は数十万円~数百万円程度で、50種類程度のメニューが設けられています。
雇用の安定や労働環境の向上は国の重要課題であるため、設定されている条件を満たすならば、高確率で受給することができます。
特に、現在安倍内閣では、「働き方改革」を推し進めていることからも、受給しやすい助成金と言えるでしょう。
助成金は「ご褒美」

助成金の性質を理解するとき、これは国からのご褒美のようなものと考えれば分かりやすいでしょう。
雇用関係の事柄に対して助成金が交付されるわけですが、交付を受けるためには労働環境を整備します。
その上でもらうことになります。
労働環境の整備にあたって社員を教育したり、有給休暇を増やしたり、残業時間を削減したりすると、短期的には会社はマイナスになるでしょう。
それまでこれらの取り組みをしてこなかった会社というのは、「取り組まなかった」というよりも「(余裕がなくて)取り組めなかった」のです。

CFブルー
それに取り組もうとするのだから、当然マイナスの影響も生じるのだ。
例えば社員の教育をすれば、それまでは生産に充てていた時間を教育に充てることになります。
有給休暇を増やしたり、残業時間を減らしたり、育児休暇を促進したりすれば、売上にダイレクトに響くでしょう。
しかし、教育を受けた社員は、じわじわと会社に貢献するようになってきます。
休暇を増やしたり残業を減らしたりすれば、その中で生産性を維持するために、業務の効率化を促進させることになります。
これも会社を強くするのです。こうして、労働環境は向上していきます。

CFレッド
このようなことは、会社でもわかっているのだ!
しかし、いざ取り組むとなると手間もお金もかかるために躊躇し、後回しになっているのです。
そこで、「手間とお金をかけて労働環境を改善し、日本経済の成長に貢献してくれた会社」には、国からご褒美として助成金を交付するのです。
上記の通り、雇用関係の助成金は数十万円から数百万円の交付となるのが一般的です。
就業規則を変更したり、教育プログラムを作って実行したり、簡単な内容ならば少額の受給となります。
受給したとしても、マイナスのほうが大きいと感じることもあるでしょう。
このため、「なんだ、これだけしかもらえないならやらないほうがいいじゃないか」と考える経営者もたくさんいます。
お金をもらうために受給すると考えてしまうと、どうしてもマイナス面が気になり、取り組むことが難しくなります。
しかし、助成金はあくまでご褒美のようなもので、雇用や労働環境改善に努力したことへのボーナスがもらえると考えましょう。
資金繰りのためという考え方では、助成金はそれほど役立たないかもしれませんが、それを言い出せばキリがありません。
融資や社債や出資なども、資金繰りのためにやっていると同時に、会社の成長のためにやっていることです。
その意味では助成金も同じと考えることもできます。
積極的に取り組んで会社を強くし、ボーナスまでもらえてありがたい制度だと考えるべきなのです。
近年の傾向

以前、助成金の多くは雇用調整に対して支払われていました。
雇用調整とは、失業率を低く抑えるための取り組みです。
例えば、不況に陥って会社の業績が悪くなれば、クビになる社員が出て失業率が高まってしまいます。
それを、クビを切ることなく、給料を大きくカットして自宅待機にするなどして、失業率を下げることを雇用調整といいます。
このような取り組みをした会社に対して助成金が交付されていたのです。
このほか、新たな雇用が生まれることを期待して、起業に際して助成金が交付されることも多かったものです。
起業したばかりのタイミングでは資金繰りも厳しく、最低限の人員で回そうとするため、雇用が全く生まれないこともあります。
そこで、従業員を雇った場合に助成金を交付し、それを給料の一部に充てられるようにします。

CFイエロー
しかし、近年の助成金の傾向は、社員教育やパート社員の正社員化が中心になりつつあるわ。
これも、働き方改革の流れを受けて変化したものです。
既にある雇用をともかく維持したり、新たに雇用を生み出したりするよりも、優秀なパート社員を正社員化したり、正社員の質を教育によって高めたりすれば、優秀な人材が会社を回していく流れが生まれます。
会社が成長して安定的に雇用が生まれていくのです。
これは、雇用調整や起業よりもはるかに効率的な方法です。
税金を効果的に活用していくにあたり、このようなシフトが起きているのです。
補助金の全体像

補助金とは、経済産業省や地方自治体(あるいは外郭団体)が交付しているものです。
これは助成金とは異なり、基本的に研究費の性質を帯びています。
新しい製品・サービス・技術などを開発するための費用を交付しているのです。
新しい製品・サービス・技術などが開発されると、その周辺でビジネス環境ががらりと変わり、新たな経済圏が生まれることがあります。
例えばスマホが開発されたことで、それに必要となる様々な部品を製造したり、スマホ関連サービスなどが立ち上がったりしたことで、巨大な経済圏が生まれました。
とはいえ、スマホのような画期的な開発をすることが目的ではありません。

CFブルー
製品・サービス・技術などの開発によって、起業やものづくり、地域活性化などを目的としているのだ!
そのため、補助金の制度はバラエティに富んでおり、3000種類ほどのメニューがあります。
開発には多額の費用が掛かりますし、開発が完了しても、それをビジネス化するためにお金がかかります。
宣伝広告やコンサルティングにも費用が掛かります。
このため補助金は、最大で5000万円程度まで交付されることがあり、厚生労働省の助成金より受給額が大きいことが分かります。
それだけに公募は年に1~2回行われ、書類審査と面接に合格しなければ交付されません。
厚生労働省の助成金は、要件を満たせば交付されるため、倍率という概念がありません。
それに対し補助金は、認められた一部に交付され、その倍率は10~20倍になるのが普通です。
資金繰りに役立つ補助金

助成金がご褒美的な性質を持っているのに対し、補助金は資金繰りに役立つ制度だと考えることができます。
そもそも、補助金は資金需要を補助するためのものだからです。
新しい製品やサービスを開発するためには、開発費が必要です。
新製品を開発したならば、その製品を製造して事業を展開するための設備投資が必要になるでしょう。
新しいサービスを展開していこうとするならば、専用のホームページを作る必要がありますし、販路を開拓するために展示会を開く費用なども必要です。

CFイエロー
その資金繰りのために、補助金が交付されるのよ!
つまり、せっかくアイデアなどがあってもお金がなければできないところを、補助金を交付することで実行可能とします。
その延長上で経済の活性化を目指すものなのです。
したがって、補助金を受給するための審査では、事業計画書を提出する必要がありますし、面接も受けることになります。
面接の際には、事業計画書をもとに説明し、その事業が社会にどのように有益であるかを説明しなければなりません。
このPRによって、経済産業省や地方自治体が社会的に有用だと認めたならば、補助金を交付することになります。
以上によって、助成金と補助金のそれぞれの特徴や違いが分かったと思いますが、ここでその違いをまとめておくこととします。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
助成金・補助金のメリット
助成金や補助金は、捉え方によっては資金繰りに役立てていけるものです。
しかし、助成金や補助金をもらうということは、実はお金以上に効果のあるものです。
そのメリットを知っておくとさらに魅力が増します。
特に助成金がそうですが、助成金の交付を受けるための取り組みが受給金額に見合わないことも多いのです。
ですが、お金以外のメリットがあるからこそ、やる意味があると考えることもできるのです。
そのメリットとは、主に以下の二点です。
自己資金が増える
上記の通り、助成金や補助金は一定の条件をクリアした会社に支給される、返済不要のお金です。
返済不要のお金ですから、丸々自己資金となります。

CFレッド
自己資金が増えると、更なる資金調達に役立つことも多いよ!
例えば、日本政策金融公庫の融資では、融資希望額の一定の自己資金があることが要件になっているものもあります。
その他の融資制度でも自己資金を求められることは多いです。
この時、助成金や補助金によって自己資金を増やしていれば、これらの融資制度の利用が可能になってきます。
公的金融機関だけではなく、銀行など民間の金融機関からの融資も受けやすくなります。
銀行の融資審査では、決算書が非常に重要となるため、貸借対照表の純資産はできるだけ潤沢である方が好ましいのです。
ここでも自己資金が増えることが役に立ちます。

CFイエロー
また、起業後間もない会社は、経営実績がないため決算書もないわ。
その場合には、事業計画書や収支計画書が審査に用いられますが、この収支計画表でも、自己資金がどれだけあるかが重視されます。
事業計画がうまくいかず、利益が出ない期間があったとしても、自己資金があればある程度は経営を続けることができます。
事業が軌道に乗る可能性があるのです。
さらに、融資した資金が回収困難になったとしても、銀行はその自己資金から回収することもできますから、これも融資にプラスに働きます。
政府が認めたことになる

自己資金が増えるよりも大きなメリットがあります。
それは、政府に認められた証拠になるということです。
助成金ならば、厚生労働省が認めなければ交付されません。
国が求めている労働環境の整備を進めており、人材教育に力を入れていたり、効率的な業務を推進していたりすることの証拠となるのです。
補助金をもらうためには、経済産業省が認めなければなりません。
これによって、その会社の事業が社会的に有益であり、将来性があるものであることを国が認めたことになります。
このように、助成金や補助金をもらうことによって、国からのお墨付きをもらうことになります。
これが、取引先や地域、金融機関などに与えるプラスの印象は大きなものと言えます。
「お金をもらえる経営をする」ということ
助成金や補助金には、上記のようなお金に換えられないメリットがあります。
受給のためには手間がかかりますが、それによって会社は成長し、イメージも良くなるのです。
長期的に見れば支払った手間や費用以上のリターンが期待できるでしょう。

CFレッド
会社の経営には、長期的な視点が必要だ!
短期的に見ればマイナスが大きかったとしても、長期的に見てプラスが大きいならば、今後も長く経営を続けていくために、様々な取り組みをしていくべきでしょう。
今後、何十年も経営を続けていくためには、社会から必要とされる会社でなければなりません。
だからこそ、長期的な視野を持って取り組める会社には、助成金や補助金が受給されるのです。
したがって、「お金(助成金や補助金)をもらえる経営をする」ということは、すなわち「いつまでも社会から必要とされる会社であり続ける」ことでもあります。
そのような会社であるからこそ、利益も生み出すことができ、会社を成長させることができます。
雇用を生み出すことができ、地域を活性化することができるのです。
このように考えると、助成金や補助金をもらえる会社であることが、いかに大切であるかが良くわかると思います。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
助成金の種類と申請
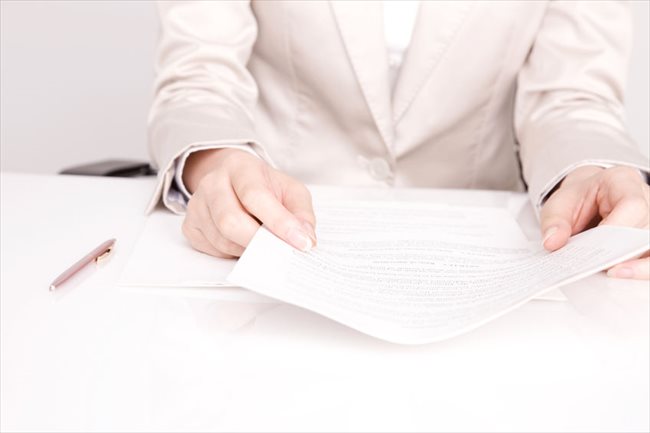
さて、助成金の種類と申請についても見ておきましょう。
基本的な分類
制度助成
制度助成とは、社内の雇用環境や労働環境を向上させるための制度を導入したり、制度を導入するための設備投資をしたりすることでもらえる助成金です。
実施型助成
実施型助成とは、制度を実施することでもらえる助成金であり、単発ではなく実施するたびにもらうことができます。
例えば、ある制度を会社が導入します。
実際に1人の社員がその制度を利用すれば10万円が交付され、2人目以降は10人目まで5万円が交付されるというような仕組みになっています。

CFイエロー
ちなみに、交付される回数には上限があるため、永遠に交付され続けるわけではないわ。
目標達成型助成
目標達成型助成とは、目標の達成に伴って交付される助成金です。
会社が目標を設定し、そのために色々な経費を支払い、目標が徐々に達成されていくと、達成率に応じて助成金が支給されていきます。
達成率が上がるにつれて助成金の支給額も増えていき、達成すれば満額受給となります。
ただし、最終的に達成に至らなければ半額しか助成されないこともあります。
起業時にはこの助成金を

上記の通り、最近のトレンドとして、起業に際しての助成金は行われにくくなりつつあります。
しかしそれでも、起業の際に利用できる助成金もあります。
特に、起業間もないころに活用できる助成金が充実しています。
トライアル雇用奨励金
トライアル雇用とは、ハローワークの求人などでよく目にするものです。
経験や知識、技能などの面から就職が難しい人を、職業安定所などを通して、一定期間だけ試験的に雇用することを言います。
トライアル雇用奨励金は、このようなトライアル雇用に対して支給されます。
特定就職困難者雇用開発助成金
いわゆる障碍者雇用や高齢者雇用にともなう助成金がこれに当ります。
このような就職が困難な人をハローワークなどの紹介によって雇用した場合に支給されます。

CFブルー
ちなみに、ここでの高齢者は60歳以上65歳未満を指しているよ!

CFレッド
障碍者は重度障碍者とその他の障碍者で支給額が異なるのだ。
キャリアアップ助成金
これは、有期契約労働者に対して職業訓練を行った場合に支給されます。
地域雇用開発奨励金
これは、雇用が特に足りていない地域で雇用を増やすために、その地域の人を雇用した場合に支給されます。
以上のような助成金を受けることで、起業時の人材獲得に役立つ可能性があります。
助成金申請の際の注意点

助成金を受けるためには、当然ながら申請する必要があります。
上記の通り、補助金に比べれば随分を受給しやすいものですが、それでも簡単なものではありません。
再確認になりますが、助成金をもらうためには、そのための要件を満たす必要があります。
したがって、申請のために書類を揃えるだけでいいから簡単というわけにはいきません・

CFイエロー
そもそも要件を満たすことが簡単ではないといえるよ!
いくら書類を揃えたといっても、要件を満たしていなければ受給することはできないのです。
また、制度の導入や新規雇用の助成金は、事後報告で助成金をもらうというものではないのです。
事前に計画書などを提出し、認定を受け、それから取り掛かることで初めて受給資格が発生するものです。
申請前に着手して報告したり、新規雇用後に報告したりすると申請できず、したがって受給もできないことに注意しておいてください。
このほか、必要になる書類や申請の手順は画一的なものではなく、申請を希望する助成金によって異なるということにも注意が必要です。
さらに、受給要件を満たし、申請の手順を守って書類を揃えることの他に、労務管理が行われていることが前提条件となっているので、この基本を漏れなく押さえておくことも重要です。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

補助金の種類と申請

次に、補助金の種類や申請の際の注意点を見ていきましょう。
代表的な補助金
3000種類以上もあるといわれる補助金ですから、その代表的なものを紹介するにとどめます。
創業促進補助金
第二創業を含む創業を行う際、個人・法人を問わずに経費の一部を補助するものです。
創業費用の一部として
- 店舗などの借入費
- 人件費
- 設備費
- 原材料費
- 市場調査費
- 宣伝広告費
などとして利用可能な補助金であり、創業促進効果があります。
申請のためには、事業計画書その他の書類を揃える必要があります。
認定支援機関が作成した書類も揃えます。
ものづくり補助金
その名の通り、ものづくりのための補助金であり、新たな製品・サービス・技術に関する新事業を創出することが目的です。
革新的な開発を手掛ける中小企業に対して交付されます。
補助金交付の流れ
補助金が交付されるまでの一般的な流れは、以下の通りです。
- 補助金の申請期間に、必要書類を地域の事務局に提出する。
- 書類や面接を通して審査を受け、補助金の交付が決定すれば、交付申請書を事務局に提出する。
- 申請した事業を始める。事務局に対して、定期的に進捗状況の報告書を提出し、中間審査を受ける。
- あらかじめ設定した事業完了期限までに、補助金事業の実績報告書を提出する。
- 実績報告書をもとに最終審査を行い、それにもとづいて補助金額を算出し、補助金を交付する。
このように、助成金は申請の流れがまちまちであるのに対し、補助金はある程度固定されているのが特徴と言えます。
助成金・補助金と詐欺

ここまで読んで、助成金・補助金の申請を前向きに考えている人も多いのではないかと思います。
資金繰りに困っている会社は、時には高金利でノンバンクから借り入れることもあるくらいですから、返済不要の助成金や補助金は喉から手が出るほど欲しいことでしょう。
しかし、助成金や補助金に関する詐欺事件が後を絶ちません。
これは、会社側が制度を利用して詐欺をするケースもあれば、悪質業者がこの制度を利用して会社を騙すケースもあります。
会社による詐欺
まず前者の場合を考えていきます。
例えば、雇用調整にあたってもらえる助成金がありますが、これは会社の業績が低下した場合などに、従業員を解雇するのではなく、休業させて休業手当を支払うことによって、国から助成金がもらえるというものです。
ある会社は、この制度を利用して助成金を受け取っていたのですが、申請していた「休業している従業員」というのが架空の従業員であったことが発覚しました。

CFブルー
架空の従業員を利用した助成金詐欺は、しばしばみられるよ。
キャリアアップ助成金などでも、架空の従業員の教育を行ったとして助成金を受け取り、詐欺が発覚したケースがあります。
雇用関係の助成金は、要件を満たせば問題なく交付されることが多いため、このような詐欺がしばしば起こります。
しかし実際には、会社が申請通りにやっているかどうかを必ず調査するため、実態を伴っていなければ間違いなくバレてしまいます。
例えば、キャリアアップ助成金を申請した会社は、職業訓練計画を作成して提出しています。
この計画に記載されている日時には、本当に職業訓練が行われているかどうかを、ハローワークの職員が調査します。
調査の結果、申請内容に虚偽があった場合はもちろんのこと、要件が一つでも欠けていれば助成金は支給されず、既に交付された助成金は回収されることになります。

CFイエロー
悪意のないうっかりミスで要件を満たせなかった場合にも、助成金の交付停止と回収が行われるよ!
また、申請に虚偽があったり、故意に要件を満たしていないなど悪意が見られた場合には、ブラックリストに載ります。
その後は助成金を受けられることができなくなります。
ブラックリストに載る期間は3年間とされています。
悪質な業者

CFブルー
次に、悪質業者によって、会社に対して仕掛けられる詐欺を見ていこう。
助成金による資金調達を支援している社労士や税理士は多く、そのような専門家を利用すれば大きな問題はありません。
むしろ、専門知識のない経営者や社員が独力で申請するのも難しいですから、支援を受けるべきでしょう。
しかし、悪質業者が助成金受給を支援するとし、会社に詐欺的行為を働くことがあるので注意が必要です。
悪質業者は、助成金の返済義務がないことやリスクがないことなどを前面に押し出し、助成金が経営に与える影響を過大に評価します。
会社が業者を利用して申請するように促してくるのです。
その業者に依頼して申請し、実際に助成金がもらえることも多いです。
しかし、その業者は税理士や社労士に依頼するよりもずっと高い、法外な手数料を求めてくることがあります。
また、申請は確かに通ったものの、申請した計画が達成困難なものであり、結局は遂行できずに助成金を得られなかったり、ペナルティを与えられたりすることになるケースも見られます。
助成金の申請を専門家に依頼するのは、大切なことです。

CFレッド
しかし、このような専門家を騙る悪質業者に騙されないように注意が必要だ!
まとめ
助成金や補助金は、返済不能の資金であり、それをもらうことで資金繰りに役立てることができます。
しかしそれ以上に、助成金の要件を満たして取り組んでいくことによって、会社は成長力を得られます。
補助金をもらうことで、会社の事業の将来性を国に認められることなど、お金をもらえる以上のメリットがある方法であるといえます。
融資や出資などといった方法と比べるならば、資金調達としての効果は大きくはないでしょう。
しかし、資金調達以外のメリットにも目を向け、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。