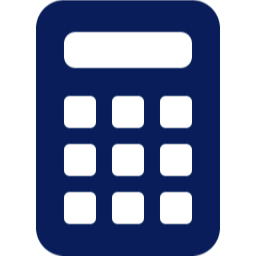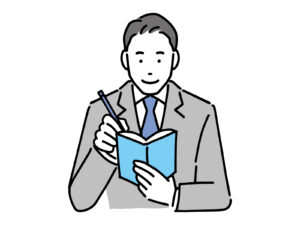ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
弁護士に相談するだけでは不十分なことも

破産をすすめる背景とその理由
破産を検討している経営者の多くは、まず弁護士に相談します。
しかし、場合によって弁護士へすぐに相談するのは避けた方がいいケースもあります。
破産手続きは弁護士にとっても比較的手間が少なく、報酬が見込める案件であるため弁護士は安易に破産を勧めるという声も聞かれます。
破産以外の支援先を探すべき理由
民事再生や私的整理といった破産以外の手続きは時間も労力もかかるため、積極的に取り組まない専門家も存在します。
そのため、破産を回避したいと考える場合は、再建支援を得意とする専門家や経営コンサルタントの協力を得ることが望ましいでしょう。
返済不能でも即破産とは限らない

期限の利益喪失とその影響
銀行からの借入返済が困難になったとしても、即座に破産に至るわけではありません。
返済の遅延があれば「期限の利益喪失」となり、一括返済を求められる可能性はありますが、すぐに差し押さえが行われるわけではないのです。
信用保証協会との交渉
信用保証協会付きの融資であれば、代位弁済により銀行からの追及は止まります。
代わりに、保証協会が債権回収に動くことになりますが、保証協会は元金の返済を優先し、誠実な対応をすれば利息の免除など柔軟な措置をとってくれる場合もあります。
返済可能な金額を提示し、計画的な返済を申し出ることで、破産を避けられる可能性は十分にあります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングという選択肢も検討してみて

ファクタリングの仕組みと利点
近年注目を集めている資金調達手段のひとつに「ファクタリング」があります。
これは、保有している売掛金(未回収の請求書)をファクタリング会社に売却し、即時に現金化する方法です。

借入とは異なり、信用情報に影響を与えず、返済義務も生じません。
売掛金さえあれば利用できるため、金融機関からの融資が難しい企業にとって、非常に有効な資金調達手段となります。
特に、売上は立っているが入金までに時間がかかる業態や、資金ショートが一時的な場合には、ファクタリングの活用によって事業を継続できる可能性が広がります。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
サービサーへの債権譲渡とその対応
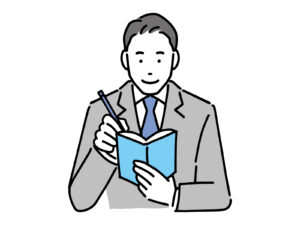
債権譲渡後の現実的な交渉
保証協会や銀行が回収不能と判断した債権は、最終的に債権回収専門会社(サービサー)に譲渡されることがあります。サービサーは債権を割安で購入しているため、返済額の大幅な減額に応じるケースも多くあります。
例えば、担保がない無保証の債権であれば、額面の10分の1以下の返済で和解が成立する場合もあります。これにより、経営者は法的手続きによらずに債務整理が可能になるケースもあります。
このように、破産せずに債務を整理し、事業再建や生活再建を目指す選択肢は存在します。
破産の影響とリスク
自己破産は、全ての借金が免除される一方で、資産の全てを失い、社会的信用を大きく失うことになります。
信用情報に履歴が残り、一定年数はクレジットカードの作成やローン手続きが非常に困難になります。
また、取引先や関係者に多大な迷惑をかけることにもなり、築き上げた信用を失う可能性大きいでしょう。
そのため、破産を選択する場合は、再起可能な業種で新たな収入の道があるかどうかを慎重に見極める必要があります。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
経営が厳しくなったとき、破産は決して唯一の選択肢ではありません。
弁護士に相談する前に、ファクタリングやリスケジュール、保証協会との交渉など、他にも多くの打開策が存在します。
事業再建の余地が少しでもあるならば、破産にかかるコストを事業継続に投じ、もう一度立て直す道を探る価値があります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

「破産しかない」と思う前に!ファクタリングなどで資金繰り改善で破産回避する方法まとめ