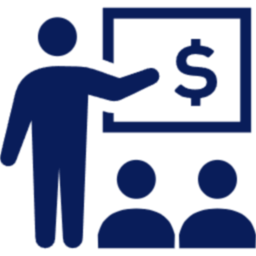ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
通帳をわけて管理する

「すでに個人のお金と会社のお金を混同してしまっている」
「今後そうならないために対策をしておきたい」
このような場合におすすめなのは「通帳をわけること(=通帳を帳簿代わりにする)」です!
大変簡単な方法ですので、簿記の知識がない人にもおすすめです。
まずは、個人の口座と会社の口座を明確にわけ、個人と会社の支払いが混同しない体制を作ります。
その後、会社用に通帳を二つ持ち、一つを入金用、もう一つを支払用として使うようにします。
入金用口座・通帳の使い方
入金用の口座を作り、入金用通帳を作れば、これが「売上帳」となります。
この時に使う銀行口座は、事業形態にあわせて選びましょう。
会社の規模が大きくなれば、取引先が振り込みやすいように、支店が多い都市銀行の口座を入金口座にするのが良いでしょう。
会社の規模が小さいうちは都市銀行である必要はありません。
特定の地域に限って事業を展開するならば、地方銀行の方が便利ということもあります。
売上金を取引先や顧客から直接振り込んでもらう場合には、入金用口座を指定します。
そうすることで、銀行が記帳してくれた通帳が、そのまま売上帳となる仕組みです。
【ポイント】
現金で売上金を受け取った場合は、定期的に入金用口座に預けて記帳をしてください。
売上金が反映されるまでほかの売上金には手を付けない
売上金がまだ入金されていない段階で、何らかの支払いを売上金の中から支払ってしまうケースがあります。
これをやってしまうとルールが崩れ、どんぶり勘定への一歩を踏み出してしまいます。
入金用通帳を売上帳にするためには、入金用通帳に売上高がしっかり反映されなければ意味がありません。
このルールさえ厳密に守れば、簿記の知識がなくとも、売上帳に代わるものができあがります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
支払用口座・通帳の使い方
次に作るのが、支払用の口座です。
可能な支払いは全てこの口座を通して行うことで、支払いを記録していくことが目的です。
会社が支払っているもののなかには、口座引き落としにできるものがたくさんあります。
事務所家賃、車場代、インターネット料金、光熱費、電話代、リース料、税など、さまざまな支払いを口座引き落としにしましょう。
各種支払いを口座引き落としに切り替えれば、この通帳が帳簿に早変わりします。
自宅で仕事をしている場合の支払い管理
起業したばかりの会社や業種によっては、自宅で仕事をしている人も多いでしょう。
そのような場合、家賃や水道光熱費などの料金は個人と会社で共有している状態になります。
ここで、個人が負担するべき費用を会社負担にしてしまうと、どんぶり勘定の始まりになってしまいますから、厳密にわけるべきです。
一部支払いはインターネットバンキング
なお、一部には口座引き落としができない費用もあるかと思います。
その際は、自宅から振込できるインターネットバンキングの利用がおすすめです。
自宅から手が空いたタイミングで、PCやスマホで簡単に振込ができます。
さらに、インターネットバンキングを利用していれば、口座データと会計ソフトを連動させ、会計処理の手間を省けるサービスもあります。
人手の足りない小さな会社だからこそ、支払用口座を作って会計処理を簡素化するといいでしょう。
資金管理は可視化が重要
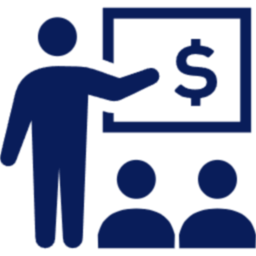
厳密に資金管理をしておけば、売上がいくらあって、支払いがいくらあるかが可視化されます。
売上の変化も見えますし、経費の変化も見ることができます。
売上が下がっていれば対策を練ることもできますし、経費が増えていればコスト削減の努力をすることもできます。
会社と個人の支払いが混同されているどんぶり勘定では、このようなことは不可能です。
売上は感覚的に把握できるかもしれませんが、正確な経費はわかりません。
その結果、コスト意識が生まれず、経費削減の努力などもできず、会社の現金を無駄に流出させ続け、いずれお金が不足することになるのです。
【応用編】資金管理に慣れてきたら……
この方法は結果を記帳するにすぎません。
さらに、数ヶ月先の資金繰り予定表も作り、資金繰り予定と実際の資金繰りの乖離を分析して資金繰りに工夫を加えていくのが良いでしょう。
その場合にも通帳を帳簿代わりにして記録を取っておけば、資金繰り予測を立てる際の参考になります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
財布を分けて管理する

入金用口座と支払用口座に分けて管理しておくと、お金の流れが非常にわかりやすくなります。
しかし、口座をわけて管理していくにも限界があります。
たとえば、コンビニでちょっとした会社用の買い物をする場合などです。
この例のように、どうしてもさまざまなタイミングで小口の現金支払いが発生してしまうことがあります。
このような小口現金払いで、個人と会社の支払いを混同させない方法として「財布を2つもつ方法」があります。
やり方はシンプルで、「個人用の財布」と「会社用の財布」をわけてもつだけでOKです。
あとは支払いごとに、会社の支払いは会社用財布から、プライベートな支払いは個人用財布からと使い分けをするだけです。
そして、定期的にたまった領収書の合計金額を預金通帳から引き出し、内訳を記録しておきます。
【注意】
内訳記録時の注意点は、使う額を概算して事前にお金を引き出したり、使った後に大体の金額を引き出したりしないことです。
※9999円の支払いでも、10000円を引き出すのではなく9999円を正確に引き出してください。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
法人カードで管理する

財布を2つに分けて持つという方法は、領収書の保管や資金管理で若干の手間が発生します。
とにかく手間をなくして、簡単に個人と法人の支払いをわけたい方におすすめなのが「法人クレジットカード」の使用です。
クレジットカードには、個人向けと法人向けの2種類があり、法人向けはおもに個人事業主や会社経営者を対象に発行されています。
法人カードを発行し、口座引き落としができないものを中心にカード決済を利用していきましょう。
法人カードと聞くと審査ハードルが高いように感じますが、実は「決算書類不要」、「必要書類は本人確認書類のみ」で申し込めるカードも多くあります。
会社の決算書類が不要なカードなら、立ち上げ直後の会社でも申込可能です!
法人クレジットカードの細かい仕組みやおすすめカードについては、「法人カード調査部」をご覧ください。
▼おすすめ法人カード一覧
法人カードを作れない場合は個人カードを2枚使う

上記の通り、法人カードの審査は必要書類も難易度も個人カードと大きくは変わりません。
ただ、何かしらの事情で審査に通内ことも考えられます。
そういった際は、個人カードを2枚用意し、1枚を法人用カードの代わりにしてください。
この方法を使うことで、下記2つのメリットが得られます。
▼個人用カードを2枚使うメリット
- 口座引き落としにできない支払いをカードに集約できる
- 利用明細書を資金管理に役立てられる
なお、個人カードの引落としは個人口座からしかできません。
せっかく作った法人用口座は使えませんが、片方のカードを完全に法人決済用としておけば支払いが混ざることもなく問題なく使えます。
【注意】
「この方法で税務上問題ないの?」という最終確認は、最寄りの税務署や税理士さんに確認するようお願いします!
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」

まとめ:どんぶり勘定はやめましょう
個人と会社のお金を混同しないためには、個人と会社のお金を明確にわけて運用していくことが大切です。
銀行口座を個人と会社でわけ、財布やカードも個人と会社でわけ、個人的なお金と完全に切り離しておくようにしましょう。
このように管理すると、銀行の記帳やクレジットカード会社の明細表からお金の流れを把握することができ、コスト意識が高まるというメリットもあります。
どんぶり勘定に陥らないためにも、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼ ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
 ▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼