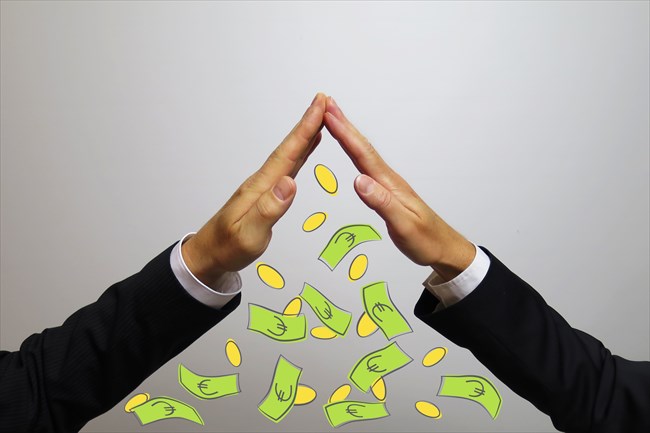ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
売掛債権流動化を円滑に行うための要件

売掛債権流動化を円滑に行うためには、企業側にも備えておくべき要件があります。
売掛債権のデータ管理
まず、売掛先の企業データをはじめとした売掛債権のデータがきちんと管理されていなければ、話になりません。
売掛債権流動化は、どの方法を利用するにしても、対象となる売掛債権の信用力に依存した方法となります。

CFレッド
売掛債権の譲渡を受ける側としては、その売掛債権の信用力がどれほどのものかわからなければ、取引のしようがないのだ。
したがって、売掛先の企業データ、決済期日、決済金額など、売掛債権に関するデータをきちんと管理しておかなければ、売掛債権流動化は円滑に進まず、資金調達が難航してしまいます。
このほか、このようなデータが管理されていない状態では、売掛債権流動化を行うことによって、自社がどの程度の恩恵を受けられるのかさえも把握できないでしょう。
対抗要件の具備
次に、対抗要件の具備です。対抗要件とは、権利関係を第三者に主張するための法律要件です。
つまり、その売掛債権を譲渡するにあたって、どのような契約になっているかを証拠づけるものです。
特にファクタリングなどに言えることですが、売掛債権を譲渡したとき、売掛債権に関するリスクを切り離せるというメリットもあります。

CFイエロー
このメリットを損なわないためにも、対抗要件の具備は欠かすことができないわよ。
対抗要件を具備するためには、それなりの手間がかかります。
売掛先に承諾を得る必要がありますし、売掛先に通知を送ったり、法務局で登記を行ったりしなければなりません。
この際にも売掛債権のデータが管理できていなければ円滑に進みませんから、やはり売掛債権の管理は大切なことです。
売掛先への代金振込みの要求
最後に、売掛先に対して、支払期日には譲受先が指定する口座に代金を振り込むよう求めることです。
これは、以下で解説するコミングリングリスクを低減させるためのものです。
ただし、売掛先としては、支払い口座を変更するのは面倒なことであり、拒否されることも考えられます。
そのような場合には、すでに振込先となっている自社の口座を債権流動化専用口座とするなどの対策が考えられます。

CFレッド
以上の要件を満たすことによって、売掛債権の流動化が円滑になるぞ!
それでこそ、初めてスピーディな資金調達も可能となります。
これらの要件を満たすにあたっては自社の経営資源をいくらか割くことになるため、費用対効果を考えながら、売掛債権流動化を行うかどうかを検討しなければなりません。
売掛債権とリスク
売掛債権流動化にあたって、売掛債権に潜むリスクを把握しておく必要があります。
そのリスクとは、主に以下の五つです。
デフォルトリスク
これは、売掛先が倒産したり、資金繰りに行き詰るなどして代金が回収できなくなるリスクです。
フロードリスク
これは、不正取引リスクとも言われるものです。
実在しない債権や、実在していてもすでに第三者に譲渡された債権を流動化に利用し、代金が回収できなくなるリスクです。
ダイリューションリスク
これは、希薄化リスクともいわれるものです。売掛先が商品を返品などすることによって、売掛債権が消滅したり、当初より額面金額が減少するリスクです。
コントラリスク
これも、売掛債権の額面金額が減少するリスクですが、ダイリューションリスクとは異なり、企業が所有する債権と売掛先が所有する債権を相殺することによって、額面金額が減少するものです。
そのため、これを相殺リスクと言うこともあります。
企業が債務不履行に陥った場合、債務者対抗要件を具備していないと生じるものです。
コミングリングリスク
これは、混在リスクとも呼ばれるものです。
一般的に、売掛債権を譲渡した場合には、売掛先は債務者に対してではなく、譲受先の口座に直接代金を支払うことになります。
しかし、あえて二社間ファクタリングを採用していたり、売掛先が支払口座の変更を拒否した場合には、債権者の口座を経由して譲受先に支払われることがあります。

CFブルー
口座の管理がしっかりしていなければ、支払われた代金と他の資金が混在することになるのだ。

CFイエロー
資金の流れが把握できなくなってしまい、売掛先から支払われた代金を、譲受先に振り込まずに他の目的に流用してしまうことがあるのよ。
これがコミングリングリスクです。
特に、企業が経営難に陥っているとき、意図的に流用したり、混乱して流用してしまうことがあります。
このようなリスクを避けるために、譲受先は売掛債権の信用力を重視するものの、いくらかは債権者の信用力を調査することになります。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
売掛債権証券化の流れ

では、ここからは具体的に、売掛債権流動化の方法について説明していきましょう。
売掛債権証券化は、売掛債権の支払期日に支払われる代金を裏づけとして、売掛債権を証券化して資金調達を行うことです。
流れは、以下のとおりです。
- 企業から売掛先へ商品が販売され、売掛債権が発生する。
- 企業は売掛債権をSPVと呼ばれる事業体に譲渡する。
- SPVは売掛債権の信用力を元に証券を発行し、投資家に販売する。
- 投資家から得られた証券購入代金のうち、契約に基づいてSPVから企業に資金が提供される。
SPVとは?

CF戦隊
SPVというのは、Special Purpose Vehicleの略であり、特定目的事業体と訳されるもの。

CFイエロー
売掛債権などの資産を企業から譲渡され、証券などを発行する事業体全般を指してSPVというのよ。
なぜ売掛債権証券化にあたってSPVが介在するのかといえば、売掛債権証券化にあたっては、売掛債権を保有する企業から売掛債権を分離し、保有企業が倒産した場合のリスクを切り離す必要があるからです。
このことは、SPV側から見ると同時に、売掛債権の保有企業の立場から見てみると、よりいっそうよくわかります。
売掛債権流動化を行わない場合や、企業がSPVを介在させずに証券化し、投資家に販売する場合を考えて見ましょう。
このとき、売掛先が倒産したらどうなるでしょうか。

CFブルー
企業は売掛債権を自ら買い戻す必要が生じるため、リスクを負うことになるのだ。

CFレッド
しかし、SPVが介在することによって、売掛債権は企業からSPVに譲渡されており、企業は倒産の場合にも買い戻す必要はなくなるよ!

CFイエロー
売掛債権のリスクは、すでに自社から移転されているからよ。
また、売掛債権の保有企業が自社で証券化を行い、投資家に販売した場合に、その企業が倒産したらどうなるでしょうか。
売掛債権は債権回収の対象となり、債務者の差し押さえの対象となります。当然、投資家に対して証券の支払いもすることができなくなります。

CFブルー
しかし、SPVに譲渡されていれば、企業が倒産した場合にも差し押さえの対象とはならないのだ。
投資家が被害をこうむることもなくなります。SPVには以上のような意義があるのです。
売掛債権証券化のメリットとコスト
![AdobeStock_121795613-[更新済み]](https://factoring.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/e5dc558c183d40201380f811dd73b1e5.jpg)
売掛債権証券化は、売掛債権流動化の方法の中では、それほどメジャーなものではありません。
2000年度末時点で、日本企業は焼く191兆円の売掛債権を保有していましたが、そのうち証券化に利用されたのはわずか3.3兆円であり、割合にして全体の1.7%に過ぎません。

CFイエロー
資金調達において、売掛債権証券化はまだそれほど活用されているとはいえないわ。
ちなみに、売掛債権流動化は欧米では大いに活用されているものであり、売掛債権証券化においても2002年度末時点のアメリカでは、全体の31%に相当する33.5兆円の売掛債権が証券化に活用されています。
売掛債権証券化のメリット
売掛債権証券化を実施すると、企業にはさまざまなメリットがあります。
売掛債権証券化の実施にあたって、以下の3つのステップを踏むことになります。
1、 資産の特定
証券化では、売掛債権を投資家に対して販売することから、まずは企業全体のリスクから売掛債権のリスクを抽出します。
2、 売掛債権の分離
次に、企業から売掛債権の分離を行います。
このことによって、企業が倒産した場合のリスクを売掛債権から切り離すことができます。
3、 売掛債権の売却
最後に、売掛債権を証券として投資家に売却します。

CFイエロー
このとき、投資家に対しては売掛債権そのものを売却するのではなく、証券という金融商品の形で販売することになるの。

CFブルー
そのため、リスクに応じて異なる金融商品として販売することが可能となるよ!
例えば、リスクの高い売掛債権は証券Aとして、リスクが中程度の売掛債権は証券Bとして、リスクが低い売掛債権は証券Cとして販売することができるということであり、売掛債権のリスクをコントロールしながら運用が可能となります。

CFレッド
このように証券化した結果、企業は資金調達の多様化、オフバランス化などのメリットを享受できるようになるのだ。
売掛債権を証券化することによって、手形割引や融資などと比較して良い条件で資金化できることもあり、新たな資金調達のソリューションになりえます。
オフバランス化も見逃せないメリットです。

CF戦隊
これは、貸借対照表の資産の部を可能な範囲で簡素化し、経営効率を高め、企業価値を高めることだ!
このほか、売掛債権のリスクをSPVに移転することができることもあります(SPVとの契約によって、売掛債権のリスク移転は限定的になることもあります)。

CFイエロー
このほか、売掛債権の売却が容易になるメリットもあるわ。
これは、ファクタリングのように売掛債権をそのまま売却するのではなく、証券という金融商品として資金化することによって、流動性が高くなるからです。
さらに、リスクコントロールの過程で複数の金融商品として販売することによって、投資家によって適正な価値での買い取りが見込めます。
売掛債権証券化にかかるコスト

売掛債権証券化には、どれくらいのコストがかかるのでしょうか。
売掛債権証券化にあたっては、SPVに支払う手数料のほか、自社で行う事務手続きにコストがかかります。
売掛債権証券化におけるSPVに支払うコストは、信託配当(投資家に支払う配当)、信託報酬(信託財産を管理する費用)、その他手数料から成り立っています。

CFブルー
信託報酬は、対象となる売掛債権の信用力、そして証券化の金額・期間・頻度で決まるよ。
売掛債権の信用力が高いほど、また証券化の金額が大きく、証券として流通する期間が長く、証券化の頻度が少ないほど低利で資金調達が可能となるのが一般的です。

CFイエロー
その他手数料とは、例えば確定日付料や手形取立手数料などよ。
これに加えて、自社での手続きや管理に伴ってかかるコストも考えておかなければなりません。

CFレッド
具体的には、売掛債権の管理や対抗要件の具備にコストがかかるのだ。
証券化を円滑に進めるためには売掛先と売掛債権に関するデータ管理が必要となりますし、対抗要件の具備にも時間・労働力・金といった経営資源を割かなければなりません。
これが、売掛債権証券化にかかるコストです。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
売掛債権担保融資とは

次に、売掛債権担保融資についてみていきましょう。
売掛債権担保融資とは、企業が保有している売掛債権を担保として差し出すことによって、金融機関から融資を受ける資金調達法です。
売掛債権担保融資も、資金調達の新たな方法として知っておくことは、大いにメリットとなることでしょう。

CFレッド
決済期日前の売掛債権を担保として資金調達ができるため、回収までの期間が長い売掛債権を活用したいときに有効だ。
売掛債権を担保として融資を受ける取引自体は、昔からある方法でした。
しかし、2001年12月に信用保証協会が売掛債権担保融資保証制度を創設したことで、現在の売掛債権担保融資となりました。

CFイエロー
売掛債権を担保として融資を受けた企業が、万が一返済ができなくなったときに役立つのよ!

CFブルー
信用保証協会が借入残高の90%を金融機関に弁済するのが売掛債権担保融資保証制度だ!

CFレッド
そして、信用保証協会と金融機関が担保となった売掛債権から回収を行うのである!
この制度は2001年12月から運用が開始され、2003年5月末には融資件数にして約8200件、約3000億円の融資が行われました。
売掛債権担保融資保証制度によって、従来に比べて売掛債権担保融資が利用しやすくなりました。
ただし、現時点では手続きがわずらわしいとする声もあります。
売掛債権担保融資保証制度の枠組み

売掛債権担保融資保証制度には、個別保証と根保証の二つのタイプがあります。
個別保証

CFレッド
個別保証は、借入のつどに信用保証協会の保証手続きを経るものだ!

CFレッド
借り入れの際には売掛債権の信用力が評価され、掛け目によって担保価値が決まるよ!

CFレッド
担保価値を上限として融資額を決定していくのが個別保証!
個別保証には、大口の売掛債権や回収までの期間が長い売掛債権が適しています。
例えば、建設業者は少ない取引先に多額の売掛債権を保有していることが多く、プロジェクトごとに単発で大口の売掛債権が発生します。
また、回収期間が長いのが問題となっています。
このような売掛債権を早期に資金化するためには、個別保証が適しているのです。
根保証

CFイエロー
根保証とは、あらかじめ一定の借入限度額について信用保証協会の保証を受けられるの!

CFイエロー
一年間にわたって借入限度額の範囲内で借り入れを行うものよ。
例えば、企業の状況に応じて1億円を上限として借入限度額が決まったとします。
企業は将来的に発生する売掛債権も含めて売掛債権を担保として譲渡し、1億円の範囲内で一年間にわたって、反復して借り入れを行います。

CFブルー
根保証においても、借入限度額は売掛債権の信用力に応じ、掛け目によって決まるのだ!

CFイエロー
いったん借入限度額が決まれば、その中で繰り返し融資を受けることができるよ。

CFレッド
回収期間が比較的短く一定の水準の売掛債権が継続的に発生する、安定した企業に向いているぞ!
このような企業では、将来的にも安定的に売掛債権が発生することが見込めるため、将来の売掛債権も担保として譲渡することができるのです。
また、借入限度額が定まれば、その後一年間は新規申し込みの必要がなくなるのも魅力です。
売掛債権担保融資の流れ

売掛債権担保融資の流れを解説していきます。
流れは以下のとおりです。
- 企業から売掛先に商品が販売され、売掛債権が発生する。
- その売掛債権を担保として融資を受ける場合、まず金融機関に融資の申し込みを行う。このとき、手続きに必要な書類として、商業登記簿、決算書、売掛先と取引関係があることと対象となる売掛債権を確認できる資料(対象となる売掛債権の明細書、取引基本契約書、発注書、請求書、支払通知書など)を提出する。
- 金融機関は融資の審査を行う。融資可能となれば金融機関が信用保証協会に保証を申し込む。
- 信用保証協会が保証可能と判断すると、信用保証書が金融機関に発行される。
- 融資を申し込んだ企業は、金融機関とともに借り入れ準備を行う。このとき、債権譲渡禁止特約の解除など対抗要件を具備する際には、売掛先との交渉が必要となる。
- 対抗要件を具備すると、売掛先に対して振込口座の指定を行う。特に根保証の場合には、融資を申し込んだ企業の名義で返済専用口座を開設する必要があり、この口座は融資返済以外の目的では利用できない。
- 金融機関と企業の間で融資関係契約書が締結されると、借り入れを受けることができる。

CFイエロー
流れの2からもわかるとおり、売掛債権担保融資はあくまでも銀行からの融資よ。

CFイエロー
そのため、通常の融資に必要な書類を提出しなければならず、それに加えて売掛債権のデータも提出することになるの。
根保証の場合には、将来的に発生する見込みの売掛債権も対象となるため、売掛先との取引を確認するための書類も必要になり、一年以上にわたって取引があることを証明しなければなりません。
以上のように、売掛債権担保融資保証制度は、通常の融資と売掛債権譲渡の二つの側面を持っており、権利関係の当事者が多くなります。
それだけに、手続きが煩雑になるとする見方も多く、間接コストが高くつく傾向があります。
売掛債権担保融資とリスク

売掛債権担保融資保証制度では、まず担保をする売掛債権を決定した段階で、売掛債権の評価を行います。
対象となる売掛債権の信用力を元に評価を行い、掛け目を決めていきます。
一般的な掛け目は、官公庁や一部上場企業ならば90%、その他上場企業は80%、一般の中小企業は50~70%といったところです。

CFブルー
信用格付けが高い売掛債権であれば掛け目は高くなるし、対抗要件が売掛先の承諾として具備されている場合にも高くなるのだ。

CFレッド
逆に、信用格付けが低い売掛債権や、対抗要件が登記としてしか具備されていない場合には、掛け目は低くなるぞ。
掛け目によって売掛債権の担保価値が決まると、企業が必要とする資金量や返済能力、経営計画などから判断し、担保価値を上限として融資額が決まります。
このことから、融資額を決める段階では、企業のリスクが評価されているといえます。

CFレッド
根保証の場合にも、売掛債権の信用力で掛け目が決まるという点では変わりない。
借入限度額の設定においても、企業が必要とする資金量、返済能力、経営計画などが反映されます。

CFブルー
以上からわかるとおり、売掛債権担保融資では、企業の信用力が借入額に影響しするのだ。
しかし基本的には、担保とする売掛債権に裏付けられて行われる融資であるため、企業の信用力が同等のA社とB社が融資を申し入れたとしても、売掛債権の質によって借入額が変わります。
これが、売掛債権担保融資と通常の融資の大きく異なる点といえるでしょう。
売掛債権担保融資にかかるコスト

売掛債権担保融資にかかるコストを見ていきましょう。
まず、直接的なコストとして、利息、信用保証料、その他費用(担保管理手数料や事務管理手数料)がかかります。
繰り返しになりますが、売掛債権担保融資はあくまでも融資です。
そのため、通常の融資と同じように、借入利息を支払わなければなりません。

CFブルー
信用保証料は、個別保証ならば借入金額の90%、根保証の場合には借入限度額の90%に対して信用保証料率を乗じて計算!
担保管理手数料や事務管理手数料は、担保の設定や融資期間における売掛債権の管理にあたって、金融機関が定めているコストのことです。
このほか、対抗要件具備のためにもコストが発生します。
また売掛債権担保融資においても、売掛債権証券化と同様に間接的にかかるコストもあります。
特に、根保証を利用する場合には、担保として売掛債権の毎月末の残高を、翌月10日までに金融機関に報告する義務があるため、自社における売掛債権管理がいっそう重要になり、コストも大きくなると考えておく必要があります。
ファクタリングとは

最後に紹介する売掛債権流動化の方法は、ファクタリングです。
ファクタリングにはいくつかの方式がありますが、基本的には買取ファクタリングと呼ばれるものです。
これは、ファクタリング会社が企業から売掛債権を買い取り、資金の調達を行うものです。

CFブルー
ファクタリングにおいても、他の売掛債権流動化と同様に、新たな資金調達法として活躍!

CFレッド
売掛債権のリスクを切り離すためにも役立ち、オフバランス化も期待できるぞ!

CFイエロー
特に、ファクタリングでは償還請求権なし(売掛先が倒産しても弁済する必要はないとするもの)で買い取るのが一般的であるため、売掛債権のリスク切り離し効果が大きいといえるわ。
また、企業がファクタリング会社に売掛債権を完全に譲渡してしまうため、企業は売掛債権の管理を行う必要がなくなり、業務の効率化を図れます。
このほか、三社間ファクタリングであれば回収業務もファクタリング会社に委託することができます。
もっとも、三社間ファクタリングを利用して資金繰りをすることによって、取引先や他企業から資金繰りが困難であることを悟られることを嫌い、売掛先を巻き込まない二社間ファクタリングを行うのがより一般的です。
ファクタリングは、欧米ではごく一般的に認知されているものであり、多くの企業が活用しています。
これに対して、日本ではまだそれほど一般的ではありません。

CFイエロー
それでも、最近は利用件数は急速に伸びており、これは、手形取引の縮小が影響しているの。
手形取引に関する業務を効率化するために手形取引自体が減少傾向にあり、売掛金や現金での決済に移行している流れがあります。
これに伴い、売掛債権を活用した資金調達が注目されるようになってきているのです。
このほか、1998年に債権譲渡特例法が施行されたことで法的基盤の整備が進んだことも、ファクタリングの利用拡大に拍車を掛けています。
ファクタリングの流れ
ファクタリングの流れを、一般的な買取ファクタリングを例としてみていきましょう。
- 企業から売掛先に商品が販売され、売掛債権が発生する。
- 企業はファクタリング会社と契約し、売掛債権を買い取ってもらい、資金を調達する。
- 売掛債権の支払期日になると、売掛先は企業に支払いを行い、それを企業はファクタリング会社にスライドさせて支払う(二社間ファクタリングの場合)

CFレッド
このように、ファクタリングは売掛債権証券化や売掛債権担保融資と比較して、簡単な流れで取引が行われているのだ。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

ファクタリングの種類
ファクタリングの枠組みとしては、買取ファクタリングと保証ファクタリングがあります。
買取ファクタリング

これは、すでに述べたとおり、売掛債権を買い取ることによって資金化を行うものです。
特に、今後利用拡大が予想されるのが一括ファクタリングです。
日本では、売掛債権を個別に譲渡する個別ファクタリングがよく利用されてきました。
しかし、近年では企業・売掛先・ファクタリング会社の三社合意の上でファクタリングを行い、売掛債権を一括でファクタリングする一括ファクタリングの利用が広まりつつあります。

CFブルー
ファクタリング会社と長期契約を結んで一括でファクタリングを行うのがおすすめ!

CFイエロー
企業は売掛債権を常に資金化し、売掛債権管理や回収業務もファクタリング会社に委託することができるのよ。
これによって、売掛債権を流動化して機動的な資金調達が可能となり、また業務の効率化・経営資源の集中が図れるというメリットがあります。
保証ファクタリング
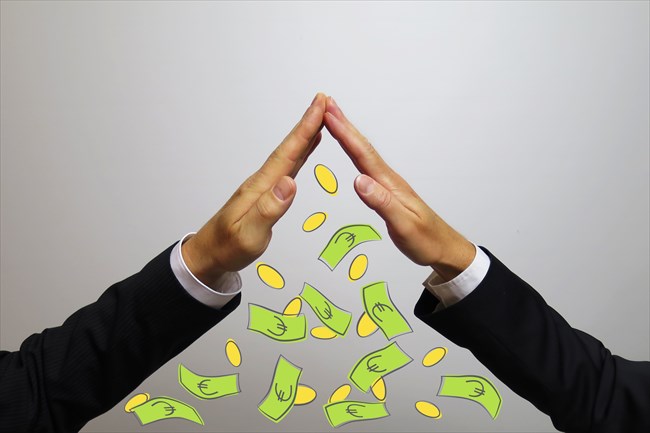
保証ファクタリングは、日本でのニーズが高まっているファクタリング方式です。
保証ファクタリングでは、企業はファクタリング会社と保証契約を結ぶことで、売掛債権の回収に関する保証を受けることができます。

CFブルー
万が一売掛先が倒産してしまい、売掛債権の回収が不可能になった場合、企業はその売掛債権をファクタリング会社に譲渡する事で保証を受けられる!
この場合、あらかじめ決められた保証の範囲内で保証金を受け取ることができるのだ!
保証ファクタリングにも、個別保証方式と根保証方式があります。
個別保証方式は、個々の売掛債権について信用力を評価して保証額を設定します。
これに対して、根保証方式では、売掛先の信用力を個別に評価し、一定期間の保証限度額を設定するものです。
根保証方式では、売掛債権を特定して保証額を設定しないという特徴があります。
ファクタリングにかかるコスト

では、ファクタリングにかかるコストを見ていきましょう。
ファクタリングでは、売掛債権の信用力が買取料に反映されます。
売掛債権の金額が大きいほど、ファクタリングに必要な費用の割合は小さくなるため、割安で資金調達が可能となります。

CFイエロー
事務手数料や振込み手数料、回収手数料などが請求されることがあるわよ。

CFブルー
ファクタリング会社によって費用体系が異なるため、きちんと把握しておくことが大切。
保証ファクタリングの場合には、売掛債権の信用力によって保証額を決めるか、売掛先の信用力によって保証限度額を決めていきます。
このときの直接コストとしては、売掛債権の額面に保証料率を掛け合わせることで算定された保証料がかかるのが一般的です。
ファクタリングを利用する際にも、売掛債権管理や対抗要件具備にあたって、自社における間接コストがかかります。
手形割引

手形割引がファクタリングの一部というわけではないのですが、類似の方法として紹介しておきます。
売掛先に販売を行った場合、約束手形が振り出されることがあります。
手形取引は減少傾向にありますが、日本の商取引文化に根付いたものであり、まだまだ手形取引を行う機会もあるでしょう。

CFイエロー
約束手形は、支払期日に手形交換によって額面金額を受け取ることができるものよ。
しかし、金融機関や手形割引業者に手形割引を申し込むことによって、支払期日前に資金化することができます。
手形も売掛債権の一種ですから、これも売掛債権流動化のひとつに数えてよいでしょう。
手形割引の際には、割引料がかかります。
一般的に割引料は銀行では安く、手形割引業者では高い傾向があります。
また、銀行では手形の買い取りではなく手形を担保とした融資と認識されるため、手形の振出人ではなく手形割引の依頼人に対して審査が行われます。
一方、手形割引業者では手形の買い取りと認識しているため、手形割引の依頼人ではなく手形の振出人に対して審査を行います。
このとき、審査の結果に応じて割引料が変動します。
まとめ
企業が資金調達を考えるとき、事業者ローン以外にもたくさんの方法があることがわかったことでしょう。
売掛債権は、一見すると支払期日までは眠っているものなのですが、売掛債権を流動化して資金調達に利用するために、いろいろな方法を利用することができるのです。
売掛債権流動化は、単に資金調達のためだけではなく、それ以外にもいろいろなメリットがあることも解説してきました。
資金調達と同時にオフバランス化、経営資源の集中、リスクの軽減などさまざまなメリットを享受することができるため、ぜひ活用していただきたいと思います。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング



























![AdobeStock_121795613-[更新済み]](https://factoring.co.jp/wp-content/uploads/2016/12/e5dc558c183d40201380f811dd73b1e5.jpg)