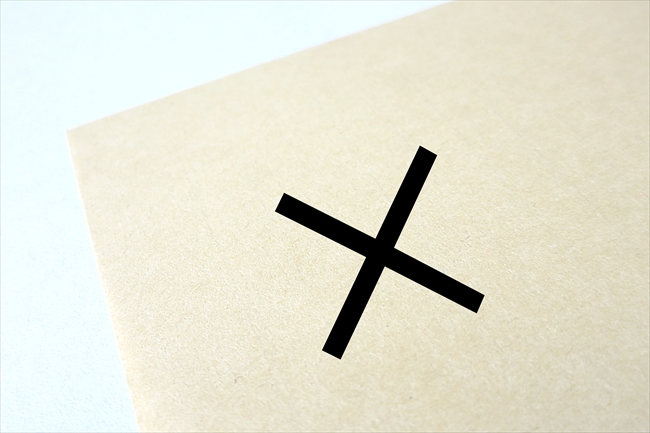つまり、書類をプリンターでスキャンすることによってパソコンに取り込み、電子的に保存するかのように、指名債権や手形を電子的に管理するものだと勘違いしている人が多いのです。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
でんさいのメリットとは?

では、でんさいにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
それは、電子記録債権と指名債権や手形を比較してみるとよくわかります。

CFイエロー
そもそも、電子記録債権とはどのような債権なのだろうか。
これは、電子債権記録機関によって管理されている債権です。
発生記録や譲渡記録は、電子債権記録機関の記録原簿に記録されることによって、初めて効力が発生するものです。
このことが、でんさいに様々なメリットをもたらしています。
指名債権との比較
例えば、従来の指名債権には、債権を譲渡しようとした時にその債権が存在しなかったり、二重譲渡されているというリスクがありました。
民法上では、指名債権の譲渡のためには「譲渡人と譲受人の合意さえあれば良い」とされています。
しかし、その債権が本当に存在するものなのか、二重譲渡されたものではないかといったことを確認する必要があるのです。
このように、手間とコストがかかっていました。
しかし、でんさいは電子記録によって債権の存在と帰属が明確化されています。

CFレッド
あらゆるごまかしが効かず、債権の不存在や二重譲渡のリスクがなくなったのだ!
また、債権を譲渡する際には、債務者に対抗するために債務者に通知する必要がありましたが、でんさいでは債務者への通知が不要です。
そもそも、なぜ債務者に通知するのかと言えば、債務者が知らない間に譲渡が行われることによって、不特定の債権者から請求を受けることを防ぐためのものです。
しかし、でんさいでは債権の存在と帰属が可視化されており、債務者も簡単に確認ができます。
通知が不要となっているのです。
このほか、従来の債権には人的抗弁を対抗されるリスクがあったのですが、でんさいでは人的抗弁は切断されているというメリットもあります。
手形との比較
次に手形ですが、手形は何と言っても紙で交付するものです。
すなわち、銀行が交付する手形の券面に必要な情報を記入して振り出すのですが、この作成と交付には相応のコストがかかりました。
しかし、でんさいは電子データの送受信によって債権が発生するため、このようなコスト負担が軽くなります。
また、手形には紙としての物理的な実態があるため、支払い期日までは保管しておく必要があります。
保管のコストがかかることのほか、紛失や盗難のリスクが常にありました。

CFイエロー
でんさいは電子データで管理されるものだから、保管のコストはかからないよ!
電子債権記録機関がきちんと管理している以上、紛失や盗難のリスクもないのだ!
そして、運用開始から現在に至るまで、でんさいが紛失や盗難による被害がにあったことは一度もないため、安全性は非常に高いと言えます。
このほか、手形は紙面に必要事項を書き込むものであり、記載できる事項が限られています。
しかし、でんさいは電子記録であり、記録できる量に限りがないため、様々なことを記録することができます。
さらに、従来の手形では分割して利用することができませんでした。
つまり、100万円の手形があったならば、そのうちの一部を譲渡したり、分割したりすることはできなかったのです。
しかし、でんさいならばそれが可能であり、制限なく分割が可能です。
そのため、債権金額のうち必要な額だけを割引し、そのほかは支払い期日まで待って満額を受け取るという利用も可能です。
でんさいには、このようなメリットがあるのです。
これらのメリットを、債務者と債権者に分けて考えると、より一層メリットが見えてきます。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
債務者のメリット

コスト削減・事務手続きの軽減
手形を発行する際には事務手続きが必要なであり、搬送代も負担になります。
しかし、でんさいを使えば手形の発行や振り込みの準備など、支払いのための事務手続きが軽減されます。
また、手形の搬送のためのコストも削減できます。
印紙税不要
手形を振り出す際には印紙を貼る必要がありますが、でんさいでは印紙が不要であるため、節税効果があります。
印紙税は取引額に応じて異なり、振り出す枚数や金額によっては負担が大きいものですが、それをゼロにできることは大きいでしょう。
業務効率化
複数の取引先で支払い方法が異なる場合、手形、振り込み、一括決済など、複数の支払いを行うのは煩雑であり、業務的にも非効率です。
これをでんさいに一本化すれば、業務が大幅に効率化します。
債権者のメリット

紛失・盗難リスク・コスト削減
手形を受け取っている場合、紛失や盗難の心配があるため、厳重に保管しなければなりません。
しかし、でんさいはペーパーレスであるため、紛失や盗難の心配がありません。
保管のためのコストも削減できます。
分割が可能
手形を受け取っている場合には、額面金額をそのままでしか利用できませんが、でんさいならば必要なだけ分割して譲渡や割引に活用することができます。
取り立て手続き不要
手形の支払いを受けるためには、銀行に呈示する必要があり、取り立て手続きが面倒です。
しかしでんさいならば、支払い期日になると自動で口座に入金されるため、取り立て手続きが不要です。
有効活用が可能
振込の場合、入金日までの資金繰りに悩まされることがあります。
しかし、でんさいは流通性の高い債権であることから、譲渡や割引に利用することが容易であり、資金調達への有効活用が可能です。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
でんさいのデメリット
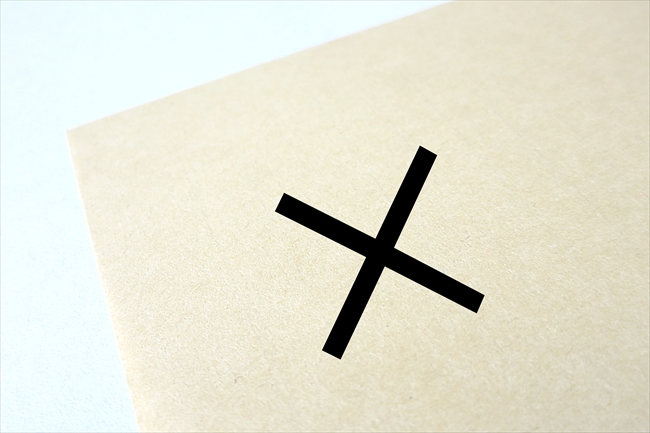
このように書けば、でんさいにはメリットばかりのようなイメージがあるかもしれません。
しかし、でんさいにもデメリットはあります。
それは、次の条件があることです。
- でんさいを利用するためには、でんさいネットに参加している金融機関に申し込みを行わなければならないこと
- 取引にでんさいを用いるためには、取引する双方の企業がでんさいを申し込んでいること
つまり、いくら自社がでんさいを使いたいと思っていても、金融機関に申し込んででんさいの利用契約を結んでいなければ、利用することはできません。
また、自社がでんさいでの取引を望んだとしても、そのためには取引先もでんさいの利用契約を結んでいなければなりません。
つまり、取引先がでんさいを利用できない場合には、でんさいでの取引を諦めるか、でんさいの利用の申し込みをするように依頼するほかないのです。
これは、でんさいを利用したいと思っても利用できないという事態を生むものですから、やはりデメリットと言わねばならないでしょう。
でんさいは利用しにくいのか?

しかし、これは必ずしもでんさいが利用しにくいものであるということではありません。
でんさいそのものは利便性が高く、特別なケースを除けばどのような会社でも利用が可能です。
窓口となる金融機関の数も非常に多いのです。
窓口となっている金融機関は、2014年末のデータで491となっております。
- 都市銀行が5
- 地方銀行が64
- 信託銀行が7
- 第二地方銀行が41
- 信用金庫が267
- 信用組合が107

CFブルー
このように、参加機関は多いのだ!
これをみれば、日本全国のあらゆる会社が、希望すればいつでも申込みが可能となっていることがわかると思います。
でんさいの利用状況
しかしながら、日本では指名債権や手形での取引が長く続いてきました。
新しい便利な技術があったとしても、それに乗り換えるためには未知のものを理解し、会計処理などもそれに応じて変更する必要があります。
このため、まだまだ普及はこれからといった状況です。
2014年10月の時点で、利用者登録数は40万社弱であり、月間発生記録請求件数は6万5000件程度です。
利用者登録数よりも月間発生記録請求件数が大幅に少ないことから、登録はしているものの利用できていない会社が非常に多いことがわかります。
これも、自社ではでんさいでの取引を希望して登録していたものの、取引先がでんさいを利用していないために、でんさいでの取引ができなかったというケースが多いためです。
都道府県別の利用状況
ちなみに、2014年10月の都道府県別の利用状況をみてみると、利用が最も多いのは東京都です。
利用状況は次の通りです。
- 利用契約件数は8万6919件
- 発生記録請求件数は1万4066件
- 発生記録請求金額は1769億4500万円
第2位は大阪府です。
- 利用契約件数は4万3574件
- 発生記録請求件数は7010件
- 発生記録請求金額は624億3600万円
第3位は愛知県です。
- 利用契約件数は2万8807件
- 発生記録請求件数は4653件
- 発生記録請求金額は362億63000万円

CFイエロー
このことから、大都市圏から徐々に普及が進んでいるということがわかりるわね!
したがって、地方ではそれほど普及が進んでいないため、でんさいを利用したいと思っても利用できないというケースも多くなると予測できます。
業種別の利用状況
続いて、同時期の業種別のデータを見てみましょう。
このデータでは、業種別に利用状況が大きく異なることがわかります。
利用が最も多いのが製造業です。
- 利用契約件数は12万5269件
- 発生記録請求件数は3万1173件
- 発生記録請求金額は2176億2000万円
第2位は卸売業・小売業です。
- 利用契約件数は12万6275件
- 発生記録請求件数は2万2395件
- 発生記録請求金額は2155億3800万円
第3位は建設業です。
- 利用契約件数は9万4902件
- 発生記録請求件数は7684件
- 発生記録請求金額は461億9000万円
業種ごとに発生件数に差があるということは、業種によってでんさいによるメリットに差があるということです。

CFブルー
業種によってでんさいの普及速度も異なり、利用しにくい業種があることがわかるね!
2014年10月において、手形は月間約140万枚振り出されており、その金額は6兆円に上ります。
これに対し、でんさいは月間約6万件が発生しており、金額は5000億円です。
このことから、まだまだでんさいには普及の余地があることがわかり、逆に言えば利用できないケースも多いことがわかります。
でんさい自体は非常に優れたものであり、今後普及が拡大していくことでしょうが、現時点では利用したくてもできないケースもあるというデメリットを覚えておくと良いでしょう。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

でんさいに切り替えない理由

では、でんさいが優れているにもかかわらず、でんさいを利用していない企業があるのは、どのような理由からなのでしょうか。
代表的な理由は以下の四つです。
- でんさいに切り替えたいと思っているが、手形とでんさいを同時に取り扱うことを避けたいと思っており、全ての取引先の同意を得るまで利用開始を見合わせている。
- 手形の振り出し枚数が少ないため、でんさいを利用するメリットが小さい。
- 手形からでんさいに切り替えたいがと思っているが、これまで裏書譲渡をしていた取引先がでんさいに対応していないため、でんさいに切り替えてしまうと取引先への支払い手段がなくなってしまう。
- システム対応や取引先への説明に時間がかかる。
どれももっともな理由ですが、それぞれの場合でもでんさいを利用して良いでしょう。
1の場合、従来の債権からすべてでんさいに切り替えることができた企業は少なくても、手形とでんさいの併用でも十分にメリットはあります。
2の場合、振り出す手形が少ない企業でも、印紙税が不要になるというだけではなく、事務負担が軽減されるというメリットがあります。
3の場合、手形を裏書していた取引先にもでんさいの利用をすれば、自社も取引先も、譲渡にあたっての事務負担軽減などのメリットがあります。
4の場合、取引金融機関からサポートをうけることができます。
このように、一見でんさいを利用しなくても良いと思える場合でも、でんさいを利用することで確実にメリットを享受できることがわかります。
したがって、でんさいによる取引を見送っている企業でも、とりあえずでんさいの利用を始め、可能な範囲ででんさいの取引をしていくことで、メリットがあることでしょう。
【コラム】いざという時の資金調達に備えてGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」に申込んでおこう!

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
▼必要な資金をいつでも借りられる▼
「融資枠型ビジネスローン」