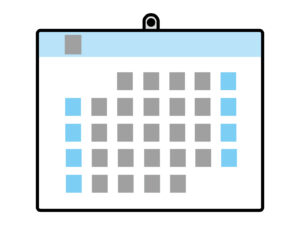ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
資金繰り上級企業の特長

現金にこだわる
「現金にこだわる」というのは、「いま会社にある現金にこだわる」ということです。
このこだわりがあるからこそ、会社に現金を残すように努力をします。
売上を闇雲に伸ばすよりも利益を伸ばすように努力し、節税によって現金が残るように工夫します。
たとえば、売上を中心に考えるA社と、利益を中心に考えるB社があったとしましょう。
A社は売上を1億円上げることを目標とし、利益率10%の商品によってその売上を達成しました。
つまり売上1億円に対して利益は1000万円です。
しかしB社は、コスト削減によって利益率を高めることを目標とし、利益率20%で1億円の売上を達成しました。
この場合、利益は2000万円です。
売上は同じでも、B社の方が倍の利益を出し、会社により多くの現金を残しています。
現金にこだわるからこそ、利益率を高めるためにコスト削減に取り組むことができ、結果的に多くの現金を残すことができたのです。
回収が早く支払いが遅い
平均回収30日、平均支払75日が1つの目安です。
売掛金の回収を早くすれば、商品やサービスを販売した代金が早期に会社に入ってくることになり、いま会社にある現金が増えます。
また、買掛金の支払いをできるだけ先延ばしにすれば、会社から現金が出ていくスピードが遅くなり、これもいま会社にある現金が増えます。
だからこそ、資金繰りがいい会社は、取引先に販売する際の契約で、回収サイトが1日でも早くなるように契約を結びます。
既存の取引先ならば、代替案などを提供しながら交渉し、回収サイトの短縮を図ります。
現金での回収にこだわる
現金で支払うことは、取引先にとっては資金繰りを悪化させることになりますから、うまくいかないことの方が多いでしょう。
しかし、数ある取引の中から、現金で回収できる局面があれば積極的に現金での回収を図った方が良いです。
手形による決済を行う会社もあるでしょうが、手形は受け取り側にとってはあまり好ましいものではありません。
取引先との交渉がうまい
現金にこだわって取引していくためには、取引先と回収サイト・支払いサイトでの交渉をしたり、現金で支払ってもらうように交渉したりする必要があります。
値下げ要求より「分割請求」「前受金」「月2回締め」などキャッシュ条件を交渉し、双方がウィンとなる代替案を複数提示します。
取引先に現金での支払いを交渉し、それがうまくいけば上々です。
どうしても手形でなければ無理だといわれることも多いでしょうが、その場合にもせめて支払期日を短縮してもらうべく交渉をします。
手形の支払期日は、一般的に30日、60日、90日、120日となっています。
このため、取引先が120日を希望したら90日で交渉、90日を希望したら60日で交渉というように、できるだけ回収サイトが短くなるように交渉していきます。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
手形を現金のように扱える
電子記録債権(でんさい)の分割譲渡を月3回使い、手形期日の偏りを平準化します。
金融機関との定例ミーティングで割引枠を更新し、金利競合を起こすことで手形割引料を年1%台に抑えている企業もあります。
折り返し資金を調達している
資金繰りのために運転資金を借り入れることによって、資金繰りの不足分を補い、事業を続けながら返済し、返済と共に再び運転資金を借り入れることがあります。
このような資金のことを「折り返し資金」と言います。
たとえば、回収サイトが2ヶ月、支払いサイトが1ヶ月の会社は、サイト間のギャップによって、常に資金不足が起こっています。
このような不足分を補うのが運転資金であり、通常、銀行などからの借入によって賄います。
無借金経営をしているごく一部の会社を除けば、どの会社も運転資金の借入と返済を繰り返しながら事業を継続しています。
その中で、現金での取引を増やしたり、回収サイトを早めたり、支払いサイトを遅らせたりといった改善に取り組み、必要となる運転資金を減らしていくのです。
借入で利益をしっかり増やせる
借入によって資金繰りを賄っている会社は、借入をしつつ、借り入れた資金をできるだけ有効活用して、利益を増やしていくようにしなければなりません。
銀行から借り入れをし、返済をしながら利益を増やしていき、銀行への返済後の経常収支をプラスにするのが理想的です。
固定費と変動費のバランスが適正である
会社が置かれている状況や業種によっても異なりますが、その会社に適切な固定費と変動費のバランスというものがあります。
適正なバランスからのギャップが大きければ大きいほど、資金繰りは悪くなっていくものなのです。
このことは、起業した会社の固定費と変動費のバランスがどのように変化していくかを知れば、よく理解できます。
起業して間もない頃は、固定客がいません。
会社の知名度も、商品やサービスの知名度も低いため、固定客の獲得は容易ではありません。
このため、月ごとの売上が大きく異なる場合もあり、利益は安定しないでしょう。
この時期は、安定しない利益の中で、いかに経営していくかが求められる時期です。
固定費をできるだけ削減し、事業を軌道に乗せるように努力していくはずです。
逆に、この時期を過ぎて固定客も増え、一定以上の利益が常にも込めるようになれば、変動費率は低くなっていくはずです。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
在庫管理がうまい
在庫管理を徹底している中小企業は多くなく、ほとんど管理していなかったり、感覚に頼った管理だけをしていたりといったケースが非常に多いです。
そのような会社は、売上が落ち、利益が少なくなり、資金繰りに悩んでから、はじめて在庫をコントロールしようとします。
悪い状況に陥ってしまったら、在庫管理をしないわけにはいかないのですが、在庫管理をしても既に手遅れということも少なくありません。
在庫管理は、平常時から取り組んでおいて、初めて効果が表れるものなのです。
与信管理を徹底している
売掛先が倒産し、売掛債権が不良債権になってしまうと、会社は受け取れるはずの代金を受け取れなくなり、資金繰りが悪化します。
特定の取引先と多額の取引をしている場合には、その取引先が倒産したことによって、巨額の損失が生まれてしまい、自社も連鎖倒産してしまうこともあります。
中小企業は、このリスクが大きい場合も少なくありません。
事業の規模がそれほど大きくなく、取引先が限られていれば、取引先一社当たりの売掛金が大きくなるからです。
その取引先が倒産してしまうと多大な被害をうけることになります。
そこで中小企業は、取引先が倒産しないように与信管理を徹底しなければなりません。
手形割引で手早く資金化
既存の取引先の悪い噂を聞いた場合などに、相手方の信用状況を手っ取り早く知りたい場合には、手形割引を行うという方法もあります。
手形割引は、銀行に手形を買い取ってもらうことで現金を手に入れる方法です。
銀行としては、不渡りになる手形を割り引くわけにはいきませんから、手形割引の依頼を受けると、手形の振出人の信用調査を行います。
その結果、銀行から「手形割引はできません」と言われたとすれば、それはその手形が不渡りになる可能性と言われたようなものです。
それがわかれば、今後継続して取引をする場合には、小口の取引に限定したり、現金で支払ってもらったり、取引そのものを停止したりする必要があります。
経営セーフティ共済に入っている
経営セーフティ共済とは、万が一の貸し倒れの際の保険です。
年間240万円を上限として積み立てておくことで、もし売掛債権が回収不能になった場合には、積立額の10倍までの金額を無利息で借り入れることができるという仕組みです。
この保険金は損金になり、7年間の積み立ての後には満額で返還されるため、経営セーフティ共済に加入することによって経営が圧迫されることもありません。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
高度な資金繰りテクニック

サプライチェーン・ファイナンス
大手取引先との間で、請求書を裏付けに金融機関が早期支払する仕組みです。
サプライヤーは早期現金化、買い手は支払サイト維持という双方メリットがあるため、製造業で導入が急増しています。
インボイス・ファイナンス
インボイス発行事業者であれば、発行済み請求書を債権譲渡し即日資金化できます。
ファクタリングに近いスキームですが、消費税計算が厳密になる2023年10月以降は与信査定が高度化し、手数料低下が進みました。
売掛保証+ファクタリング併用
信用保険会社の売掛保証で貸倒をカバーしつつ、保証付き債権をファクタリングする手法です。
保証がある分、手数料は1%台まで圧縮でき、複数社比較で0.5%近い差が出ることもあります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
資金繰り表を作る5ステップ
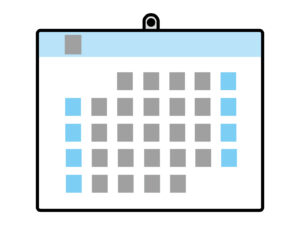
キャッシュフロー計画を見える化するには、以下の手順が王道です。
1. 現金残高を前提とする開始日を決める
2. 週単位で入金予定と支払予定をリスト化
3. 入金サイトと支払サイトを反映して日付を調整
4. 差引残高が最低ラインを下回る週をハイライト
5. 資金不足週に対し、手形割引・短期融資・支払延期など具体策を紐づける
この5ステップをクラウド会計と連携させれば、入出金の実績自動取込と予実差異アラートが可能になります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
よくある質問(FAQ)

Q:資金繰り改善に最短で効く施策は何ですか?
A:売掛金早期回収です。
1件でも即日入金が増えれば、短期借入利息より高い効果があります。
Q:ファクタリングと手形割引、どちらが安いですか?
A:同じ3ヶ月サイトなら手形割引が低コストな傾向ですが、保証人不要で与信が柔軟なのはファクタリングです。
自社与信状況で選択しましょう。
Q:資金繰りが苦しいと銀行格付は下がりますか?
A:営業利益が黒字でも、現預金が減少し続けると自己資本比率が下がり格付けに影響します。
早めに手元流動性を回復させることで格付け低下を防げます。
まとめ:資金繰り強化こそ最大の成長戦略
「利益は意見だがキャッシュは事実」という格言どおり、手元資金こそ企業の真の体力です。
本記事のノウハウを実装し、攻めるべきときに堂々と投資できるキャッシュフロー経営を実現しましょう。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼ ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
 ▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼