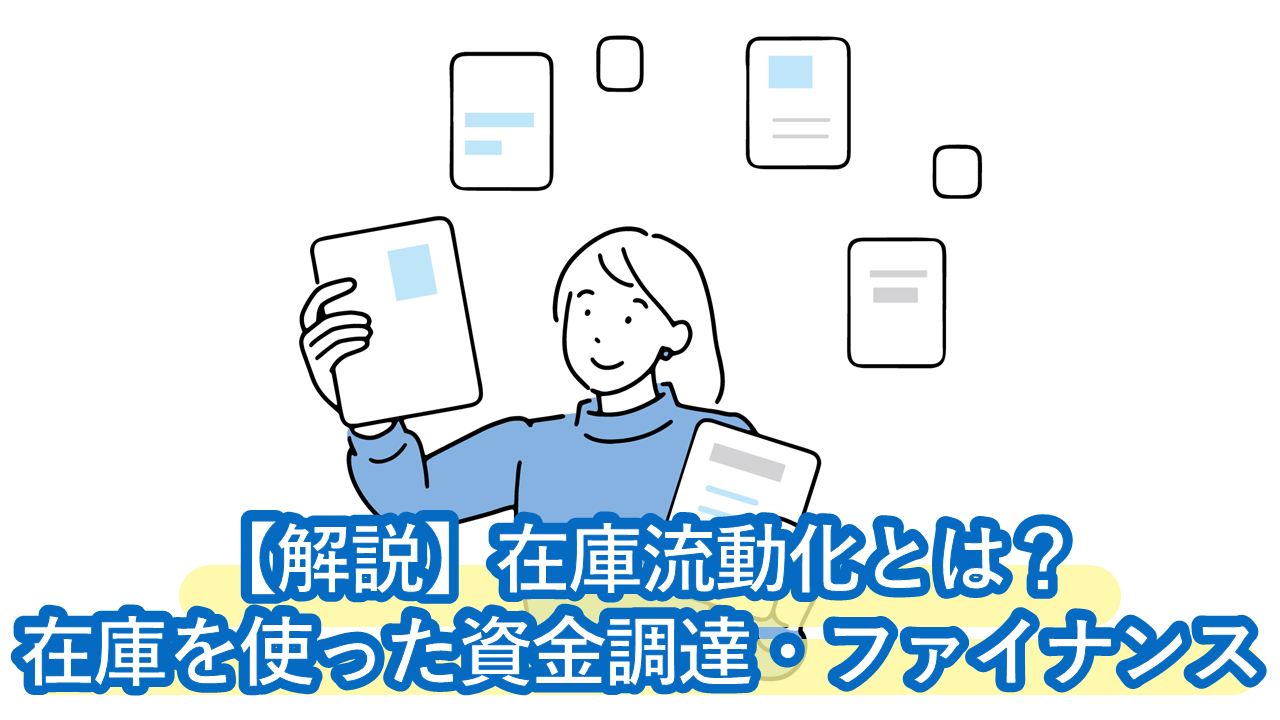「在庫流動化(=在庫ファイナンス)」とは、自社資産を使った資金調達法の1つです。
そもそも自社の資産を使って資金調達を行う方法を「動産担保融資(アセット・ベースト・レンディング、ABL)」と言います。
現在使用していない商品在庫等を担保に資金調達を行います。
本記事では、資金調達方法として「在庫流動化」や急ぎの際に使える「ファクタリング」について解説していきます。
急ぎの際はファクタリングがおすすめ

※上記の図解は2社間ファクタリング
ファクタリングとは、「債権買取り」を意味しています。
法人がファクタリングにおいては、保有している売掛債権(=請求書)を売却することで現金を得る資金調達方法の一種として認識されています。
企業は、ファクタリングを利用すれば、売掛債権の予定日よりも早く現金を受け取れます。
ファクタリングは売掛債権の売買で資金調達を行うため、銀行からの借入とはことなり融資にはあたりません(調達した資金の返済は不要です)。
融資ではないため金利はありませんが、利用時にファクタリング業者に手数料を支払います。

在庫を見直すことの効果

在庫過剰の状態は、経営にとってあまりよくありません。
過剰な在庫も、元は仕入れや製造によって生じています。
これらの在庫が売れていない状態は、「資金繰りを圧迫している」とも言えます。
まずは、社内で過剰な在庫を抱えていないか確認してみましょう。
▼過剰な在庫の例
- 旧タイプの売れ残り商品
- 季節が過ぎて売れ残った商品
- 仕入れ過ぎてしまった商品
こういった過剰在庫がある場合は、在庫の売却や在庫を担保に資金調達法の利用で処分を進めていくといいでしょう。
銀行や政府系金融機関からの融資を受けられなかった会社でも、過剰在庫を活用することで資金調達できる可能性があります。
過剰在庫を抱え続けることのデメリット
貸借対照表に過剰在庫が記載されると、それらは流動資産の一部として計上されると同時に、債務も増加し流動負債も多くなります。
逆の見方をすれば、過剰在庫を何らかの形で処分することができれば、貸借対照表における債務も減少します。
このように、過剰在庫の処分は資金調達と同じ価値をもっています。
もちろん、通常通り製品を販売・製造し、それを販売して利益を出している会社では、在庫不足は利益獲得機会を逃すため好ましくありません。
しかし、だからこそ販売機会を逃したくないと、企業は在庫を積み増し、過剰在庫に陥るケースが多いです。
過剰在庫を見直すメリット
まずは、過去の販売実績や納品サイトなどから、どれくらいの在庫が適正かを割り出します。
適正な在庫量がわかったあとに、過剰になっている部分をできるだけ少なくしていきます。
▼過剰在庫を見直すメリット
- キャッシュフローが改善する
- 貸借対照表の総資産増加を防ぎ、財務内容を改善できる
- 過剰在庫の処分で資金調達ができる
- 在庫の品質を新鮮に保てる
- 管理や棚卸にかかるコストを削減できる
在庫の見直しには、資金調達や貸借対照表上のメリット以外に、管理等の手間を減らせるメリットもあります。

在庫を担保にするとは?(ABLについて)

冒頭でも少し触れましたが、過剰在庫を担保にして融資を受ける方法があります。
通常、融資の担保で多く用いられるのは「不動産」ですが、不動産がない場合も在庫などの「動産」を担保にする方法があります。
たとえば、在庫、売掛債権、機械設備などの動産を担保として利用できます。
これらの動産を担保とした融資が「動産担保融資(アセット・ベースト・レンディング、ABL)」です。
ABLを使えば、不動産を所有していない会社でも、自社製品や工場機械などを担保に金融機関から融資を受けられる可能性があります。
不動産担保と同じで、機械を担保にしたとしても、営業の範囲内であれば担保にした機会を使うことができます。
ABLを利用したとしても、営業に大きな影響はでないでしょう。
金融機関はABLにあまり積極的ではないって本当?

中小企業にとっては利便性が高く感じるABLですが、金融機関にとっては取り扱いの難しい仕組みだと言われています。
なぜなら、万が一貸し倒れた際に、担保としている在庫や機械を差押えてもこれらを販売できる販路が少ないからです。
担保としてよく使われる不動産と比べると、売却しにくいイメージが伝わるかと思います。
在庫や機械の販売を専門としている業者に委託したとしても、二束三文でしか売れないことも多いです。
そのため、銀行はABLを行う前に「処分しやすい在庫か」、「貸し倒れは起きなさそうか」といったリスクや担保価値の精査を行います。
通常、在庫を担保とした融資では、在庫の価値の30%を上限とした融資が行われます。
※第三者による客観的な評価証明によって、最大70%の融資を受けられる場合もあります
こんなものもABLに使える

ここまで登場した在庫は、工業的な製品や商品というイメージが強いかもしれませんが、実はABLで担保にできる在庫の幅は広いです。
たとえば、農業や漁業でも使えます。
農家が融資を受ける場合、農地は担保価値が低く融資に活用しにくいため、コメや野菜といった農産物を動産担保にすることがあります。
ほかにも、牛や豚といった家畜や、魚や貝・カニなどの海産物も動産担保とすることができます。

動産担保融資(=ABL)の流れ

では、「動産担保融資(=ABL)」の流れを見ていきましょう。
本章では、「在庫」を担保に使った例を紹介していきます。
なお、設備や売掛債権といった動産を担保にする場合でも、基本的に流れは同じです。
1.融資の申し込み
まずは、普段から取引のある金融機関に融資を依頼してみましょう。
プロパー融資や信用保証協会保証付融資など、通常の形で融資が受けられればそれでいいです。
通常の融資に難色を示された場合は、在庫を担保に融資できないか打診してみてください。
2.審査
決算書や資産状況、在庫などのチェックをしながら審査を進めていきます。
審査の結果、融資が問題ないとなれば、融資額や融資条件の決定のために、担保とする在庫の資産価値を評価していきます。
取引先との販売契約資料や、在庫の実物確認によって評価していきます。
外部の調査会社によって評価が行われる場合もあります。
3.融資契約
融資額や融資条件を決め、その条件で問題なければ融資契約を結びます。
契約形態には、借り手と貸し手の二者間で契約を結ぶ場合、複数の貸し手が共同で融資を行なう場合、信用保証協会の保証を付ける場合などがあります。
4.担保資産の登記
担保とする動産を譲渡するにあたり、第三者に対抗するために、動産の譲渡登記を行います。
譲渡をすることで所有権が移りますが、一定の要件を満たすことによって、借り手が担保とした動産を経営に利用することができます。
資産の評価が不動産などよりも難しいため、通常の融資よりも融資実行までに時間がかかります。
補足:ABL保証
上記の流れの中で、信用保証協会の保証を付けた動産担保融資があると書きました。
これはABL保証いい、正式名称を「流動資産担保融資保証」と言います。
おもに中小企業を対象として、会社が保有している動産を担保として融資を行なう時、信用保証協会が融資額の80%を上限とした保証を行なう制度のことです。
この制度を使う場合、借り手の会社は担保となっている動産の状況を、3ヶ月に1回以上のペースで報告する義務があります。

【コラム】時間に余裕があるならGMOあおぞらネット銀行の「あんしんワイド」が使いやすい

GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。

まとめ
資金調達方法にもいろいろな方法があります。
資産による資金調達は、利用によっては大きなメリットが得られる方法です。
過剰在庫を売れば、資金調達と同時に財務内容の改善に役立ちます。
在庫などの動産担保にすれば、不動産などを所有していない会社でも融資を受けられる可能性がありますよ!