※本記事はプロモーションを含みます。

助成金は、会社にとって非常にありがたい制度であり、積極的に活用していくべきものです。
しかし、助成金の仕組みや手続きについて理解している経営者はあまりおらず、助成金ビジネスの食い物にされてしまう会社が後を絶ちません。
助成金ビジネスとは、会社に助成金の受給を持ち掛け、会社の事情を考えない助成金申請で多額の報酬を受け取るビジネスのことです。
このようなビジネスを手掛けるコンサル会社が、中小企業に無作為に営業をかけています。
本記事では、助成金ビジネスの危うさ、コンサル会社の悪質性、それに騙されない考え方などについて解説していきます。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
【注目】お急ぎの場合はファクタリングがおすすめ
 ※上記の図解は2社間ファクタリング
※上記の図解は2社間ファクタリング
ファクタリングとは、「債権買取り」を意味しています。
法人がファクタリングにおいては、保有している売掛債権(=請求書)を売却することで現金を得る資金調達方法の一種として認識されています。
企業は、ファクタリングを利用すれば、売掛債権の予定日よりも早く現金を受け取れます。
ファクタリングは売掛債権の売買で資金調達を行うため、銀行からの借入とはことなり融資にはあたりません(調達した資金の返済は不要です)。
融資ではないため金利はありませんが、利用時にファクタリング業者に手数料を支払います。
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
悪質な助成金ビジネスに要注意

助成金の基本を知らないと、「助成金ビジネスの被害」に遭ってしまう可能性があります。
助成金ビジネスとは、会社に電話やDM、FAXなどで助成金の受給を持ち掛け、多額のコンサル費用や着手金、成功報酬などを稼ぐビジネスです。
コンサル会社や極一部の社労士がそれを手掛けており、その営業に乗ってしまうと社内で多くの問題が発生してしまいます。
▼助成金ビジネスで想定される被害
- 一般的な社労士に依頼するよりも費用が割高であり、会社に残るお金が少なくなる
- 正しい知識を持っていないコンサル会社に依頼した結果、助成金を受給することはできず、コンサル費用や着手金だけを払うことになる
- 会社のためにならない助成金も見境なく受給させられ、会社の負担が大きくなってしまう(人件費が重くなりすぎる、必要のない制度だけが残るなど)
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

特に注意すべきはコンサル会社
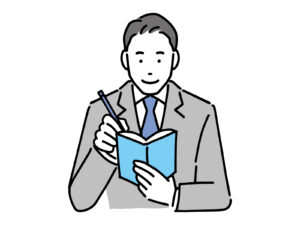
このような営業に乗せられてしまうと、助成金を活用することはできません。
社労士は、士業同士の横のつながりも強く、横のつながりによって経営が成り立っている側面もあるため、業界内で悪い評判が立つことを嫌うのが普通です。
したがって、社労士が自ら、悪質な助成金ビジネスを手掛けていることはそれほど多くありません。
しかし、コンサル会社には要注意です。
コンサルタントという肩書で営業を持ち掛けられると、強く信用してしまう経営者がたくさんいます。
しかし、国家資格の裏付けがある社労士とは異なり、コンサルタントは誰でも名乗れるため注意が必要です。
コンサルタントは実績が大事
コンサルタントの信用を裏付けるのは「実績」です。
実績のあるコンサルタントであれば、電話・DM・FAXなどで無作為に営業をかけることはあまりありません。
長期的にお付き合いのある顧客を抱えているほか、評判を聞いて相談してくる顧客が多くいるからです。
逆に言うと、助成金コンサル名目で積極的に営業をかけてくるコンサルは「あまり実績のないコンサルタントである」ということができるでしょう。
そのようなコンサル会社に助成金のサポートを依頼すると、「割高、申請に失敗する可能性が高い」などのリスクが高まります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
コンサル費と着手金を無駄した実例

ある会社では、コンサル会社からの話を聞き、「両立支援等助成金の育児休業等支援コース」の利用を検討し始めました。
両立支援等助成金では、次のような場合に28.5万円の助成金を受給できる制度です。
▼両立支援等助成金
就業規則を整備しする
社員が3ヶ月以上の育児休業を取得する
育児休業後に職場復帰を果たし、6ヶ月以上の勤務をした
しかし、この助成金を受給するためには、事前にいろいろな準備をしてから取り組む必要があります。
具体的には、育児休業規程の作成や仕事の引継ぎ、上司との面談などです。
ところがこの会社の社長は、コンサル会社の「育児休業を与えた社員がいるなら、受給できます」という案内だけを信じ、事前準備をしていませんでした。
コンサル会社の説明不足により準備ができなかったこの会社では、コンサル費用と着手金をムダにしてしまいました。
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングについての記事はこちら

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
コンサル会社は社労士よりも報酬が割高

以上のように、一部のコンサル会社では、専門知識や経験の欠如によって間違った案内をし助成金が受給できないケースが良くみられます。
最悪のケースでは、最初からコンサル費用と着手金だけを目当てに、嘘の案内をする悪質なコンサル会社もあります。
このような悪質なコンサル会社を避けるには、直接社労士に依頼する方が安心かつ安上がりです。
「自社⇔コンサル会社⇔社労士」という流れで無駄な仲介を挟むよりも、「自社⇔社労士」としてやり取りしたほうがスムーズです。
悪質でなくてもコンサル会社の見積もりは割高になりがち……
さらに問題なのが、コンサル会社の案内で手続きすると、どうしても割高になってしまうことです。
次章で詳しく解説しますが、コンサル経由で助成金取得に動いた場合、着手金や成功報酬のほかに「コンサル費用」が必要となります。
このコンサル費用のせいで、無事に助成金を獲得できたとしても会社の手残りが大幅に減ってしまいます。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
悪質コンサル会社と社労士の相場比較
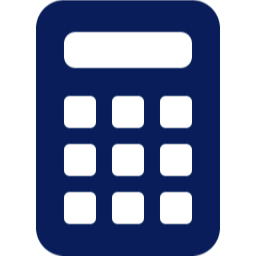
悪質コンサル会社と一般的な社労士で、助成金に関する見積書の相場を比較してみましょう。
悪質コンサル会社の相場
悪質なコンサル会社の見積書は、以下のような内容になっていることが多いです。
【悪質コンサル会社の相場】
- 受給予定金額:150万円
- コンサル費用:30万円
- 着手金:10万円
- 成功報酬:20%(30万円)
依頼にあたって必要となる費用は、コンサル費用と着手金の計40万円です。
仮に助成金を受給できなかった場合も、このコンサル費用と着手金は返金されません。
コンサル会社にとっては、これだけでも大きな売り上げになっています。
無事に受給に至ったとしても、150万円の受給で会社に残るお金は80万円となり、半分近くをコンサル会社に支払うこととなります。
一般的な社労士の相場
これに対し、一般的な社労士に依頼した場合の費用はおおよそ以下のようになっています。
【一般的な社労士の相場】
- 受給予定金額:150万円
- コンサル費用:なし
- 着手金:10万円
- 成功報酬:10%(15万円)
コンサルティングが入らない分、コンサル費用は請求されません。
よって、仮に受給できなかった場合も、会社の損失は着手金10万円だけです。
150万円の受給となれば、最終的に会社に残る金額は125万円と80%以上の手残りとなります。
社労士の一般的な相場では、受給した助成金の大部分が会社の手残りになるケースが多いです。
このように比較してみると、無駄なコンサル費用を支払うことによって、コンサル会社の見積もりがかなり割高になっていることがわかるでしょう。
【ポイント】
社労士報酬の中心となるのは成功報酬で、成功報酬は10~20%に設定している社労士が多いです。
上記の例で成功報酬を20%としても、会社の手残りは約73%となります。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
コンサル会社に依頼した場合の事例
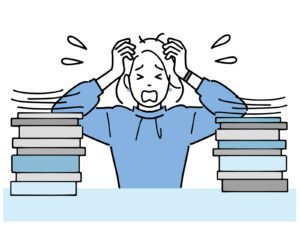
以下では、実際にコンサル会社経由で助成金の利用をした会社の実例です。
コンサル会社は会社に次の内容を伝えました。
「契約社員がいる会社で、無期雇用あるいは正規雇用に転換するとキャリアアップ助成金を受給できる。」
これ自体は何ら嘘ではなく、実際に「キャリアアップ助成金の正社員化コース」は次のような条件を満たすと受給可能になります。
▼キャリアアップ助成金の正社員化コース
有期契約から正規雇用への転換:57~72万円
有期契約から無期雇用あるいは無期雇用から正規雇用への転換:28.5~36万円
そこで社長が「今後、正社員に雇用に切り替えたい社員がいるが、助成金はでるのか」と聞いたところ、コンサル会社は「可能です」と答えました。
これ自体も嘘ではないのですが、結局この会社は想定より低い助成金しか受け取れなくなってしまいます……。
コンサル会社を利用した会社が陥った罠
キャリアアップ助成金を受給するためには、次のステップを踏む必要があります。
▼キャリアアップ助成金受給のステップ
- 転換を見据えたキャリアアップ計画を作成する
- 労働局に提出して認可を受ける
- 転換前に6ヶ月以上の継続雇用
- 転換にあたって賃金を5%以上アップ
- 転換後に6ヶ月の継続雇用
コンサル会社は、このような説明もしたうえでコンサル費用と着手金として40万円を受け取りました。
その後、従業員2人を有期契約から正規雇用へ転換したことで、114万円の受給となりました。
しかし、社長は事前の説明から150万円程度受給できると思っていたため、助成金がずいぶん少なく感じました。
この150万円は、あくまでも生産性が6%以上アップし、1人当たりの助成金が57万円から72万円へと増額された場合の金額です。
社長の勘違いであったと言われればそれまでなのですが、その結果、見込んでいたよりも会社の手残りは少なくなりました。
コンサル費用と着手金で40万円、成功報酬は22.8万円(受給金額の20%)、会社の手残りは50%以下となったのです。
【ポイント】
社労士に直接依頼し、着手金10万円、成功報酬10%の条件で受給していれば、80%以上が会社の手残りになっていたでしょう。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
コンサル会社の提案を安易にOKしてはいけない

社労士に依頼した場合の一般的な相場を知っていれば、コンサル会社の見積書を見たとき、「高すぎる」と気づくはずです。
悪質なコンサル会社を見抜く方法としては、見積りの高さ以外に下記のような営業トークにもヒントがあります。
「助成金は、返済不要の資金です。150万円の受給でしたら、諸費用を差し引いても半分以上が残ります。
80万円がそのまま収入になりますが、これを事業で稼ごうとすれば大変ですよね。
利益率10%の会社であれば、800万円も売り上げなければいけません。
申請するだけでもらえるものですから、ぜひおすすめしますよ」
悪質なコンサル会社ほど、「(割高な見積なのに)半分以上“も”残る」、「申請する“だけ”」などと強調します。
助成金に関する専門的な知識や、利用することによって会社に生じる負担などを説明しません。
また、提案を受けた会社が社労士や税理士に相談すれば、あまりにも見積もりが割高であることがバレてしまいます。
このため、次のように持ち掛けます。
「助成金は、申請期間を過ぎてしまうと受給できなくなります。
もうあまり猶予がないので、すぐに取り掛かったほうがいいですよ」
「助成金について熟慮する時間を奪う」、「ほかの専門家に相談する機会を奪う」こういったコンサル会社にはご注意ください。
コンサル会社を利用する際の注意点

依頼しようと考えているコンサル会社の能力を見極めるために、下記の項目を確認してみてください。
- 経営の実態に即した助成金を選択してくれる
- 助成金に関する専門知識や経験
- 助成金受給や活用の実績
- 労働法についてもアドバイスをしてくれる
- 助成金の受給に伴い、会社に発生する負担やリスクを説明してくれる
- 経営者からの質問に、的確に答えられる
悪質なコンサル会社では、これらの項目を見ていくうちに何かしらの不安点が出てくると思われます。
もちろん、優秀なコンサル会社が助成金を提案しているケースもあります。
そのようなコンサル会社では、多少割高になったとしても、助成金をフル活用できるように指導してくれるため役に立つでしょう。
【注意】
コンサル会社の中にはあの手この手で助成金利用を持ち掛け、会社を食い物にしようとする悪質な会社があるのも事実です。
利用前に不明点、不安点がないかを十分確認してください。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
助成金を受給できるからと言って、悪質コンサル会社の提案に乗ってしまうと、助成金を活用しての経営改善は望めません。
怪しいコンサル会社に依頼するくらいならば、最初から助成金の専門家である社労士に依頼したほうが安心です。
費用も比較的安く、助成金活用のアドバイスも期待できます。
もし、コンサル会社を利用する際は、安心して依頼できる会社かしっかり見極めることを心掛けてください。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼ ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
 ▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

注意すべき悪質・悪徳な補助金コンサル会社の特徴|助成金に潜む闇とリスク





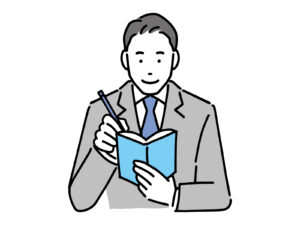







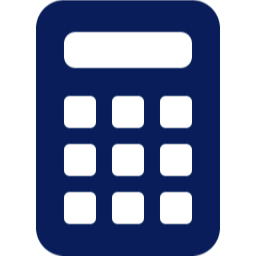
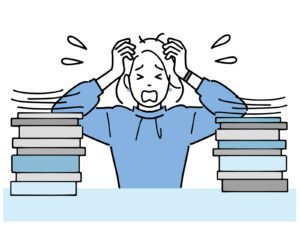







コメント