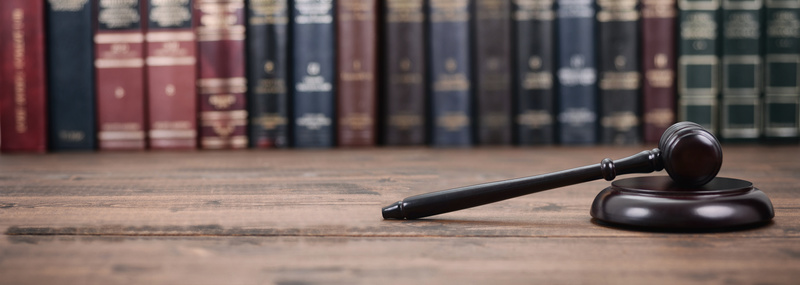ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
債権者と債権者のパワーバランスを保つ働きがある

次に、電子記録債権法第12条を見ると「意思表示の無効または取消しの特則」というものが設けられています。
これは、電子債権記録法における権利関係において、その権利が無効になったり、取引が取り消しになる特例を定めたものです。
債権記録の請求における相手方に対する意思表示についての心裡留保、錯誤による無効、詐欺もしくは強迫による取消し。
とあります。
これは、債権記録の請求、つまり「取引が成立して売掛債権が発生したので、記録原簿に登録してください」という請求を電子記録債権機関に出すのですが、その請求が無効になる特例を書いたものです。

CFレッド
心裡留保について簡単に説明しよう。

CFイエロー
これは意思表示をするときに「自分の本当の気持ちと結果の食い違いを自覚しながら行う意思表示」のことだよ!
つまり、表面的には取引が成立して売掛債権が発生するという結果になっているのですが、実際にはその結果を望んでいなかったのにそうなってしまったということです。
そのような食い違いが起こってしまう原因として、以下の事が考えられます。
- 取引先との間に誤解があって売掛債権が発生してしまった
- 取引先の詐欺によって売掛債務を負ってしまった
- 取引先から強迫されて売掛債務を負ってしまった
そのような場合には、たとえ一旦は電子記録債権が発生していたとしても、それは取り消しが可能になるということです。
ただし、この項目に続けて、
対抗しようとする者が個人である場合等は前項の規定は適用しないこと。
とあります。
これは、売掛債権に関する権利関係を争うことになったとき、それが個人である場合には、上記の無効または取消しの特則が適用されません。民法の規定に従って争っていくということです。
ただし、記録原簿において取引しているのが個人事業主であると記録されている場合には、電子債権記録法に基づいて権利関係を争うことになります。
次に、電子記録債権法第13条には「無権代理人の責任の特則」というものが記載されています。
無権代理とは、代理権がないにもかかわらず代理行為を行ったり、代理権限を超えて代理行為を行うことを言います。

CFレッド
このとき、無権代理人の行った行為は無効とされるよ!
ここでは、
無権代理人の免責事由(民法117条2項)を、意思表示の相手方が悪質重過失であることを要求することにより、限定して、無権代理人の責任を加重すること。
とあります。
これは、無権代理人が免責事由、つまり債務の放棄などを主張したとき「その意思表示の相手に悪質な過失があったことを要求した場合には、無権代理人に責任を追及できる」というものです。
たとえば、売り手企業と買い手企業の権利関係において、売り手企業が無権代理人から債務の免責を要求されたとき、その要求の根拠が悪質重過失であるとされているようなものです。
それが根も葉もないことであれば、売り手企業が根拠のないことで信用を失うことになりますし、代理制度の信用も壊れてしまいます。

CFイエロー
そのようなことがないように、無権代理人の責任を加重するとされているよ。
実際には、損害賠償責任を負うか、取引の履行責任を負うかによって責任を果たすことが求められます。
つまり電子記録債権法は、債権者だけではなく債務者の権利も守る機能を果たしているということです。
もし、このような取り決めがなかったとすれば、詐欺被害をはじめとした不本意な取引で電子記録債権が発生してしまうと、債務者は何の手立てもなく支払わなければならなくなります。

CFブルー
しかし、特則によって取引を取り消せると決めているため、その心配はないのだ!
また、そのような定めだけが存在してしまえば、債務者の力が強くなってしまい、債権者が権利を主張することが難しくなることがあるかもしれません。
それを防ぐためにも、電子記録債権法では第13条のような定めも設けているのです。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
電子記録債権の発生から消滅まで

以上のようなことを定めたうえで、電子記録債権記録法では、電子記録が発生から消滅するまでのことを、以下のように定めています。
電子記録債権の発生
電子記録債権法第15条において、電子記録の発生は、
電子記録債権は、発生記録によって生じる。
と書かれています。
つまり電子記録債権は、企業間で取引が成立したとき、電子債権記録機関に発生記録をするように請求がなされ、発生記録がされて初めて発生するということです。
発生記録について
次に、電子記録債権法第16条では、発生記録を以下のように定めています。
まず、
必要的記録事項は、債務者が支払うべき金額、支払期日、債権者および債務者の指名などとすること。
とありますが、「必要的記録事項」とは、絶対に記録しなければならない事項のことであり、これによって支払金額・支払期日・債務者・債権者などが確実に記録されるわけです。
次に、
任意的記録事項は、支払方法の定め、債権者または債務者が個人事業主である旨、譲渡記録を禁止または制限する旨の記録などとすること。
とあります。
「任意的記録事項」とは、絶対ではなく必要に応じて記録する事項のことです。
下記のような事が任意的に記録されます。
- 支払方法は一括なのか分割なのか
- 債権者または債務者は法人ではなく個人事業主であること
- 債権の譲渡を禁止したり制限したりしているのかといったこと
紙の手形は一括払いしかできなかったのですが、電子手形では分割払いに応じるようになりました。手形割引をする場合にも、分割しての手形割引が可能となっています。
そのため、場合によっては任意的記録事項において、支払方法を記録することがあるのです。
また、取引の際には債権譲渡禁止特約を設けることで、売掛債権の譲渡を禁止しておく場合があります。
これは、知らない間に売掛債権が譲渡されることによって、債務者が不特定の債権者から請求を受けることを防ぎたい場合に利用する特約です。
電子記録債権を利用した場合にも、この特約はしっかりと記録することができます。
電子記録債権の譲渡

紙の手形を裏書譲渡や手形割引に利用したり、売掛金をファクタリングや売掛債権証券化などに利用する際には、売掛債権の譲渡が行われます。
電子記録債権でも譲渡は可能となっており、その場合には電子記録債権の譲渡を行います。
電子記録債権法第17条では譲渡に関して、
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力は発生しないものとする。
と定めています。
つまり、電子記録債権の発生と同様に、電子記録債権を譲渡する場合には、電子債権記録機関に譲渡記録を請求し、その記録がなされて初めて譲渡したことになるのです。
譲渡記録について
電子記録債権の譲渡に関して、電子記録債権法第18条には、
必要的記録事項は、譲受人の氏名等とし、その任意的記録事項は、譲渡人が個人事業主である旨、譲渡人と譲受人の通知の方法などとすること。
とあります。
発生記録と同様に、必要的記録事項によって権利の所在を明確にし、さらに任意的記録事項を記録することによって、取引がより正確に行われるようにしています。
また、
消費者についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力を有しないこと。
とあります。
これは、本当は消費者であるにもかかわらず、個人事業主であるとして譲渡記録がなされた場合には、無効になるということです。
電子記録債権は法人・個人事業主・国・地方公共団体などが利用できるものですから、事業主ではない一個人を個人事業主であると偽って電子記録債権を譲渡した場合、無効になります。

CFイエロー
あまり縁のないことかもしれないけど、電子記録債権法が不正防止のために設けている条項として知っておけば良いよ!
その他、
電子債権記録機関は、発生記録において譲渡記録を禁止または制限する旨の記録がなされているときは、その記録に抵触する譲渡記録をしてはならない。
とあります。
上記の通り、取引契約の際、債務者の便宜上の問題から債権譲渡禁止特約を設けることがあります。この場合、債務者が承諾しない限り、債権者の一存で売掛債権を譲渡することはできません。
電子記録債権においてもこのことはきちんと守られなければならないため、このような定めを盛り込んでいるのです。
善意の取得について

さらに、電子債権法第19条には、善意取得に関することが書かれています。
善意取得とは、民法や有価証券法において、善意によって動産や有価証券を取得した人の権利を守るためのものです。
ちなみに、ここでいう「善意」とは、道徳でいう「善い行いをする意思」の意味ではありません。
譲渡する電子記録債権の元の持ち主が無権利者であったり、過失を犯していたりしたことを知らずに、譲渡を受けることを指しています。
電子債権記録法第19条には、
債権記録の請求により譲受人として記録されている者は、悪意重過失でない限り、当該電子記録債権を取得するものとする。
とあります。
つまり、電子記録債権の譲渡を受けた場合、それが悪意でなければ(つまり善意によるものであれば)、その電子記録債権を取得することができるということです。
ただし、第19条には
前項の規定は、発生記録に善意取得の規定を適用しない旨の記録がある場合や譲渡人が個人(事業主記録があるものは除く)であって譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合でその譲渡記録の後に転得者が譲渡記録を受けた場合などは適用しない。
とあります。
これは、まず善意取得の場合でも、基本となる取引契約において、「善意取得でも譲渡は認めません」という取り決めをしておき、電子記録債権の発生記録のときに記録されていれば、善意取得は認められないということです。
このほか、譲渡人が個人であれば善意取得でも認められないとされています。
抗弁の切断について

CFイエロー
そして、電子債権法第20条には、抗弁の切断に関する規定があるよ!
抗弁の切断とは、売掛債権を第三者に譲渡するときに「債務者が異議を唱えなかった場合、仮に旧債権者に対して何らかの対抗理由があったとしても、その理由を元に新債権者に対抗できなくなる」というものです。
抗弁の切断については、
電子記録債務者は、電子記録債権の債権者が当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得した場合を除き、当該債権者に当該電子記録債権者を譲渡したものに対する人的抗弁をもって当該債権者に対抗できないものとする。
とあります。
電子記録債権を譲渡されたとき、新債権者はその債権が債務者に何らかの被害をもたらすものであることを知らずに譲渡を受けていることがあります。
通常、債権者に過失がある場合には、電子債権法第12条に基づいて取引を取り消すこともできるのですが、いったん新債権者がその悪質性を知らずに譲渡を受けた場合には、債務者は新債権者に対して抗弁できなくなるということです。
これに続けて、
前項の規定は、発生記録または保証記録において人的抗弁の切断を適用しない旨記録されている場合や電子記録債務者が個人(事業者記録がなされているものを除く)である場合は適用しない。
ともあります。
これは、あらかじめ発生記録を請求する際に、抗弁の切断を適用しないという特約を設けていた場合、あるいは債務者が個人である場合には、抗弁の切断は適用されず、債務者は新債権者に対しての抗弁が可能となるということです。
電子記録債権の消滅

電子記録債権法では、電子記録債権の消滅についても規定しています。
支払免責について
電子記録債権法21条には、支払免責についての記載がされています。
支払免責とは、債務者の支払いが無効になることです。第21条には、
電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しなくてもその効力を有する。ただし、その支払をしたものに悪いまたは重大な過失があるときはこの限りではない。
とあります。
つまり、電子記録債権においては、名義人が無権利であった場合にも支払いを受ける権利があるものの、支払人に悪意や過失がある場合には免責の対象となるということです。

CFレッド
悪意や過失とは、名義人が無権利であることを知りながら支払った場合のことだよ!
消滅時効について
電子記録債権法第23条には、電子記録債権の時効について記載されています。
電子記録債権の消滅時効は3年である。
これは、電子記録債権の有効期限は支払期日から3年間であり、それを時効として消滅するということです。
支払記録の請求について
代金を支払ったならば、その旨の請求を行うことで、電子記録債権が消滅することになります。
このことに関して、電子記録債権法第25条には、
支払等記録は、電子記録義務者、電子記録義務者の承諾を得た電子記録債務者等だけが請求できる。電子記録債務者は、電子記録義務者に対し支払等をした場合は、支払等記録をするように請求することができ、支払をするものは、支払と引き換えに支払等記録の承諾をすることを求めることができる。
とあります。
電子記録義務者とは、その電子記録債権の債権者のことだよ!
つまり、きちんと支払いが行われたならば、電子記録債権の消滅を請求しなければならないわけですが、それは基本的に債権者しかできないということです。
債務者でも請求が可能となれば、支払ってもいない債務者が勝手に支払等記録を行うことにもなりかねないからです。
逆に、支払っても債権者が支払等記録をしてくれない事態に備えて、債務者は支払いと引き換えに支払等記録をしてもらうこともできます。
口座間送金決済等に関する措置

CFイエロー
電子記録債権法の第62条~第66条には、口座間送金決済に関することが書かれているよ!
それによると、債務の全額が銀行口座間で決済されたことが銀行から通知されたときには、電子債権記録機関は支払等記録をし、電子記録債権を消滅させなければならないとされています。
つまり、電子記録債権の決済を銀行で行う場合には、送金と同時に支払等記録がされることになります。
そのため、債務者から債権者に対して支払等記録を請求する必要はなく、自動で行われることになります。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

その他の重要なポイント

電子記録債権法で非常に重要となる部分は上記において説明しましたが、その他にも知っておいたほうが良い部分があるので、解説していきましょう。
電子記録保証について
電子記録保証とは、その電子記録債権に何らかの保証(保証人など)をつけることです。
保証を付けている場合には、電子債権記録機関に保証記録をすることによって、効力が生じます。

CFブルー
この保証によって生じる債務は、本来の債務者が債務を負担しない場合に効力が発生するよ!
分割について
電子記録債権は、分割が可能です。
債権者に対して分割して支払うことができるほか、ファクタリングなどで譲渡する際に分割して利用することができます。
債権記録の失効
あまり考えられないことですが、電子債権記録機関が業務移転命令を受けることがあるかもしれません。
そのとき、業務移転命令において定められた期限内に電子債権記録業を移転することができなかった場合には、電子債権記録機関の記録原簿に記録されている債権記録は効力を失います。
しかし、記録原簿に記録された電子記録債権は、その権利の内容とする指名債権として存続することになります。
指名債権とは、債権者が特定している債権のことであり、ほとんどの場合は通常の債権と変わらないものです。

CF戦隊
仮に電子債権記録機関の運営が破たんしたとしても、債権が消滅することはないのだ!
まとめ
以上のことから、電子記録債権は、通常の売掛債権と同様に法的整備が行き届いており、安心して利用できることが分かったと思います。
従来の売掛債権になじみのある人にとって、まだ歴史の浅い電子記録債権を利用することは不安もあるかもしれませんが、安全に利用することができるのです。