
ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
試験で求められる原価計算の知識は役に立たない?

原価計算を的確に行うことは、簡単なことではありません。
日商簿記検定試験や公認会計士試験で求められる原価計算基準を理解している人でさえ、正しく原価計算ができないことが多々あるのです。
原価計算を資金繰りに活かしていくことは、原価について正しい知識を持ち、なおかつ経験がそこに加味されて、初めて可能となります。
試験で求められる原価計算の知識は原価計算基準が根拠となっているのですが、これは伝統的な理論であり古いものだからです。
時代にそぐわない部分を更新したこともありますが、それも1980年代のことです。
原価計算とは何者なのか?
多くの経営者は、経理担当者が学んだ原価計算の知識について、会社経営に役立てるためのものだと考えていると思います。
ところが、試験のために学習する原価計算の知識は、主に以下を目的としています。
- 財務諸表作成のため
- 価格計算のため
- 原価管理のため
- 予算管理のため
- 経営計画策定のため
1962年に原価基準が公表された時、旧大蔵省はこれら5つが原価計算の目的だと明言しています。
財務諸表作成のため
会社は、買掛先や銀行などの債権者のほか、出資を受けているならば出資者に対しても、財務諸表を公表する必要があります。
それに当たって、財務諸表に記載される損益と財務に嘘が紛れ込まないためにも、原価の集計を求めています。
制度会計では一定期間の損益を報告するものであり、期末時点で製造中である仕掛品や製品の在庫については、製造原価を期間原価とはみなしません。
したがって、期首と期末の仕掛品を加味して当期の製造原価、そして販売した製品の売上原価を計算することが必要となります。
財務諸表では、原価を製造原価と販管費に分類しますが、製造原価は期首と期末の在庫金額の調整によって計算し、販管費は当期の売上高と対応する金額を期間原価とします。
このことから、原価計算は財務諸表を正しく作成するものであり、その中で棚卸資産の評価をすることはあっても、それが主たる目的ではないということがわかります。
ここでは、外部の利害関係者のために原価計算を用いているのです。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
価格計算のため
これも、外部の利害関係者を目的とするものです。
会社が販売する商品の価格は、会社が価格を設定しているように考えがちですが、実際にはそうではありません。
購入者が買いたいと考える価格でなければ売ることはできないため、市場の需給バランスが価格を決めていると言えます。
したがって、市場性がない商品はお金が支払われません。
購入を検討する外部との関係の中で、合理的な販売価格を設定するためには原価計算が必要となります。
これも、原価計算が純粋に自社の経営のためのものとは言えない部分です。
原価管理のため
原価管理とは、経営を管理する立場にある人が、原価の維持や原価の引き下げなどを適切に行うことを指しています。
しかし、旧大蔵省の公表している見解によれば、原価維持を主要な目的としており、原価引き下げについては特に触れられていません。
原価維持とは、ある商品があった場合、その商品の材料や生産方法を一定に維持するために、標準原価を定め、その標準に近づけるためのものです。
同じ商品を同じように生産していくだけでは成長がなく、経営的にも好ましくないため、原価の引き下げを考える必要があります。
原価を引き下げるためには、製品を企画する段階で原価低減を図る原価企画、既に生産している製品について、材料や生産方法を改善することで原価低減を図る原価改善があります。
もし、原価管理が原価維持と原価引き下げの両方を対象としているならば、そのような原価管理のための原価計算は経営に役立つものとなるでしょう。
しかし、旧大蔵省の見解によれば、このような原価管理は原価の発生額をしっかりと記録し計算し、標準的な原価の水準と比較して、差がある場合には原因を分析したうえで能率アップにつなげることが目的であるとしています。
このことからも、あくまで基準における原価管理では原価維持を目的としており、原価引き下げは考えていないことが分かります。
また、原価計算基準では、直接材料費と直接労務費だけを原価管理の対象としており、間接費や販管費は原価管理を求めていません。
▼緊急で資金調達が必要ならファクタリング▼ ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
予算管理のため
次に、原価計算は会社の予算編成と予算管理を効率化するために必要だとされています。
予算を定めるためには具体的な中長期計画が事前に必要です。
そして、その中長期計画を1年間あたりで表示したものが年度予算となります。
計画を金額に置き換えて予算とする際には、原価計算が必要となります。
もし、原価計算の知識が誤っていたとすれば、計画を金額で置き換えて予算を立てたとしても、その予算で事業を進めていくことが困難となり、経営計画も失敗に終わることとなります。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
経営計画策定のため
経営にあたっては、中長期の経営戦略が必要であることは、皆さんもよくご存知だと思います。
その中で、設備投資や企業買収などといった重要な意思決定を伴う場合もあると思います。
そのための方策を検討するにあたり、最善の策によって進めていくためには、原価計算が欠かせません。
経営計画を設定するためには、現状における業績や財政、将来的に予測される変化などを踏まえて計画していく必要があるからです。
原価計算基準が指す原価計算とは?
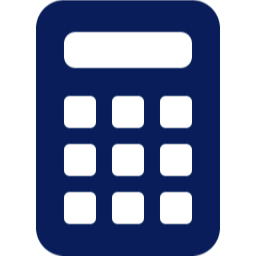 >
>
以上のように、旧大蔵省が見解では、原価計算基準は色々な目的があることが分かります。
しかし、ここで言われる原価計算とは、制度としての原価計算に過ぎないこともわかります。
財務諸表を作成し、原価を管理し、予算を管理するための制度として、原価計算を捉えているのです。
日商簿記検定や公認会計士試験で求められる原価計算の知識とは、あくまでも制度としてのものに他なりません。
経理担当者が、試験で求められる原価計算の知識を持っていたとしても、それがそのまま全ての会社に当てはまるものではありません。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
資金繰りに困っている会社の中には、原価計算に問題がありそうだという実感を抱いている会社もあるかもしれません。
しかし、経理担当者は一般的な原価計算の知識を活用して原価計算を行っているのですから、そこに問題があるとは考えないことも多いです。
一般的な原価計算の知識というものは、あくまでも制度としてのものに過ぎないのです。
多くの会社に必要となる知識ではあっても、多くの会社が資金繰りに役立てていけるとは限らないことに留意しておきましょう。
売上増でも赤字になるのはどうして?原価計算が役立っていないのかも・・・











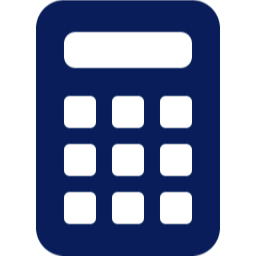 >
>


コメント