※本記事はプロモーションを含みます。助成金は、中小企業が積極的に活用していくべきものです。
特に、数ある助成金の中でも、多くの中小企業が有効活用しやすいものとして、キャリアアップ助成金がおすすめです。
色々な助成金の中から、どれを活用すべきか迷う人もいると思いますが、まずは本稿でまとめる基本情報を読んで、キャリアアップ助成金を検討してみてください。
助成金は中小企業向け!おすすめの助成金はコレ!

助成金は、大企業でも受給できるものですが、主に中小企業を対象とした仕組みとなっています。
このことは、各種助成金の支給額を見たとき、大企業よりも中小企業に手厚くなっていることからも、よくわかると思います。
本来ならば、大企業のほうが資金需要は圧倒的に大きいのですから、中小企業よりも大企業の助成額のほうが大きくなっても良さそうなものです。
しかし実際には、中小企業のほうが、助成額が大きくなっているのです。
また、助成金の目的は労働環境の整備や生産性の向上であり、延いては経済成長を促そうとしています。
大企業と中小企業を比較すれば、労働環境が十分に整備されておらず、生産性の低下に苦しんでいるのは間違いなく中小企業です。
ならば、政府が助成金の主な対象を中小企業と考えていることも、納得がいくでしょう。

CFイエロー
このように、中小企業だからこそ助成金を活用していくべきと言えるわ!
しかし、助成金は約50種類ほど設けられており、はたしてどれを活用すればよいのか、あまりピンとこない経営者も多いはずです。
色々ある中で、自社が受給できる助成金はどれであるか、特に自社に適した助成金はどれであるかについては、ケースバイケースです。
その都度税理士や社労士に相談するなどして選択していく必要があります。
しかし、助成金の中でも代表的なものについては、どの会社も等しく利用すべき、むしろ利用しなければもったいないものもあります。
その代表格と言えば、キャリアアップ助成金です。
キャリアアップ助成金は、ほとんどの会社が受給対象となるため、「自社に適した助成金は・・・」などと考えるまでもなく、まず利用して間違いない助成金です。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
キャリアアップ助成金の基本情報と利用すべき理由

なぜ、キャリアアップ助成金ならばどの会社でも利用すべきと断言できるのでしょうか。
それは、会社を経営していれば当然のように行う「採用」「賃金アップ」といった取り組みにあたって、受給できる助成金だからです。
「キャリアアップ」というからには、従業員のキャリア、すなわち職業上の地位をアップさせるものです。
ここでいう地位には色々な意味が含まれており、有期契約から無期雇用への転換、有期・無期雇用から正規雇用への転換といった地位向上のほか、賃金をアップすることなども含まれています。
- 創業したばかりで当分は社長が一人でやっていく
- そもそも個人事業主である
- 事業の規模が小さすぎて従業員を雇っていない
など、従業員を抱えていない会社では、キャリアアップ助成金を利用できません。
しかし、従業員が一人でもいる、あるいはこれから従業員を雇い入れていくという会社であれば、キャリアアップ助成金を利用できる可能性が高いです。
特に、政府はバブル崩壊後に増加を続けている、非正規雇用労働者を減らすことに腐心しています。
したがって、キャリアアップ助成金の支給対象となる色々な形態の中でも、特に正規雇用を増やしている会社には、手厚い助成金が支給されています。
もちろん、従業員の正社員化だけではなく、以下のように色々なコースが設けられています。
キャリアアップ助成金のコースは全7種類

キャリアアップ助成金のコースは、全7種類となっています。
正社員化コース
上記でも述べた通り、これは有期契約労働者を無期雇用労働者に転換したり、有期・無期を問わず正規雇用に転換したりすることで、助成金を支給するコースです。
このほか、「多様な正社員」への転換も助成金の対象となっています。
多様な正社員とは、一般的な正社員とは異なり、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員を指すものです。
賃金規定等改定コース
これは、有期契約労働者等の賃金規定を改定し、賃金をアップした場合に助成金を支給するものです。
政府の政策により、最低賃金の引き上げが毎年のように行われていますが、政府に先んじて自発的に賃金をアップすれば、助成金の支給対象となります。

CFレッド
黙っていても賃金は上がるのだ!少し早めに行動を起こして、助成金を受け取ったほうが賢明だよ!
健康診断制度コース
会社が健康診断の実施を義務付けられているのは、「常時使用する労働者」と定められています。
このため、期間の定めがない契約によって働いている無期雇用・正規雇用の従業員に対して、健康診断を実施する必要があります(一部例外あり)。
有期契約労働者には、健康診断を実施する義務はありません。
しかし、労働環境整備の一環として、有期契約労働者も健康診断を受けられるよう、新たに制度を規定した後に4人以上実施した会社に対して、助成金が支給されます。
賃金規定等共通化コース

CFブルー
通常、有期契約労働者は賃金が低くなっているものだ。
ベースが低めの賃金で設定されていることから、正規雇用労働者と同じ仕事をこなした場合でも、有期契約労働者には低い賃金しか支払われません。
そこで、有期契約労働者が正規雇用労働者と同じ仕事をこなした際に、その職務に応じた賃金を支払うよう、賃金規定を共通化し、実際に適用した会社では、助成金を受給することができます。
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
ファクタリングについての記事はこちら

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
諸手当制度共通化コース
有期契約労働者は、正規雇用労働者と比較して、適用される手当が少なくなっています。
正規雇用労働者ならば手当を支給される場合でも、有期契約ゆえに手当が受け取れないこともあるものです。
そこで、正規雇用労働者と同じように手当を受けられるように、諸手当制度を共通化し、適用した会社では、助成金を受給することができます。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労働時間が短い有期契約労働者は、社会保険に加入していないのが普通です。
これにより、会社が社会保険料を負担する必要はありません。
有期契約労働者が社会保険に加入する場合には、
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 学生ではないことに加え、1ヶ月の所定内賃金が8.8万円以上であること
が必要となります。
労働環境の整備に伴って、社会保険の適用拡大措置をとる場合、加入条件を満たすために給料を増やす必要があります。

CFイエロー
そこで、基本給の増額の割合に応じて、助成金を受給することができるよ!
短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の中には、会社が必要とする時間だけ働いており、もっと働きたいと思いつつも働けていないことがあります。
このような労働者が働きやすい環境を作るために、週所定労働時間を5時間以上延長し、なおかつ社会保険を適用した会社では、助成金を受給することができます。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
使いやすいのは正社員化コース

全部で7種類あるキャリアアップ助成金の中でも、多くの中小企業にとって利用しやすいのは「正社員化コース」です。
正社員化コースは、助成金の中でも特に受給額が大きく、要件を満たせば最大で1440万円(有期契約から正規雇用へ、年間の上限である20人を転換し、生産性の向上も見られる場合)もの助成金を受給することができます。
受給額は、以下のようになっています。
さらに、助成金によっては一度きりしか使えないものもある中で、正社員化コースは毎年継続して利用することができます。

CFレッド
急成長によって毎年複数の人材を雇い入れている会社などでは、かなりの恩恵に浴することができるよ!
正社員化コースを利用するにあたっては、従業員をどのように転換するのか、生産性の要件は満たせるかどうかを考え、受給額を最大化できるように、計画的に利用していくことが大切です。
キャリアアップ助成金を受給できる会社の条件

なお、キャリアアップ助成金を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
雇用保険に加入していること
助成金の財源は雇用保険料であるため、雇用保険に加入している会社以外は受給することができません。
キャリアアップ計画を作成していること
キャリアアップ計画とは、キャリアアップの対象者、目標、期間、目標達成のための措置について、対象となる有期契約労働者の意見を反映したものです。
キャリアアップ助成金を利用するためには、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受ける必要があります。
当然、キャリアアップ計画期間中に、キャリアアップに取り組んでいる必要があるよ!
キャリアアップ管理者がいること
キャリアアップ管理者とは、有期契約労働者のキャリアアップに取り組むために「必要な知識と経験」を持っている人のことです。
会社が雇用している従業員の中から選びますが、事業主、役員、人事部長などがキャリアアップ管理者になるのが普通です。
コースごとに必要となる書類を整備していること
それぞれのコースの処置によって、必要となる書類が異なります。
書類をきちんと整備していることも、受給の条件となっています。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

まとめ
助成金制度の中には、活用すべきものがたくさんあります。
中でも、キャリアアップ助成金は様々な中小企業で活用可能です。
受給額を最大化する工夫の余地も大きく、使い方次第で非常に役立ってくれるものです。
活用の際には、まずは顧問税理士に相談し、人材投資が生産性アップにつながる計画を立てることがポイントです。慎重かつ積極的に利用してください。
中小企業が真っ先に検討すべき助成金はこれだ!キャリアアップ助成金の基本情報



















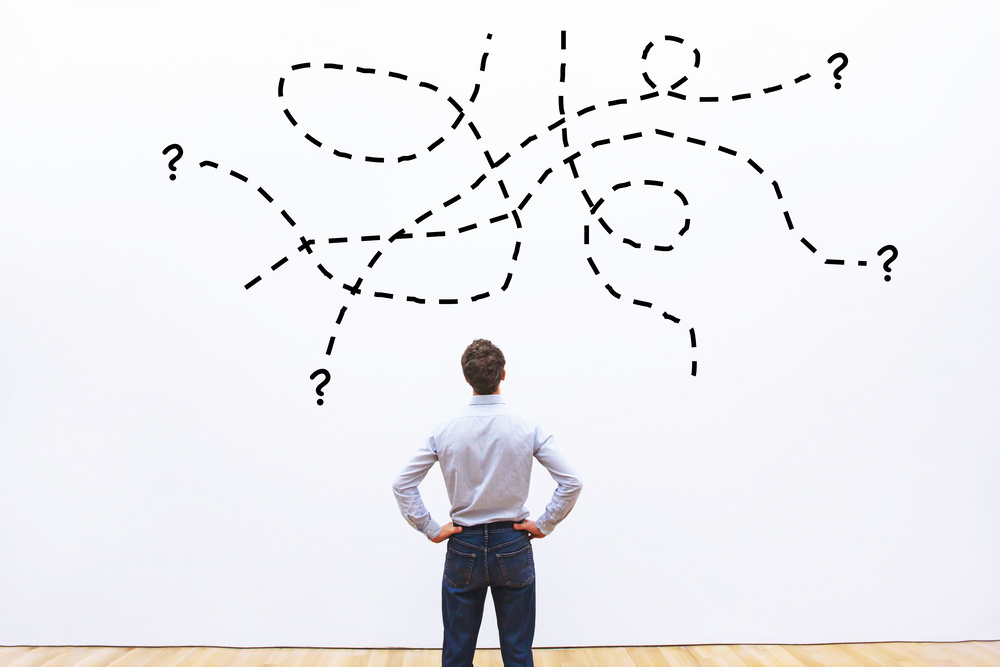
コメント