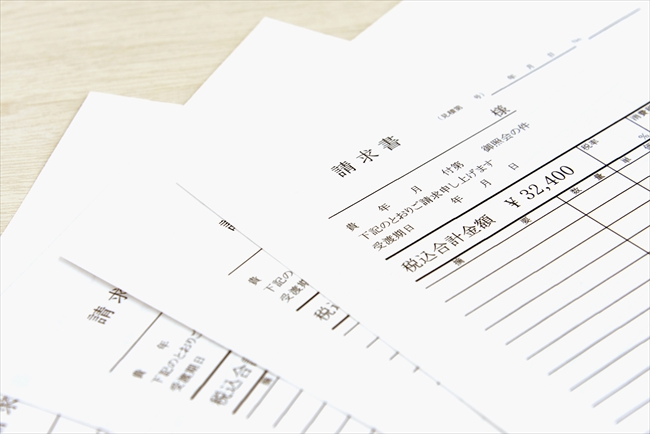ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
でんさいについて
でんさいは、全国銀行協会が設立した、電子決済ネットワークを持つ株式会社です。
電ペイがみずほ銀行独自のサービスで相互性がないのに対し、でんさいは全銀行参加型となっているので、銀行が違っても取引可能です。
金融機関を通してでんさいのネットワークにアクセスできるので、従来通りの決済システムをそのまま利用できます。

CFイエロー
手形のように毎回発行する手間や印紙代もかからないので大幅なコスト削減が可能よ!
でんさいは電子債権ですから、取引や記録は全てネットワーク上で行います。
このため、手形のように紛失や盗難とリスクも大幅に軽減できるのが最大のメリットとなります。
保管するにはパソコンのセキュリティ対策は必要ですが、それさえしっかりしていれば保管や管理に欠かすコストも削減できます。
さらに分割譲渡や分割割引ができるため、資金繰りが効率よく行えるのです。
資金繰りに頭を悩ませる企業にとっては、メリットが多い方法です。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
電ペイの仕組み

みずほ銀行が独自に導入している決済サービス、電ペイについてもう少し掘り下げます。
正式名は、みずほ電子債権決済サービスといいますが、電ペイの愛称で呼ばれています。
みずほ銀行には、電ペイが導入される前から、一括決済スキームという手形レスのサービスがありました。
電子債権を活用することで、一括決済スキームより利便性が高まっています。

CFブルー
電ペイでは決済サービスと買取サービスを行うよ!
決済サービスは、支払い企業に対して電子記録債権という選択肢を与えます。
支払い企業は電子記録債権発生と決済処理を行いますが、手形に比べて事務効率が格段にアップします。
納入企業は、電子記録債権の期日になれば、場所にかかわらず全国の預金取り扱い金融機関の口座から資金を受け取ることができます。
一方買取サービスは、債務者が発生させた電子記録債権を、債権者は支払期日前でも必要に応じて、全額または一部だけ分割で資金化することができます。
債務者がみずほ銀行に依頼し、みずほ銀行が期日決済を行うと、ダイレクトに債権者に渡すこともできます。
一旦債権買取会社に売却し、債権買取会社が譲受人に売却することもできます。
これらの記録はすべて、記録請求依頼により、請求事務代行をするみずほファクター株式会社により、電子債権記録機関となる、みずほ電子債権記録株式会社で記録されます。
すべての手続きが完了すると、みずほ電子債権記録株式会社から、みずほ銀行に決済データが送られます。

CFレッド
ただし、これらは全てみずほ銀行が独自に導入している、電ペイを利用した場合のことだ!
利用には審査がありますので、審査に通過しなければ電ペイの利用はできません。
利用にあたり、債務者にも債権者にも所定の手数料を支払う必要が出てきますが、双方にメリットはあります。
債務者のメリットは次の通りです。
- 手形に比べて発行に伴う事務の軽減と合理化
- 手数料や印紙税の削減
- 盗難や紛失のリスク軽減
- 二重譲渡リスクの軽減
債権者のメリットは次のとおりです。
- 資金調達の選択肢が増える
- 期日前に資金化できて割引も可能
- 資金調達にかかるコストも大幅に削減
コストがかかっても、低利での資金調達が可能になるのはメリットです。
債権者が資金を受け取る際、他の金融機関を含む既存の口座が利用できるので、わざわざ新規に口座を開設する手間もかかりません。
2次債権者への譲渡も可能となり、債権の一部のみの譲渡もできます。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼

資金繰りが悪化する理由

中小企業の多くが資金繰りに頭を悩ませています。
なぜ資金繰りが悪化するのでしょうか?
中小企業の資金繰りが悪化する理由には、それぞれの企業事に理由は異なります。
しかし、統計として見るといくつか共通しているところもあります。
資金繰りが悪化する原因となるのは、主に6つの理由が考えられます。
- 売掛債権が多い
- 在庫が多い
- 必要以上の設備投資
- 収益減少
- 売上債権と支払い責務のバランスが悪い
- 費用ばかり増加していく
商談が成立しても、売掛金や手形などの売上債権が増えるとすぐに現金化できないことが多いでしょう。

CFイエロー
至急資金が必要という場合は資金繰りがうまくいかないわ。
売上債権が多いのは、売上が伸びている証拠ですが、売上高と売上債権のペースが違えば効率は悪くなってしまいます。
取引先との商談を成立させても、取引先に資金力がないと売掛金の回収に不安が出てきます。
売り上げを伸ばすためのことでも、結果的に自社にとってマイナスとなってしまうこともあるのです。
売上高が増加すれば企業にとってメリットに思えますが、在庫も増えます。
売上高と在庫のバランスが取れていれば、資金繰りが悪化するリスクは軽減されます。
しかしバランスが悪いと、運転資金だけが増えてしまい、結果的にマイナスとなってしまいます。

CFブルー
バランスという意味では、売上債権と支払い責務の入金も共通しているぞ!
バランスが取れていれば不安はありませんが、一旦バランスが崩れると資金繰り悪化の原因となってしまいます。
あまりにも売上金回収までの期間が長い取引は、先を見越して慎重に判断することが大切です。
設備は整っている方が安心して仕事ができるイメージですが、設備投資にかけた分を回収できる見込みがないような場合は、考え直す必要性がでてきます。
ただし一旦設備を整えてしまうと、どうにもできないので導入前の検討が重要です。
収益が減少すれば、手元に入る現金も減少しますので、当然資金繰りが悪化します。
この場合は対策するにも限界があるでしょう。

CFレッド
企業全体で収益力を高める努力と工夫が必要になるよ!
費用については必要経費などもありますが、支出が増えれば資金も減るのでその影響で資金繰りが悪化しやすくなります。
無駄な経費を削減することも、資金繰り悪化を防ぐための一つの方法です。
資金繰りが悪化している場合、それに気づくのが早いほどダメージを最小限に抑えることができます。
早期発見のためには、日頃のリスク管理が重要となってきます。
▼【最短即日】手持ちの請求書を現金化▼
 ▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

その他考慮すべき資金調達方法

資金の金額もピンキリですが、資金調達方法にはファクタリングやでんさい以外にもまだいくつかの方法があります。
その方法について種類ごとに紹介します。
ファクタリングやでんさい以外の資金調達方法としては
- 金融機関から融資を受ける
- 投資家から出資を受ける
- 家族や知人から借金する
- 社債を発行する
- 補助金や助成金を受ける
- ノンバンクから借り入れをする
などがあります。
選択肢は豊富ですが、それぞれにメリットがあればデメリットもありますので、慎重な見極めが大切です。
金融機関から融資を受ける
金融機関から融資を受ける場合は、低金利なのが魅力です。
しかし、審査はかなり厳しく行われますので、条件によっては融資が受けられない可能性があります。
ただし審査に通れば、比較的高額な融資を受けられるのは大きなメリットです。
審査に通る条件もいくつかありますが、事業計画書や決算書など必要書類はあらかじめ準備しておくことが大切です。
ノンバンクから借り入れをする
金融機関からの融資では、ノンバンクからの借り入れも可能です。
ただし、銀行からの融資を考えている場合、ノンバンクからの借り入れがあるとマイナス要素になります。
審査も銀行に比べてゆるいと言われていますし、融資までの期間も短いというメリットはあります。
しかし、金利が高めですし、銀行からの融資が受けられなくなる可能性があることを覚えておきましょう。
家族や知人から借金する
家族や知人からお金を借りることができれば、金融機関からの融資より気は楽です。
しかし、よほどの資産家でもない限り、借りられる金額には限界があります。
ただし事業がうまくいかなくなった場合は、身近な人ほど揉める原因となります。
いかなる理由があっても、借金したら返済義務があることを十分理解し、返済できる範囲で借りることが大切です。
投資家から出資を受ける
投資家からの出資を受ける場合、出資は借金とは違うので返済しなくていいのが最大のメリットです。
しかし投資家も自分にメリットがなければ簡単には出資してくれません。

CFレッド
返済されないお金を出す以上は、経営などに口出しをしてくるぞ!
出資額にもよりますが、自分の出資比率を51%以上に保っておくことで、乗っ取りなどは防げます。
社債を発行する
社債の場合は社債を買ってくれる一般の人を探さないといけません。
これは投資家にも共通していますが、対象となる人が簡単に見つからないのがデメリットです。
補助金や助成金を受ける
補助金を受ける場合、後払いになるのでそれまでの資金調達は自分で行います。
全額補助されることはなく、最大でも出資額の50%となります。