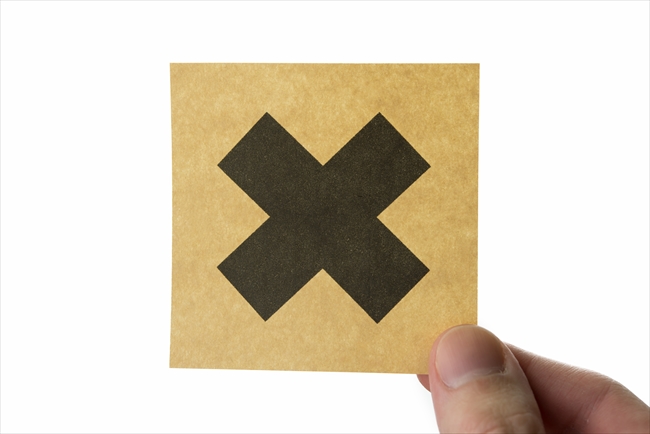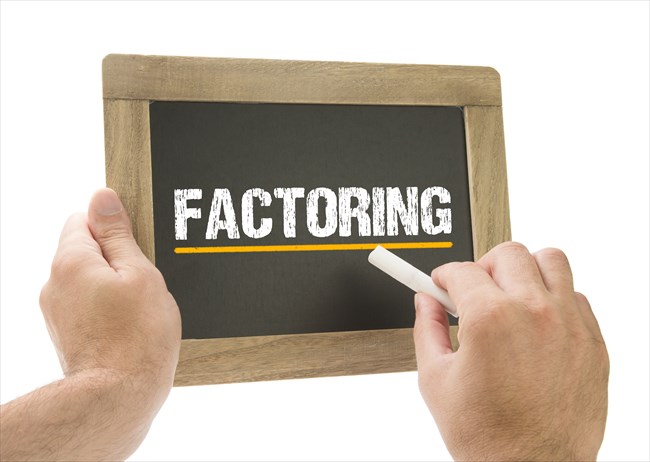ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
手形と印紙

取引の規模によっては、手形に記載される金額は相当に大きくなるものです。
手形を降り出す際には、10万円未満の手形ならば印紙は不要ですが、10万円以上になると印紙が必要です。金額が大きくなるほど印紙代も大きくなるのです。
これは印紙税法で決められているものですから、必ず貼らなければなりません。
税額は200円から20万円まであり、負担するのは手形の振出人です。
手形の支払い

手形を受け取った企業は、支払い期日まで待っておき、支払い期日が来ると銀行に呈示します。
指名債権ならば支払い期日に債権者が振り込みによる決済にをするものですが、なぜ手形の場合は受取人が銀行に呈示しなければならないのでしょうか。
それは、そもそも手形の性質というものが、後述する裏書譲渡などによって流通することを想定しているものだからです。

CFイエロー
つまり、本来の売り手から第三者へ、第四者へと手形の譲渡が行われていれば、振出人は誰に振り込んだらいいのかわからなくなるよ!
そこで、振出人は銀行の当座口座に決済代金を振り込んでおきます。
支払い期日の時点で手形を持っている人が銀行に呈示することによって、支払いを受けることができるという仕組みになっているのです。
銀行は、持ち込まれた手形の現物を確認し、間違いなく現時点での債権者であることを確認してから支払いを行います。これによって、トラブルなく代金の授受が行われるのです。
この一連の流れを、手形交換と言います。
手形の裏書譲渡

ここまでは、買い手企業側の都合を元に解説してきました。
しかし、本稿を読んでいる人の多くは、手形の活用方法を知りたいと考えている人であり、いわば売り手企業側、債権者側の人たちでしょう。
買い手の都合によって支払いが先延ばしになるのは、売り手にとっては都合の悪いことです。
なぜならば、商品を納入したにもかかわらず、その代金が入って来るのが数ヶ月先のことになるからです。
それまでは売り上げを活用できない期間があるわけです。

CFイエロー
それどころか、実質的にはマイナスを抱えた期間ともいえるわ。
手形の発生のためには商品の納入があり、商品の納入のためには商品の仕入れや在庫管理など、いろいろなことにコストがかかっているからです。
それらのコストを負担して、販売にこぎつけたとしても、それを回収するのは数ヶ月先のことなのですから、資金繰りが厳しくなることも少なくありません。
掛売りというものはごく一般的に行われているものです。
しかし、支払いが先送りになること自体は仕方がないにしても、手形サイト(手形の決済期日までの期間)があまりにも長くならないように契約を交わすなどの努力は必要となるでしょう。
しかし、手形サイトの短縮にも限界がありますし、売り手は買ってもらう立場にありますから、ある程度の譲歩も必要となります。

CFレッド
資金繰りを大幅にラクにするほどの短縮はありえないのだ!
そのような場合、支払い期日前の手形をどうにかして活用したいと考えるのが人情でしょう。
その手形には、支払い期日になれば額面金額を受け取れるため、その金額同等の価値を持ったものです。ですから、活用の道もあります。

CFイエロー
活用方法には複数あるけど、その代表的なものが裏書譲渡よ!
裏書譲渡とは、その手形を譲渡することによって、額面金額分の決済に活用できるというものです。
裏書譲渡の例を見て見ましょう。
自社が取引先Aに対して、1000万円の商品を販売しました。
その代金支払いのために1000万円の手形を振り出されていました。支払い期日は平成29年5月20日でした。
手形の振出日は平成29年2月20日ですから、3ヶ月後でなければ1000万円の商品代金を受け取ることはできません。
さて、これより前に自社では取引先Bから1000万円分の商品の仕入れをしており、その支払い期日が平成29年3月20日でした。
自社ではそのための資金繰りをしたのですが、3月20日までに現金を用意することができませんでした。
支払いが遅れてしまえば、取引先や業界全体からの信用を損なうことになり、今後の経営に響くため、何としても支払わなければなりません。
そこで、取引先Aが振り出した1000万円の手形を取引先Bに譲渡し、1000万円の清算を行いました。

CFブルー
このように、受け取った手形を支払いに充てることを、手形の譲渡と言うよ!
手形の譲渡に回数制限はなく、手形の支払い期日までの期間であれば、取引先Bも取引先Cに譲渡することができます。
手形を譲渡するためには、手形の裏面に譲渡人の署名をし、それに続いて譲受人の名前も記載しなければなりません。
手形の裏面に必要事項を記入して譲渡が行われることから、これを裏書譲渡と言います。
裏書のメリットは、何と言っても支払い期日前に手形を活用できることです。
裏書をすることによって、手形の支払い期日を待たずに支払いなどに利用することができるのは、現金をあまりもっていない企業にとってはありがたいことでしょう。
しかし、裏書にはデメリットもあります。それは、裏書には責任が伴うということです。
手形を裏書譲渡した時、当然ながら譲受人はその手形から支払い期日に現金が得られることを期待して、譲渡を受けています。
もし、支払い期日に手形の振出人が支払うことができなかった場合には、譲受人も現金を受け取ることはできません。
このとき、譲受人は損をするのかというとそうではなく、譲渡人に対して支払いを請求できるようになっています。
つまり、手形を裏書譲渡するということは、いわば
「この手形を譲渡しますから、決済の代わりにしてください。もちろん、この手形が支払い期日に支払われることは私が確約します」
という約束をしているのです。
そのため、手形の振出人が支払わなければ、譲渡人は譲受人に対して責任を負うのは当然のことです。

CFイエロー
このような暗黙の了解があるからこそ、譲受人は安心して譲渡を受けることができるのよ!
もしこのような裏付けがないならば、そもそも譲受人は振出人のことを全く知らないこともあるのですから、裏書譲渡など受けようとは思わないでしょう。
この暗黙の了解があり、また譲渡人への信用があるからこそ、裏書譲渡が行われます。
もっとも譲渡人をそれほど信用していなかったとしても、振出人が有名企業や大企業であり、手形そのものの信用力が高いと判断した場合には、裏書譲渡を受けることでしょう。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
裏書譲渡のデメリット
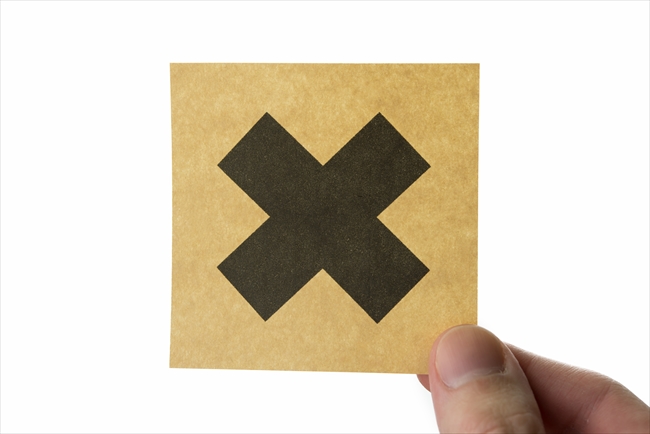
このように、裏書譲渡には責任が伴い、手形が不渡りになれば遡求を受けるというデメリットがあります。
不渡りの理由にも色々ですが、多くの場合には当座預金の残高が不足している(一円でも不足していれば支払いは行われない)というものです。
この他には、納品された商品に欠陥があるとして相手が支払いを拒否していることもあります。
手形の不渡りは、基本的には起こるものではありません。
なぜならば、不渡りを6ヶ月以内に2回以上だしてしまうと、振出人は銀行停止処分となり、その後2年間は当座勘定取引と貸出取引の停止を受けることになります。
そうなってしまえば、手形による取引をすることはできなくなります。
売掛金取引ならば制度上の問題はないため可能ですが、銀行停止処分を受けているような企業と売掛金取引をしたいと考える企業などありません。
ですから、銀行停止処分を受けた会社は、経営を継続して取引をするためには現金取引しかできなくなり、事実上は経営の継続が困難にります。つまり倒産です。

CFレッド
手形が不渡りになり、振出人が倒産すればそれで終わりではないぞ!
裏書譲渡をしていたならば、譲受人から譲渡人へと遡求が行われるからです。
譲渡人はさらに振出人に遡求することができますが、振出人がまだ倒産していなかったとしても、不渡りを出した経営内容なのですから、取り立ては難航する可能性が極めて高いです。
ですから、多くの場合は譲渡人本人が責任を取ることになるのです。
ちなみに、裏書譲渡が連続して行われている場合には、遡求も連続して行われることになります。
例えば、このように連続して遡求されるのです。
- 譲渡時:「振出人→自社→取引先B→取引先C→取引先D」
- 不渡り時:「取引先D→取引先C→取引先B→自社→振出人」
以上のことから、裏書譲渡は手持ち現金がない時に支払いなどに活用できるというメリットがある反面、手形が不渡りになった場合には遡求を受けて弁済しなければならないというデメリットがあります。
振出人に十分な支払い能力がある場合には、裏書譲渡を活用するのも良いでしょう。
しかし、振出人に支払い能力がないにもかかわらず裏書譲渡をすると、結局は遡求を受けることとなってしまい、何の意味もなくなってしまうのです。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
裏書譲渡以外の方法はない?
さて、ここで疑問になることがあります。
それは手形の使い道は「支払い期限まで待って手形交換をして代金を受け取る」か、「支払い期限前に裏書譲渡をおして決済に使う」しかないのかということです。
もしそうであるならば、少し利用の幅が狭いと言えます。
しかし、安心してください。手形にはこの他にも使い道があります。
それは、手形割引とファクタリングです。
手形割引とは?

手形割引とは、支払い期日前の手形を資金化することです。
裏書譲渡では決済にしか使えなかったのですが、手形割引では手形を現金に換えることができます。
例えば下記のように様々な用途に利用することができます。
- 買掛先への決済だけ
- 従業員の給料の支払い
- 銀行への返済や
- 必要な備品の購入
裏書譲渡と比較すれば、かなり利便性が高い方法であると言えるでしょう。
手形割引をするためには、銀行か手形割引業者に手形割引を依頼しなければなりません。
どちらに依頼するべきであるかということは、依頼する会社が置かれている状況にもよるでしょう。
早急に現金化をしたければ手形割引業者
銀行では審査が慎重であるため、実際の資金化までに時間がかかります。
場合によっては一週間程度かかることもありますが、手形割引業者では即日で資金化できることもあります。
少しでも良い条件で取引を希望するなら銀行
銀行では手形割引を融資の一種として行なっているため、審査は非常に慎重です。
ただし一旦割引が実行されるとなれば、信用は確保されたようなものです。そのため、通常の銀行融資と同様に低い利率での割引が可能です。
これに対し、手形割引業者では手形割引を手形の買取として行なっているため、手形そのものの信用力に応じて割引率を設定しています。
また、銀行ほど原資に余裕がなく、割引料が重要な収入源となっています。
手形の信用力が高い場合でも銀行よりは割引料が高いことも多く、信用力が低い場合にはかなり高い割引料を取られることがあります。
担保がない場合の依頼先

CFイエロー
担保がないならば、手形割引業者に依頼するべきよ。
上記の通り、銀行は手形割引を融資の一種と考えているため、手形割引の依頼者に対して審査を行います。
決算書などから審査するだけではなく、不動産や預金などの担保が求められます。これに対して、手形割引業者では融資ではなく手形の買取と考えるため、担保は不要です。
逆に言えば、担保が用意できるならば、銀行で割引をしたほうがお得です。
以上のように、会社が置かれている状況によって、手形割引の依頼先は変わってきます。
手形割引のデメリット

しかし、手形割引にもデメリットがあることを知っておきましょう。
割引料がかかる
まずは、割引料がかかることです。
手形割引の際の割引料は、銀行では1.5〜5.5%程度、手形割引業者では3.0〜20.0%程度となります。
裏書譲渡ならば、額面金額をそのまま決済に利用することができますが、手形割引では割引料の分だけ目減りすることになります。
そのため、手形割引は銀行に依頼するのがおすすめです。
ただし手形割引業者に依頼する場合には、信用力の高い手形割引に限定するなどすれば、それほど大きく目減りすることはなく資金繰りにも役立ちます。
特に、銀行での割引が可能なのであればそうすべきです。
銀行はあくまでも依頼主に対して審査を行い、手形の信用力は考慮せずに低い割引料での割引を行います。
そのため信用力が低めの手形でも、十分に資金調達に役立てることができる可能性があるのです。
しかし、手形割引業者では、信用力の低い手形にはかなり高い割引料を適用します。
20%の適用となれば、1000万円の手形が800万円に目減りすることになります。

CFブルー
割引料だけを考慮すると、銀行での割引の方が好ましいのだ!
不渡りの場合には全額遡求を受ける
さらに、デメリットは割引料によって目減りするだけではありません。
手形割引の際には、銀行や手形割引業者に手形を譲渡することになりますから、これも裏書譲渡の一種です。
ということは、手形が不渡りの場合には遡求を受けるということです。
これは大きなデメリットであり、この点に関して手形割引は通常の裏書譲渡より劣っていると言えます。
通常の裏書譲渡では、額面金額をそのまま決済に利用し、手形が不渡りになれば額面金額の遡求を受けます。
一方、手形割引では、額面金額から割引料が差し引かれ、しかも手形が不渡りになれば額面金額の遡求を受けます。
つまり、手形割引業者に依頼し、1000万円の手形を20%で割引して800万円を受け取り、その手形が不渡りになれば1000万円の支払いを請求されるのですから、200万円の割引料がそのまま損失となるのです。
手形割引業者に依頼した場合
- 依頼時:1000万円の手形を20%で割引→800万円の受け取り
- 不渡り時:1000万円の支払い→200万円の損失
これが銀行ならば、1000万円の手形を3%で割引して970万円を受け取り、その手形が不渡りになって1000万円の請求をされれば、30万円の損失となります。
銀行に依頼した場合
- 依頼事:1000万円の手形を3%で割引→970万円の受け取り
- 不渡り時:1000万円の支払い→30万円の損失

CFレッド
この意味からも、不渡りに備えるならば、銀行に依頼しておいた方が無難だ!
これらのデメリットを踏まえれば、手形割引を利用する際には、できるだけ銀行を利用して安い手数料で割引するべきであると言えます。
しかし、自社の信用力が低い、担保を持っていない、早急な資金調達が必要であるなどの場合には、手形割引業者に依頼するほかありません。
その際には、できるだけ信用力の高い手形を割引して割引料を抑える、不渡りに備えて弁済を分割できる業者を選んでおくなどの工夫をしましょう。
このような工夫ができれば、手形割引業者を利用して便利に手形割引することも可能です。
ファクタリング
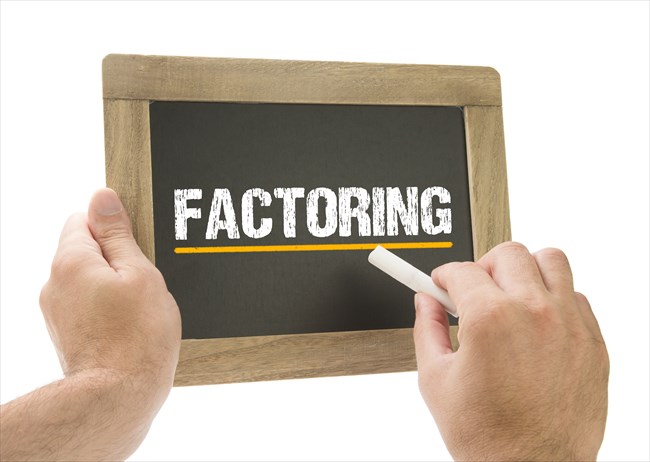
次に紹介する方法は、ファクタリングです。
ファクタリングとは、自社が保有する手形をファクタリング会社に買い取ってもらうことで資金化することです。
手形割引のように、ファクタリングを依頼するにはファクタリング会社に買取料を支払う必要があります。
銀行に手形割引を依頼するよりも手数料が高くなることが多いのですが、ファクタリングには手形割引よりも優れているところがあります。
それは、ファクタリングした手形が不渡りになったとしても、弁済を求められることがないということです。

CFイエロー
ファクタリング会社と契約を結ぶ際に、基本的には償還請求権放棄での契約になっているからよ!
償還請求権とは、売掛先が倒産するなどして手形が不渡りになった時、弁済を請求する権利のことです。
この権利を放棄した上でファクタリング契約を結んでいるということは、不渡りの際にはファクタリング会社自身がリスクを負ってくれるということです。
このことから、ファクタリングは手形割引とは異なり、不渡りの際のリスクをファクタリング会社に移転できる機能も持っているということができます。
もっとも、償還請求権放棄での契約は一般的なものですが、契約の形態としては償還請求権留保での契約も可能となっています。
償還請求権留保の方が手数料が低いため、信用力が十分にある手形をファクタリングする場合には、償還請求権留保でファクタリングして手数料を低くするということも可能です。
しかしながら、償還請求権放棄で契約したいと思っていたのに「契約内容を十分に確認しなかったために、償還請求権留保での契約になってしまった」などということがないように注意したいものです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

ファクタリングの流れ
ファクタリングによって手形を資金化するためには、以下のような流れで行います。
- 取引先に商品を販売し、手形を受けとる。
- ファクタリング会社に申し込みを行い、手形の信用力を審査してもらう。審査の結果、買取料が提示される。
- 見積もり内容に納得したならば、ファクタリング契約を結ぶ。
(この時、償還請求権をどうするかに注意する。契約が成立したら、手形はその時点でファクタリング会社に譲渡される)
- ファクタリング会社から自社に、買取代金が支払われる。
- 後日、支払い期日になるとファクタリング会社は銀行に手形を呈示し、代金を受け取る。
(不渡りの場合にも遡求は行われない)
このような流れで行われます。
ファクタリングのいろいろなメリット

- 手形を資金化できたり
- 償還請求権放棄での契約によって不渡りの際のリスクを移転
先にお伝えしたようなメリットの他、ファクタリングにはまだメリットがあります。
財務内容の改善
ファクタリングによって手形を資金化すれば、手形の額面金額によってはまとまった資金を調達することができます。
償還請求権放棄での契約であれば、万が一不渡りになっても弁済する必要はないため、調達した資金は自由に使うことができます。
この時、銀行からの借入金の返済や買掛金の決済などにも資金の一部を回せば、財務の圧縮につながり財務内容が良くなります。
売掛債権回転率・売掛債権回転期間の改善
また、償還請求権放棄で手形が譲渡されると、バランスシートにおける「受取手形及び売掛金」の額、つまり売掛債権が減少することになります。
これは、売上は変わらずに売掛債権額が小さくなるということですから、売掛債権回転率や売掛債権回転期間の改善にもつながります。
売掛債権回転率や売掛債権回転期間は、企業の経営効率を図るための重要な指標となるため、銀行や取引先からのイメージが良くなります。
手形割引では、不渡りの際に遡求されることから、たとえ銀行や手形割引業者に譲渡したとしても、それは弁済の可能性があるものです。
そのため、バランスシートの売掛債権額が減少したことにはならないため、財務内容の改善には効果がありません。

CFイエロー
このように、ファクタリングには「資金調達・リスクマネジメント・財務内容の改善」に効果があるよ!
また、手形をファクタリングして完全に譲渡してしまえば、手形を管理したり、代金を受け取るために銀行に持ち込んだりする必要はなくなります。
そのために必要な手間やコストが不要となれば、経営資源の有効活用にもつながります。
まとめ
手形を活用するためには、裏書譲渡や手形割引といった方法があります。
しかし、これらの方法は不渡りの際には責任を取らなければならなかったり、費用がかかってしまうというデメリットがあります。
そのため、信用力が高く不渡りの可能性が低い手形のみ活用する、手形割引の場合には極力銀行に依頼して割引料の削減に努めるなどの工夫が求められます。
もう一つの方法としては、ファクタリングによる資金化があります。
ファクタリングも手数料はかかるものの、不渡りの際にも責任を取る必要がありません。
そのことから、単に資金調達手段としてだけではなく、リスクの移転のために利用したり、財務内容の改善のために利用したりすることもできます。
これらのいずれの方法がよいのかということは一概には言えず、各企業が置かれている状況にもよるでしょう。
そのため、それぞれの方法の特徴をよく理解し、その時々で最も有効な手段を選択できるようにしておきましょう。