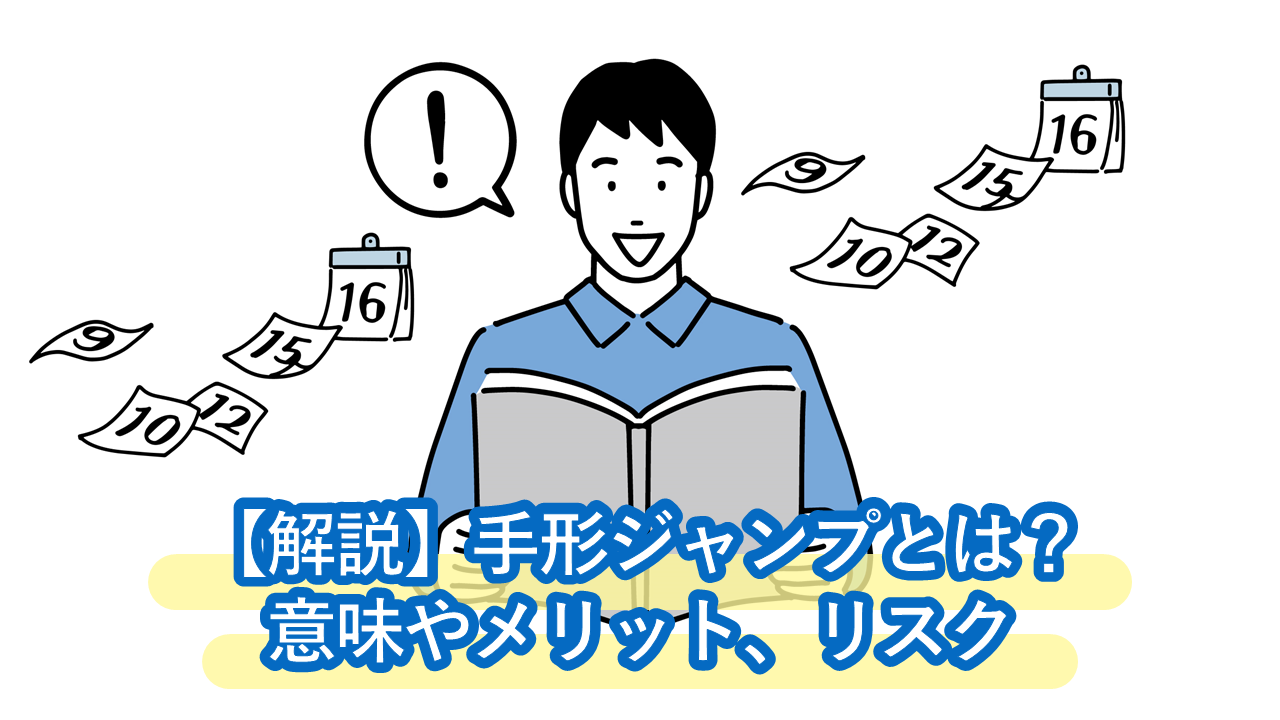
手形ジャンプの依頼があった時は、そのリスクについてきちんと把握しておくことが大切です。
基本的に手形ジャンプの引き受けはリスクのある行為です。
安易に引き受けることがないようご注意ください。

手形ジャンプとは?
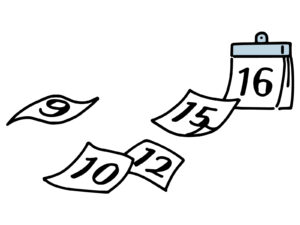
手形ジャンプとは、約束手形の支払期日に支払いができないときに、支払期限を延ばす方法です。
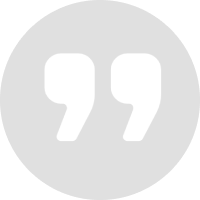
約束手形の支払期日に決済が困難になった際、手形支払先への支払いを延ばすこと。
交渉は個別に行われることが多く、一般的には公表されない。
資金繰り悪化が原因の場合が多く、与信上では要注意事項のひとつ。
引用:東京商工リサーチ
手形ジャンプは取引先ごとに個別に行われ、交渉の事実が公表されることはありません。
なお、具体的な延長方法は2パターンあります。
▼手形ジャンプの方法
いずれの方法にせよ、経営者にとって取引先からの手形ジャンプのお願いは資金繰りを悪化させる原因になります。
手形ジャンプを承諾すると、手形の支払期日は延長され、現金の入手が遅くなります。
リスク上の観点だけでなく、資金繰りの観点からも、手形ジャンプは贔屓にしている取引先であっても安易な承諾は避けるべきでしょう。
▼おすすめファクタリング比較表
※一部、ファクタリングとは異なるサービスも紹介しています
| アクセルファクター | ベストファクター | BestPay 注文書ファクタリング | CoolPay | QuQumo | 支払い.com (請求書後払いサービス) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 2%~ | 2~20% | 5%~ | 問い合わせ時確認 | 1%~ | 一律4% |
| 入金スピード (最短) | 即日 5割以上が即日入金 | 即日 | 翌日 | 即日 | 最短2時間 | 最短1日後の 振込に対応 |
| 利用可能額 | 30万〜無制限 | 30万円~1,000万円 | 100万円~3億円程度 | 初回15万円~ | 金額上限なし | 1万円以上~ |
| 手続き方法 | オンライン、電話 対面、郵送 | オンライン、電話 | オンライン、電話 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 |
| 対象 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 | 法人宛ての請求書を お持ちの方 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
| 2社間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 3社間 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| ポイント | 5割以上が 即日入金を実現! | 審査通過率が 92.25%と高い! | 「注文書」による ファクタリング! | 初回15万円~と 少額でも利用可能。 | 手数料が安く 利用しやすい! ※事前にGMOあおぞらネット銀行の 口座作成が必要 | 請求書の支払いを 最大60日後にする サービス。 |
| 公式サイト |

手形ジャンプのリスク

手形ジャンプの受け入れにはおもに2つのリスクがあります。
手形ジャンプの依頼を受けた際は、事前に考えられるリスクをよく知っておきましょう。
1.支払われない可能性
手形ジャンプを引き受ける際は、「支払期日に支払えなくなった理由」をよく見極めましょう。
取引先に「なぜ支払期日を延長したいのか」、「延長後の支払い期日には支払えそうか」などを確認します。
理由に正当性がある場合、取引先に大きな非がなく延長後にはきちんと支払ってもらえそうな場合は、手形ジャンプを受け入れてもいいでしょう。
手形ジャンプには、受け入れ・拒絶の両方にリスクがあります。
安易な判断は行わず、慎重な見極めが必要です。
安易に手形ジャンプを受け入れた結果、自社の売掛金が回収できなくなると、それがきっかけで資金繰りが悪化したり、他社に迷惑をかける可能性もあります。
2.資金繰りが悪化する可能性
手形ジャンプを許可すると、仮に後日きちんと支払われたとしても資金の回収には時間がかかってしまいます。
予定通り資金が回収できないことで、自社の資金繰りを悪化させる可能性があります。
手形ジャンプを検討する際は、取引先の倒産リスクだけでなく、自社の手元資金や資金繰りの状況もよく考えるようにしてください。
取引先のことを思って手形ジャンプを受け入れたとしても、自社が資金繰りで困り、他社に迷惑をかけてしまっては意味がありません。

手形ジャンプは倒産の兆候?

取引先企業から、手形ジャンプをして欲しいと依頼があったとき、取引先に不安を覚える人は少なくないでしょう。
手形ジャンプは、簡単に言うと「本来の支払期日に支払いができなくなったので期限を延長して欲しい」というお願いです。
このようなお願いをされた場合に真っ先に疑ってしまうのが「倒産」でしょう。
長く続く不況のあおりで、2007年以降倒産する企業が増えています。
これを受け2009年12月4に施行された、中小企業金融円滑化法により2009年からは倒産数は減少しています。
しかし、中小企業金融円滑化法が2013年3月いっぱいで効力を失ったため、その後は倒産する企業が増える傾向にあります。
倒産する企業に見られる兆候
倒産前の企業には何かしらの兆候が見られます。
たとえば、今回の手形ジャンプなら「複数回依頼される」、「頻繁に依頼される」このような状況になると、経営はかなり悪化していると推測されます。
手形ジャンプ以外にも、資金繰りが苦しい場合は、契約時に支払った保証金を返還して欲しいと求めてくるケースもあります。
融通手形の発行
倒産前のよく見られる兆候としては「融通手形」の発行もあります。
新しい取引先に依頼して、実際には取引がないにもかかわらず手形だけを振り出すものです。
融通手形を割り引くことで資金繰りにあてるのですが、ここまで来るとかなり経営が悪化していて倒産寸前の可能性もあります。
長く取引している企業には言いにくいこともあり、新しい取引先に依頼することが多いです。
融通手形は資金繰りの一つですが、その後も資金繰りが悪化し続けると、取引をした企業も連鎖破綻するという最悪の結果となってしまいます。
取引先企業が融通手形をしているかどうかは、地元の同業者に聞く方法が有効でしょう。

資金調達、資金繰り改善には「ファクタリング(売掛債権の買い取り)」が有効なケースがあります。
手形ジャンプのリスクを回避する方法

手形ジャンプは、その性質やリスクを考えると付き合いの長い取引先であっても簡単に受け入れられるものではありません。
手形ジャンプの許可には「倒産リスク」、「資金繰り悪化リスク」等があるため、ジャンプの理由を確認するようにしてください。
また、複数かつ頻繁な手形ジャンプの依頼があった場合は、取引先の経営状況の悪化を頭に入れたうえで、手形ジャンプを許可するか考える必要があります。
手形ジャンプによるリスクを完全に回避するには「手形ジャンプを断る」しかありません。
手形ジャンプの安易な受け入れは、自社が経営危機に陥る可能性があることをよく理解しておきたいです。
万が一の時のための債権回収方法

取引先との取引が成立して売掛債権が発生したら、通常は支払期日に指定した口座に売掛金が振込まれます。
しかし、さまざまな事情により、売上債権を回収できないこともあります。
そういった際は、まず電話や書面で債権の請求をします。
可能なら対面で請求してもいいでしょう。
うっかりミス等であれば、この段階で問題なく債権を回収できるはずです。
相手企業に資金がない場合は、連絡を無視されたり、遠方に引っ越されたりする可能性があります。
売掛債権の時効は5年です。
時効成立前に、一部弁済や債務承諾書の作成等で時効を中断できるようにしておきましょう。
▼おすすめファクタリング比較表
※一部、ファクタリングとは異なるサービスも紹介しています
| アクセルファクター | ベストファクター | BestPay 注文書ファクタリング | CoolPay | QuQumo | 支払い.com (請求書後払いサービス) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 2%~ | 2~20% | 5%~ | 問い合わせ時確認 | 1%~ | 一律4% |
| 入金スピード (最短) | 即日 5割以上が即日入金 | 即日 | 翌日 | 即日 | 最短2時間 | 最短1日後の 振込に対応 |
| 利用可能額 | 30万〜無制限 | 30万円~1,000万円 | 100万円~3億円程度 | 初回15万円~ | 金額上限なし | 1万円以上~ |
| 手続き方法 | オンライン、電話 対面、郵送 | オンライン、電話 | オンライン、電話 | オンライン完結 | オンライン完結 | オンライン完結 |
| 対象 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 | 法人宛ての請求書を お持ちの方 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
| 2社間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 3社間 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| ポイント | 5割以上が 即日入金を実現! | 審査通過率が 92.25%と高い! | 「注文書」による ファクタリング! | 初回15万円~と 少額でも利用可能。 | 手数料が安く 利用しやすい! ※事前にGMOあおぞらネット銀行の 口座作成が必要 | 請求書の支払いを 最大60日後にする サービス。 |
| 公式サイト |

債務弁済契約公正証書の作成
債務弁済契約公正証書の作成で、債務者に債権を支払ってもらうよう契約ができます。
ほかにも債権者がいる場合は、不動産などの担保をとっておきます。
連帯保証人や、連帯債務者がいれば、そちらに請求することもできますので、確認してみてください。
債権の回収方法はいくつもあります。
困った際は専門の会社や弁護士に相談することをおすすめします。





