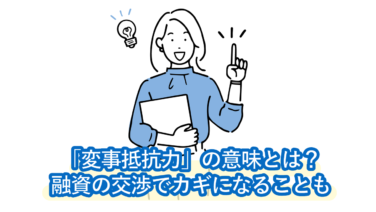 融資
融資 自社の「変事抵抗力」の意味とは?後ろ向き融資の交渉でカギになることも、無理ならファクタリングがおすすめ
「変事抵抗力」とは、非常時の抵抗力のことであり、会社の財務的な強さを意味しています。
会社の変事抵抗力を銀行がどう見ているか、融資交渉にどのように影響するかなどを理解していると会社に経営に役立ちます。
意味を...
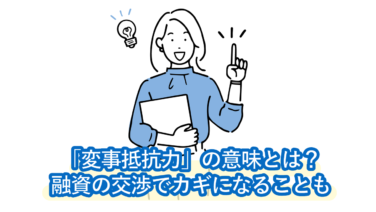 融資
融資  ファクタリング
ファクタリング 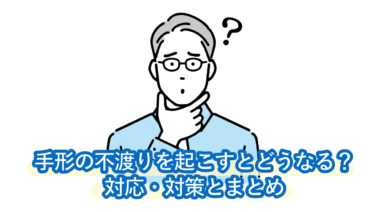 資金繰り
資金繰り  融資
融資  融資
融資  融資
融資 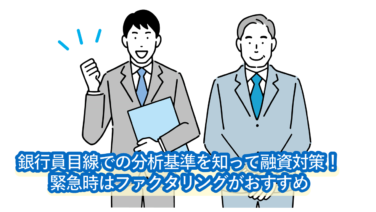 融資
融資  融資
融資  融資
融資 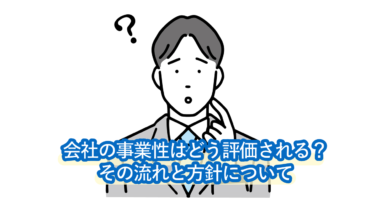 融資
融資