とはいえ、資金ショートが起こる可能性を完全にゼロにしてしまうことは不可能ですから、資金ショートが起こった場合にいかにしてそのリスクを軽減するための手を打っておかなければなりません。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
見落とせない資金ショートの7つ危険信号

売掛金の回収困難による資金ショートを未然に防ぐためには、もちろん自社における売掛金管理をしっかりと行う必要があります。
売掛金管理にあたって重要なこととして、取引先の変化に常に注意を払っておく必要があります。
取引先に注意を払い危険信号をキャッチすることができれば、取引から撤退したり与信限度額を低くしたりと回収準備を進めることができます。
取引先に起こる様々な変化や、それによって発せられる危険信号をキャッチするためには、ささいな変化もしっかりと情報としてとらえて記録に残しておくことが大切です。

CFレッド
取引先が大きな企業ならば、新聞記事を保存しておいたり、インターネット上にあらわれた情報を保存しておくのがよいだろう。
しかし記事にならない取引先も無数にありますから、そのような取引先の変化については、独自に調査をしてその都度記録に残しておかなければなりません。

CFイエロー
販売にあたる営業マンは気に留めなかった情報でも、見る人によっては危険信号としてとらえることもあるわ。
そのため、取引先の変化はありのままに記録しておくことが大切です。取引先の変化は、信用状況のチェックのために非常に重要なものになります。
よい変化であればそれほど気にすることはなく、場合によっては取引強化に利用することができます。
しかし業績悪化や資金繰り悪化、不良債権の発生などといった悪い変化であれば、注意しなければなりません。
特に、月末は注意です。
月末近くになると、支払いに絡んだ資金繰りの問題が発生する頻度が高くなります。変化を逃さずキャッチし、キャッチしたならば素早く対応していくことが大切です。
では、売掛金の回収困難を引き起こす危険信号を見ていきましょう。
業績の悪化
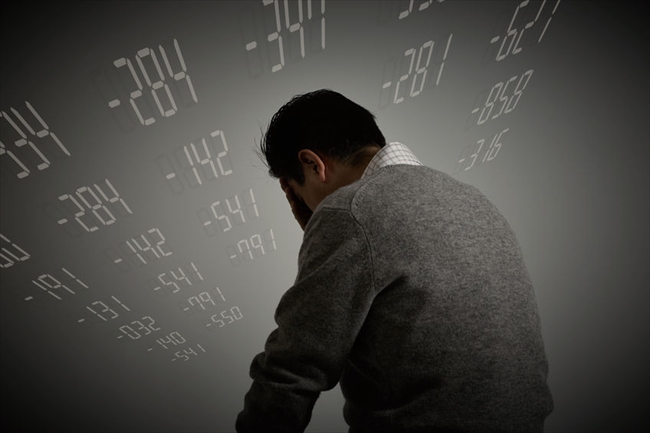
業績悪化は、取引先に資金ショートを起こしかねない危険信号です。
取引先が資金ショートを起こして売掛金が回収できなくなれば、自社も資金ショートにつながるのですから見逃してはいけない変化です。
たとえば、取引先の赤字決算には注意しなければなりません。
赤字決算になるのは、なにも売上が低下したときばかりではなく、売上が横ばいのときや増加したときにも起こります。
- 売上原価が高い場合
- 販売管理費が高い場合
- 営業外費(おもに支払利息)が多い場合
- 特別損失が発生している場合

CFイエロー
売上が減っていないのに赤字になる原因はこれらが考えられるわ。
粗利益の段階で赤字になっているならば、赤字は拡大します。
有価証券や固定資産の売却によって特別利益を計上していれば問題ないことも多いのですが、そうでなければリスクは大幅に高まります。
営業利益の段階で赤字になっている企業は販売費が高いため、経費削減が行われているかどうかを調査する必要があります。
人件費の削減、無駄な経費の削減などがそれにあたり、なんらかの手が打たれていなければリスクは高まります。
債務超過
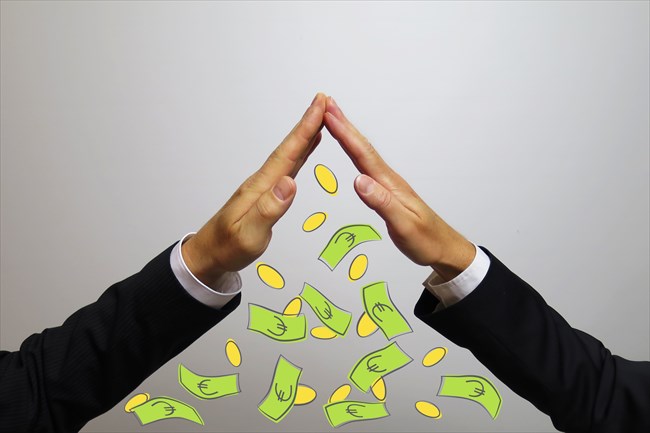
業績悪化が続けば売上は減りますが、出費は従来と変わらないか場合によっては増加します。
当然ながらそれまで内部留保してきた資金に食い込み、さらには資本金にまで食い込み純資産がマイナスになります。
この状況を債務超過と言います。
累積損失が増えて行くと、運転資金が不足して資金ショートを起こします。
売上が増えている状態で損失も出ている状態ならば、売掛金の回収がうまくいけば資金ショートには至りません。しかし売上不振の上に損失が出ているときは問題です。

CFブルー
そんな企業が資金ショートを起こして銀行に融資を申し込んでも、融資に慎重な銀行が債務超過の企業に融資を行うはずがないのだ。

CFレッド
銀行は債務超過の企業へ貸出を行うと、不良貸出として金融庁から指摘を受けることになり、引当金の積み増しを求められるからだ。

CFイエロー
相当の担保があれば融資を受けられる可能性もあるけど、中小企業は基本的に担保に乏しく、融資を受けることは難しいでしょう。
そこで、資金繰りに困っている企業同士で融通手形を発行し、これを手形割引して運転資金に充てる方法があります。ですが、その頃には銀行で手形割引をしてもらえません。

CFイエロー
銀行での手形割引は融資と同じものだと認識されているため、融資を受けられない企業は手形割引もしてもらえないのが普通よ。
もし銀行が手形割引に応じてくれたとしても、銀行は手形に不信感を持っているはずです。
毎月の売上や手形の割引額はほぼ決まっているのですから、売上が増えていないにもかかわらず手形だけが増えて行けばおかしいのは当たり前です。
そこで、手形割引業者に依頼することになります。
手形割引業者は融資ではなく手形の買い取りと捉えているため、手形自体に問題がなければ買い取ってくれます。しかし、銀行に比べると割引金利が高くなります。
それでも、企業は資金ショートを起こすかどうかの瀬戸際(あるいは起こしている)ですから、やむを得ず利用することになります。
しかし、融通手形は恐ろしいものです。

CFレッド
資金繰りに困っている企業同士で融通手形を交換し合うのだから、相手企業が倒産する可能性は高い。
相手企業が倒産すると、割引した手形は不渡りとなり手形割引業者から弁済を求められます。資金繰り困難ゆえにそれを支払うことは難しく、連鎖倒産する可能性が高いのです。
大口の不良債権の発生

取引先に、大口の不良債権が発生している場合には要注意です。
どれくらいの額をもって「大口の不良債権」と捉えるかということは、取引先の規模によっても異なりますが「一般的には一ヶ月分の売上に相当する不良債権が発生した場合」には売掛金管理における危険ラインといわれています。
もちろん、小口の不良債権でも、その累積額が一ヶ月分の売上に相当する場合には、同じく危険であるといえます。

CFブルー
不良債権が発生したということは、売掛金の回収ができなくなったということだ!

CFイエロー
それは、取引先の売掛金管理がまずいということであり、ここに危険性があるのよ。
売掛金管理がまずい企業は、常に資金ショートの危険性をはらんでいるということであり、資金が足りなくなれば銀行などから融資を受けることで乗り切るほか無くなります。
しかし、銀行とて売掛金管理がまずいために資金ショートに陥った企業に対して、簡単に融資を行うことはありません。
価値のある担保があれば融資も可能かもしれませんが、そうでない場合には断る可能性が高くなります。
そのような取引先に債権を持っているならば、直接事情を聴きに行ったり信用調査機関に調査を依頼する必要があるでしょう。
このとき、取引先が銀行から融資の確約をもらっているならばひとまず安心ですが、そうでない場合には十分に注意をし、早期に対策を講じなければなりません。
役員や幹部社員の退社

役員の退社も、ひとつの兆候といえます。
役員の場合、任期満了で辞めるならばなんら問題ありませんが、企業内の役員争いが原因で辞めたり、経営者と意見が対立したために辞めたりしているならば注意が必要です。
特に、財務経理担当の役員が辞めた場合には、注意しなければなりません。
財務経理担当役員は会社の業績や資金繰りを熟知していますから、そのような役員が役員争いや経営者との対立で辞めている場合には、財務になんらかの問題がある可能性が高いからです。
銀行からも不信感を持たれ、資金繰りが厳しくなることもあり得ます。
また、同業者間で噂が立つことで今後の取引に支障をきたし、業績に響く可能性もあります。

CFイエロー
そうなれば、自社の売掛金回収に響く可能性も出てくるわ。
また、幹部社員の退社にも注目しましょう。
辞めた幹部社員が、会社に対する不満や会社の問題点を漏らす可能性があり、これも役員の退社と同様の結果を引き起こすかもしれません。
役員交代

役員交代の原因は様々です。
役員交代の際に取引先から十分な説明がなされ、問題なければそれでよいです。
- 経営者が亡くなって子息が後を継いだ
- 親会社から派遣されていた社長が交替した
- 経営不振の責任をとって役員が交代した」

CFブルー
このような場合には、十分注意しておこう!
経営者が亡くなった場合、中小企業では子息が後を継ぐのが普通です。しかし子息に事業経験が少なかったり、あまりにも凡俗であった場合には、問題が起こりがちになります。
また、子息がいなかった場合にも問題が起こるものです。
経営者の生前から子息がしっかりと教育を受けており、社内でも信頼されているような場合は問題ありません。
しかし経営者の子息というだけで甘やかされるということは多く、そのような子息が経営者になった場合は、社内に問題が起こる可能性が高いでしょう。

CFイエロー
ワンマンになったり、放漫経営に陥ることが多いのよ。
子息がいない場合には兄弟や妻が後継者になることが多いのですが、そのような場合にも同じことがいえます。
後継者を決める際に、遺産相続で争いが起きた時には要注意です。
親会社から派遣されていた経営者が交代したならば、それは経営不振の責任を問うて親会社が交代させています。
経営能力がある経営者に交代したならばよいのですが、交代する経営者がより能力の低い人ということもあります。
そうなれば業績はより悪化し、売掛金回収が困難になるかもしれません。親会社がしっかりしていればこのような問題は起きにくいのですが、どのような人物が派遣されるかということには注意しておきましょう。
巨額の設備投資

企業では、業務拡大のために設備投資を行います。
設備投資は経営者の事業拡大意欲の表れでもありますから、一面では良い兆候であるといえます。
しかし、どれくらいの設備投資を行うかということは非常に重要です。

CFレッド
設備投資額の目安は、減価償却額の範囲内であるということだ。
しかし、これでは他社との競争に勝てないということから「設備拡大の投資や合理化投資といった投資」を減価償却額以上の額で行うことになるのですが、これも一概に危険とは言えません。
ただし、やはりあまりにも巨額投資となってしまい、自社の能力を上回る設備投資を行っているような場合には、そこから経営が傾いていく可能性があります。

CFイエロー
設備資金はどうなっているか、設備投資によってどのような結果が期待できるかをしっかりと把握しなくてはならないわ。

CFブルー
生産能力アップによって「売上はしっかり伸びるか・原材料はどう調達するか・人員・人材は十分か」に注目しよう!
たとえば、従来と比較して生産量が倍増するような場合、過剰な設備投資であるといえるでしょう。
需要予測が狂う可能性が高く、そうなれば稼働率が上がらず、売上は伸びず、借入金の返済だけを行わなければならなくなり、資金ショートに陥りかねません。
不動産における担保設定の急増

銀行から借入金がある場合、社有・個人所有を問わずに不動産に抵当権が設定されます。
赤字や設備投資によって銀行借入が増えると、不動産の評価額(担保価値)以上の担保設定がなされることになります。
取引先の担保設定が急増している情報をキャッチした場合には、それは取引先がより多くの資金を必要としているということです。
そのこと自体は問題ないこともありますが、調達した資金がどのようなことに使われ、それによってしっかりと利益を上げているかどうかを見極めなければなりません。

CFレッド
もし、借入の際に仕入れ先やノンバンクが担保設定をしていることが分かれば、リスクが高いため特に注意が必要だ。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
資金ショートを防ぐための対策
さて、上記のように取引先が発する危険信号にはいろいろなものがあります。
これらの危険信号をキャッチしたならば、さまざまな対策を講じて、売掛金回収に伴うリスクの軽減に努める必要があります。
そうすれば、回収不能を未然に防げる可能性は高まりますし、万が一回収不能に陥った場合にもリスクを軽減することができます。

CFブルー
そうすれば、資金ショートを防ぐことができるということだ。
資金ショートへの対策は主に信用不安がある要注意先、要注意先よりも危険性が高い要警戒先に対して行います。
この両者ではそれぞれ対策が異なります。
要注意先への対策

要注意先とは、信用不安につながる噂がある企業です。具体的には以下のような企業を指します。
【信用調査の評点が50~55点である企業】
このような企業は、何らかの問題を抱えていると思ってよいでしょう。そのため、要注意先と考えられます。
信用調査によってすぐに判断できるので、その時点でリスク軽減を図ります。
取引歴が浅ければ、取引先に保全を申し入れても断られることでしょう。むしろ、取引を打ち切られてしまうこともあります。
取引先としては公になっている問題がないにもかかわらず、保全措置を提供して取引を続ける必要はないのです。
したがって、何らかの保険をかける必要があります。

CFイエロー
保険会社に保証を依頼したり、ファクタリング会社の信用保証ファクタリングを利用することが考えられるわ。
【二期連続で赤字決算となり、累積損失が資本金に食い込んでいない企業】
二期連続赤字決算の企業は内部留保の資金から運転資金を捻出しているものですが、それによって自己資本がプラスの状態を維持しているならば、要注意先となります。
この場合取引先は業績の悪化を認識しており、業績改善のための経営努力を払っているものの、なかなかうまくいかない状態であると考えられます。
三期連続赤字決算となると、信用不安の噂はさらに広まるので取引先や銀行から敬遠されることとなります。
したがって、粉飾決算をしてでも利益を出したいと考えることもあるでしょう。

CFレッド
このとき自社では「赤字決算の原因を調査し、一過性のものであれば問題なし」「慢性的なものであれば保全を申し入れる」ことになるぞ!
このような取引先と取引を継続していくためには、その企業に買掛金を持っている企業を探し出し、その企業経由の取引を行ったり、なんらかの保険をかけたりする対策が考えられます。
要注意先としてよくみられるのは、上記の二つのタイプです。
この他、以下のようなタイプも見られます。
- 品質管理に問題があり、マスコミに謝罪広告が出る頻度が高い企業(クレームが絶えないため要注意先)
- 不良債権が続発している企業(売掛金管理が甘いため要注意先)
- 粉飾決算の噂がある企業(噂がある時点で要注意先)
要注意先への対策にはいろいろなものがあります。
それらを見ていきましょう。
信用リスク保証の利用
信用取引保険は損害保険会社が行っているものであり、信用リスクが高い企業に対する債権保全のための保険です。
ファクタリング会社が提供している信用保証ファクタリングも、これに類するものです。

CFブルー
ファクタリング会社ではなく保険会社を利用する場合、保険の対象となるためには「信用調査の評点が50点以上」であることが条件となるのだ。
しかし、取引先に信用不安がある企業ばかりという場合には、保険会社が成り立たなくなるため、すべての取引先を対象とするなどして対応します。
ファクタリング会社の信用保証ファクタリングの場合には「保険会社と同じような総合保証を行うもの」と「それぞれの債権を個別保証するもの」があります。
信用リスクが高いほど保証料が高くなるという仕組みになっています。
帳合先を探す
要注意先との直接取引を避けるというのもよい対策です。
そのためには、要注意先に多額の売掛金を持っている企業を探し、その企業を経由して取引を行うようにします。また、取引先に多額の買掛金を持っている企業に依頼し、その企業経由で取引を行うという手もあります。
このとき、ただ乗りはできませんから帳合料としていくらかの手数料を支払いますが、それでリスク回避になるならばよい方法といえます。
連帯保証を取る
通常の債権保全の方法は、取引先の代表者の連帯保証を取ることです。
しかし、連帯保証はよほど個人資産がある場合や、金融機関や大手仕入れ先に差し入れしている場合でなければ、保全措置としてはあまり期待できません。

CFブルー
実際、倒産間際になると個人資産の移譲が見られるようになりますから、倒産してから差し押さえに向かうと個人資産は何もないということがよくあるのだ。

CFイエロー
連帯保証は気休め程度の保全効果しかないのよ。
ただし、それが真面目な経営者相手であれば、倒産しそうになった時に個人保証の差入れ先に対して事前に知らせてくれることもあります。
そうして情報をキャッチし、活用することができれば、別の保全措置を講じて行くこともできるでしょう。
物的担保を取る
これは、不動産などの担保を取ることです。
この場合、保全のために不動産などの担保をとった事実が公になるため、取引先の信用不安は増大することを知っておかなければなりません。
金融機関以外が不動産担保を設定すると、他の債権者もその情報を元に何らかの動きを見せ、そのために取引先が一層の経営不振に陥る可能性もあります。

CFブルー
したがって、物的担保を取る際にはこっそりと取得する必要があり、そのためには有価証券を担保に取るのが上策だ!
ただし、その場合には評価を低く見積もっておくことが大切です。
取引先の訪問頻度を高める
要注意先へは訪問頻度を高めることによって、精確・詳細に情報を把握しておかなければなりません。

CFレッド
このような取引先は、表面に見て取れる以外に隠れた問題を抱えているもの!

CFブルー
できるだけ早い時期にその問題を見つけて対処するためには、訪問頻度を高めることが大切なのだ。
取引先の経営者が外出しがちであったり、経理担当部長が頻繁に銀行に行っているような場合には、重大な変化が起きている可能性が高いです。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
要警戒先への対策

次に要警戒先ですが、これは要注意先以上にリスクが高い取引先のことです。
おもに、以下のような企業のことを指します。
- 信用調査の評点が49点以下の企業
- 三期連続で赤字決算となっている企業
- 債務超過となっている企業
- 割止めリスト(手形割引業者が割引を断った企業のリスト)に名前が出た企業
- 一ヶ月の売上に相当する不良債権が発生した企業
信用調査の評点が49点以下の企業は、統計的に見て、倒産に至る確率がきわめて高いため、要警戒先となります。
格付けにおいて、50点以下の企業はすべてDランクとなりますが、このような企業は経営基盤に問題がある、財務内容が債務超過になっているなどの重大な問題を抱えています。
これらの企業群はいつ倒産してもおかしくないと考えられます。取引信用保険が掛けられないことも多く、より対策が難しくなります。
対策としては、以下のようなものが考えられます。
保全措置
要警戒先には、保全措置を前提として取引を行うことになります。もちろん、確実に価値が見込めるものを保全措置として入手します。

CFイエロー
取引保証金を差入れてもらうのがベストよ!
しかし要警戒先になっている企業はすでに資金ショートを起こしている可能性も高く、おそらく不可能だろう。
そこで、連帯保証はもちろんのこと不動産や有価証券などの担保を取るようにします。
不動産ならば所在地を聞いて不動産登記簿謄本を取り、担保設定状況を見てから担保に取るようにしましょう。
このほか、月次決算や資金繰表などを毎月取り入れることによって、経営状態を常に把握するようにします。
債権譲渡契約を結ぶことによって、いつでも債権譲渡できる準備をしておくことも重要です。
覚書を取り交わす
要警戒先との取引は避けたいものですが、それができない場合には取引先と覚書を取り交わすようにします。
覚書の内容は、たとえば、
- 毎月の月次決算を報告し、損失が出た場合には対策を講じること
- 取引先の仕入れ先や販売先のリストを提出すること
- 売掛債権に問題がある場合には両社で処置すること
- 資金繰表を提出してもらい、三ヶ月先までの資金繰りを検討すること
- 本決算が終了したら、税務申告書と勘定科目明細を提出すること
- 人員採用の際には事前に相談をすること
- 設備投資の際には、事前に計画を相談すること
などであり、取引先の経営状態が細部まで把握できるものとします。
取引先と連絡を絶やさない
要注意先の場合と同様に、取引先の訪問頻度を高めることはもちろんのことです。

CFイエロー
要警戒先とは毎日何らかの連絡を取り続けておくことが重要よ。
倒産に至る重大な変化を突然知らされてからでは対処のしようがありませんから、常に連絡を絶やさないようにしておこう。
取引先から売掛金を確実に回収するためには、売掛金管理が絶対に必要です。そのためには取引先の情報を常に把握して、取引先の状態に合わせた対策が必要となります。
そうしておけば、売掛金をしっかりと回収していけます。もし回収困難になってしまったとしても、完全な貸し倒れを防ぐことができる可能性は高まります。
そうすれば、売上をきちんと回収していき、自社の資金ショートを防ぐことができるのです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

資金ショートを解消するファクタリング

しかし、売掛金管理を自社で完璧に行っていくことは簡単なことではありません。
すでに管理体制に問題がある場合には、社員教育や構造改革に取り組まなければならず、そのためには時間もコストもかかります。
管理体制を構築すれば非常な強みになりますが「それまでに不良債権が発生してしまう・すでに不良債権が発生している・社員教育や構造改革に伴うコストに耐えられない」などの問題を抱えている企業も多いことでしょう。
資金ショートの危険がある、あるいはすでに資金ショートに陥ったならば、社員教育や構造改革に取り組むための時間もお金もなく、悠長なことはやっていられません。

CFレッド
すぐさま資金ショートを解消し、自社の存続のために手を打たなければならないのだ!
資金ショートのために銀行借入の返済ができない、買掛金の決済ができない、社員に給料を支払えない、仕入れができないなどの事態に陥れば、倒産のほかありません。
そのような場合、まず考えられるのが融資を受けることです。多くの経営者が、どこからかお金を借りられないかと奔走することでしょう。
売掛金管理に問題を抱えて資金ショートに陥っているような企業は、銀行から見れば要警戒先にほかならず、新規融資・追加融資に限らず融資はしてくれないはずです。
高金利の事業者ローンは、銀行に比べてかなり審査が甘いものの、資金ショートを起こしている企業に対してはごく少額の融資をするか、融資しないと考えられます。
そのような場合、残る方法は資産の売却によって資金を調達し、資金ショートを解消することです。
とはいえ、中小企業においては売るべき不動産や有価証券はあまり保有していないのが普通ですから、それもなかなか難しいと考える経営者がほとんどです。

CFイエロー
しかし、本当に売れる資産がないかどうか、もう一度考えてみて!
売掛債権はどれくらい残っているでしょうか。それを売ることによって、資金ショートを解消できるかもしれません。

CFブルー
売掛債権を売却することによって資金調達をすることを、ファクタリングと言うぞ!
ファクタリング会社は、売掛債権を評価して買い取り、支払期日に売掛金を得ることで利益を得ている企業です。
売掛先の信用度によって買取率は異なり、信用不安が大きい場合には買取率は低くなるのが普通ですが、それでも売掛債権を広く買い取っているため、資金調達に便利です。
ファクタリングの利用の流れは、以下の通りです。
- 自社が取引先に、商品を掛け売りする
- 売掛債権が発生する
- 売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金を調達する(資金ショートが解消される)
- 支払期日に売掛先から回収し、ファクタリング会社にそのまま振り込む
このような簡潔な流れで取引が行われます。

CFイエロー
ファクタリングの便利なところは、ファクタリングを依頼すると、(業者によって異なりますが)最短即日で資金を提供してくれることよ!

CFブルー
基本的には償還請求権なしでの売却になるため、売掛先が倒産した場合でも、自社で弁済する必要はないのだ。

CF戦隊
つまり、回収リスクをすべてファクタリング会社に移転できるということだ!
単に資金ショートの解消のみではなく、売掛債権をファクタリング会社に売却することで、売掛金管理が非常に簡単になるというメリットもあるのです。
もちろん、ファクタリングは資金ショートを起こした場合だけではなく、健全な状態のうちに利用することもできます。
通常は数ヶ月先にしか回収できない売掛金を、ファクタリング会社に売却することによって、早期に現金化することができるため、資金繰りを大幅に改善することができるのです。
売掛債権の評価にあたっては、ファクタリング会社は売掛先の調査を行います。
その調査結果は自社に報告されるため、信用調査を独自に行う必要はなくなります。その点においてコスト軽減にもなりますし、プロの手で調査してもらえるというメリットもあります。
コンサルティング業務も行っているファクタリング会社ならば、適正な与信限度額の設定など、調査結果をもとに取引上のアドバイスを受けることもできます。

CFレッド
このほか、取引先に信用不安が出てきた場合には、信用保証ファクタリングを利用することもできるぞ!
これは、ファクタリング会社に売掛先や売掛債権を評価してもらい、あらかじめ保証限度額を決めて契約することです。
売掛先が倒産して売掛金が回収できなくなった際には、保証限度額の範囲内で保証が受けられるというものです。
信用保証ファクタリングを利用していれば、売掛先が倒産した場合のリスクを軽減することができますし、それを原因として資金ショートに陥る可能性もかなり低くなるでしょう。
資金ショートに陥っている場合の解消法としてはもちろんのこと、資金ショートを未然に防ぐための対策としても、ファクタリングは大いに役立ってくれる方法です。
経営者の方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング












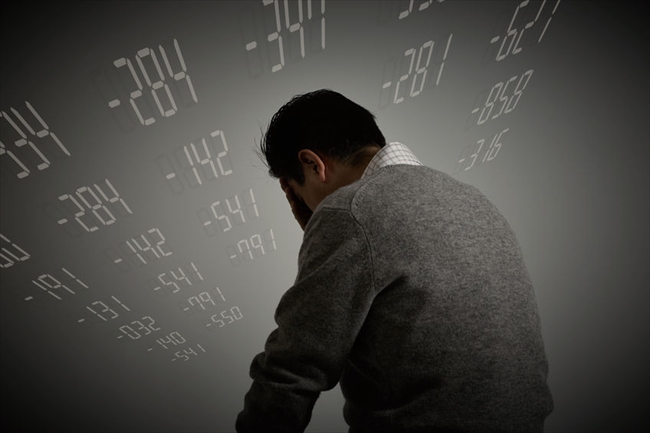
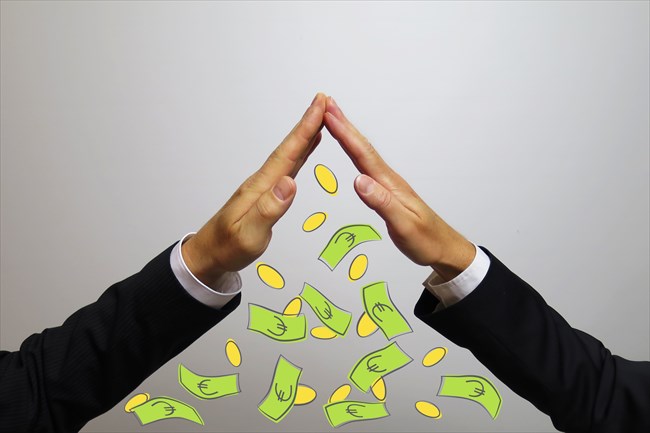


















コメント