会社が資金調達をする方法には、いくつかの方法が考えられます。最も代表的な方法は金融機関からの融資であり、これが資金調達の基本となります。
しかし、融資には返済がつきものです。そこで、返済義務がない資金調達の方法があるとすればどうでしょうか。
すなわち助成金の受給によって資金調達を図り、融資以外によって調達した資金も活用していくことで、経営を大きく改善することができます。
本稿では、助成金を資金調達に役立てるための知識として、
- 助成金を活用すべき理由
- 成功報酬型の社労士を活用するメリット
- 代表的な助成金であるキャリアアップ助成金の活用方法
これらの内容を中心に解説していきます。
助成金をもらわないと損な理由

助成金とは、国や地方公共団体が交付しているお金です。金融機関などの融資とは異なりますので、返済の義務がありません。
助成金にもいくつかの種類がありますが、本稿で取り扱う助成金は「雇用関係の助成金」であり、厚生労働省が実施しているものです。
- 新たな雇用を生み出す会社
- 雇用環境・労働環境などを改善して定着率の向上に努める会社


近年、中小企業の人材不足が深刻化してきています。人口の減少に伴う生産年齢人口の減少により、人材の確保が困難になっているのです。
今や、中小企業の経営課題の中でも、ヒト・モノ・カネの経営資源のうち、「ヒト」の不足は最大の課題となっています。
このような問題を考えれば、雇用環境・労働環境の改善に取り組むことで人材不足の解消に取り組む会社や、生産性の向上に取り組むことで人材不足の解消に取り組む会社に対し、助成金を通して公的支援を行っている政府の意図がよくわかるはずです。

助成金の大きな3つのメリット

以上のような政府の意図を汲めば、助成金のメリットもはっきりします。助成金のメリットについて、簡単に見ておきましょう。
融資ではないので返済義務がない
まず、助成金には返済義務がありません。助成金に返済義務を課してしまうと、会社に返済負担が生じてしまいます。
助成金は公的支援として支給しているのですから、返済負担によって本末転倒の結果にならないよう、返済義務を課していないのです。
経営改善のために人材不足の解消に取り組む会社、事業を拡大するために人材確保に取り組む会社などは、限られた資金の中で取り組んでいきます。
この時、融資を受けて取り組むのではなく、助成金をもらいながら、返済負担のない状態で取り組んでいくことには大きなメリットがあります。

中小企業に有利
政府は助成金を通して、主に中小企業を支援しています。
日本にはたくさんの企業がありますが、そのうちの99.7%を中小企業が占めており、中小企業で働く労働者は全労働者の70.1%と言われています。
つまり、中小企業経営が成り立たなければ、日本経済も成り立たないと言えます。
そして、中小企業は深刻な人材不足に陥っているので支援を必要としています。だからこそ、政府は中小企業の支援を主眼として、助成金制度を実施しているのです。
実際に、助成金の支給額は中小企業のほうが大きくなっていますし、中小企業だけを対象とした助成金も少なくありません。

手間・労力・原価ゼロ
受給した助成金は「営業外利益」として計上されるものであり、本業による儲け(営業利益)ではありません。
これは、非常に大きなメリットです。
本業による儲けである「営業利益」を得るまでには、様々なコストがかかっています。
販売するために商品を仕入れたり、製造するための原材料を仕入れたり、販売や製造に従事する従業員がいたり、様々なコストがかかり、それらの経費を売上高から差し引いたものが営業利益となるのです。
粗利率を30%とすれば、100万円の利益を得るためには約333万円の売上が必要です。もちろん、この売上がいったん売掛金となる場合には、貸し倒れリスクも付きまといます。
助成金には、そのような手間と労力がかからない、原価ゼロの純利益です。
粗利率30%の会社で100万円の助成金を受給すれば、それは約333万円の売上に匹敵する価値があるのです。

助成金の原資は雇用保険料

以上のように、助成金の魅力を知れば知るほど、「利用しなければ損」ということが分かります。
「利用しなければ損」と言える理由は、これだけではありません。
助成金は、受給要件さえ満たせばほとんどの会社で受給できるものであり、毎年多くの会社が受給しています。
果たしてどこからそのお金がでているのだろう、と疑問に思う人もいるでしょう。助成金の原資は皆さんの会社でも支払っている雇用保険料です。
雇用保険といえば、失業した人に失業手当を支給する制度というイメージが強いかもしれません。しかし、失業手当の支給は事後的対応です。
そもそも失業しなければそれを支給する必要もなく、むしろ経済にとってはそのほうが重要です。
このため、雇用保険では失業の予防や雇用構造の変動への対応にも重点を置いております。
失業手当の支給以外にも「就職の促進、雇用の継続、教育訓練」なども給付の対象として規定し、また「雇用安定事業・能力安定事業」のためにも雇用保険料が活用されています。
このことは、雇用保険法の内容からも明らかです。雇用保険法の第1条には、
労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする
と明記されています。
企業が納めた雇用保険料は、このような目的を以て運用されており、助成金の原資にもなっています。
したがって、助成金を受給するということは、雇用保険料を納めている会社の当然の権利と言えます。
雇用保険法で定めているように、失業の予防や雇用状態の是正、雇用機会の増大などの「労働者の福祉」に努めたからこそ受給できるのです。
これはあたかも、税金を納めている一国民として、様々な公共のサービスや施設を利用することと、何ら変わりありません。
このことからも、「助成金を利用しなければ損」ということができます。

取り組みに必要なコスト考えよう

もっとも、いくら「助成金を利用しなければ損」といっても、これは「手あたり次第になんでも利用すべき」ということではありません
あくまでも、自社が人材不足の解消や生産性の向上など、経営課題に取り組んでいくうえで、利用できる助成金は積極的に利用すべきということです。
助成金を受給するためには、受給要件を満たすために制度を整備しなければならないことも多いです。
中には、一度作ったら廃止できない制度もあります。むやみやたらに助成金を受給しようとすると、自社にとって不要な制度を作ってしまいかねません。
廃止することもできず、負担を抱え続けることになってしまうでしょう。
また、助成金は取り組みの後に支給されるものですから、取り組みに必要なコストが先行することも忘れてはなりません。
「人材を雇用・転換したり、賃金を引き上げたり、設備・機器などを導入」したりするにはコストがかかります。
そのほか、社労士に相談して活用すべき助成金を案内してもらったり、受給要件を満たすためのサポートや申請手続きをしたりする場合にも、着手金が先行することがあります。
「資金繰りの計画や、受給後の節税対策」をしっかり立てたうえで取り組まなければ、取り組みの途中で資金繰りが厳しくなり、取り組みが途中で頓挫することも考えられます。
そうなれば、その時点までに負担したコストは全て無駄になり、助成金も受給できなくなってしまいます。
したがって、助成金を活用するにあたっては以下の2点が大切です。
- 社労士とよく相談しながら、活用すべき助成金、制度や職場環境などの整備が後々会社のためになる助成金を選ぶ
- 資金繰り計画をよく考え、先行するコスト負担をできるだけ軽減しながら取り組む

社労士報酬の考え方

ここで特に意識したいのが、社労士にかかるコストです。
上記の2点を考えるとき、社労士という要素がカギになります。助成金を正しく選ぶには社労士の協力が欠かせませんし、資金繰り計画や先行するコスト負担には社労士にかかる費用も含まれます。
- 社労士にコストをかけすぎないこと
- コストがかかるタイミングをよく検討すること
社労士にしっかりサポートを受けつつも、これらをよく考えておく事が重要です。
もっとも、これは社労士に支払うコストを惜しんだり、支払いを渋ったりすることではありません。そのようなことをすれば、社労士の十分なサポートが期待できなくなります。
あくまでも「社労士にかける費用が適正価格であること・先行するコスト負担ができるだけ小さくなるプラン設定の社労士を利用すること」を意識するのです。
具体的には、価格とコスト負担を以下のように考えていきます。
社労士は費用対効果で考える
社労士は報酬を自由に定めることができるため、社労士に設定が異なります。このため、相場よりも安い社労士もいれば、高い社労士もいます。
依頼する社労士を比較検討することなく決めてしまうと、割高な社労士に依頼してしまう可能性があるので、複数の社労士を比較して決めるべきです。
また、相場より割安・割高な設定をしている社労士には、それなりの理由があるのかもしれません。例えば、
- 報酬が割安であるものの、依頼と同時に顧問契約を結ぶプラン設定になっている
- 報酬が割高であるものの、税理士と社労士のダブルライセンスであり、より充実したサポートが期待できる
などの理由です。このため、検討している社労士のサポート内容と照らし合わせて、適正価格かどうかを検討すべきです。

完全成功報酬型の社労士を選ぼう

では、価格を比較する具体例を見てみます。
ここでは、3人の社労士A~Cに、それぞれ以下の条件で依頼し、計200万円の助成金を受給した場合を考えます。
【社労士A】
- 着手金:5万円
- 成功報酬:20%
- 顧問料金(年間):なし
【社労士B】
- 着手金:10万円
- 成功報酬:10%
- 顧問料金(年間):12万円(1万円/月で顧問契約あり)
【社労士C】
- 着手金:なし
- 成功報酬:30%
- 顧問料金(年間):なし
それぞれの条件で比較してみると、社労士に全ての費用を支払った場合の最終的な手残りは、以下の通りになります。
| (単位:万円) | ||||||
| 着手金 | 成功報酬 | 顧問料金 | 合計金額 | 会社の手残り | 手残り率 | |
| 社労士A | 5 | 40 | 0 | 45 | 155 | 77.5% |
| 社労士B | 10 | 20 | 12 | 42 | 158 | 79% |
| 社労士C | 0 | 60 | 0 | 60 | 140 | 70% |
この結果を見ると、最終的な手残りが最も多いのは社労士Bですが、長期的に顧問契約を継続した場合には、手残り率はどんどん下がっていきます。
したがって、最も無難な社労士はAにも見えますが、ここに落とし穴があります。
社労士A・Bでは、それぞれ着手金がかかっています。これは、助成金の利用に先立って支払うものであり、コスト負担が先行します。
結果的に助成金が受給できなかった場合にも、着手金は返還されず損失となります。つまり、着手金はリスクを伴う費用と言えます。
そこで、社労士Cのように着手金不要の社労士に依頼すれば、助成金を受給してから成功報酬を支払えばよいため、着手金が損失になるリスクもありません。コスト負担が先行することもないのです。
また、着手金ゼロの社労士に依頼すれば、社労士は助成金を受給しない限り売上がなくなるため、しっかり取り組んでくれるというメリットもあります。
上記の例では、社労士Cの手残り率が最も低くなっています。
また実際に、本来着手金として支払うべきものが成功報酬に加算されていること、着手金を払わないことで会社にメリットがあることなどから、成功報酬はやや高めに設定されていることも多いです。
しかし、リスクの回避、先行コストの軽減、社労士の積極的な働きなど、様々なメリットがあることを考えれば、多少高めの費用を支払うだけの価値はあると言えるでしょう。
もちろん、当サイトで紹介する「社会保険労務士法人ミライズ」のように、非常に良心的な価格に設定されている社労士を選べば、リスクをさらに下げることができます。
したがって、助成金活用にあたって選ぶべき社労士は、「完全成功報酬型の社労士に限る」と言えるでしょう。

手続きは専門家に任せよう
着手金がかからない社労士を選ぶにせよ、成功報酬などの支払いは生じます。
これは、社労士に助成金の申請手続きを代行してもらうことを始め、助成金を受給するために必要となる取り組み全般をうまくこなしていくためのものです。
助成金の申請は社労士の専売業務ではないため、経営者が自分で調べて、労務局などから何度も差し戻しを受けながら、四苦八苦して手続きをすることも不可能ではありません。
しかし、経営者は助成金のプロではありませんから、申請のためには多くの手間がかかりますし、どこかでミスをして受給できなくなる可能性も高いです。
今でこそ(平成30年10月から)、提出書類を郵送で受け付けてもらえるようになり、窓口まで持参する必要はなくなっていますが、手続きで負担が軽減されたのはこの点くらいのもので、やはり多くの手間がかかることは変わりありません。
だからこそ社労士に報酬を支払って、労務局とのやり取りを全て任せたり、就業規則その他の整備や事業計画の策定などをサポートしてもらったりする価値があります。

むしろ、様々なことを社労士に任せるからこそ、経営者がこなす必要のない業務の負担がなくなります。
経営者のやるべき仕事に邁進することができるのです。社労士に任せたほうがミスもなく、助成金は受給しやすくなります。
着手金の有無に関わらず、申請に必要となる書類は社労士が全て用意してくれます。
もちろん、受給要件を満たしていることを示すために「請求書や会計書類、給与台帳、出勤簿」などを社労士に提供する必要がありますが、社労士の求めに応じて資料を提供すれば、手続きは社労士がこなしてくれます。
取り組みの初期段階で書類・資料を求められたり、取り組みの途中途中で追加の書類・資料を求められたりすることはありますが、助成金の申請手続き全体から見れば、経営者の負担はごく一部に限定されます。


こんな時にキャリアアップ助成金を受給できる!

助成金を活用するにあたって、多くの会社が積極的に活用すべき助成金は「キャリアアップ助成金」です。
キャリアアップ助成金は、人材不足の解消に役立てることができるほか、近年活発化している働き方改革への対応にも役立ちます。
会社で問題となっていることに対処しつつ、助成金によって負担を軽減できるのですから、まさに「利用しなければ損」な助成金だと言えます。
助成金制度には非常に多くの種類がありますが、特別な事情を抱えた会社が対象となっている制度も多いです。
それらも、自社に役立つものは積極的に活用を検討していくべきですが、まずは多くの会社が対象となるキャリアアップ助成金に取り組みましょう。
助成金への理解を深め、他の制度の活用も検討していくのがおすすめです。
キャリアアップ助成金には7つのコースがあります。
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金のコースはどれも活用しやすいものであり、それが7つも設けられていることから、多くの会社でキャリアアップ助成金を活用できるものと思います。
それぞれのコースについて、どのような会社がキャリアアップ助成金を受給できるのかを見ていきましょう。
正社員化コース

正社員化コースは、キャリアアップ助成金の中でも最も活用しやすいコースです。
- 有期契約から無期雇用や正規雇用へ転換
- 無期雇用から正規雇用へ転換
このような転換をした場合に助成金を支給するものです。
このような転換をすることで「労働者の勤務日数や勤務時間が固定されたり、増えたりする」ことで労働力の確保につながります。
また、有期契約では契約期間の満了に伴って離職する従業員も少なくありませんが、無期雇用や正規雇用に転換することで、その人材を長期的に活用していくことを前提に、戦略を立てやすくなります。
正社員化コースを受給するための条件は以下の通りです。
- 対象となる有期契約労働者を6ヶ月以上雇用した後に転換
- 転換後の待遇で6ヶ月分の給与を支払う
活用のポイント
人材不足に悩んでいる会社では、正社員化コースを利用することで、
- すでに雇っている有期契約労働者を転換することで、人材を確保する
- これから雇う労働者を6ヶ月以上有期契約で雇用し、その後転換することで人材を確保する
といった場合に正社員化コースを利用することができます。
既存の従業員に対しても、新規に雇用する従業員に対しても活用できる便利な制度と言えます。
これによってリスクをコントロールできるほか、無期転換ルールへの対応にも役立ちます。
平成25年4月に施行された改正労働契約法によって、有期労働契約が通算5年を超えた有期契約労働者は、無期雇用に転換しなければならなくなりました。
正社員化コースでは、有期契約から無期雇用への転換の際にも助成金を受給できるので、無期転換ルールへの対応にも役立てることができます。

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは「すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定を増額改定し、2%あるいは3%の昇給を実施」した場合に助成金を支給するものです。
このコースは、有期契約労働者と正規雇用労働者の賃金格差を小さくするために設けられているコースです。
賃金格差を是正するにあたって職務評価の実施も促しているため、しっかりと取り組むことで賃金規定の問題を解消することができます。
活用のポイント
賃金格差が大きく、有期契約労働者の離職率が高くなっている会社などでは、賃金を増額するときに賃金規定等改定コースを利用できます。
これにより、有期契約労働者の定着やモチベーションアップを図りつつ、助成金も受給するのがおすすめです。
また、働き方改革が推進されている昨今では、最低賃金の引き上げが毎年のように続いています。最近では少なくとも2%、基本的には3%の引き上げとなっています。
最低賃金は、最低賃金法によって定められており、違反すれば罰金が課せられます。したがって、会社の資金繰りに関係なく、最低賃金の引き上げに応じていく必要があります。
最低賃金の引き上げに対し、ただ受け身になって引き上げに応じるならば、人件費負担が大きくなるばかりです。
そこで、賃金規定等改定コースを利用し、積極的な姿勢で賃金を引き上げて助成金を受給しましょう。人件費負担を少しでも吸収することが重要です。
特に、最低賃金ギリギリで雇っている会社にとっては、最低賃金の引き上げに対応しつつ、賃金規定等改定コースによって助成金を受給しましょう。

健康診断コース

健康診断コースは「有期契約労働者等を対象に法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施」した場合に助成金を支給するものです。
健康診断を実施すれば、従業員の健康維持に役立ちます。これは病気による欠勤や、体調不良による生産性の低下を防ぐことにつながり、経営に良い影響をもたらします。
通常は、法定健康診断の対象となる従業員だけに健康診断を実施すればいいのですが、あえて法定外の健康診断を実施することで、有期契約労働者も健康を維持しやすくなります。
経営者の中には、有期契約労働者は出勤日数や勤務時間、生産力などで無期雇用・正規雇用より劣っており、辞めても替えが利く存在である、健康診断なども必要ないと考える人がいると思います。
しかし、常用雇用の従業員だけでは人手が足りないからこそ有期契約労働者を雇っているのですから、これも欠けては困る存在です。
健康で働いてくれるに越したことはありませんし、いずれ有期契約から無期雇用や正規雇用に転換する際にも、健康だとわかっている人を優先的に転換することも可能となります。
活用のポイント
健康維持の観点から人材確保に取り組みたいと考えている会社では、法定外の健康診断制度を作るにあたって、健康診断コースを利用することができます。

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは「有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合」に助成金を支給するものです。
会社で行われている様々な業務の中には、大きな責任を伴う業務もあれば、高い技術や経験が求められる業務もあります。
多くの場合、このような業務は正規雇用労働者が行うものであり、有期契約労働者は比較的責任の伴わない業務や、高度なスキルを求められない業務に従事するものです。
これによって、正規雇用労働者と有期契約労働者の賃金にも差が付けられています。
しかし、有期契約労働者が従事する業務の中に、正規雇用労働者と共通する業務が含まれていることがあります。
これはしばしばみられることで、例えば「パート社員も正社員も、どちらもフォークリフトを運転して倉庫内で作業をしており、仕事の内容も労働量もほとんど変わらないものの、給料には大きな差がついてしまう」といったケースです。
賃金規定等共通化コースでは、このような差を埋めるために、業務内容に応じた賃金テーブル規定を作ります。
「有期契約・無期雇用・正規雇用」などの区分だけで区別することなく、共通の賃金テーブルによって給与を支給する仕組みを作っていきます。
中小企業の中には、慢性的な人手不足に陥っており、有期契約労働者にあれもこれもと業務を命じている会社も少なくありません。
会社にとっては、低賃金で便利に使える労働者かもしれませんが、有期契約労働者本人は「あれもこれもやらされて、給料が増えるわけでもないし・・・」と不満を抱きます。
当然、有期契約労働者の離職率は高くなり、新たな人材を確保するためのコストもかかります。
賃金規定等共通化コースを活用すれば、そのような問題の解決に役立ちます。
活用のポイント
雇用形態に関係なく共通する業務で賃金格差がある会社では、賃金規定等共通化コースを通して賃金の共通化を図り、有期契約労働者の処遇を改善することができます。
それにより有期契約労働者のモチベーションが高まったり、職場への定着率が高まったりすることが期待できます。

諸手当制度共通化コース

労働協約や就業規則には、従業員に支払われる手当が定められています。
諸手当制度共通化コースは、「会社が雇用している有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合」に助成金を支給するものです。
これも、雇用区分によって生じている格差を小さくすることを目的としています。
非正規雇用労働者と正規雇用労働者の間には、支給される手当にも色々な差があります。
通常、手当を支払う目的が雇用形態に左右されない手当は、雇用形態を問わず共通の手当が支給されるべきとされています。
例えば、通勤手当は会社に出勤して労働に従事するにあたり、交通費の負担を軽減するものです。これは有期契約・無期雇用・正規雇用などを問わず共通する目的ですから、共通の手当を支払うのが合理的です。
このため、正規雇用と非正規雇用で通勤手当に差が生じているのは問題とされ、上場企業のハマキョウレックスに対しても、最高裁判所から「通勤手当の格差は不合理な格差である」と判決が下されています。
大企業でもこのような格差が生じているくらいですから、中小企業ではなおさらでしょう。従業員が訴えを起こさないために、見過ごされているだけとも言えます。
しかし、諸手当制度の共通化によって不合理な格差を是正すれば、有期契約労働者の金銭的負担は軽減されます。
働きやすくなり、職場への定着率やモチベーションが向上します。
活用のポイント
諸手当制度が不合理な状態にある会社では、諸手当制度共通化コースを活用し、有期契約労働者等の処遇を改善しつつ、助成金を受給するのがおすすめです。
また、会社によっては一部の手当を共通化することで、大きなメリットが得られる場合があります。そのような手当の共通化を図ることで、共通化の効果を高めていくことが重要です。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース
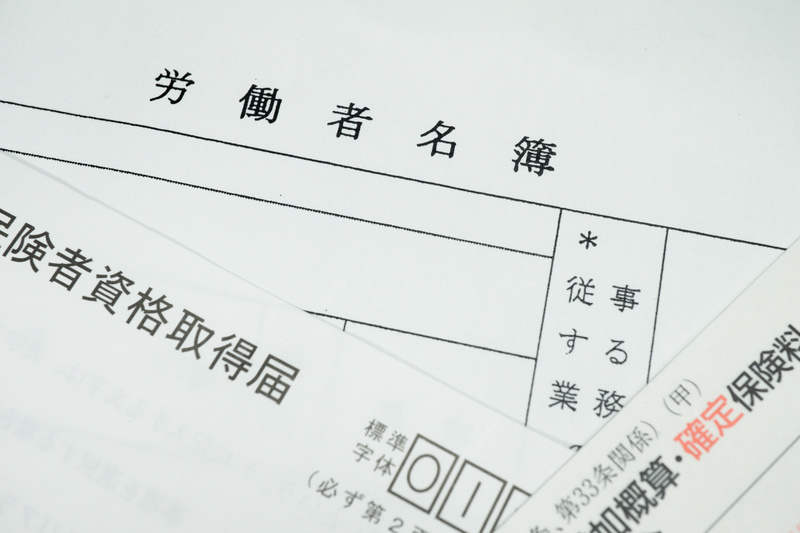
社会保険は、一定の基準を満たしている労働者のみが加入するものであり、有期契約労働者では加入していないこともあります。
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、このような格差を是正するためのものです。
「社会保険の適用範囲を拡大し、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、なおかつ社会保険に加入したことで基本給を増額した会社」には、助成金が支給されます。
本来ならば社会保険に加入する必要がない従業員を加入させるため、会社の負担は大きくなります。
しかし、社会保険に加入できる会社で働きたいと考えている有期契約労働者も多いため、社会保険の適用拡大によって人材確保が容易になります。
社会保険の適用拡大はそれほど広がっておらず、有期契約で働いている人は社会保険に加入していない状態で働いていることが多いです
そのため、自社で適用拡大に努めることで、定着率を大きく高めることができます。もちろん、定着率以外にも生産性、モチベーションの向上も期待できます。
活用のポイント
キャリアアップ助成金のすべてのコースで、従業員の定着率アップの効果が期待できますが、選択的適用拡大導入時処遇改善コースでは、特に大きな効果が期待できます。
定着率の低さに悩んでいる会社では、離職につながる色々な要素を解消していく中で、社会保険の適用拡大措置を取ることで大きな改善につながる可能性があります。
このような会社は、選択的適用拡大導入時処遇改善コースを活用しながら取り組みましょう。
なお、基本給の増額も要件となっていることから、最低賃金の引き上げに対応することも可能です。

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースはその名の通り「短時間労働者の労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合」に助成金を受給できるコースです。
「短時間労働者」とは、正社員よりも所定労働時間が短く設定されている従業員のことです。
例えば、正社員が週に5日出勤、1日8時間勤務の会社では、1週間の所定労働時間は40時間となります。この会社では、週所定労働時間が40時間未満の従業員を「短時間労働者」とみなします。
短時間労働者と非正規雇用者を混同している人もいると思いますが、非正規雇用でも所定労働時間が正社員と同じ従業員は、短時間労働者には該当しません。
短時間労働者の中には、もっと働きたいと考えていても、会社の定める所定労働時間に従わざるを得ない人もいます。
そのような人は、バイトを掛け持ちしたり、何かと苦労を強いられることになります。
そのような人が所定労働時間の延長を受ければ、より働きやすくなり生産性やモチベーションなどの向上にもつながるでしょう。
また、会社としても新規に採用することなく、短時間労働者の労働時間延長によって労働力を確保することができます。
新規の採用は、能力や適性が定かではない人を雇い入れるのですから、期待した働きが得られない可能性もあります。
そこで、短時間労働者の労働時間を延長することによって、
- すでに能力や適性がはっきりしている人材を活用するため、新規採用のようなリスクがない
- 人材募集にコストをかける必要がない
といったメリットが得られます。その上で助成金も受給できるのです。
なお、短時間労働者労働時間延長コースでは、労働時間を延長したうえで新たに社会保険に適用する必要があります。この時、手取り収入が減少しないように賃金を増額する必要があります。
活用のポイント
労働力が不足しているものの、採用活動にコストをかけられない会社、新規採用に伴うリスクを避けたい会社は多いはずです。
そのような会社では、短時間労働者の労働時間を延長することで、それらのリスクを避けることが賢明です。
特に、すでに雇用している短時間労働者の有能な人材がいる会社では、労働時間を延長して有能な労働力を確保するのがおすすめです。
また、短時間労働者労働時間延長コースは、1時間以上の延長でも助成金の支給対象となっています。
このため、労働力が少し足りていない会社では、新規雇用よりも労働時間を少し延長することで、低コストで労働力を確保することができます。
なお、延長する週所定労働時間が5時間未満の場合には、社会保険に適用することで手取り収入が減少しないよう、賃金を増額する必要があります。
これにより、最低賃金の引き上げに対応することも可能です。


キャリアアップ助成金を使えばこんな額を資金調達できる

キャリアアップ助成金の各コースについて、制度の概要や活用のポイントについてみていきました。各コースがどのような会社に向いているかも、なんとなく分かったと思います。
活用の具体例は後述するとして、それぞれのコースを利用したときの受給額はどれくらいなのか、どれくらい資金調達が可能であるのかについてみていきましょう。
生産性要件について
キャリアアップ助成金の受給額を把握する際、生産性要件の知識が必要となります。
キャリアアップ助成金の各コースに共通して、生産性要件を満たした場合に助成金が加算される仕組みとなっています。
生産性要件は、助成金の支給を申請する会社の直近の会計年度における生産性が、3年度前の会計年度の生産性に比べて、
- 6%以上伸びていること
- 1%以上6%未満伸びていること
のいずれかが要件となっています。
本稿の支給額の表では、全て「生産性が6%以上向上している場合」に統一しています。
生産性が1%以上6%未満の向上で生産性要件を満たすためには、金融機関の自社に対する事業性評価を参考にして、労働局が事業性を認めた場合が対象となっています。
しかし、金融機関の事業性評価は自社で把握することはできませんし、労働局が何を以て判断するのかも不明です。このため、基本的には「生産性が6%以上向上している場合」を基準に考えるのが良いでしょう。
生産性は、以下のように計算します。
生産性=
(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険費保険者数
この計算式によって、3年度前の会計年度の生産性と、直近の会計年度の生産性を算出します。
両者を比較し、6%以上伸びていれば生産性要件を満たしていると判断され、助成金の加算を受けられます。

正社員化コース
正社員化コースでは、どのように転換するかによって受給額が異なります。それぞれの助成金額は、以下の通りとなっています。
| 基本的な支給額 | 生産性が6%向上している場合 | |
| 有期契約から正規雇用へ転換 | 1人当たり57万円 | 1人当たり72万円 |
| 有期契約から無期雇用へ転換 | 1人当たり28万5000円 | 1人当たり36万円 |
| 無期雇用から正規雇用へ転換 | 1人当たり28万5000円 | 1人当たり36万円 |
(※すべての転換を合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数は20人まで)
有期契約から正規雇用への転換は、最も政府の方針に沿っている転換で会社への負担も大きいことから、助成金額も大きくなっています。
1年度1事業所当たり支給申請上限は20人ですから、20人を有期契約から正規雇用へと転換した場合には、57万円×20人=1140万円となり、基本的な支給額だけで1000万円以上の受給が可能です。
さらに、生産性要件を満たした場合には、最大で1440万円の受給となります。3種類の転換を随時活用していけば、数百万円単位での受給も十分に可能です。
1年間での上限は決まっているものの、毎年利用できることも大きなメリットです。
成長力が旺盛な会社や事業拡大を図っている会社などでは、人材を確保することが重要です。正社員化コースを積極的に活用していくことにより、毎年数百万円を受給することも可能です。

賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースは、支給額の設定がやや複雑です。まず「全ての有期契約労働者を対象とするか、一部の有期契約労働者を対象とするか」によって支給額が異なります。
これは一口に賃金を増額すると言っても、以下の違いがあるからです。
- 有期契約労働者の基本給を時給・日給・月給などに換算して、全ての有期契約労働者に一律の増額をする場合
- 有期契約労働者の基本給を時給・日給・月給などに換算して、一部の有期契約労働者に増額をする場合
- それぞれの有期契約労働者の職務を個別に評価し、有期契約労働者を増額の対象にする場合
また、賃金の増額率が2%と3%のどちらであるか、対象労働者数が何人であるかによって支給額が異なるほか、職務評価の実施によって加算を受けられます。具体的な支給額は以下の通りです。
(※すべての場合で、1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ。職務評価の実施による加算は1事業所当たり1回のみ)
全ての有期契約労働者に適用する場合
【増額率2%の場合】
| 対象労働者数 | 有期契約労働者全員に2%増額の場合 | |
| 基本的な支給額 | 生産性が6%向上している場合 | |
| 1~3人 | 1 事業所あたり9万5000円 | 1事業所当たり12万円 |
| 4~6人 | 1 事業所あたり19万円 | 1事業所当たり24万円 |
| 7~10人 | 1 事業所あたり28万5000円 | 1事業所当たり36万円 |
| 11~100人 | 1人当たり2万8500円 | 1人当たり3万6000円 |
全ての有期契約労働者に賃金2%アップを適用した場合、1年度1事業所当たり支給申請上限は100人ですから、最大で3.6万円×100人=360万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
【増額率3%の場合】
| 対象労働者数 | 有期契約労働者全員に3%増額の場合 | |
| 基本的な支給額 | 生産性が6%向上している場合 | |
| 1~3人 | 増額率2%の場合の基本的な支給額に加えて、 1人当たり1万4250円の加算 |
増額率2%で生産性要件を満たした場合の支給額に加えて、 1人当たり1万8000円の加算 |
| 4~6人 | ||
| 7~10人 | ||
| 11~100人 | ||
同様に、全ての有期契約労働者に賃金3%アップを適用した場合には、最大で(3.6万円+1.8万円)×100人=540万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。

一部の有期契約労働者に適用する場合
【増額率2%の場合】
| 対象労働者数 | 有期契約労働者の一部に2%増額の場合 | |
| 基本的な支給額 | 生産性が6%向上している場合 | |
| 1~3人 | 1 事業所あたり4万7500円 | 1事業所当たり6万円 |
| 4~6人 | 1 事業所あたり9万5000円 | 1事業所当たり12万円 |
| 7~10人 | 1 事業所あたり14万2500円 | 1事業所当たり18万円 |
| 11~100人 | 1人当たり1万4250円 | 1人当たり1万8000円 |
次に、一部の有期契約労働者に賃金2%アップを適用した場合には、最大で1.8万円×100人=180万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
【増額率3%の場合】
| 対象労働者数 | 有期契約労働者の一部に3%増額の場合 | |
| 基本的な支給額 | 生産性が6%向上している場合 | |
| 1~3人 | 増額率2%の場合の基本的な支給額に加えて、 1人当たり7600円の加算 |
増額率2%で生産性要件を満たした場合の支給額に加えて、 1人当たり9600円の加算 |
| 4~6人 | ||
| 7~10人 | ||
| 11~100人 | ||
同様に、一部の有期契約労働者に賃金3%アップを適用した場合には、最大で(1.8万円+0.96万円)×100人=276万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。

職務評価を実施する場合
職務評価とは、従業員の職務に応じて適切な賃金を支払うための評価です。
これを実施した会社には、上記のそれぞれの場合の支給額に対して、1事業所当たり19万円(生産性が6%向上している場合には24万円)の加算を受けることができます。
したがって、職務評価を実施したうえで、全ての有期契約労働者に賃金3%アップを適用した場合には、最大で(3.6万円+1.8万円)×100人+24万円=564万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
対象となる従業員の人数や増額率によって差はあるものの、数十万円~数百万円のまとまった助成金を受給できることが分かります。
最近は毎年のように最低賃金の引き上げが続いているため、それに伴う賃金増額を実施する場合には、賃金規定等改定コースを活用すると良いでしょう。
申請回数は1年度につき1回となっているため、毎年の最低賃金引上げにも対応可能です。

健康診断コース
健康診断コースは、1事業所当たり1回限りの助成となっています。受給のために作った法定外の健康診断制度は、その後も運用し続ける必要があることに注意が必要です。
健康診断コースの受給額は、1事業所当たり38万円(生産性が6%向上している場合には48万円)(※1事業所当たり1回のみ)となっています。
法定外の健康診断の実施人数に関係なく、この金額が上限となっています。

賃金規定等共通化コース
賃金規定等改定コースは毎年利用できますが、賃金規定共通化コースは1事業所当たり1回限りの助成となっています。
助成金額は、1事業所当たり57万円(生産性が6%向上している場合には72万円)(※1事業所当たり1回のみ)です。
共通化した対象労働者が2人以上いる場合には、2人目以降の1人につき2万円(生産性が6%向上している場合には2.4万円)の加算(※上限20人まで)を受けることができます。
したがって、賃金規定の共通化に取り組み、上限である20人を対象として助成金の支給を申請した場合には、最大で72万円[共通化による基本支給]+(2.4万円×19人)[対象労働者2人目以降の加算]=117.6万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
この助成金は1回しか受給できないため、受給額を最大化する工夫が求められます。

諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースの助成額は、やや複雑な計算となります。
基本的な支給額は「1事業所当たり38万円(生産性が6%向上している場合には48万円)」(※1事業所当たり1回のみ)となっているものの、対象労働者の人数や、共通化した手当の数によって加算されます。
まず、共通化した1つ目の手当を支給する労働者が2人以上いる場合には、2人目以降の1人につき1.5万円(生産性が6%向上している場合には1.8万円)の加算(※上限20人まで)となっています。
また、複数の手当を共通化した場合には、2つ目以降の手当について、1つ当たり16万円(生産性が6%向上している場合には19.2万円)の加算(※上限10手当まで)となっています。
したがって、諸手当制度共通化コースで受給できる助成金額は、対象労働者を上限の20人、対象手当を上限の10手当と仮定した場合に、最大で48万円[共通化による基本支給]+(1.8万円×19人)[対象労働者2人目以降の加算]+(19.2万円×9手当)[対象手当2つ目以降の加算]=255万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
この助成金は1回しか受給できないため、共通化すべき手当は積極的に共通化を検討して受給額を最大化する工夫が求められます。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、有期契約労働者等を新たに社会保険に適用して給料を増額する必要があります。
賃金の増額率によって支給額は異なり、以下のようになっています。
| 基本給の増額の割合 | 基本的な支給額 | 生産性が6%以上向上している場合 |
| 3%以上5%未満 | 2.9万円 | 3.6万円 |
| 5%以上7%未満 | 4.7万円 | 6万円 |
| 7%以上10%未満 | 6.6万円 | 8.3万円 |
| 10%以上14%未満 | 9.4万円 | 11.9万円 |
| 14%以上 | 13.2万円 | 16.6万円 |
(※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は45人まで)
この表から、選択的適用拡大導入時処遇改善コースで受給できる助成金額は以下のようになります。
対象労働者を上限の45人、基本給の増額率を14%以上と仮定した場合に、最大で16.6万円×45人=747万円の受給が可能です(生産性要件も満たしている場合)。
キャリアアップ助成金のコースの中でも、支給額が大きいことが分かります。

賃金規定等改定コースとの使い分け

同じように賃金をアップすることで受給できる助成金には、すでに解説した賃金規定等改定コースがあります。
賃金規定等改定コースと選択的適用拡大導入時処遇改善コースには以下の違いが上げられます。
- 社会保険の適用の有無
- 増額率の違い
- 利用回数の制限
1:社会保険の適用の有無
社会保険の適用拡大に取り組むことを第一と考えており、なおかつ賃金アップにも取り組むならば「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」を利用すべきです。
最低賃金の引き上げに対応する必要がある会社では、社会保険の適用拡大と同時に、最低賃金もクリアできて一石二鳥となります。
2:増額率の違い
しかし、社会保険の適用拡大を考えておらず、賃金アップだけに取り組むならば「賃金規定等改定コース」を利用すべきです。
賃金規定等改定コースならば2%アップから取り組むことができるため、人件費への負担も小さく、ゆっくりと進めていくことができます。
また、賃金規定等改定コースで3%アップしたほうが、助成金額も大きいです。
例えば、労働者5人を対象に賃金を3%アップした場合の支給額を比較してみると、
《選択的適用拡大導入時処遇改善コース》
2.9万円×5人=14.5万円(生産性要件を満たした場合には18万円)
《賃金規定等改定コース》
1事業所当たり26.125万円(生産性要件を満たした場合には33万円、さらに職務評価を実施した場合には57万円の加算)
となり、賃金規定等改定コースのほうが支給額が多いことが分かります。
このため、賃金アップだけを考えて取り組むならば、賃金規定等改定コースを利用すべきです。
3:利用回数の制限
選択的適用拡大導入時処遇改善コースの受給は1事業所当たり1回のみとなっています。これを受給した後に賃金増額で助成金を受給するならば、賃金規定等改定コースを利用することになります。
賃金規定等改定コースでは、3%超の引き上げで助成金が加算されることはありませんが、選択的適用拡大導入時処遇改善コースでは14%まで助成金が加算される仕組みになっています。
したがって、賃金を大幅に引き上げたいと考える会社では、1回きりの選択的適用拡大導入時処遇改善コースを利用する際に大幅な引き上げを図って受給額を最大化し、それ以降は賃金規定等改定コースによって2~3%の小幅な増額を繰り返すのが効率的と言えます。

注意したいこと
選択的適用拡大導入時処遇改善コースで複数の労働者を対象としており、基本給の増額割合が異なる場合には、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
例えば、10人の労働者を対象としており「そのうち9人が14%の増額、1人が3%の増額」であれば、全て3%増額の場合として計算されます。
したがって3.6万円×10人=36万円(生産性要件を満たした場合)の支給しか受けられません。
このような失敗に陥らないよう、低い増額割合の区分に引っ張られないように調整しながら取り組むべきです。
短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者労働時間延長コースは、延長する週所定労働時間によって支給額が異なります。
週所定労働時間を5時間以上延長する場合
まず、短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合には、1人当たり22.5万円(生産性が6%向上している場合には28.4万円)の支給を受けることができます。
1年度1事業所当たりの支給上限人数は45人ですから、上限いっぱいまで申請した場合の最大の受給額は、28.4万円×45人=1278万円(生産性要件を満たした場合)の受給となります。

週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する場合
延長する週所定労働時間が1時間以上5時間未満の場合には、要件がやや複雑になります。
まず、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させるにあたって労働者の手取り収入が減少してはなりません。
そのため、基本給の増額率は下記の要件を満たす必要があります。
- 1時間以上2時間未満:13%以上昇給
- 2時間以上3時間未満:8%以上昇給
- 3時間以上4時間未満:3%以上昇給
- 4時間以上5時間未満:2%以上昇給
同時に、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施することも要件となっています。
この場合の支給額は、以下の通りです。
| 週所定労働時間延長時間 | 基本的な支給額 | 生産性が6%以上向上している場合 |
| 1時間以上2時間未満 | 4.5万円 | 5.7万円 |
| 2時間以上3時間未満 | 9万円 | 11.4万円 |
| 3時間以上4時間未満 | 13.5万円 | 17万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 18万円 | 22.7万円 |
(※1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで)
したがって、1年度1事業所当たりの支給上限人数である45人を対象とし、週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した場合には、22.7万円×45人=1021.5万円(生産性要件を満たした場合)の受給となります。

あなたの会社でも受給できる?

ここまで、キャリアアップ助成金を受給できるケースや、受給額についてみてきました。
ここからは、あなたの会社でも受給できることを理解してもらうべく、様々な受給例を紹介していきます。
正社員化コースの受給例
A社では、人材不足の解消のために新規の雇用を検討していました。
新規の雇用では、能力や適性が分からない人を雇うため、期待外れの人材を雇ってしまうこともあります。
したがって、A社はトライアル雇用助成金を利用し、トライアル期間で試しに働いてもらうことを検討していました。
しかし、社労士に相談したところ、トライアル雇用助成金は満額受給しても12万円に過ぎないため、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用し、転換することでより多くの助成金を受給することをアドバイスされました。
トライアル期間は3ヶ月であり、期待外れの人材は最短3ヶ月で契約期間満了退職とすることができます。一方、正社員化コースでは最低でも6ヶ月の雇用の後に転換する必要があります。
正社員化コースでも、期待に沿わない人材は6ヶ月の後に、契約期間満了退職とすることができるため、リスクを抑えることができます
さらに、転換によって得られる助成金は、トライアル雇用助成金よりも多くなります。
A社でも、トライアル雇用助成金ではなくキャリアアップ助成金の正社員化コースを利用することにしました。
契約社員を募集したところ、5名を6ヶ月間の有期労働契約で雇用することができました。
このうち1名は適性がなかったため、6ヶ月で契約期間満了退職となりましたが、残る4名は適性があったため、正社員に転換することとしました。
有期契約から正規雇用への転換では、1人当たり57万円の助成金を受給できるため、A社は4名で合計228万円の助成金を受給することができました。
正社員化コースで得られたメリットは、求人活動のコストや人件費負担を軽減できただけではありません。


賃金規定等改定コースの受給例
B社は小規模事業者で、社長以外は全てパート社員でカバーしていました。
パート社員の時給は最低賃金に設定しており、従業員からは不満の声も上がっていたものの、資金繰りを考えると容易に昇給させることはできませんでした。
しかし、近年では政府が最低賃金を盛んに引き上げており、その対応に苦しめられていました。
最低賃金をクリアするために苦労して昇給しても、それほど良い影響はありませんでした。
従業員たちは賃金アップを喜ぶものの、政府の方針・社会の流れの中で賃金は上がるべくして上がったという印象しかないのです。
そのため、賃金アップに伴うやりくりに社長が苦労しても、従業員がありがたみを感じることはなく、モチベーションや定着率の向上にもつながりませんでした。
そこで社長は、賃金規定等改定コースを利用することにしました。
ここ数年、最低賃金は3%程度の上昇を続けているため、次の年も3%程度引き上げられることを見込み、政府が最低賃金の引き上げを発表しないうちから賃金を引き上げることとしたのです。
B社のパート社員は総勢10名でしたから、賃金規定等改定コースで全ての従業員に対して賃金を3%アップしたことで、42万7500円を受給することができました。
B社の従業員は、政府の方針によって賃金が上がったのではなく、社長が従業員の処遇を改善してくれたものと考えたため、意欲的に働くようになり生産性も向上しました。
また、常に一足先に賃金を引き上げることによって、最低賃金ギリギリのラインで雇用している他社よりも待遇が良くなります。


賃金規定等共通化コースの受給例
C社では慢性的な人手不足に陥っており、従業員一人当たりの負担が大きくなっていました。これは有期契約労働者に対しても同じです。
C社では、商品の検品・梱包などの軽作業に有期契約労働者を使っており、賃金も低めに設定されています。
しかし人手不足のため、軽作業だけではなく「重量物の運搬や製造のサポート・倉庫内の清掃」など、有期契約労働者に様々な業務を命じていました。
時には、正社員と全く変わらない業務を命じることもありました。
有期契約労働者としては、軽作業に従事するものと思って就職したにも関わらず、負担の大きい業務も与えられ、なおかつ軽作業員としての賃金しかもらえずに大きな不満を抱くことになります。
そのため、これまでにも多くの有期契約労働者が短期間で離職してしまい、人材不足が人材不足を呼ぶ悪循環に陥っていました。

これにより、有期契約労働者6人が対象となり、67万円の助成金を受給することができました。
この結果、有期契約労働者は「軽作業の賃金で色々な業務をこなす従業員」から、「相応の賃金をもらって色々な業務をこなす従業員」となり、職務にふさわしい賃金を受けられるようになりました。

諸手当制度共通化コースの受給例
D社は建設業者です。近年、夏場には猛暑の影響を受け、現場の作業員が熱中症などによって働けなくなったり、生産性が低下したりすることが増えていました。
従業員には、作業の合間にスポーツ飲料や塩飴などを摂ること、栄養価の高い弁当を食べることなどを呼びかけましたが、自腹ではそのような対策をしない従業員も多く、思うように改善できていませんでした。
そこでD社は、諸手当制度共通化コースを利用し、それまでは正社員のみを対象としていた食事手当を共通化し、高カロリーの弁当やスポーツ飲料水、塩飴などを支給して熱中症対策を図りました。
共通化の対象となる有期契約労働者は15人であったため、59万円の助成金を受給することができました。

まとめ
雇用保険料を原資としている助成金制度は、使わなければもったいない制度です。自社に効果的な制度を見つけ、積極的に活用していきたいものです。
中でも、キャリアアップ助成金は多くの会社で活用することができます。
助成金には様々な制度があって分かりにくい、何に取り組んだら良いのか分からないという人もいると思います。
まずはキャリアアップ助成金の中から自社で活用できるものを見つけ、取り組んでみるのが良いでしょう。
具体的な手続きなどは、助成金の専門家である社労士に依頼して進めましょう。
この時、着手金ゼロの社労士に依頼し、リスクを下げることもお忘れなく。






コメント