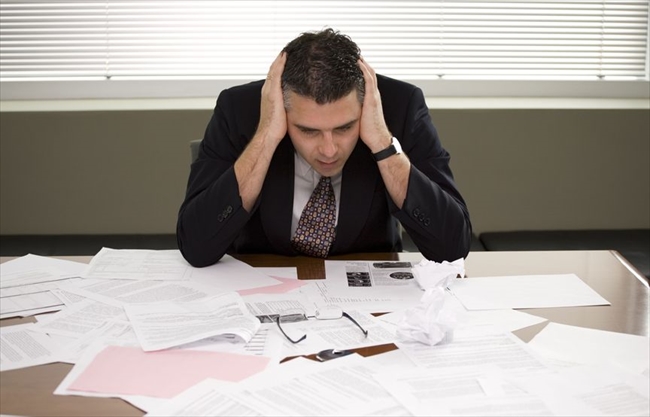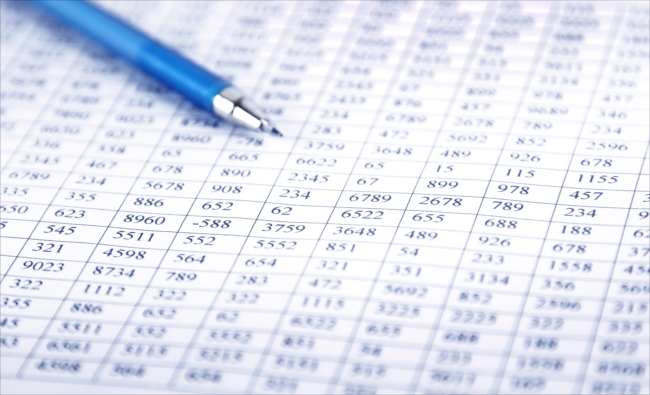短期の資金計画では、仕入、支払、販売、入金といった、目先で行われる資金の流れを把握するものであり、その中で起こる資金不足の理由は割と明確で、原因と対策は立てやすいものです。

ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
先行き資金不足の原因と対策

上記でも簡単に触れましたが、先行き資金不足に陥る原因をもっと具体的に見ていきましょう。
先行き資金不足の原因として想定されるものには、大きく分けて「売上に関すること・費用に関すること・信用に関すること」の三つに分けられます。
売上に関すること
これは、主に売上が減ったり、売掛金の回収が難航したりすることです。
- 競合商品によって自社のシェアが減り、これによって在庫が増えて資金が足りなくなる。
- 設備投資をしたものの、想定していたほど売上に貢献せず、投資資金の回収がうまくいかなる。
- 営業活動が功を奏して売掛債権が増加したものの、回収がうまくいかなる。
- 大口の取引先が倒産してしまい、多額の資金不足を起こす。
- 為替相場が不安定になり、売上が減少してしまう。または自社は為替の影響を受けずに売上を維持できたとしても、取引先が痛手を被って取引が縮小したり、貸し倒れが起きたりすることも予想される。
- 売上代金の支払い延長を要請される。
費用に関すること
これは、主に費用に関することです。
突発的な費用の発生には注意が必要です。
- 地震や火災によって倉庫が倒壊して在庫が被害を受ける。
- 豪雨によって生産地が被害を受けて仕入価格が高騰する。
- 労働問題が起きて多額の支払いが必要になる。
- 公害問題に巻き込まれて訴訟費用が発生した。また巨額の損害賠償が発生する。
- 債務保証をしている関連会社が倒産し、保証実行に追い込まれる。
信用に関すること
これは、自社の信用状況に応じて想定されるリスクです。
- 業績が悪化し、銀行から一括返済を求められる。あるいは金利の上乗せを求められる。
- 業界内で信用不安の噂が広がり、仕入先が売ってくれなくなる。あるいは支払いサイトが短くなる。

CFレッド
以上のようなことが原因になりやすいと考え、長期資金計画を作っていく必要があるよ!
長期資金計画は、通常5年を見込みます。
資金計画に先立ち、売上・利益計画を立て、それに基づく長期資金計画を立てるのがスタンダードなやり方です。
▼【最長60日】請求書の支払いを先延ばしにできる▼
 ▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼
 ※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
財務体質を改善しよう

様々なリスクを織り込んで長期資金計画を立てると、全く問題がないといえる会社は少なくないものです。
多くの会社は、何らかの対策を講じなければ「先行き資金不足」に陥ることが分かると思います。
突発的な支出に備え、環境の変化に対応していき、先行き資金不足に陥らないようにするためには、何といっても資金を増やす取り組みが大切です。
長期の対策のために会社の資金を増やすには、ともかく利益を増やすことが大切です。
融資でも資金を調達することができますが、長期的な取り組みとはいいがたく、やはりしっかりと儲けることが一番の基本です。
売上と利益を伸ばすように努力することも重要ですが、それ以外にも自己金融と呼ばれる方法によって、会社の内部で資金を増やしていくことが重要です。

CFイエロー
自己金融では、会社の各部門で生じている無駄を省くよ!
無駄を省けば利益率は高まりますから、利益を増やすことにつながるのです。
自己金融に取り組むべき部門は「営業部門・製造部門・購買部門」の三つであり、それぞれが以下のように取り組むことで利益を増やすことができます。
営業部門
- 売上拡大と早期回収を目指す(売上を拡大するだけでは必要資金も増えるため、売掛債権の早期回収を同時に目指す)。
- 製造部門と密に連携し、過剰生産を防ぐ。
- 経理部門と密に連携し、業績を把握しながら効率的な営業を心がける。
- 売掛債権管理を徹底し、不良債権の発生防止と回収の促進を心がける。
製造部門
- 在庫を減らすと運転資金が圧縮されることを理解し、見込み生産を止め、無駄な経費を減らす。
- 経理部門、営業部門と連携し、売れるものと売れないものを把握したうえで生産を調整する。可能ならば売れるものだけを作る。
- 製造コストのカットを常に意識する。
購買部門
- 必要なものを必要なタイミングで購入する。
- 自社に有利な支払条件へと改善する。
- 製造部門、経理部門と連携し、収益向上を目指す。

CFブルー
色々な取り組みがあり、無駄を省くことで利益は増えていくのだ!
一つ一つの無駄は僅かでも、確実に利益が増えていくのです。
しかしながら、上記の取り組みの中でも効果が大きいといえるのは、売掛債権と在庫の圧縮です。
売掛債権の回収を促進し、在庫の適正化と現金化を促進すれば、この両者は圧縮されて必要となる運転資金も減ります。
これは、以下の図を見れば明らかです。
このように、売掛債権と在庫を圧縮すれば、それと同額分だけ必要運転資金も減り、資金繰りがラクになります。
これは、短期の資金繰りでも長期の資金繰りでも同じです。
むしろ、これは長期的に取り組むべき事柄ですから、長期のスパンで取り組むことで、先行き資金不足に備えていくことができるのです。
なお、各部門間の連携は非常に重要です。
各部門で情報を共有したほうが自己金融はスムーズに進みます。
先行き資金不足の際の融資

なお、先行き資金不足に備えて財務体質の改善を図っても、それだけでは対応できないことがあります。
この場合には、社外から資金を調達することを考えることでしょう。
民間の金融機関からの借入を検討する人が多いと思いますが、民間の金融機関は審査が厳しいものです。
先行き資金不足を計画的に改善できない会社には、融資してくれない可能性もあります。
そこで、民間の金融機関以外に、社外で借りられる機関を頭に入れておくと良いでしょう。
政府系金融機関
まずお勧めしたいのは、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、中小企業基盤整備機構などの政府系金融機関です。
営利目的の民間金融機関とは異なり、政府系金融機関は政府の経済政策をもとに運営されているため、民間金融機関が貸し渋る会社でも融資を受けられる可能性があります。
また、低金利かつ固定金利で、預金の拘束がないなどのメリットもあります。
制度融資
都道府県などの自治体の制度を使って融資を受けることもできます。
これは、自治体が信用保証協会に打診して保証を付け、民間の金融機関から借り入れる制度です。
金利の一部を自治体が支払うため、優先的に検討したいものです。
生命保険解約
生命保険を中途解約することで、返戻金を受け取るという方法があります。
あるいは、契約者貸付制度を利用し、返戻金の範囲内で借り入れることも可能です。
セール&リースバック
会社の所有する資産をリース会社に売却して資金を調達し、再び借り受ける方法です。
単に売るだけならば、事業場欠くべからざる資産は売却することができませんが、セール&リースバックならば再び借り受けることによって経営環境が変化しないため、資金調達に役立てることができます。
私募債
会社の縁故者に対し、50人未満であることなどを条件として小規模な私募債を発行することが可能です。
縁故者に発行することから、低金利で長期間の調達が可能となります。
▼創業期・赤字でも借りられるビジネスローン▼ ▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
▼【最短60分】少額から請求書で資金調達▼
先行き資金が大きく不足している場合

先行き資金不足を計算した時、想像以上に多額の資金が不足した場合にはどうすればいいのでしょうか。
多額の資金が不足すると、上記のような社外での調達では足りないこともありますし、民間の金融機関は貸したいとは思わないでしょう。
多額の先行き資金不足が明らかになった場合には、資金不足がいつ訪れるのかにもよりますが、長期計画で資金を蓄えていくほかありません。
その方法としては、自己資本を増やして体力をつけ、その体力を担保に社外からお金を集める方法の二通りがあります。
自己資本を増やす

CFイエロー
自己資本を増やすためには、以下の方法が考えられるわ。
利益を留保する
長期計画で資金を蓄えるべく、収入を増やし、支出を減らす方策を固め、社内の総力を結集して臨みます。
毎年獲得した利益から税金などを差し引き、残った利益をできるだけ他に回さず、内部留保して自己資本を増やし、体力をつけていきます。
増資を受ける
株式を新規に発行して既存の株主に割り当てる、あるいは新規の出資者を見つけて新株引受権を与える方法によって増資が可能です。
増資する人は、将来的に株価が値上がりした時に利益を得ることを目的としているため、会社が出資に値するだけの魅力を持っていなければ、この方法は成り立ちません。
投資育成会社から出資を受ける
中小企業庁が管轄する会社に中小企業投資育成会社というものがあり、これは中小企業の自己資本を充実させ、成長させることを目的としています。
安定して配当できるだけの利益を上げているならば、投資育成会社から出資を受けることができます。
社外からお金を集める

自己資本が増えるということは、会社がいざという時に使える手元資金が増えるということであり、会社の体力が充実することです。
先行き資金不足に陥った際にも、完全にカバーとはいかないまでも、それなりの対応は可能となります。
この体力を担保として、つまり自己資本を裏付けとすれば、社外からお金を集めて多額の先行き資金不足に対応できる可能性があります。
少人数私募債
私募債については既に説明しました。
いかに縁故者とはいえ、多額の先行き資金不足が見込まれる場合には、なかなか引き受けてくれないものです。
しかし、利益の留保や増資・出資などによって会社の体力が充実したとわかれば、引受人を見つけやすくなるでしょう。
長期借入
金融機関からの長期借入も同じです。基本的に、金融機関は長期の融資を嫌います。
融資期間が長期になると、融資期間中に会社の財務状態が悪化し、貸し倒れになるリスクが高まるからです。
したがって、金融機関は長期融資よりも短期融資を好むものであり、それが多額の先行き資金不足が見込まれる会社ならばなおさらです。
しかし、自己資本を増やして体力をつけ、長期融資を受けることによって先行き資金不足を解消していけることをきちんと説明し、返済計画も金融機関が納得するものを提供できるならば、長期借入が可能となる場合もあります。
リスケジュールの検討

自己資本を増やすことや、社外からお金を集めることなどは、上記の通り先行き資金不足解消に役立ちます。
しかし、資金繰り状況を洗い出した結果、現在抱えている借入の返済条件が厳しいために、多額の先行き資金不足に陥っているならば、金融機関にリスケジュール(返済金額や返済期間、金利などの返済条件の変更)をお願いすることも視野にいれます。
考え方としては、税引き後純利益と減価償却費の合計額を、返済元本が上回っている場合には、リスケジュールをお願いします。
これは、いわば返済元本が返済原資を上回っている状態なのですから、早急にリスケジュールをお願いしなければ、状況はどんどん深刻化してしまいます。
リスケジュールをお願いする場合には、現在の財務状況から考えて、適正な(可能な範囲内で最大限努力した)返済スケジュールを考え、金融機関と交渉します。

CFレッド
この時、複数の金融機関から借り入れている場合には、各金融機関から承認を得る必要があるよ!
リスケジュールを受け入れてもらえば資金繰りは改善し、先行き資金不足も緩和されるという事。
会社の安定性が高まり、借入金の返済もきちんと行えるということを説明することが重要です。
ただし、リスケジュールは金融機関にとっては好ましくないことであり、お願いすれば金融機関との関係は悪化する可能性もあります。
先行き資金不足を解消したのちの資金繰りに悪影響を与える事もあります。
したがって、何としてでもリスケジュールをお願いしなければいけないと判断できる場合に利用したいものです。
▼【注文書OK】注文書で資金調達できる!▼

先行き資金不足どころではない場合
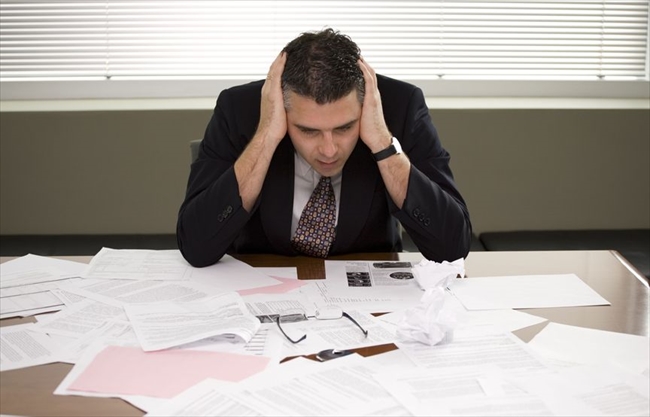
先行き資金不足が発生する場合と、それが多額の場合を見て来たわけですが、中には、「先行き資金不足どころか、すでに資金不足に陥っている」という人もいるでしょう。
現状で資金繰りが困難ならば、上記で説明したような長期的な取り組みはできませんから、短期の緊急避難を考える必要があります。
この場合に有効な方法は、保有している資産を換金するか、簡単に借りられる方法を検討するかのどちらかになります。
銀行などの民間金融機関は、基本的に資金繰り困難な会社へは貸し渋るものですから、あまり期待できません。

CFイエロー
最初に検討したいのが、保有資産の換金よ!
以下のような資産は換金が可能です。
有価証券
上場企業の株式などを保有しているならば、まずこれを換金するのが良いでしょう。
含み損が出ていると売りたくない気もするでしょうが、このような上場有価証券は差益で儲けるというよりも、緊急時にこそ活用すべき資産です。
受取手形
受取手形は、銀行や手形割引業者、ファクタリング業者などによって現金化が可能です。
売掛金
売掛金も、ファクタリング業者に譲渡することで現金化することができます。
また、売掛債権を担保にすることで、売掛債権担保融資という制度を活用できる場合もあります。
固定資産
会社の利益に結び付いていない遊休固定資産があるならば、これも売却しましょう。
固定資産は保有しているだけでコストがかかりますから、含み損が出ていても売った方が賢明な場合が多々あります。
また、保有している資産の換金とは異なりますが、「預金を解約したり、保険積立金を解約したり」することによっても、手っ取り早く資金を調達することができ、短期の対策に有効です。
保有資産によって賄いきれない場合には、借り入れに頼ることになります。
この場合に頼れる先としては、役員からの借入が最も良いでしょう。
それができなければ、日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資など、公的な機関に融資をお願いすることになります。
信用不安を起こさないように注意

このような短期の資金不足の際には、信用不安を引き起こさないように注意してください。
例えば、資金不足のために支払いを猶予してもらいたいと思っても、相手を選んで交渉しなければ、資金繰り困難の噂を流され、誇張されて噂が広がり、その後の経営に悪影響になる可能性があります。
このため、信用不安を引き起こさないためにも、あくまでも慎重に行動することが大切です。
交渉事を慎重に行うと同時に、自社の雰囲気から悟られないように気をつけなければなりません。
- 会社が窮地に陥っている時には、
- 経理担当者と連絡が取りにくくなる
- 会社に活気がなくなる
- 従業員の対応が落ち着かない
- 従業員が会社の悪口を言うようになる
- 主要仕入先の管理部門が訪問を始める
などの兆候があるものです。
したがって、自社にこのような兆候が表れないように、従業員に窮状を悟られないようにしたり、接客指導を行ったりすることも重要です。
資金繰り困難の場合に信用不安を引き起こさない方法は、他の記事でも詳しく解説していますので、そちらを参考にして欲しいと思います。
まとめ
会社は、何年、何十年と経営していくものです。
それだけの長期間にわたって資金繰りをしていくのですから、目先の資金繰りだけを見て経営していくのではいけません。
もっと長期的に見たら、先行き資金不足が起こるのは明らかであるのに、目先しか見なかったばかりに経営が破綻してしまうことになります。
したがって、長期的に安定した経営のためにも、先行き資金不足の発生を把握し、それに向けて長期的な対策を行ないましょう。
そうすれば、会社の安定性は飛躍的に高まるはずです。